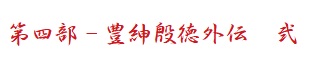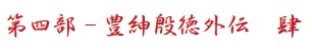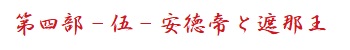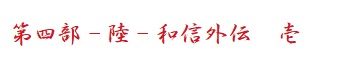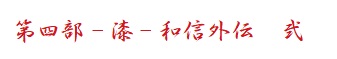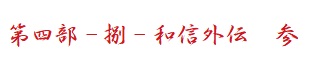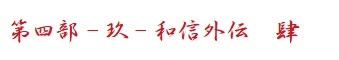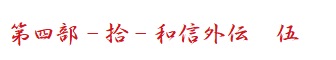|
“ 仁泉亭
”
文化十一年九月二十二日(1814年11月3日)・伊香保
“ 仁泉亭
”の朝食は一汁二菜。
汁-豆腐味噌汁
皿-塩鮭焼き物
平-里芋と氷豆腐煮物
小皿-菜の漬物
飯
昨日の案内で次郎丸達が昔物語の好きものと知った弥二郎は父親弥吉と“
ますや ”の店番を替わり“ 仁泉亭 ”へ弥吉を寄越した。
「昨日は湯元まで御出でと」
「野天風呂に蒸し風呂も有ったぞどこの管理だね」
「隻腕不動尊堂守が面倒みておりますが。蒸し風呂は地熱だけでなく、簀子の下を湯が流れております。その簀子の上で汗を流します」
「昔大和の明日香では風呂は蒸し風呂だったと聞いたことが有る。ここのも相当古そうだ」
隻腕不動尊は湯元不動、隻腕には伝承が二つ在るという。
「一つは災害で元湯と不動様が土砂に埋まってしまい、村人は不動様を掘り出すと湯が再び湧き出しましたが、不動様の片腕は見つからなかったそうで御座います。一つは災害で湯が止まり、千明当主が不動様に願をかけ申したそうで御座います。 願掛け最後の日、釜の中に熱湯が噴出しましたが、不動様の右腕がなくなっていたという話で御座います」
湯元の野天風呂に蒸し風呂を番頭ともども勧めてくる。
「草津(くさず)に熱さは劣るという方も居りますのでお試しを」
蒸し風呂の浴衣は洗いざらしを六文で貸し、それが湯銭に為るのだという。
「新しいのが良ければ三十二文で宿の名の物をお出しします」
「もって帰られては大損だな」
弥吉の言う所に寄れば、伊香保神社は別当寺の温泉寺(寛永年間創建)が支配、湯前明神、薬師堂は医王寺の支配だそうだ。
薬師堂が温泉明神であり、伊香保神社は湯前大明神として東側に鎮座した。
温泉明神の本地が薬師如来、湯前大明神の本地が十一面観世音菩薩と言う。
「なぁ、番頭さんよ。うな丼を追加できるか」
「お任せください。二十人でも間に合うくらい入れて居りますので」
「大きく出たな。それでな、弥吉さんよお前さんの所は何人家族だ」
「五人ですが。一人はまだ七歳で」
「鰻が嫌いではないよな」
「わし等にも御馳走して下さるので」
「“ 流行りものには目がない ” のだ付き合いな。番頭さん出前を頼みますよ」
斜め前の見世で弥吉は「今晩、旦那様が儂らにも鰻丼を届けてくださると仰せだ」と伝えた。
今日も薬師堂まで階段を上った。
「高山彦九郎様の名をご存知でしょうか」
「聞き知って居る」
「この伊香保にも立ち寄ったそうでござってな。崇拝する人は腰掛けた石まで見に来られます」
「亡くなって二十年余りと聞くが、もうそのような伝説まで作られたか」
遠くに稲妻が光った、音は遠くに聞こえる。
「二ツ嶽から榛名の方へ雲が流れていきます、こちらへは来ないようです」
次郎丸は又万葉を思い出して詠った。
“ いかほねに かみななりそね わがへには ゆゑはなけども こらによりてぞ ”
“ 伊香保祢尓 可未奈那里曽祢 和我倍尓波 由恵波奈家杼母 児良尓与里弖曽 ”
川沿いの紅葉は一日で赤みが増している、野天風呂には介重と朗太の二人が入っていた。
十人も入れば一杯の湯壺だ。
「熱さは草津(くさつ)とどうだ」
「向こうの温い湯くらいですぜ。蒸し風呂で汗を流してから入ると気持ち良いですぜ」
此処の湯は昨日見た元湯に比べ湧き出し口が低く、石段下へも送ることが出来ず、湯量も少ないのだと弥吉が教えてくれた。
湯番の老婆は「五人様一緒だかね。三十文だに」と言っているので大野が支払った。
今日は両刀とも宿へ置いてきて身軽だが、介重と朗太に懐の財布などの番をさせた。
荷駄は此処から先へは通れないが、口留番所からの草津道へ通じているそうだ。
汗をかいた肌襦袢は湯を浴びてから絞って湯番の老婆へ戻した。
若い女が井戸から盥へ汲んだ水につけ、揉み洗うと竹竿にそでを通して干してゆく。
介重と朗太から荷を受け取ると湯元不動尊を観に高みへ上がった。
「この後二人はどうするんだ」
「石段に有る下の“ もりた ” ってとこで蕎麦を食いやす」
二人と別れ川沿いを下って弁天へ向かった、湯治客が十人ほどお参りしていた。
礼拝して坂を下り、橋を渡って坂を上ると医王寺の下へ出た。
石段を横切り、楽山館下を先へ入ると突き当りに天宗寺と言う禅寺、下に天満宮、その奥に八幡宮の屋根が見える。
川に石橋が掛かり左手を差して「あの水車が回る家が兄貴の家で御座います」と言う。
春米屋(つきまいや・米搗き)だそうだ。
「水車で米を搗いているのか」
「七分搗きまでで、後は拝み搗きで仕上げています」
荒糠は牛に馬の餌、拝み搗きで出る生糠は漬物用に売れるという。
坂を下ると小さな地蔵堂が有る。
その先に水澤寺からの街道が有り、追分を左にいくと口留番所に行きつく、丘の円山道先に円山稲荷、躑躅の名所だと言うが時期が悪い。
大根畑の中に参道が有る、石段を登り社に拝礼した。
二町程西にも稲荷の社が有る「こちらは中子稲荷と申しますが、円山と違い名所に為りませんでした」
「榛名富士や榛名湖は遠いのかな」
「湖まで一里二十七町と言いますが、峠もあるで一刻半(とき・百八十分)位ですかな、近間の物聞山など見晴らしも宜しくてお勧めです」
「足馴らしには手ごろかな。上の山とどちらが良い」
「上の山は上までの道は獣道で。物聞山は頂の琴平(ことひら)さんまで道が整備されております」
弁天、不動、琴平、八幡、稲荷、天神(天満宮)、無いのはお伊勢様にお諏訪様位だという。
温泉の守護の伊香保神社は大己貴命、お辰(おとき)たちは残りの日程も無事で有りますようにと日参している。
宿へ戻ると大野は、弥吉と番頭から付近の見取り図と距離を聞きとっている。
「未雨(みゆう)は前に伊香保と草津は十五里位と言っていたが歩いたのか」
「耳学問ですよ。全国行脚をしかねない先輩が多いですから」
坂東三十三か所観音霊場を巡る先達の心覚えが一番頼りに成るそうだ。
伊香保から榛名神社経由は三ノ倉まであっても五里だという事に話しは落ち着いた。
三ノ倉から須賀尾五里五町は案内記に出ている。
須賀尾から草津温泉が六里十五町で合わせると長くても十六里二十町。
他には伊香保から中之条経由で草津への道もあるという。
「若、昼はどうします」
「大野は甘酒と言わないな」
「見かけないからですよ。茶と団子ばかりでしたよ」
「その団子でも食おうか」
弥吉は甘酒なら兄貴の見世で作っているという。
「いい塩梅に毎日七つには売り切れています。わっしの所で売るほど回せぬと言われるのですが、仕込を増やしたくとも手が足りぬそうで御座います」
酒蔵が伊香保には無く弥吉の見世は藤岡、渋川、高崎辺りからの酒を売っているという。
「八つ前だ。見世が近けりゃ行ってみよう」
大野は熱いのも、井戸で冷やしてもどちらも好きで飲めるのだ。
石段を上の踊り場で“ ますや ”にいる弥二郎へ「兄貴の所へ行ってくる」と告げて後閑楼下の路地へ入った。
天宗寺下天満宮手前、水路で水車を回す家へ入った。
「弥太郎兄さん」
「おお、弥吉か大勢さんでどうした」
「今日の甘酒はまだ有るかい」
「薄めりゃ三十人分はあるぞ」
「己(おのれ)でそんな冗談くっちゃべるから本気にされるがね」
いつも冗談の好きな男の様だ。
「今奥でタネが江戸の人を連れてきて休んでいるが、お仲間かい」
「聞いているだろ。新之丞様のお仲間だがね」
大きい椀へ若い娘が銅壷から柄杓で汲んで一同へ振る舞った。
次郎丸は竹箸でかき回して飲みやすくした、濃口で甘さは控えめだ。
大野は飲み終わって「もう一杯所望」と二杯目を頼んでいる。
「外で蕎麦の香りがするぞ」
「裏の小屋で蕎麦を石臼で挽いています。三軒分の粉を引き受けて居ります。今日の分はもう終わるころでしょう」
大野は又地図の話を聞いている。
「伊香保案内でも出す気か」
「そうではありませぬが。大殿に聞かれたときの用心で御座る。石段の南北が曲っていて少しずれてご坐る故、周りの位置は話すものでずれてき申す」
水澤観音から西北へ上ってきた道は幾度かの鉤手(曲尺手・かねんて)で方向感覚がずれると言う。
「それは武田甲州流の陣立ての名残が今の石段ですから」
弥太郎と弥吉は目の先、段の坂道下が水澤観音への街道で、この坂道は最近出来たという。
向山観音の坂道も石段の中ほどへ繋げようと計画は出ているそうだ。
「明日五つに出て物聞山の琴平(ことひら)さんへお参りして此処まで戻るにどのくらいだね」
「頂上まで行って戻って一刻(とき・百二十分)、上でどのくらいいるか次第で御座いましょう」
湯前大明神と比べて四十丈とは変わらないという。
「上の山へ登った者ははるかに見晴らしが良いと申しますが、なんせ行者も音を上げる獣道なのだそうで御座います」
大野は「はは、それで上の山で観る月でなく、上の山の月を観るとしたか」と得心している。
夜はうな丼に松茸も出て大野が喜ぶ食事に為った。
汁-松茸
平-里芋と氷豆腐煮物
鉢-二度芋の芋膾
椀-松茸と鶉の叩き団子茶碗蒸し
小皿-菜の漬物
鰻丼
|