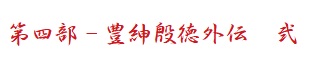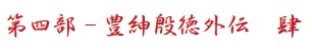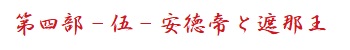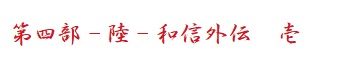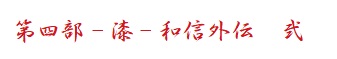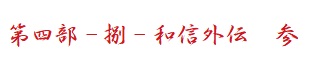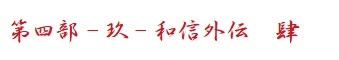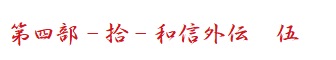|
白川“ やなぎや ”柳下源蔵
文化十一年五月二日(1814年6月19日)・白川
卯の下刻(五時十五分頃)前には馬方も来たので六人は南湖へ向かった。
桝形の先追分を棚倉街道へ入ると三蔵と十郎が馬から降りて休んでいる。
「随分早いな」
「卯の刻の鐘で出てきました」
次郎丸達が早く出てくるとは思ってもいない様だ。
「朝の南湖を見るために早く出てくるとは思わないのか」
「桝形の番人は通っていないと教えてくれましたので、ここで待っておりました」
四日の朝日を南湖で見たいから、近くで泊まるが付き合うか訊くと「お願いします」と二人が喜んでいる。
「ついでだ、明日の三郭御園へも付き合うか」
「宜しいので。水練の時に入っただけで見学の余裕も有りませんでした。三蔵は私の所へ泊めますので何刻に門前へ出れば宜しいですか」
「朝は辰に大手を通れるように出るよ。水練は卒業かい」
「二人とも南湖での試験も受かりました」
十郎は十八歳だが三蔵は十四歳、何歳から調練に駆りだされるのだろう
生沼に聞くと「十二歳から三郭御園での水練を始めます。十五歳までに受からぬと罰役に回され申す」と言う。
棚倉街道から東、山の西斜面に大きな屋敷が見えている。
九番町桝形からわずか五丁程の所だ、共楽亭迄この家(や)から十五丁だという。
生沼が先導でその家へ向かった、母親の実家だという。
「あにさ、手紙で伝えた人たちだ。明日は三人の積りが五人に為ったよ」
谷五郎(やごろう)と言う生沼の叔父だという。
藤吾に弥助、忠兵衛は明日から勝手歩きだ。
「馬に博労さはどうするね」
「歩いてくるから心配いらんよ。そん替わり七つにゃ起きだすようだ」
「戻って朝飯にするかい、それともおらが握り飯でも届けるかね」
「巳の下刻(十時三十分頃)過ぎには戻るからその時世話してくれ」
「引き受けただよ」
生沼が先に立って崖地を使った“ かきつばた ”の群落を案内してくれた。
「祖父と祖母が此処を使って増やしました。まつむしの原の奥にも群落が有るそうですが見たことは無いのです」
“ 花菖蒲(はなあやめ) ”と言われて東勝寺で見た物に似ている。
「江戸で言う“ かきつばた ”とは違うようだ。江戸の“ あやめ ”は花弁に丸みがある、“ 花菖蒲 ”は中心が黄色で“ かきつばた ”は白かったが、ここのは黄色で膨らみも有る」
江戸の“ 杜若(かきつばた) ”は水辺を好み、東勝寺で見た物も水辺に咲いていたがここのは水はけのよい崖地だ。
「どうも郡山辺りの“ あやめ ”とも違うようだな」
生沼も詳しくはない様だ。
「北齋戴斗でも連れて来て書き別けさせるのが良いようだな」
谷五郎も「爺も婆もこれが“ かきつばた ”だと信じていました。まつむしの原のは白だから別だろうとも言っていました」と言う。
「東勝寺で“ 花菖蒲(はなあやめ) ”で“ はなしょうぶ ”とは言ってなかったような」
「同じ字で読みが違うのも困りものだ。おまけに“ はなかつみ ”がどれだか知れやしないと来ている」
大和、飛鳥の“ 花かつみ ”は水辺では無さそうだと次郎丸が言うと、郡山では水辺の花と思われていると多代女が話していた。
“ 杜若 ”は水中にあり“ 花菖蒲 ”は水際に“ あやめ ”は陸地で網目が有る。
「松平様に師事されれば江戸の分け方だけでも区別がつきましょう」
甲子郎は興味が薄いようだ、花園はほかの者に任せる様だ。
大井源蔵のほうが適任かなと次郎丸は心に留め置いた。
谷五郎は両親のいる離れへ次郎丸と生沼を連れて行った。
爺(じじ)婆(ばば)二人は大笑いだ。
「やごよう。まつむしの原の白筋が“ 杜若(かきつばた) ”だ。家のはその裏山で六十年前におらたちの親たつが見っけたもんで“ かきつばた ”で通しているだよ。おまえが聴いたのは大分と昔だべさ」
「おらが七つの時だ」
「うだべさ。その後(ご)のこんだが、これさ“ はなかつみ ”がもとの“ はなしょうぶ ”だとその頃来た新二郎先生さまが言うとったで」
「その新二郎先生、何時頃来られたのですか」
「知り合いかの」
「私の知る物知りの新二郎先生は松平で四十歳くらいの方です」
「苗字はすらねだが、一緒にぎた服部丹後様がそう呼んでいただが、天明四年の今時分だすらな、見たところ四十過ぎているようでしたら。今なら七十は過ぎている筈じゃな」
「違う人の様ですね父君なのかな」
「三十年前の事でな。服部丹後様も代が替わられ取るで」
「よく天明四年と覚えておられますね」
「だどよ。前の年の暮れに飢饉の最中(さなか)殿様が御代替わりに為られただ。忘れりゃ困るだな。出羽から陸奥は餓死したもんも多がったが、ここあ越後はまずまずだで米を分けて貰えただ」
「まつむしの原の“ かきつばた ”は沼地ですか」
「そうだんだ。一段上の小川の縁に生えていたんがうちらの花だ」
「水の手は良いのですか」
「近くへ行けばみえるだね。真ん中で水の路が掘ってあるだよ。花畑に入ると少し土地に湿りが出るでな。水遣り過ぎたり、雨が続いたりすれば余分は流れいくだ」
「新二郎先生という方は持ち帰られたのでしょうか」
「服部丹後様が後でまつむしの原で種を集めて送られましただ」
「じゃ、ここの種では無かったのですか」
「谷五郎やい。この若い人に種を半分遣っていいかのう。江戸で咲くならここいらより変化(へんげ)して綺麗かもよ」
「文平様の親戚ならわいらとも親戚じゃ。やっとくんなされやとっさま」
次郎丸は知らないが、その時の新二郎先生は肥田頼常と言い、天明の頃は表祐筆から奥祐筆へ移るころだ。
その後(のち)奥祐筆組頭に為り、寛政十一年から八年間も長崎奉行を務めている。
小普請奉行、作事奉行を勤め、今は文化七年から四年目の勘定奉行すでに七十五歳と云う高齢だ。
「残しているのは二升も無いだで半分ですまねえだ。今年の秋の彼岸頃に種が採れますで、文平様に頼んでそれも送らせて貰いますだ」
「有難うござる。良き先生も居られるので大切に育てさせて頂きます」
二つに分けて弥助、忠兵衛二人の笈摺(おいずる)へ入れさせた。
笈摺(おいずる)から奉書紙と筆に墨壺を出して縁側を借りて劉禹錫“ 望洞庭湖 ”を四枚に分け書くと爺(じじ)、婆(ばば)に贈った。
“ 湖光秋月両相和 ”
“ 潭面無風鏡未磨 ”
“ 遥望洞庭山水翠 ”
“ 白銀盆裏一青螺 ”
思いついて細筆と紙をもう二枚出させ本川次郎太夫と左下に書いてから訳詞を書いて渡した。
「本名は都合で書けぬのでこれで勘弁してくれ」
“ 劉禹錫 望洞庭湖 ”
“ 湖光秋月 両つは相和し 潭面に風無く 鏡未だ磨かず 遥かに望む 洞庭の山水翠なり 白銀盤里の 一せいら ”
“ 洞庭湖を望む 劉禹錫 ”
“ 湖と秋の月の光ふたつあい和し みなもに風は吹かずいまだ磨かぬ鏡のごとし 遥かのぞむ洞庭の山水はみどりにして しろがねの盆に転がるひとつの田螺のごとし ”
「二十八文字を大和言葉で説明すると倍以上に為ってしまう。湖に映る月の光が見事で、田螺は君山という山の緑が湖面に映えていると例えたのだ」
“ はなかつみ ”がもとの“ はなしょうぶ ”と教えたのが新二郎先生と確認して「後とくに気を配ることは」と訊いた。
「まんず初手から始めるだが、春彼岸の前に肥料の無い花壇に薄く蒔くだ。朝夕の灌水(かんすい)を怠らないことだ。鉢植えなら植えつけは秋の彼岸が良かっただ。鉢の底に穴は必要だ。あとはお江戸に合ったやり方に従うこった。肥料は土地によって違うそうだで調べておんなさい」
婆が「餅を昼から搗く用意してあるで、帰りも寄って下されや」と誘いをかけた。
「午の下刻に向こうを出ることにしよう」
「未なら十分此処まで戻れますな。ばっぱそれで良いかい」
「文平様が言うだらそうすべえな」
孫でも士分で横目付の文平に敬意を絶やさぬ家族だ。
「ぺろも用意しとくべ」
「大食らいが居るので五人前は余分に踏んでくれ」
十郎が笑っている「ぺろは久しぶりだ。大根をかぁぺごと摺って辛くしてほしいな」と谷五郎に頼んでいる。
次郎丸は何のことだと考えている。
「饂飩(うどん)ですよ、渋紙に包んで足で踏むんです。柔くするも腰を強くするもばっぱ次第です。ばっぱ馬方の分も頼むよ」
うんうんと嬉しそうに頷いている、孫は可愛いとは此のことだ。
「ならかぁぺは皮ごとという事か。十郎、家の忠兵衛は辛い物が好きでな、矢吹の大根蕎麦五鉢食って物足りなそうだった」
「若さんは」
「俺には辛くて一枚がやっとだ」
次郎丸の時計は八時になった「丁度いい時間に千代の堤に到着できそうだ」
「いま辰の下刻あたりでしょうか」
「五月の今頃は一刻(とき)が百五十分くらいだ。今出れば余裕をもって番所に着く」
三蔵は文平と話しながら先頭を進んだ。
「夏至を過ぎれば昼間が短くなるのですね」
「そうだよ。須賀川で元禄二年に閏が有って夏至は今年と同じというので気に為っていろいろ調べたら、暦によって一日ずれていた」
「今年の夏至は何日です」
「五月五日だったり六日だったり」
次郎丸が後ろから「来年は十日ほど後に為る」と声を掛けた。
生沼が「再来年も後に為って、八月に閏が入るので次の年は又五日前後に為る」と教えている。
「天文方の暦なら狂わないだろうが、町で出すのはいい加減な物も有るな。伊勢暦の贋も有ると噂だ。御師のおかげで全国の半分は伊勢暦と自慢された」
「少しくらい狂っても影響はないのでしょうね」
「領内同じ暦じゃないと祭日の日取りに困るよ」
「縁起担ぎ位な物ですよ」
若いだけに暦を頼っては居ない様だ。
文化十一年五月五日(1814年6月22日)夏至
文化十二年五月十五日(1815年6月22日)夏至
文化十三年五月二十六日(1816年6月21日)夏至(閏八月・清国閏六月)
文化十四年五月七日(1817年6月22日)夏至
元禄二年五月六日(1689年6月21日)夏至(閏一月)
南湖を対岸まで進み、藤吾たち三人は馬方と一刻(こく)程茶見世で遊ばせた。
「餅と饂飩を食えるくらい腹は空かせておけよ。九人分の茶代だ」
甲子郎は忠兵衛に四文銭十枚を通した物五つに南鐐二朱銀を手渡した。
千代の堤の番所で藩の役人に「二人増えたので儂が船頭に為る」と生沼が伝えて小舟を借り受けた。
兼葭洲を右手に見て舟を進めた。
今日も水練の舟が逗月浦に三艘出ていた。
次郎丸は遠眼鏡でまつむしの原から千代の松原を見渡したが、“ 杜若 ”の群落は見つけられなかった。
有明岬の渚には幾種類もの鳥が漂っている。
五徳村は鶏鳴村だという。
「此処の詩は読んだ事がある。儒者広瀬豪斎殿作だ。和歌を土井様へ頼まれ為されとも聞いた」
|
鶏叫林霧気消
|
鶏 林嘘に叫(な)いて
霧気(むき)消え
|
|
東方初旭赤如焼
|
東方の初旭(はつあさひ)
赤きこと焼(も)ゆるが如し
|
|
青山界断晴湖外
|
青山 界断(だんかい)す
晴湖(せいこ)の外(そと)
|
|
穿破松間路一条
|
穿破(せんぱ)す 松間
路一条
|
「花月様はもう国元への御出で(おいで)はないのでしょうか」
「殿の御参府、儂の養子縁組の後になるだろう。早くも来年の秋だろうな。この度手に入れた深川の作庭が一段落するころだ」
「和名、漢名の十六勝十七景も造られるとか」
「いろいろご用意はされているようだ、南湖十七景の花月様の和歌は見せて頂いた」
谷文晁の描いた文化二年(1806年)南湖勝覧から南湖十七景へと名称は大きく変化している。
例-千代の堤・千世の堤(和名)・使君堤(漢名)などが有る。
|
南湖十七景
・関の湖・共楽亭・鏡の山・真萩が浦・錦の岡・月待山
・月見浦・常盤清水・松風の里・松虫の原・下根の嶋・みかげの嶋
・千世の堤・小鹿山・八聲村・有明崎・千代の松原
|
|
関の湖(せきのみずうみ)・近衛基前(このえもとさき)従一位左大臣
影うつる 山もみどりの 波はれて 見わたしひろき 関のみつうみ
|
|
共楽亭(きょうらくてい)・松平定信(まつだいらさだのぶ)白河藩主
やま水の 高きひきゝも 隔なく 共にたのしき 円ゐすらしも
|
|
鏡の山(かがみのやま)・松平定信(まつだいらさだのぶ)白河藩主
湖の こゝもからみの 山なれや こゝろうつさぬ 人しなけれは
|
|
真萩が浦(まはきがうら)・芝山前大納言持豊(しばやまさきのだいなごんもちとよ)
かけひたす 波も錦に よせかへる 真萩が浦の 花ざかりかな
|
|
錦の岡(にしきのおか)・加納久周(かのうひさのり)伊勢八田藩主
さざ波の なみに浮める 花紅葉 にしきの岡の 春秋の色
|
|
月待山(つきまちやま)・広橋伊光(ひろはしこれみつ)従一位准大臣
うちむかふ 月まつ山の きり晴て さきたつひかり そらにくもらぬ
|
|
月見浦(つきみがうら)・鳥丸資薫
たくひあらし 出しほの影も 秋にすむ 月見かうらの なみのみるめは
|
|
常磐清水(ときわしみず)・牧野忠精(まきの ただきよ)越後長岡藩主
萬代を 懸てむすはん 深みとり ときはの清水 たへぬ涙に
|
|
松風の里(まつかぜのさと)・小笠原長尭(おがさわらながたか)陸奥棚倉藩主
世のちりは よそにはらへる 松風に この里人や 千代おくるらむ
|
|
松虫の原(まつむしのはら)・佐竹義和(さたけよしまさ)出羽久保田藩主
旅ころも ゆきゝかざねて いく秋か めてみん千世を 松むしの原
|
|
下根の島(しもねのしま)・大久保忠眞(おおくぼ ただざね)相模小田原藩主
せきのうみや 下根の嶋の 秋くれて 月かけさゆる あしのむら立
|
|
みかげの島(みかげのしま)・有馬誉純(ありましげずみ)越前丸岡藩主
神のます みかけのしまの 松か根に とはにそよする なみの白ゆふ
|
|
千世の堤(ちよのつつみ)・堀田正敦(ほったまさあつ)下野佐野藩主
雨風に ゆるかぬ千世の 堤こそ くにを守りの すかたなりけれ
|
|
小鹿山(をしかやま)・阿部正精(あべまさきよ)備後福山藩主
をしか山 月にはなれも つまこひの うらみやふかき 関のみつうみ
|
|
八聲村(やこえむら)・土井嘯月(どいしょうげつ・利徳としなり)三河刈谷藩主
明けぬよの 夢や覚ると 庭つとり やこゑのむらに 行てねましを
|
|
有明崎(ありあけざき)・廣橋胤定(ひろはしたねさだ)従一位
しら川の 関のやま風 ふくるよの 月かけてらす 有明かさき
|
|
千代松原(ちよのまつばら)・三條實起(さんんじょうさねおき)従一位右大臣
立ならふ みとりの色の さかへつゝ すゑ限りなき ちよの松原
|
鳥丸資薫は烏丸資董であろうか。
薫(クン・かおる)は常用漢字で、董(トウ・ただす)は表外字の別字。
烏丸資董(からすまるすけただ)
安永元年・明和九年九月十五日(1772年10月11日)誕生
文化十一年五月二十日(1814年7月7日) 四十三歳死去。
父親-烏丸光祖(からすまるみつもと)正二位権大納言。
母親-家女房。
藤原氏・幼名-象丸・号-清浄院。
室-飛鳥井雅威(正二位・権大納言)女。
文化元年4月1日(1804年5月10日)任参議。
文化十年~文化十一年権大納言・正二位。
采梁渚(さいりょうのなぎさ)へ回り関山を遠眼鏡で見た、此処から東南三十丁ほど先に見えるのが関山(せきさん)。
共楽亭からは真西に那須の山々が見えるという、距離にして六里程だという。
「そうだ、須賀川で見せて貰った曽良日記には関山へ登ったと出ていた。那須から回り込んで関の明神から古関を廻り関山にある寺を参詣して白川を抜けて矢吹まで出たと有った。どうも東西南北行きつ戻りつしたように書いてある。山から白川へ一里半とあった」
那須湯本~芦野の遊行柳~境の明神~小坂~白坂~旗宿~古関~関山~白河~矢吹~須賀川。
四月二十日より
一 芦野ヨリ一里半余過テ、ヨリ居村有。是ヨリハタ村ヘ行バ、町ハヅレヨリ右ヘ切ル也。
一 関明神、関東ノ方ニ一社、奥州ノ方ニ一社、間廿間計有。両方ノ門前ニ茶や有。 小坂也。これヨリ白坂ヘ十町程有。古関を尋て白坂ノ町ノ入口ヨリ右ヘ切レテ旗宿ヘ行。廿日之晩泊ル。暮前ヨリ小雨降ル
一 廿一日 霧雨降ル、辰上尅止。宿ヲ出ル。町ヨリ西ノ方ニ住吉・玉嶋ヲ一所ニ祝奉宮有。古ノ関ノ明神故ニ二所ノ関ノ名有ノ由、宿ノ主申ニ依テ参詣。ソレヨリ戻リテ関山ヘ参詣。行基菩薩ノ開基。聖武天皇ノ御願寺、正観音ノ由 。成就山満願寺ト云。旗ノ宿ヨリ峯迄一里半、麓ヨリ峯迄十八丁。山門有。本堂有。奥ニ弘法大師・行基菩薩堂有。山門ト本堂ノ間、別当ノ寺有。 真言宗也。本堂参詣ノ比、少雨降ル。暫時止。コレヨリ白河ヘ壱里半余。中町左五左衛門ヲ尋。大野半治ヘ案内シテ通ル。黒羽ヘ之小袖・羽織・状、左五左衛門方ニ預置。矢吹ヘ申ノ上尅ニ着、宿カル。白河ヨリ四里。 今日昼過ヨリ快晴。宿次道程ノ帳有リ。
○白河ノ古関ノ跡、旗ノ宿ノ下一里程下野ノ方、追分ト云所ニ関ノ明神有由。相楽乍憚ノ伝也。是ヨリ丸ノ分同ジ。
「甲子郎、古関に有る花月様の碑を見ていないぞ」
手控えを出してみている。
「五日旅立ち、白川~越堀迄七里十二丁と有りますから遠回りしますか」
「白川から関山、古関を廻って街道へでて芦野でどのくらい見ればよかろう」
生沼は「棚倉街道から関街道で芦野まで遠回りで七里二十丁程。街道は五里一丁」と甲子郎へ伝えた。
甲子郎は控えを見ながら計算している。
「二里で一刻(百二十分)、道が険阻の分と山へ登れば半刻、見物に刻が掛かれば半刻、〆て二刻、のんびり五刻の予定でいたので急げば六刻半ですか」
卯の刻に出て酉の下刻だが十二時間なら大丈夫だろうという。
「遠回りしても九里二十七丁とみれば十分。四時に出て越堀に十六時、悪くも夕暮れ前の申の下刻でも十八時」
「ホトトギスも聞き飽きたから茶見世で名物でも食いながら回り込むか」
生沼も板屋の一里塚迄付き合うという。
「板屋の一里塚からなら桝形が閉まる前に戻れそうで、悪くても祖父母の家に泊まります」
道順は生沼が言うのを甲子郎が書き取った。
「棚倉街道から別れて南湖で関街道へ入るのが近道だ」
白川“ やなぎや ”柳下源蔵~一番町~九番町桝形~南湖千代の松原~五徳村~関山成就山満願寺~古関~芦野宿~越堀宿。
「先ほど関山から白川一里半とおっしゃりましたがこの道順だと二里半は有るはず。五徳村で一里に為るでしょぞ」
「確かに。采梁渚(さいりょうのなぎさ)から遠眼鏡で三十丁は先に見えた。曽良の白川で尋ねた家しだいなのだろう」
境の明神の南側に黒羽藩と白川藩の境が有り、古関のあたりにも領境が有ると言う。
領内を出るまで監視しないと報告が不十分と笑わせた。
三蔵と十郎にも生沼は同行を勧めている。
「行く気が有るなら横目付の頭への許可は明日儂が取るよ」
「明日の朝までに親の了解を取り付けます。今日閉門に遅れても三蔵の家に泊まると言って有ります」
二人が言うので次郎丸も了解した。
共楽亭から見える明後日の朝日は、屏風山事問月峯の北へ卯の刻の後で出るか峯に邪魔されて明るくとも朝日が見えるのが下刻頃だろうと生沼が言う。
「それで屏風山ですか」
「三蔵は良い事を云うが、秋には山に邪魔されないだろう」
「昔月の出を待って、邪魔された人でもいたんじゃないですか」
機転が利くと十郎に褒められている。
「確かに城下で見る中秋の月は出が東に近い三蔵は正しいよ」
生沼も認めている。
十郎は自分の屋敷からは、東の小山の頂きに酉の鐘の一刻(いっこく・15分程)後に昇って来たという。
玉女島(ぎょくじょとう)は松嶼(しょうしょ)、漕ぎ寄せて辯天社に参詣した。
午の刻に近くなり前に見える番所の船着きで番人に舟を戻した。
馬を連ねて棚倉街道へ出ると爺(じじ)婆(ばば)の家へ向かった。
爺(じじ)婆(ばば)の子供に孫たちが集まって賑やかな振る舞いだった。
申の下刻には大手門の前で三蔵と十郎に分かれて“ やなぎや ”へ戻った。
源蔵は「白川近辺で百二十両に為りました」と祝い金が増えていると顔がほころんだ。
「予定の半分国元に預けたから分けて持ち帰ろう」
「では明後日の夕刻までで締めて御預けいたしましょう」
「明日は三人此処に置いてきぼりだが、特別御馳走でも出してくれとは言わんよ」
甲子郎がそんなことを言って巫山戯(ふざけ)ている。
|