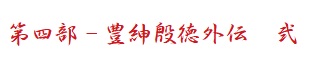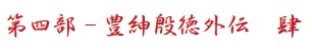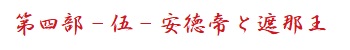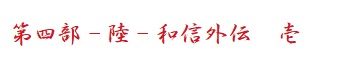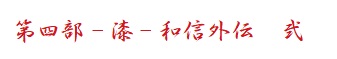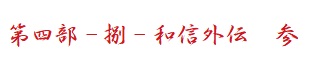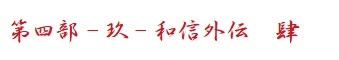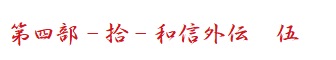|
“ 薬研掘
”
文化十一年八月十七日(1814年9月30日)・“薬研掘
千十郎が持って来てくれた領内見とりに照らすと、この日程の間に長楽寺から姨捨を見渡せるという。
「矢代を渡って八幡村なら十人くらい泊めて貰えます。八月は少の月でこのようになりますかな。手前の稲荷山は上田藩で本陣も有り申す。渡しは向こうへ渡っておいた方が宜しいかと。我が領分は桑原宿に藩の本陣が有り申す」
「確か宿屋営業は禁止されたと」
「藩の名での継立は出来もうす」
「今回は無理を通さぬ方が良いだろう、松本へ脇往還で行くわけでもない」
十七日目・鼠(九月五日)
十八日目・矢代(九月六日)八幡もしくは稲荷山
十九日目・田野口(九月七日)
二十日目・小市(九月八日)できうれば善光寺へ
小市の渡し、丹波島の渡しで善光寺へと云う。
二十一日目・善光寺(九月九日)
大野は領内の見取り図で「此の月見堂より八幡で二十町くらいですかな」という。
「月見堂は近くにあるとしか。矢代の渡しから八幡宮まで二里と聞いており申す。渡しから善光寺へ四里程度。五日で周るには余裕が有り申す」
田野口と八幡で三里程と記憶通りなら、昼まで月見堂で刻を使えるという。
田野口から小市も三里のはずで小市と善光寺は二里程度と云う。
どうやら幼少より領国の様子は教えられてきたようだ。
若(も)しかすればもっと細かく知って居そうに思えた。
吾郎は親子三人旅支度でやってきた。
“ なほ
”と“ つかさ
”にも挨拶させた。
「こいつは“ おとき ”、辰の刻の辰を書いてときと読むんでございます。娘はくさかんむりに方向の方で“
およし ” で御座います」
“ なほ
”と“ つかさ
”も交えて旅の話しに為った。
「昨日、手形の準備で寺へ出て俳句のお仲間に更科姨捨月之弁という一文の抜書きを見せて貰いました。監物様の勧められた八幡の近くと知れました」
寺受け証文は信濃善光寺、上州温泉めぐりの療治としてある。
“ 思ふにたがはず、その夜さらしなの里にいたる。山は八幡といふさとより一里ばかり南に、西南によこをりふして、冷じう高くもあらず、かどかどしき岩なども見えず、只哀ふかき山のすがたなり
”
「肝心の月見堂と姨岩には触れて居りませんでした。おばとしてあり姨ではなく姥の字を別ランで使っておりました」
次郎丸は可笑しくて笑った。
「おいおい、師匠幾ら家族の前でもその調子じゃ疲れるぜ。普段通りでいいよ」
神さんと娘もほっとした顔をした。
「それと娘の名を付けたのは誰だい」
「おたつの父親ですが」
「大分物知りだ。おっかさんの辰の字は“ よし
”とも読めるのをご存知の様だ」
「あればれちまいましたか。字を替えて親娘揃いだと教わりました。孫が出来たら“ のぶ
”と読める字だと言われちまいました」
娘は「若さまがちゃんに更級の和歌を教えてくれたと。あたいにも覚えられますか」と言いだした。
「更級の話は多くて大変だ。小野小町なら覚えやすい」
“ あやしくも なぐさめがたき こころかな をばすてやまの つきもみなくに
”
書いて渡すと、濁音を抜いてもう一度読み上げた。
「小町集と云う古い時代の歌集に有るのだが、小町は本当にいたのかと疑問は多い」
「いないのに歌集が出るのですか」
「紀貫之と云う有名な人より前の人だからね。あれも小町、これも小町と寄せ集めたようだ。姨捨伝説も昔は孝行者を称えた話だったのをつくりかえた人がいたんだ」
延暦十六年(797年)完成-続日本紀に建部大垣
神護景雲二年五月辛未二十八日(かのとひつじ・768年)条
更級郡の建部大垣(たけるべのおおがき)は性格が恭順で親孝行であった。
水内郡の刑部智麻呂(おさかべのともまろ)は友情厚く苦楽をともにした。
水内郡の倉橋部広人(くらはしべのひろひと)は私稲(しとう)六万束を出し百姓(ひゃくせい)の負債を償(つぐな)った。
政府から終身の田租を免除されている。
孝行ぶりを讃え、税金を免除したという記述が続いている。
・小野小町(あやしくも 慰めがたき心かな 姨捨山の 月も見なくに)
・古今和歌集-詠み人知らず(わが心 慰めかねつ 更級や 姨捨山に 照る月を見て)
・新古今集-伊勢(更級や 姨捨山の 有明の つきずも物を 思ふ頃かな)
伊勢守藤原継蔭の娘-三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。
・新古今集-躬恒(更級の 山よりほかに 照る月も なぐさめかねつ このころの空)
凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)姓は宿禰、凡河内国造の後裔。
・大和物語-姨捨説話。
・拾遺和歌集-紀貫之(月影は あかず見るとも 更級の 山のふもとに 長居すな君)
・更級日記-菅原孝標女(菅原孝標の次女)。
信濃国の更級郡に夫(橘俊通たちばなとしみち)が国司として派遣したことによる命題。
・今昔物語-信濃国姨母棄山語。
・能-世阿弥・姨捨・伯母捨(おばすて)
「そういゃ、若さんの時計、昼夜同じでしたかね」
「そうか、十一日はもう出た後か、同じことは同じだが一時間ほど狂っている」
「一時間もですかい」
「明け六つは日の出前二刻半(一刻14分24秒)、暮れ六つは日の入り後二刻半だからそれを入れなきゃ同じだがな。これから丁度昼と夜の計算が合ってくる」
「どうしてですの」
「お芳は二挺天符を見たこと有るかい」
「祖父の家に有ります」
「あれを小さくしたのを旅では持って行くのさ」
棚から取って手渡しした。
「長崎へは時々来るそうだが高くてね。一日はその短い針が二回りだ」
「じゃ今なら半日で一回りなんですね」
「一番上の所へ二つの針が揃うのが昼の九つと、夜中の九つに合わせるのさ。今月二十六日から九月二十六日の間は長い針二回りで一刻(いっこく)に成る」
「二挺天符のように、錘で釣り合いは採らないのですか」
「これを作る国では此方とは違っていてね、一日を二十四に割り振って時刻を見るんだよ。天文方の作る暦には細かく出ているよ」
寛政暦
宝暦暦に替え寛政十年(1798年)から採用された太陰太陽暦。
高橋至時(たかはしよしとき)、間重富(はざましげとみ)達が編成し、天保十三年(1842年)まで四十五年間使われた。
京都の春分と秋分の日出、日入前後、二刻半(36分・一刻14分24秒)の太陽位置を、球面三角法を使って計算した。
太陽の中心伏角が7°21′40″になる時刻であった。
石町の鐘は、北は本郷、南は芝浜町、東は本所入江町、西は麹町、飯田町辺りまで聞こえたという。
本来の卯の刻とは子の刻九つから数えて六つとすることが混同されていますが、正確ではないそうです。
明け六つはあくまで日の出前二刻半の事ですが此方は庶民の混同をそのまま使っています。
次郎丸は道中各宿場での刻の鐘が、どのくらいずれているかも楽しんで居るのだ。
お辰(とき)は「若さん、草津の湯は温泉番付で東の筆頭、大関を張っておりやす。あたいは一生一度でいいから行きたいと思ってやした。図らずも宿六ともどもご一緒させて頂きうれしゅうござんす」とようやく口が利けた。
「親娘で初旅だそうだが沓掛までは歩く距離が長い、未雨(みゆう)に早めに軽尻(からじり)を都合させる。沓掛からは峠は在っても景色が良いし一日も距離を短く取った」
「お江戸から四十八里(しじゅうはちり)、箱根の倍と言いますが」
「今回は大回りするので五里は長いが七日掛けることにした」
大野と監物が手分けして寫した日程を各自に配った。
「善光寺からは親子三人で付近を廻るかついて回るか、それまでに決めればよい。領内十日前後の予定だ。九月二十八日までに板鼻へ戻れるようなら伊香保へ回るつもりだ」
「水沢観音の伊香保でしょうか」
吾郎そっちは行くつもりでなかった様だ。
「片道七里、往復長くて六日取れたら一所に廻ろう」
「草津の湯に善光寺だけでもとっさま、かかさんびっくり仰天していましたのに、伊香保も廻れるとは嬉しうござんす」
家族の話題で次郎丸の事が良く出る様で、のっけから親しみを覚えているようだ。
先々大宿に本陣、脇本陣、茶屋本陣が待受けているとは未雨(みゆう)は教えていない様だ。
喜多村新之丞が上田までは押える手はずだ、すでに草津までは連絡が済んでいるという。
早朝の見送りは来られぬというので、陽が落ちると遣ってきて旅程の確認だ。
大野が未雨(みゆう)親娘を引き入れたので繋ぎも付け易い。
「矢澤さま。屋代の渡しを越えるならぜひ稲荷山宿でお泊り下さいませぬか」
「何か事情でも」
「本年加賀様の御暇は東海道より越前を抜けてお戻りです。いつもならご休憩も有るのですが。ここはご近所のよしみで若さんの顔つなぎに」
「身分を明かさずにか」
「お頭という事は内内でお知らせをします。実は東海道を通る目的が、寄り道で京の都へのお許しを得たがっておられるとか」
前田斉広(なりなが)・文化十一年三十三歳。
享和二年(1802年)二十歳で家督相続。
最初の正室-享和三年(1803年)十二月に迎えた琴姫
(尾張九代・徳川宗睦養女、高須七代・松平義当長女)。
文化二年(1805年)八月、病気療養の為実家の高須藩邸に戻り、一年後の八月に離婚成立と為った。
継室-文化四年(1807年)十二月十八日、摂関家の鷹司家から夙姫(あさひめ・鷹司隆子)、関白鷹司政熙次女を迎える。
天明二年七月二十八日(1782年9月5日)~文政七年七月十日(1824年8月4日)
四十三歳死去。
改名 亀万千→勝丸→犬千代(幼名)→利厚→斉広。
普段の参府に暇は北国下街道十二泊十三日の旅程。
江戸までは百十九里程度。
平均的な行程
初日・四里-今石動
二日目・四里-高岡
三日目・十一里三十町-魚津
四日目・八里四町-泊
五日目・六里三十四町-糸魚川
六日目・十二里十八町-高田
七日目・十二里八町-牟礼
八日目・十二里二十二町-坂木
九日目・十里六町-信濃追分
十日目・十里三十一町-板鼻
十一日目・十二里八町熊谷
十二日目・十里八町浦和
十三日目・六里六町-江戸日本橋
・・・
上街道東海道経由・江戸~箱根~尾張~福井~金沢・約百五十三里。
文化十一年二月十三日に東海道を経て帰国することの許可を得る。
三月十四日に就封の暇を受け十六日辞見の後に出立し、品川に宿を取り、翌日より神奈川、鎌倉・江の島・大磯、三島、吉原、府中、金谷、浜松、吉田、岡崎、鳴海、起、柏原、大本(木之本)、晦日に今庄に入る。
今庄宿へ寄せ集められたのは人足四百人・馬二百匹で府中まで継ぎ立てをした。
四月一日より府中、金津、小松、四日に金沢に着いた。
十九日間、二千七百人余、費用銀千百貫(一万八千三百両)。
・・・
三月十六日江戸本郷藩邸七つ(午後五時前後)~品川本陣暮れ六つ(午後七時前後)
三月十七日。品川~神奈川
三月十八日・神奈川~鎌倉
三月十九日・鎌倉~江の島
三月二十日・江の島~大磯
三月二十一日・大磯~三島
三月二十二日・三島~吉原
三月二十三日・吉原~府中
三月二十四日・府中~金谷
三月二十五日・金谷~浜松
三月二十六日・浜松~吉田
三月二十七日・吉田~岡崎
三月二十八日・岡崎~鳴海
三月二十九日・鳴海~起
柏原~(彦根藩番場宿・摺針峠)~大本(木之本)
三月三十日・越前今庄宿
四月一日・府中町
四月二日・金津宿
四月三日・加賀領内
四月四日・金沢
文化十二年(1815年)参府延期が秋まで許された。
九月十四日参府のため金沢を発って、二十六日に江戸に入る。
文化十三年(1816年)・暇三月十六日江戸藩邸出立、二十七日金沢に入る。
文化十四年(1817年)・参府十月二十六日に出立、十一月九日江戸へ入る。
千十郎も他領ながら各本陣の経営が苦しいのは聞かされているようで、次郎丸の顔出しでどうなるわけでもあるまいとは思ったが新之丞の顔を立てて、その日は稲荷山と納得した。
「さっそく沓掛から先、善光寺まで手当てしますが。善光寺はお三人ご家族で寛げる宿を手配します」
お芳は「気にせんでも宜しいのに」とお決まりのお愛想を言っている。
「本陣の隣のわたや仁左衛門、ここは六人。ふぢや平左衛門に伊勢屋さん一家。連絡では間が七軒とか、ほとんどが旅籠だそうです。“
ふじや ”が多すぎてまごつくなと言ってきました」
楽旅ですよと言う、善光寺大本願の方に近しいかたよりの話として聞かせてくれた。
寛政二年に九歳(届け出は十二歳)の虎姫は京から江戸青山善光寺へ入り、寛政三年十月信濃善光寺へ出向いている。
寛政二年(1790年)九月十八日京都を出立し十月五日青山に入寺。
寛政二年(1790年)十月十五日得度式、智昭の名が授けられ冬袈裟二領が贈られた。
寛政三年(1791年)十月二十二日~二十八日(六泊七日)
「いくら御駕籠での移動でも中御門家の御姫様(おひいさま)には大変な道中と推察できます。届出はおよしと同じだ。精々駕籠に軽尻(からじり)を強請りなさい」
新之丞はまだ見習いと称している、うるさ型には、鉄爺が話しを付けるほうが簡単だからだ。
|