第伍部-和信伝-伍拾伍
第八十六回-和信伝-伍拾伍
阿井一矢
|
第伍部-和信伝-伍拾伍 |
||||
|
第八十六回-和信伝-伍拾伍 |
阿井一矢 |
|||
| 富察花音(ファーインHuā yīn)
康熙五十二年十一月十八日(1714年1月4日)癸巳-誕生。 |
豊紳府00-3-01-Fengšenhu | |
| 公主館00-3-01-gurunigungju |
|
“ つるや甚右衛門 ” 文化十一年八月二十二日(1814年10月5日)・沓掛宿~狩宿宿 “ つるや甚右衛門 ”を出る用意は六つには済んで、おしんは女中たちと別れを惜しんでいる。 馬も揃い少し早いが出ることにして表へ出ると作右衛門旦那も見送りに来ている。 「やぶちゃで見送りとはおしんもくねぽい」 おしんは笑って「大勢で見送られるとは大人になったという事だにと旦那が言ってるの」とお芳に言った。 馬を引き連れて一町先の用水を石橋で越し、右手の草津道へ向かった。 草津道道しるべの左側面に刻まれた文字は“ 右 く さ つ へ ”。 「寛政十一年、十五年前か。馬頭観音らしくないなぁ」 「観音様、菩薩様も大勢居られるから」 髪型に覚えがないが、おしんは「観音様と聞いた」で済ませた。 鼻田峠を登り出すとおしんがお芳の馬に寄せて「この先峠まで三十三町に三十三体の観音様の道案内が有るだら」と声を掛けた。 昨晩話していた茶屋へ続く百観音の事だ。 勘四郎と云う分り茶屋の主(あるじ)が浄財を集め、茶屋からの三方へ一町ごとに建立したという。 台座別で三尺三寸と話していた、茶屋に有るのは中心仏で台座が高いのだそうだ。 「ほらでてきましただら」 馬方が山側を指差した。 緩やかな上りは六里ヶ原通りと云う様に浅間の裾に広がっていた。 分り茶屋は分去り茶屋とも言われこの先は大笹宿が左へ、狩宿宿が右への追分に有る。 沓掛から百丈ほどの高みで同じくらい降りてゆくそうだ。 茶屋は引き臼からそばの香りがしている。 秋の新蕎麦にしては早い。 「若さん、戸隠の夏蕎麦だに」 おしんがもうそんな口を聞けるようになっていた。 大笹関所迄二里程、狩宿関所は一里二十町だと女将が教えてくれた。 草津へ行くが向こうでも蕎麦の旨い見世が有るか大野が聞いている。 「旦那方も蕎麦ぁ召し上がるならたっぷりとってもありましだ。今切ってるきにゆでるだけですよう」 朝の客がのんびり待つから頼むというので大目に捏ねたそうだ。 おしんが「おたのもうします。十一人有りますの」とお芳からでも習ったような口を聞いた。 「少し多めに盛っても有りますよ」 「お願いします」 辛口の汁は江戸っ子好みだ、馬方も旨そうに啜っている。 大野は「草津から戻るときも食べよう」と未雨(みゆう)と話している。 「二人前で足りますか」 「夕刻におしんの饂飩が食べられる。今は良い」 話しはかみ合っていないのに大野は気づいていない。 おしんが饂飩は寝かせるほど美味いが一刻半でも旨くするコツがあるという。 蕎麦が一人十六文、茶と黄な粉餅で十八文、これが十三人分、女将は大野が勘定と云うや「四百四十二文になりました」という。 百文の緡(さし)五本出して釣りを五十八文貰った。 馬方に四文銭十枚括りを三人それぞれに二つ「駄賃の上乗せだ」と出している。 大野持ちは二頭六百二十文、昨晩番頭は百文の緡(さし)に四文銭二十枚を釣りですと持ってきた、その時から用意はしておいたようだ。 急いで出る者、のんびり駕籠を待たせる者、軽尻(からじり)で来て「蕎麦を頼む」と横柄な者、茶見世も混んできた。 表の観音は今までのより台座が高い、道しるべは苔が生じている。 “ 元禄十六年 ” “ 右ハくさつ道 ” “ 左ハ大さ々道 ” “ 泉州堺 小西八兵衛 ” 「百十年ほどまえだ」 「おと、此の年前後は詳しいね」 芭蕉の活躍の頃の事は頭にあるのだ。 峠したに橋が有る、一里塚が出て、三十三観音は通り過ぎ、狩宿宿の関所が近いという、お諏訪様の前で馬を降り、身なりを整えて女三人は手形を用意した。 お辰(おとき)親娘のは碓氷関所の印も有る。 番人は草津に善光寺と聞いてうるさく改めはしないで通した、橋を渡ると宿場は鉤手(曲尺手・かねんて)先。 茶屋本陣“ 黒源
”は鉤手(曲尺手・かねんて)を曲がった追分の正面にある。 宿札“ 白川藩本川次郎太夫様御一行様 ”が大きい字で出してある。 黒岩源右衛門の茶屋本陣は間口八間ほどだが奥が深い造りだ。 沓掛宿から草津道を五里二十六町十五間で狩宿宿。 およそ四刻(とき・八時間)で着いている。 つるやでは此処から一日で草津へ入れると番頭は言っていたが大野は予定通りに二日に分け昼前に草津入りを計画している。 喜多村新之丞は手配も完璧で、声をかけるや足盥が用意され主人も挨拶に出てきた。 中間が馬方から荷を受け取って入ってきた。 ひとり増えたと気が付いたようだ。 「古宿のおしんだら」 小諸の姉からの土産だらと羊羹を三本取り出した。 「つるやさんでご一緒させて貰えと一緒に来ただが」 土間の続きに竈が見える。 「お客さん方饂飩が夕飯前に食うというので仕度したいだに」 「ごしたいしとらんけ」 ここらは上州訛りと言うより信州に近いようだ。 「おらほ、ごしたいなんどしとらんさぁ」 約束でもしたか、お芳にも手伝わせて荷を広げた。 沓掛で粉にしたうどん粉に塩を振りかけ、鉢で捏ねている。 「その日のお日様具合で塩の量もかえるんだに」 五合徳利からざんぶりと粉の上に振りまいた。 本陣の女将さんは「お酒なの」と聞いた。 鉢から振り向いて「馴れた沓掛の水ですよう」と言って捏ねに戻った。 「ほぉけぇ。家の水もうまいさ」 又振り向いて「水の味を確かめてからでは饂飩が落ちつかんだに」と又捏ねている。 渋紙をだし、包むと晒しで包み込んだ。 「半刻(とき・六十分)で美味しく為るだら、でも一刻(とき・百二十分)待つ方がもっといいだら」 お芳を呼びに来たので土間へ降りると包を二つに分けて一緒に踏ませた。 手を取り合うとうまく調子が揃った。 一度広げて丸め直して又踏んだ。 「馬子唄、唄っていいだに」 女将さんが許すという。 女将は「はい、はい」と良い声で促した。 “ 成夫(なれそ)なれそに ヨ~ こむろしゅに エ~なれそ ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 灰(あく)の ナ~ 垂糟(たれかす) ヨ~ イヨ 後(のちゃ)廃留(すたる) ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 小諸出て見りゃ ヨ~ 浅間の エ~山に ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 今朝も ナ~ 三筋の ヨ~ エ~煙立つヨ~ ” 「はい、はい」 “ 小諸出抜けて ヨ~ 唐松 エ~ 行けば ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 松の ナ~ 露やら ヨ~ エ~涙やらヨ~ ” 「はい、はい」 一廻りごとに三度つつみなおした。 「四度で良いのね」 「そう他の言葉も入るけどその日の気分で替えるだが」 最初の出だしを気が乗ったじゃと唄った “ なれそ なれそに~ 小室衆にゃ~なれそ~ きみのおそばにぃ~ ついなれそ~ ” 「寝かしとく間にうたうだが」 そういいながら女中に頼んで竈の大鍋に水を張り、火を焚かせている。 女将は火鉢の鍋で昆布の出汁を取っている。 いつの間にか手順を決めていた。 “ きみの~こにわの~ 松がえ~見れば~ 鶴の~巣篭り~いよ~としどしに~ ” “ いわい~めでたのぅ~ わかまつ~さまよぅ~ えだも~さかえるぅ~ はも~しげるぅ~ ” 竈の水を張った大鍋はふわふわ湯気が出てきた。 もう一つの竈では湯が沸いている。 「温いのんと熱いのん。それとつめたの注文聞いてきて、その間に切りそろえておく」 おしんの饂飩は本陣の主人夫婦にも好評で半月と云わずもっといて貰いたいという。 つるやと年内の約束で雇われたので今回のように半月約束以上は出来ないと断りを言った。 大野は「これは宿の勘定と別にわしらから褒美じゃ」と南鐐二朱銀を二枚包んで渡した。 「おひゃぁ、遠慮なんどしませんだに」 礼なのか解らぬ物言いで面白いと次郎丸は思った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“ 黒源
” 文化十一年八月二十三日(1814年10月6日)・狩宿宿~長野原宿 早くても二十九日に此処を抜けて沓掛から小諸へ出るというと主は「おいでを楽しみにしております」という。 昨晩おしんが興に乗って馬子唄を数々披露し、客だけでなく家族一同が楽しめたと喜んでいたのだ。 三味も無しに唄う声は素晴らしいと千十郎も手放しの褒めようだった。 六つに問屋から二頭の乗懸(のりかけ)が来て、荷は振り別けの荷籠へ塩梅を見て納めた。 “ 黒源
”を出て宿内を万騎峠へ向かった。 万騎峠は頼朝が狩宿から万騎の兵を従えて峠を越えた伝承が残る。 自然石にでもほったか道しるべが有る。 “ 右 くさつ道 左 志ん州道 ” 次郎丸が見ているので馬方が止まった。 大野は百文の緡(さし)を二本ずつ二人へ「駄賃の上乗せ」と渡した。 お諏訪さまの先に遠くからでもわかる賑わう町が見える。 須賀尾宿迄大野が三里は有ったと言っている、宿内は往来の人で溢れている、用水路が有るので左側の見世前は板橋が有る、いきなりその用水路は右手へ流れを替、一町ほど先で又左手へ戻って居る。 菓子屋と云う店で“ かわらせんべい ”の真新しい暖簾を見て未雨(みゆう)は大量に買い入れている。 大福、塩饅頭も有るのでそれも十五ずつ買い入れた。 高橋屋の三軒先、問屋場で乗懸(のりかけ)を乗り継いだ。 宿の先は緩やかな上り坂だ。 須賀尾峠で振り返ると未雨(みゆう)は一茶の句でこの辺りで詠んだらしいのが有ると思い出した。 “ 麦わらの まんだらもおれ 筥根山 ” おれは織れだという。 「六年ほど前だと言います、須賀尾に泊まっています。江戸を出て草津への道でいきなり相模の箱根なのかと、いつか訊こうと思っていても今年も会えて居ません」 峠を降りてゆくと狩宿宿辺りで幾つもの川を集めたという須川に琴橋が架かっていると馬方が大野に話している。 「狩宿宿から其処の追分まで田舎道は有るので利用する人は居ますんだが」 隘路が多く、馬方たちの嫌がる道だそうだが、距離は近いので、地の者は其方を通るという。 「そうか、沓掛から草津へ十里はそんな抜け道の事か」 「そうだが。なからそのくれえですだが」 もう一人の馬方が須賀尾乗継で千百五十二文、抜け道は二百八十八文で良いだろうと交渉されますが、狩宿問屋は五百七十六文でなければ引き受けませんだが」 「着くのが早けりゃ行けと云うのは多いだろうに、この乗懸(のりかけ)でも五百七十八文が二回だ」 「決まりが五百七十六文相対上乗せ五百七十六文、軽尻(からじり)でも四百三十二文に上乗せ四百三十二文で受けるようにいわれていますんで」 「いちんち一回じゃあまりいい儲けじゃないな」 長野原宿の手前に甘酒の休み茶見世が有るので一休みした。 大野は百文の緡(さし)を二本ずつ二人へ「駄賃の上乗せ」と渡した。 親娘は宿が目の前なので歩くという。 “ こまのや ”と云うと馬方が先にたって案内した。 宿は三部屋と云うので三人ずつに分けた。 大野は部屋に落ち着くと「どうにも里程と乗懸(のりかけ)の賃金の計算が合わん」と言いだした。 「峠の難度で何割増しでもしているのだろうぜ」 未雨(みゆう)が大福と瓦煎餅を持ってきた。 噛みごたえのある瓦煎餅は蕎麦の香りがした。 ほう珍しい事だと大野は気にいった様だ。 「須賀尾は周りと比べ大きくなりそうだな」 大笹街道、沓掛街道、信州街道、草津街道、交錯して人の行き来は多い。 問題は冬場だと千十郎が言う、極端に人の往来、荷の往来が減るので人足稼ぎ、荷駄稼ぎが食えないという。 冬場に氷豆腐、氷餅、轆轤細工ではそれほど儲けが出てこない。 「やはり松代、上田で紬の生産を増やすようだな」 「年中稼げるのはそれが一番でしょうが。松代の物では高値が付きません」 江戸で売れるのは結城紬に上田紬いわば名産品だ。 「八田が早々と食い込んできたのは結の販路に期待してのことだ。屑繭だって相場が揚がれば苦しいのは上田も同じだ、上田で佐藤本家と協力させようと考えては居るんだが」 次郎丸は上様に利用されるのは承知で、零細の機織りに仕事を増やすことを考えている。 「江戸で酒田屋さん以外はこれから来る二人だけですか」 夷屋は買い入れを助けると言ってきた。 本庄中屋の江戸店が協力するのか、資金提供なのかはまだこれからの事だ。 わずか二町ほどの宿場だが草津から降りてきた湯治客、これから上るという人たちの往来が多い。 一休みの立場のような間宿(あいのしゅく)に近い。 未雨(みゆう)が狩宿宿から諏訪神社が増えて来たという。 「女中が言うにはこの先の羽根尾にもあるそうです」 お芳が来て「おと、宿場の中見てきていい」という。 次郎丸が「俺と二人なら出てもいいよ。一人はだめだ」と云うと「若さんならいい用心棒で、疑問にも答えてくれる」という。 「これ、若を案内人みたいに言うな」 大野が笑いながら言う。 “ こまのや ”の前は荷駄の列が草津へ向かって追分を進んでいく。 こっちはおしんの姉が嫁いだという小雨村への道だ。 「若さんて一度読んだ本は覚えるって本当なの」 「興味のある物だけだよ」 「善光寺案内に、草津温泉案内、伊香保温泉案内は覚えてきたのですか」 「道筋に中の様子は画入りで出てるけど肝心の道順が大雑把だ。草津へ入るにはいくつも道があるが、宿場の名前だけで大野も苦労している」 鳥居が有る「この神社もお諏訪様だと聞いたわ」と言って拝んでいる。 「温泉もお諏訪様あるかしら。神田明神と親子でしょ。無事を言づけても伝えてくれるかしら」 神田明神は一ノ宮大己貴命(おおなむちのみこと)、諏訪明神は上社本宮建御名方神(たけみなかたのかみ)。 「信じて拝めば心が通じるよ」 駒形(こまかた)の諏訪明神が産土だよ云うが、神田明神は江戸総鎮守だ。 「温泉にも諏訪神社ありましたか」 「俺の見た絵図には見当たらなかった、集めれば違うことが出るので悩むのは大野だ」 「若さんは悩まないの」 「そうだなぁ、例えば草津温泉は日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が見つけて腰掛け石が有る。行基が草津で祈祷すると、そこから温泉が湧き出した」 「二人のどちらかなの」 「判らないのは二つ説があるでいいのさ」 「峠で馬方が頼朝が越えて万騎峠の名が附いたと言っていただろ、その時に草津で新しい源泉を見つけたともあるからその湯にも浸かろうか」 お芳が持って居る案内は名前が箇条書きでどこに位置しているか想像もできないと嘆く。 宿場の先まで行って戻ることにした。 「大野様、草津は何処へ泊まるか決まりましたか」 「連絡はないがな。行けば案内人が出迎えると言づけは有った」 大野が見ていた案内図は冊子をばらして板で挟んである。 「肝心の所が見えないが薬師堂が書いてあるので此処が中心で街が広がって行ったようじゃな」 彫り師が別なのか広小路の大きさが違い過ぎた。 「右のほう、是を彫り直せば売れるのにもったいないわ」 「これこれ、商売っ気を出すな。物持ちの主が趣味で摺らせた神社仏閣の見聞記だ」 もう一枚画で摺って出ていると折りたたんだ物を出して見せた。 二枚、いや三枚見比べ「東西がずれてる」と云う。 「よう気が付いた。行けば何とかなるくらいで宿の名は別の冊子で見る様だ。宝暦以後は草津七湯で五湯としてあればそれ以前じゃそうな」 其処には大宿十一軒の名と茶屋、料理屋、居酒屋も出ていた。 「さてこれが画のどこかが判らぬ」 次郎丸が「だから悩んでも無駄さ。春の東海道と同じで行きゃ判る」と笑い出した。 「是新しいわね、おしんの言ってた山本の名が有る物」 よく見ると宿屋の中に確かに山本が出ている、それも広小路とある。 「譲られたというが大分古くからの湯宿の様じゃ。同じ名の親類じゃろう」 画には広小路は分かるが宿はどれかが判別できない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“ こまのや ” 文化十一年八月二十四日(1814年10月7日)・草津入り 明け六つ(五時十五分頃)に食事を済ませ“ こまのや ”を旅立った、 問屋で約束の荷駄二頭へ荷を乗せた、身軽になった九人は新しい杖を渡され、山へ向かって進んだ。 津井村、勘木場村辺りは緩やかに登っている。 「草津は四百丈の高みと云うが、あと百二十丈ほどの登り道、残りは三里だ」 大野の言葉に馬方が、強い坂は殆どないと相槌を打った。 次郎丸はお芳に「ここで箱根の関所と高さは同じくらいだ、箱根湯本は沓掛位だ」と無駄話で励ましている。 「お爺は湯本へ毎年行くけど道は楽だと言っているわよ」 「小田原へ三日、湯本へは其処から二里もない」 「此の春もおとうが京(みやこ)へ行く前の十一日に出てひと月遊んでこられた、お婆(ばあ)は煩いのが居なくて気楽なもんだといっとる」 街道に川越しが無いので楽だとお芳が言っている。 「草津川は右手の山の向こうがわだが」 馬方が指差した。 左から上ってくる道が有る「こりゃ大笹の御関所へのみちじゃが」と教えてくれた。 休み茶見世で一息ついた。 残りは一里程だという。 大野は二人にそれぞれ百文の緡(さし)を二本ずつ駄賃に上乗せした。 長野原から一頭六百六十二文に上乗せだ。 「未雨(みゆう)師匠、草津には春秋庵加舎白雄師匠の碑は無いのかい」 「聞いたことありませんね。あっしの後に弟子入りした草津の人が芭蕉翁の碑を建てたくらいです」 その鷺白という湯宿の主は、加舎白雄が草津を訪れた安永八年夏に弟子入りしたという。 小雨村からの道が近づいて来た。 「もう草津へ入ったも同じだが」 入口町だともう一人が大野に伝えた。 入口番所はまだ話しだけの様だ形も見えない。 沼田藩真田家の時代入湯税だけで八百貫の収入に為ったという。 ひとり十日四百十六文、小判は大きく、銭にも価値のある時代だ。 百三十年前の延宝八年幕府領に為り廃止されている。 新田町の高泉寺の門前に問屋場が有る、其処で荷を降ろした。 坂を登り草津立町に着くと鉄之助爺が出迎えた。 「もう連絡が来たのですか」 「沓掛に着いたと連絡は受けた。二日は無理だろうと思っていた」 今朝長野原をでたと半刻(とき・六十分)前に連絡を受けたという。 「そうかそれで新之丞殿は草津まで手を回せたのですね。未雨(みゆう)にも内緒ですか」 「あれは今夏から新之丞付じゃから、あえて教えていない」 中町“ やまもと ”へ案内された。 お芳は大げさに驚いている。 此処にした何か理由でもあるかと思えば「此処は昨年から商売に参加した。古馴染みに頼まれて冬籠りで下へ降りぬ者を養成する手伝いじゃ」という。 四月八日から十月八日の温泉営業ではもったいないが、客が来なけりゃ食うことが出来ぬという。 津軽の冬を思えば温泉が有るだけましだという家族を紹介された。 「半年の内辛いのは十二月ですら、二十家族位に為れば安心ですら」 米、小麦、大麦、大豆を掻き集めているという。 「商売でも始めるんですか」 「一番は凍み豆腐(氷豆腐)じゃ。冬場の畑地も使える様にした。干し饂飩は出来る者を探さにゃならん。味噌に醤油は山の上ではどうにも商売にならん」 高野豆腐は人が増えればやらせるという。 「問題は生水でしょう」 「そういう事じゃ。雪を溶かして使うかと云う者もいたが、幸い此処の冷泉は冬も地熱のせいで凍らぬそうだ。不思議と硫黄の味はしないそうだ」 隣の部屋では並んで湯治の誓約書を出している。 旦那寺まで書きあげている、関所より扱いは厳しい。 番頭は布団や夜着などの枚数を書きだして計算に忙しい。 四泊五日で五日分は仕方ないが飯盛りは良いというので渋い顔だ。 吾郎が「此の金は番頭さんや女中、料理人で分けてくれ」と二十余りの包みを盆へ積み上げた。 遠慮などどこ吹く風とひとつ開けて驚いている。 南鐐二朱銀二枚入っていた、これなら女のお呼びなどない方が気楽だ。 鉄爺にお大臣一行だと吹き込まれてもいた様だ。 湯銭も一日十文で入り放題だ、一人五十文で五日は何処の共同湯でも入れるという。 沼田藩時代は湯銭の取立てが厳しく改易理由の一つだと噂が出た。 「女子に年寄は目の前のわたの湯が一番だが」と言う。 「江戸のお方衆はふんどし、湯文字はずして入りたがりますが、外湯じゃお付け下さいませぬと湯宿が叱られます」 権太はふんどしも一張羅を締めていくようだと笑わせている。 「使い捨てなら業者は喜びます。毎日新調は如何です、熱水で黄色くなりますだが」 中町“ やまもと ”は内湯も小さいながら備えたという、好みの湯を湯女が運び込むという。 山本重右衛門と名乗る湯宿の主の中年男と、もう一人少年のように見える者が来た。 二人は多くを語らず部屋を後にした。 「あの若いのが此処の湯の花の権利を持っておりますが、凍み豆腐の干場の畑地も貸し出しに同意してくれました」 「もしかして頼朝公落としだねの御子孫」 「湯の花屋三右衛門と言いますじゃ。父親とは知り合いでね」 書き入れが終わるとお芳は番頭に女将さんの手が空いていれば会いたいと連れて行ってもらった。 おしんからのお土産を頼まれたと羊羹を三本渡した。 暫くおしんと饂飩の話をして部屋へ戻った。 九つの鐘が聞こえると迎えが来た。 爺が案内して“ みのや ”という高泉寺門前の問屋場先の茶屋へ向かった。 昼と言うのに台は多くの菜が盛ってある。 「わしゃ明日から周りの村を訪ねるでな迎えの祝いと、別れの祝いの膳ですじゃ」 「鉄爺、別れも祝い膳と言うの」 「こりゃお芳、そういうほうが無難じゃろうが」 鉄之助に迎えが来て宴席はお開きとなり“ やまもと ”へ戻って明日からの相談をした。 ちくまやの三人は勝手で良い、未雨(みゆう)の親子も家族でと為り残りは次郎丸次第で動くとなった。 「お客人ですよ」 「わっ」と驚いたのは未雨(みゆう)だ。 「さあ捕まえた。借宿作右衛門旦那が知らせてきた様に知らん顔はいけっませんぜ」 七十近い男は次郎丸へ向きなおると「黒岩忠右衛門と申して此の伊勢屋の弟弟子で御座います」と平伏した。 「先ほど聞いたばかりだが春秋庵加舎白雄師匠のお弟子だそうで」 挨拶が済むと「この地の仲間もお江戸の情報が聞きとうございます。二日ほど、いや明後日の朝までお借りしとうございます」と年寄らしい強引さだ。 次郎丸は笑って親娘は俺が用心棒で周るよと未雨(みゆう)へ笑いかけた。 草津へ向かうのがどうして知れたかは分かったが“ やまもと ”へも網を張っていた様だ。 俳句のお仲間は連絡も素早いなと鷺白(ろはく)へ次郎丸が笑いかけた。 「翁の句碑を建てたそうで」 「小さいものですが宿の前に目印に置かせて頂いております」 “ 山なかや 菊は手折らぬ 湯の匂ひ ” 「加賀の山中温泉で詠まれた句ですが、草津も山の中と強引にひっかけました」 高さ二尺、幅二尺六寸ほどだという。 半ば強引に連れ出されていった。 次郎丸はまずはわたの湯から始めるかとお芳たちと出て行った。 千十郎と大野は御座之湯へ、ちくまやの三人は滝の湯を勧められて案内されていった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“ 温泉三昧 ” 文化十一年八月二十五日(1814年10月8日)・温泉三昧 江戸を出て八日目、温泉三昧の二日目は朝飯前に昨日のわたの湯から始めた。 番頭と相談して朝二、昼二、夕一の五回にした。 「子供に老人は日に三度、かぶり湯は忘れずに半分浸かって湯に馴れたら肩まで、一刻(こく・十五分ほど)以上は湯あたりします」 昼飯用の小銭以外は宿が厳重に保管してくれる。 「なまじ貴重な品を持って出て、湯に入っている間に板の間稼ぎにやられたは、草津の信用が落ちてしまいます」 番頭は胸を張って答えた。 葵御紋入り“通行勝手”の木札は宿を信用して預けるわけにもいかないと思っていたら番頭が三番の合言葉「ありがたやでございます」と指印を見せてきた。 新之丞はそれを承知で“ やまもと ”に決めたようだ。 おしんは一昨年と言っていたが十年前から権利は四軒持ち、貸し出しているという。 善兵衛と言う五十代の番頭が仕切っているという、家族は小雨村にいて神さんは月に三度荷を運ぶ時に上がってくるという。 食事は朝六つ半、夕暮れ六つ半の二回を宿が用意と大野が取り決めている。 別に顔を合わせても良いが、昨晩の内に今日の湯の場所を突き合わせた。 御座之湯は外観も綺麗だが、中も整っていると言うのでお芳が「朝飯後は其処にしたい」と大野に書いて貰った。 朝の食事が済むと湯へ向かう前に大野はお芳たちと大きな方の絵図を見ている。 お辰(おとき)がお芳から聞いて見たいと強請った。 「此処に文化七年改とあるだろ。もとは文化四年版だそうだ」 「持ち歩きには大きいですわ」 「四つにおると折り目が擦れるのがもったいないが仕方ない」 お芳とお辰(おとき)は今朝の湯の中で逗留している湯治客と仲良くなったと報告している。 「明日から、あたいたちと順路は違うけど善光寺へ向かうそうよ」 「伊香保から草津、善光寺、戸隠と廻るそうですわ。家は上州藤岡だそうですわ」 「それがね、おとうの連れて行かれた望雲という湯宿へ泊まって居るそうなの」 お芳たちが他の客とすぐに仲良くなれるのは、江戸人というのが効いている。 みな、江戸の情報には飢えているのだ。 木賃に泊まり自炊するもの、銭に糸目を付けず宿に任せる者、貧富の差なく湯の中で話の花が咲くのは、長湯してものぼせないわたの湯だからだ。 口には出さないが介重たちは「草津へ来てとろい湯になぞ浸かれるか」と思っている。 鮨も稲荷に干瓢巻の店も有り、山女の甘煮を穴子の替わりに箱寿司にもしていたので今日の昼は蕎麦か鮨かで三人は揉めていた。 「お芳ったら若さんの背中の刺青が無いか調べていましたわ」 「だって」 次郎丸、長湯は出来ないようで一刻(こく十五分ほど)は入って居られないのでさっさと出てぼんやりしている。 御座之湯は少し熱く感じたがお辰(おとき)親娘は丁度良い湯加減だという。 二人は出てくると湯ざめをしない様に浴衣をはおり、次郎丸と話をしてもう一度湯に浸かった。 「だんなぁ。暇そうでござんすなぁ」 「暇なら馬子唄か都々逸でも聞かそうか」 「お武家さまが馬子唄ですかい」 「此処へ来る途中で覚えた」 “ 小諸出て見りゃ ヨ~ 浅間の エ~山に ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 今朝も ナ~ 三筋の ヨ~ エ~煙立つヨ~ ” 「はい、はい」 “ 小諸出抜けて ヨ~ 唐松 エ~ 行けば ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 松の ナ~ 露やら ヨ~ エ~涙やらヨ~ ” 「こりゃ楽しい。わっしは熱田で覚えた神戸節でもうなりやす」 “ ありがたいやの すずしの蚊帳で
なかでするがや えいらくや ” 唄声に湯あみの客もやんやの喝采だ。 “ ソイツはドイツだ
ドドイツドイドイ 浮世はサクサク ” 「旦那も御存じの様でやんすね」 “ おかめ買う奴、あたまで知れる。油つけずの二つ折れ、そいつはどいつじゃ
そいつはどいつじゃ ” 合わせるように湯舟の客も浮れている。 “ ソイツはドイツだ
ドドイツドイドイ 浮世はサクサク ” 「一杯奢りたいが湯と酒はご法度だそうでね」 「酒を飲んで熱湯に入りゃひっくり返るのが落ちだ」 話しているうちに親娘が浴衣を羽織ったので「またな」と御座之湯を出た。 “ やまもと ”で、茶で煎り豆を齧った。 湯宿へ戻るのを待っているかのように物売りが遣って来たのだ。 買い入れは宿へ請求だという、あらかじめどの程度払えるかは調べてある様だ。 「若さんって噂以上に覚えが早いわ。馬子うたを一度で唄えるなんて凄すぎる」 「草津は何かないのかな。湯を揉むらしいがドッコイドッコイしか聞こえないぞ」 女将が大分傷んだ絵図を二枚持ってきた。 何時のものか年度は無い。 「見てみなさい。片方は羽尾へ三里半、もう一方が羽尾へ三里。羽尾は羽根の根を抜いたのだろう、だがどちらもそこから狩宿一里と一里半だ、此の道中で馬子から近道を聞いたのでもそんなはず無いのはお芳にもわかるだろ。長野原は江戸で調べたのと大差ないがすべて此の調子で頭が痛くなる。沓掛から十里に合わせたようだ」 「大野様その時は瀧を浴びれる湯へどうぞ」 女将の言葉に大笑いだ。 大野は色付のを見せると「右が手抜き」とお芳と同じようなことを言う。 「ついでだが儂の持ってきたこれには長野原三里半、そこから須ヶ尾三里。羽尾より狩宿六里でこれが一番実際歩いたのに近い」 大野が江戸で集めて集計したと書付を女将に見せている。 沓掛宿から草津道を五里二十六町十五間で狩宿宿。 狩宿宿から五里七町四十間で長野原宿。 長野原宿三里二十町二十間で草津温泉。 合わせて十四里十七町十五間が考えて出した里数だという。 実蔡歩いて十六里と言うと女将もうなずいている。 「沓掛へ九里半、多く言われるのが十里。まったく頼りに出来ませぬ」 大野と気が合うようで絵図の売り物を掻き集めると約束した。 「できれば同じものを五枚ずつ集めておいてくれぬか草津土産にしようと思う」 次郎丸は「おらずに板で挟んで江戸送りにしたらどうだ。持って居ては傷むぞ」と鷹揚に言う。 お辰(おとき)とお芳は呆れている。 「若さんいくらかかるとお思いです、絵図より高くつきますよ」 「傷まず送れる土産は」 「轆轤細工、湯の花くらいでしょうか」 「湯の花かそいつは良い、大殿、ご隠居も喜ぶ二両も掛かるまい」 まさか湯の花二両出したらと女将も呆れている。 「腰湯で浸かるくらいで三十六文、五右衛門風呂で四十八文がひと包みですよ」 三家が卸し元で、湯の花屋で年収益八十両ほどだという。 「湯の花屋の独占では」 「それは広小路の畑分だけで御座いますよ。湯の花屋様は其処だけではありませぬが、十年程前から周辺の湯の花を源泉の所有者が売り出しました」 番頭が仕切ると云え、多くの湯宿の権利を持つ女将だけは有る。 「松代へ土産に五右衛門十回分ほど持って行こう」 「私も母上に同じだけ」 それまで輪に入らずにいた千十郎も言いだした。 大野が後で〆るから勘定は此方へと女将へ頼んだ。 次郎丸はお辰(おとき)親娘と天狗瀧へ向かった、軽く瀧に肩を打たせて上がって蕎麦を食べに“ やまもと ”の裏手横町の“ たごと ”へ向かった。 ちくまやの三人が見世から出ながら「美味かったぜ明日も来るぜ」と暖簾の奥へ声を掛けている。 「何枚くろうた」 「これから海苔巻を食う都合で三枚」 盛りは良いのかと聞くと「柳谷の二割増し」という。 柳谷は向柳原の土手下に有る盛りが多いので有名な屋台店だ、お得意は博労、駕籠かき、屋敷中間、小店の手代、かけ蕎麦は一杯で次郎丸は腹が膨れる。 お芳に「二枚でも俺には多い位だぜ」と言うと「蕎麦っ食いは爺様で柳谷五枚はお茶の子」という。 此の当時風鈴蕎麦が十二文から十四文に為り、店を構えると十六文も出てきた。 お上品なら麻布永坂更級、これから行く信濃更級の出だという。 物が高い街道沿いで二八・十六文、草津も十六文と云う。 「高所の温泉地にしては安い」 大野はそのように言っていた、三人とも二枚で十分な量だった。 天狗瀧、薬師の瀧を回り込んで不動の瀧で軽く温まった。 広小路を登ると馬方が馬に湯をかけている、元カッケの湯だという熱の湯(あつのゆ)は湯揉みの音が「ドッコイ、ドッコイ」と縁に当たる“ バタン バタン ”が揃って聞こえる。 「宿はどの方角かしら」 「“ こんぴら ”の階段上から宿中が見えるよ」と通りかかった婆さんに教えられ階段を上った。 時計と陽の角度で「広小路の向こうが丑寅の方角だな」と教えた。 「午の刻が大体南に有る、今二時半だから坤(ひつじさる)の方に有るのだよ」そう言って時計を渡した。 「此のⅫ(じゅうに)が北に為るわけね」 「覚えが良いな」 石段を降りて木橋の先右手に瀧の湯が有る、日暮れに入る予定を立てている、あと一刻半(とき・百五十分)も有る。 “ 桐や
”の縁台に今朝御座之湯で神戸節を唄った男が居る。 「だんなぁ。また会いましたな」 「おれたちゃ明後日一杯、湯三昧だ」 「あっしは明日おっかあたちと善光寺でござんす」 「何処かで聞いたような話だ。俺たちも上田を廻って善光寺だ」 お辰(おとき)が「ほら今朝の人たち」と様子を話すとそうだという。 里芋を茹でた物で茶を呑んだ。 「藤岡だそうだね」 「親爺は兒玉屋という太物を商っておりやす。あっしは京(みやこ)浪速、名古屋、江戸の取引相手との用談であちこち飛び回る毎日でござんす」 望雲の雲嶺庵鷺白とは父親が発句の相弟子だという。 母親と叔母の用心棒の替わりで温泉と善光寺、ひと月かけて回るという。 「わしらも江戸から上田へ出て善光寺、その途中で草津へ寄り道だ」 店の裏の座敷から追分節を唄う声がする。 どうやら師匠が三人ほど稽古をつけているようだ。 “
一に追分 二に軽井沢 三に坂本 ままならぬ ” “ 浅間根腰の 焼野の中で あやめ咲くとは しおらしや
” “ 追分の枡形の 茶屋で ほろりと泣いたが
忘らりよか ” 「おしんが唄わぬのは沓掛が抜けているからかな」 「だんな、何処の飯盛りですおしんて、唄が旨いんですかね」 「いや、沓掛で出会ったうどん打ちの上手い娘っこだ。饂飩を寝かして置く間に馬子唄を唄っていた」 次々と唄うのではなく今日はその三つを教えているようだ。 三回り程して終わったのか十、八九の娘が三人出てきた。 男の連れと言う女二人と女中が二人金毘羅の方から来てお芳たちと話が弾んだ。 「瀧の湯へ入って戻るよ幸太郎」 おや名前からすると長男のようだ。 「あたい達も後で来るより、入っておこうか」 お辰(おとき)が言うのでお芳も賛同した。 三人の茶代は五十四文、次郎丸が四十文の括りと四文銭四枚出して支払った。 明日は又百二十文出してもらうようだ。 なに持参の浴衣用の帯に南鐐二朱銀と一分金、宿に内緒で大野が仕込んでくれてある。 帯には“ やまもと ”の焼き印の木札が下がっている、間違えるやつもいないと大野は自信げだ。 湯の温度は次郎丸好みだ、つい先ほどの追分節を唄ってしまった。 「ゲゲッ」 そう驚く幸次郎は正直者だ「だんな、ただもんじゃないね一度で覚えたんですかい」と競う様に神戸節で応じてきた。 珍しく次郎丸は二回湯へ浸かった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“ 寒露
” 文化十一年八月二十六日(1814年10月9日)・寒露 江戸を出て九日目、温泉三昧も三日目。 朝一は、またわたの湯から始まった。 昨日の朝は山菜の塩漬け、豆腐汁、山女の塩焼きだったが、今日はそれに猪肉の柔らか煮が増えている。 味醂と醤油が肉に合っていると好評だ。 昨晩も柳川にすっぽん雑炊と山の上とは思えぬ手が込んでいる。 鉄爺が気を利かして用意させたかと番頭に聞くと「金の払える人にはもっと豪勢な食事が用意できます」と言われてしまった。 大野が態と「海の物は無理でも、鰻のかば焼きなどどうだ」にも前日予約なら夕餉に間にあわせると言われてしまい「明後日最後の晩に用意してくれ」というと「おひとり前八百文」と言うが勢い余って九人前と言ってしまった。 「江戸の八百善で食べたつもりなら安いものだ」 お芳に見栄を張っている。 「茶屋で飯盛り呼んで騒いでも八百文で済むそうですよ。湯舟で若い衆が騒いでいました」 大野もお芳の悪口(あっこう)に馴れてきてまるで孫のようにかわいいようだ。 ちなみに孫は正月に生まれる予定だと聞いた。 「四十一で爺様」 次郎丸にからかわれても「生まれるころは四十二に為るので、年内厄除けをというより善光寺で厄除けの御札を貰います」と躱されている。 朝飯の後次郎丸は三人で薬師の瀧で肩に打たせ湯して戻った。 昨日煎り豆を買ったばあさんが今日は「枝豆の塩茹どうですね」と来た。 千十郎が八十文分だというと丼二杯山にして寄越した。 「どんぶりゃ。ここんのだが。廊下に置きゃかたづけるがね」 「婆さん枝豆が採れるなら、ずんだ餅は出来るのかね」 皆きょとんとしている。 「枝豆に砂糖をまぶして潰すのだよ。餅に餡や黄な粉の替わりにまぶすのだ」 「どこのほうげんだがね。江戸の人でそんな餅頼まれてないがね」 「俺の母上が白川の人で夏の終わりには必ず食べた物だ。奥州では普通に作るそうだ」 「餡にすりゃいいがね」 「粒が歯に当たるくらい残る方がいいな」 大野は江戸生まれ、江戸育ちでずんだは見たこともないという。 「あ~ねぇ。うんと作っていいだがね」 「一升餅にたっぷりまぶしてなら作る気になるかい」 「八百文出してくりゃすだが」 「いいとも番頭さんへ言い置いてくれ」 未雨(みゆう)が戻ってきて「へぇ~~」と笑っている。 「おとは知ってるの」 「ずんだというのは大豆だと聞いたが食べたことは無いなぁ。莢ごと潰したりしなさんなよ」 疲れた顔がほころんできた。 「ほうけえ、やぶちゃでからかい為さんな」 あすもこの時刻に持ってくるという。 丼二杯は九人ではあっという間に食べきってしまった。 大野が後払いは使い過ぎてしまうと言っている。 「それが温泉地の知恵だろうぜ」 按摩が来たという未雨(みゆう)が頼んだようだ、一人残して湯へ向かった。 湯宿が百軒を越して按摩も人不足だという。 「此処の布団はじょうものですな」 「手触りでわかるのかね」 「虱、蚤の付く木賃の布団などわし等には困りものでな。大宿の布団に比べりゃ高いもんに付くのですよ」 木賃へ出向くと帰りに手引きに持たせた替に着替え、元の着物は天気干しするので着替えが何着も必要だという。 ざっともんで「お腰はつようございますが、こりゃ寝不足が続いたようで」背骨の両側の筋を痛めぬように、柔らかく揉んでいる。 何処の女郎が見目良いとか、気が利くとかの話をしてくる。 二刻(こく・三十分ほど)もんで「一回り終わりましたが続けましょうか」と云う。 「いや十分だ、こりゃ宿でもらう分と別だよ」 四文銭十枚括りを渡した。 「八十文にこの手触り四十文もありがたく頂戴します。おすわよぅ、次は何処だい」 手引きが付くとは、上等の按摩かにわかめしいかと考えた。 「さて、八十文だ、いくらもらえるやら。女の評判を吹き込むとは出入りの茶屋の肝いりかよ」 宿の取り分によっては相当回るようだ。 「それにしても入らぬ湯に一日十文、まぁ江戸の湯屋(ゆうや)でも八文取るからな」 次郎丸達は地蔵の湯でゆでだこに為っていた。 「熱い湯は平気だと思ったけど、こりゃ湯揉みくらいじゃ百も数えちゃ居られないよう」 「熱の湯(あつのゆ)も熱いと聞いたけどこいつはやけどしそうだぜ」 此処の湯は仕切り壁で熱さを替えてあると言うが、湯番の言うぬる湯でも耐えられない様だ。 甘酒売る様子の良い女子に見とれていると「海苔巻と稲荷が食べたい」と、お芳が言いだした。 愛想に甘酒を三杯頼み見世を聞いた。 江戸口木戸の手前の茶見世が良いというので高泉寺の山門前を通りその見世へ向かった。 干瓢が旨い、だが稲荷が甘い。 お辰(おとき)とお芳は「こりゃ旨い稲荷鮨だ」とご機嫌だ。 大きいが江戸の半分くらいで八文、海苔巻が十二文と張り出してある。 次郎丸は店で食べている先客の様子で、一つづずつにしても腹一杯になった。 海苔が一枚でも半分でもない中途半端な大きさに感じた。 「しまった聞いた相手が若い女だ。辛口は苦手だったか」 思わず笑ってしまった。 「できたぁ」 女中っこがやってきた。 今海苔を撒くからねと飯台にもみ海苔を振りまいた。 「刻み生姜は辛いからお好み聞いて添えるんだよ」 蓋をして小皿に刻み生姜を入れて風呂敷へ包んだ。 「仕出しもされるので」 お辰(おとき)が訊くと「茶屋から頼まれると作るんだが。あれで六人分ここは山の上だで入れる物も限られるんがね」と教えてくれた。 喋り好きの様で中身は鰻のかば焼きを刻んで錦糸卵に干瓢、稲荷の油揚げだという。 お辰(おとき)が何か気が付いたようで「鰻も入れると高くつきますわね」と誘い水だ。 「六人前だと大ぶりので一匹三百文で焼き上がりを買い入れるのであの飯台で千二百文に付くんですよ。鰻の量で値も変わりますがね。もみ海苔は後で入れるかお好みでやらせて頂いて居りますがね」 店を出て「大野には内緒」と二人へ口止めした。 「でも」 「どうした」 「これだけあちらこちら廻ってもかば焼きの匂いなど、嗅いで(かいで)ないですよ」 「そういやそうだな、湯と離れた奥まった路地にでも見世が在るのだろうな」 今日四回目は鷲の湯、勇ましい名だが、傷ついた鷲がこの湯により傷を治したくらいだから、人が入るには大丈夫だろうと高をくくった。 地蔵の湯と変わらぬようだ、温め(ぬるめ)と言う湯舟でも次郎丸はさっさと上がってしまった。 親娘はそれでも三ヶ所ざっと入ってきた。 「あんたがた湯廻りで忙しいらしいが、鬼の茶釜見られたいな」 「どの辺りですかね」 「“ こんぴら ”さんの石段の右の川に沿って行けな二町もないさ。昔は遠くからでも釜鳴りが聞こえるにな、近くにいくと聞こえなかったそうじゃな。今はそんなことおこらんのさ」 「行ってみるか」と三人は広小路の西っ側を“ こんぴら ”へ向かった。 衣装を揃えた一団の巡礼姿が目に付いた。 “ こんぴら ”の由来や石段上の“ 金光院金毘羅大権現 ”は桐屋の主人、高原長右衛門様が寛政九年に寄進なさったと説明している。 川筋の緩やかな上りを進むと「ゴォウ、ゴォウ」とほえるような声が聞こえてきた。 「あっ、聞こえる」 「本当に二町もないわね。茶釜にしては変な形ね」 悪口に聞こえたのか「ごぼっ、ごぼっ」と咳き込んで湯の噴出が止まった。 「アラ本当に近寄ると止まるんだわね」 先から戻ってきた人がいたので「この先は何かありますの」と聞いている。 「鬼の角力場だと言うがね。石が土俵のように丸い輪に為ってるだけだったぜ」 鬼に聞こえたのかのように石の間から「ゴォウ、ゴォウ」湯気と湯が噴出してきた。 三町ほど先だというとお芳は石が並んでいるだけなら戻りましょ」と元へ歩き出した。 戻ると大野たちは“ ずんだ餅 ”の皿から一つずつ取り分けていた。 「明日じゃないのか」 「見本に作らせたそうです。味を甘いかしょっぱいかで良いので番頭へ教えておいてくれと持ってきました」 九人にいきわたるように九個だという。 「さて困った」 「なにがですの若さん」 「お芳にしょっぱくても俺には甘い、そん時は誰に合わせるんだ」 「若さん大抵甘く作るはずですよ」 「なぜ」 「甘いと言われたと砂糖を減らせます」 食べたら甘みが次郎丸好みだ。 「甘いわ」 お芳が言う。 お辰(おとき)もそういったので大野が「もう少し甘くていい」と言いだした。 「若さんは」 「俺にはちょうどいい、母上が乳母に作らせた甘さだ」 未雨(みゆう)が「番頭に丁度いいと言ってきます」と出て行った。 「かっけの湯へ入るには勇気がいるわ」 「そりゃ板囲いくらい欲しいやね」 「絵図には弘法も此処で脚気を直したとあるぞ」 「高名な人は皆来てるというのは宣伝くさい」 「これこれ言い過ぎじゃ」 今日の最後は桐やの湯だ。 別に“ 桐や
”の内風呂ではなく名前が無いのを見世の真ん前に有るのでそう言い習わしているのだそうだ。 瀧の湯と源泉は同じだと聞いたが、湯番は別だという。 五つの鐘で“ やまもと ”を出たら湯宿へ荷を届けるのか、荷駄が馬方一人二頭で三組遣って来た。 「若さん此処って馬宿を見てないわ」 「横町の先に馬場が有るけどその先が牛宿だろうさ」 “ 桐や
”は入ってゆく客と迎える女の嬌声が遠くまで聞こえた。 鰻を焼くのか嗅ぎ馴れた漬汁(たれ)の焦げる臭いが漂っている。 生け簀に川魚、鯉、桶に鰻といろいろ取り揃えてあった。 湯に浸かり三人で思い出し笑いだ。 三日目ともなれば熱さにもだいぶ慣れてきた。 病人も程度によって決めがあるらしく同じ湯舟には入ってこない。 噂で聞いたお余り行列も統制が取れている様で、広小路付近へは立ち入ってこない。 湯番の親父に聞くと「今の湯の花屋様に為って町中を練ることも無くなりました」と言う。 湯の花屋が湯の花を採取、硫黄の駆除のおかげで湯道は冬場も守られると言う。 “ やまもと ”へ戻ると大野が「絵図は持ち込んだのと同じので年度違いが三種十五枚、新品擦れなど雑多に三種八枚集まりました。湯の花に送りなどで四両二朱十六文でした」 十六文は笑えるなと千十郎までお辰(おとき)に言っている。 「絵図は一枚二十四文、これはみやげやで買い入れて確かめましたのと同じです」 年度の無いものだという「持ち込んだものと同じ版で年度を削ったようだ」と笑った。 「ならそいつが一番新しいのかもよ。若しかして」 「なんですよ。急に黙って」 「何処か絵師に頼んで新しい構図で描いたんじゃねえか。近いうちに出てくるだろうさ」 此の晩は湯豆腐だ葱が旨い。 「すまんな権太よ。義父上にお会いするまで酒も無しの飯ばかりだ、三人は今日明日茶屋遊びに出てもいいぞ」 「いけませんや。御酒の好きな若さんに師匠を差し置いて飲むわけにゃいきません」 「心配するな、わっちは昨晩、一昨日と大宴会で浴びるほど飲んできた」 「だめですぜ。昼を食った蕎麦屋でいつみやのおすきという姉さんが黒岩の旦那に呼ばれたが、酒席は無く俳句の会でうなってる人のお茶番だと嘆いていましたぜ」 酒は大戸宿、長野原宿から運び上げるという。 少ない日で四百人は湯治客が居るので酒の需要は多いと聞いたと言っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“ 温泉三昧 ” 文化十一年八月二十七日(1814年10月10日)・温泉三昧 十日目、温泉三昧の四日目。 早朝のわたの湯で聞いた話では熱の湯(あつのゆ)の湯も朝早くには温度が上がらないという。 「じゃ夜中は温泉の元も休むのかしら、明日の旅立ちの日は明け六つに行ってみましょうよ」 「御座の湯裏の頼朝様がお休みする時刻かな。試してみるか、その前に朝飯の後行くからどの程度違うかわかるぜ」 朝飯はわかめの味噌汁に油揚げが入り、おひらは揚げ出しと小芋のあっさり煮。 鮠(はや)の塩焼き二本、大根のはりはり漬け。 大野も沢庵がだめでもこいつは好きだという。 「今年はもうじき越後から届きますな」 柏崎の分領はこれからが切り干し大根に適した天候に為る。 ほぼ一年中大根の収穫はできるが凍み豆腐作りの前が良いと聞いた。 熱の湯(あつのゆ)は若い男たちで満員だが、湯揉みが終わると三人を混ぜてくれた。 先達の老人が「よしよし」と声をけると湯舟から上がり、また湯揉みをし「いけいけ」で中へ浸かった。 三度繰り返すと「これで終わり」と言われ次の番と入れ替わった。 「このくらいなら我慢できるわね」 「おっかぁ。あたいたちも熱々に馴染んできたのね」 「その様だ。やけどまでして入るのわ御免だけどさ」 四つの鐘の後、例の婆さんが“ ずんだ餅 ”を持ってきた。 半分を女将へ渡して残りを分け合った。 「ためしより美味くなってる」 「そうだね。昨日より餅が旨いよ」 昼間の二つの湯は昨晩話しあって新興の浴場へ行くことにした。 九つ前に“ みのや ”の玉の湯へ次郎丸と未雨(みゆう)一家。 九人で“ みのや ”で食事の予定。 その後は次郎丸と未雨(みゆう)一家は近くの瑠璃(るり)の湯に為った。 “ みのや ”は爺の頼みもあるのか生の魚は出てこずに煮物、焼き物中心に支度がしてあった。 大野が「勘定は宿へ」と入るとすぐに主に言うと「支払い済みで御座います、酒は頼まぬはずとも言われております」と手が回っていた。 席に着くと間もなく柳川の鍋が出てきた。 食べ終りしばらく明日からの道中を大野が念押ししている。 「荷は馬に乗せて歩いて下る。須賀尾宿へ六里十五町、足ならしに良い距離だが長野原に乗懸(のりかけ)六頭用意させた、下りで疲れた足の為じゃ」 可哀そうだが中間は歩かせるという。 朝飯前にひとっ風呂、五つに朝飯、清算が済み次第に宿を出ると言っている。 仕切も切り盛りも日ごとに上達してきた。 「大笹は此処で近いと知れたが、予定の通り寄らないことにする。狩宿宿でおしんの饂飩のほうがいいじゃろう」 次郎丸もせっかく新之丞のつけた連絡を崩さぬ方が良いと思った 須賀尾宿から狩宿宿わずか三里程だが顔を見せねばおしんの唄も聴けぬと思った。 瑠璃の湯は街道沿いだ、路地を入ると入口に大きく看板がある。
「草津湯の入口に合わせた功能だな。旅の疲れを取れとでも言うようだ」 街道の方へ掛けておく方が目立つのに面白い持ち主だ。 湯舟も温湯、熱湯と書いてある 湯番の爺さんは豆絞りの手のごいで鉢巻、馬子唄を唄いながら台に腰掛けている。 長湯がすぎる客に「一度あがって湯をかぶってくだされ」と威厳のある声で頼んでいる。 婆さんが女将と待っていた。 「“ ずんだ餅 ”はどうだっただが」 「美味い、一晩で腕も上がった」 帯から一分金を出して目の前で紙へ包んで「母上を思わせる味で良い思いが出来た」と膝前に置いた。 「今日は珍しいのが来ただが、唐人豆じゃ。煎りたてだが、どうしなさる」 見本に小皿を出した。 「ほっ南京豆か。珍しいな」 大野は「いくらだ」ともう買う気だ。 百年以前には江戸へも来ているが土壌のせいか大きく育たなかったという。 江戸じゃめったに手に入らず、薬研掘は銭五から薩摩の物を差し入れてくる、味は大野好みだ。 「割合大きいのが多いが、見本だけじゃないだろうな」 「みなさるがや」 食いついたとみてしょい籠から一升ほどの竹籠を三個出して蓋を開けた。 粒ぞろいだ。 大野は「一つ幾らだ」と少し控えめに言う。 「ひと籠一升で五百八十文」 「三つ買うなら」 「うんだな。ごしたいもんで五つ買うなら二千六百文だが三つじゃひけね」 大野は腹で指おって「いいだろう、女将さん出してやってくだされ」と頼んだ。 次郎丸も珍しいものに出会って嬉しそうだ。 あと二つ出してそれも蓋を開けて大野に確認させている。 女将が言うには二十貫が昨日来て婆さんが全部買ったという。 この宿でも二升買ったそうだ。 「生豆殻付一貫で千粒が上物。千二百粒以上は下物」と言っている。 煎れば軽くなるので目方で売ると驚かれるという。 煎ると均して殻付一升、中身百五十粒という、気にする客には目の前で竹籠から一升桝へ開けてみせる。 隙間が多いのは仕方ないが山に盛るので見ている方は儲けた気がするという。 大野は「計算できん」と頭を抱えている。 「一貫で一斗五升の計算で売るだが。ここでの値は高くて当たり前だ」 「殻付じゃ一升なんざ九人で食ったらひとたまりもない」 婆さんも「剥くと半分にもなんねえ」と殻無しは選別後で四倍値の引取りだという。 「一割はひねたのがあるで刎ねることに為るがだ」 見本の小皿は山になるほどおいても殻付二十粒が精々だ。 次郎丸が「殻無し百石収穫出来れば油で大もうけできるぞ」と煽った。 「なぜ」とお芳が不思議そうに聞いた。 南京豆の油は貴重品、清国でも取り合いだという。 知識人の間で一合十両の値が付くそうだ。 「三割刎ねて油を搾ると三升採れるそうだ。捨てる物で金になる」 刎ねた分で金を産むというと「若さんの大ぼらじゃん」と呆れられた。 部屋で竹籠一つ空にした。 今日の最後は富の湯だ、鷲の湯は大きいがこちらは五人ほどがやっとの湯舟だ。 湯番も居ないが小奇麗にそうじされている、次郎丸と未雨(みゆう)は番人替わりで親娘を入れ、出てくると入れ替わりにざっと沈んで出てしまい“ やまもと ”へ戻った。 鰻は江戸風に背開きで蒸しがされていた。 「これなら高くとも旨さが勝」 大野も満足そうだ。 出し巻卵に小魚の佃煮、凍み豆腐と小芋の煮物、中々のものが出てきた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一日・わたの湯 第二日・わたの湯・御座之湯・天狗瀧・不動の瀧・瀧の湯 第三日・わたの湯・薬師の瀧・地蔵の湯・鷲の湯・桐やの湯 第四日・わたの湯・熱の湯(あつのゆ)・玉の湯・瑠璃の湯・富の湯 第五日・熱の湯(あつのゆ) ・桐やの湯 文化あぶみやとしまや版-ゆと表記・文政四年巳年改上州草津温泉図-ゆと表記・安政六年丁子屋版-未記入(南側に凪の湯)・安政達磨屋版-君子の湯・幕末-山本十右衛門版-君子ノゆ・明治二十六年安倍善吉版-凪の湯。 ・瀧の湯 文化あぶみやとしまや版-瀧の湯・文政四年巳年改上州草津温泉図-ゆと表記・安政六年丁子屋版-今ひらの瀧・安政達磨屋版-滝湯・幕末-山本十右衛門版-コンヒラ滝・明治二十六年安倍善吉版-金ひら滝湯。 ・玉の湯 文化あぶみやとしまや版-未記入・文政四年巳年改上州草津温泉図-未記入・安政六年丁子屋版-玉のゆ・安政達磨屋版-玉のゆ・幕末-山本十右衛門版-玉ノゆ・明治二十六年安倍善吉版-玉のゆ。 ・瑠璃の湯 文化あぶみやとしまや版-未記入・文政四年巳年改上州草津温泉図-未記入・安政六年丁子屋版-るりのゆ・安政達磨屋版-るりノゆ・幕末-山本十右衛門版-ルリノゆ・明治二十六年安倍善吉版-るりゆ。 ・本文に出ない松の湯 文化あぶみやとしまや版-未記入・文政四年巳年改上州草津温泉図-未記入・文政十二年上州草津温泉之図-松の湯・安政六年丁子屋版-松の湯・安政達磨屋版-松の湯・幕末-山本十右衛門版-松のゆ・明治二十六年安倍善吉版-松のゆ。 ・本文に出ない千代の湯 文化あぶみやとしまや版-未記入・文政四年巳年改上州草津温泉図-未記入・文政十二年上州草津温泉之図-建屋のみ名称未記入・安政六年丁子屋版-ちよのゆ・安政達磨屋版-千代の湯・幕末-山本十右衛門版-千代ノゆ・明治二十六年安倍善吉版-ちよのゆ、文字のみ。 ・脚気の湯 文化あぶみやとしまや版・文政四年巳年改上州草津温泉図・文政十二年上州草津温泉之図では建屋無し・安政六年丁子屋版-建屋あり。 元禄以降の草津五湯 御座の湯・脚気の湯・鷲の湯・綿の湯・滝の湯。 宝暦以降 熱の湯(元脚気の湯)・脚気の湯(元タムシ、ミズムシの湯)。 ・地蔵の湯は修験常楽院私有、宝暦五年創設。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“ やまもと ” 文化十一年八月二十八日(1814年10月11日)・草津温泉~須賀尾宿 明け六つ、“ やまもと ”の前を巡礼装束の一団が立町の少しの坂を下って行った。 白い集団は二十人ほども居て、女将の話しでは善光寺を廻って美濃へ帰りという。 次郎丸は四人で熱の湯(あつのゆ)へ向かった。 昨日と違って男も、女も老人が多い、顔見知りに為った婆さんが「お宅さんら今日で下りなさりがや」と残念そうに聞いてくる。 「湯治の真似事でね、切り上げてこれから沓掛へ出ますよ」 「善光寺様へもいかっしゃるやら」 「そうなんですよ。お武家さまの道連れで頼もしぅござんす」 「この前聴いた馬子唄聞かさんしょ」 良いよと次郎丸が板場で唄いだした。 “ 小諸出て見りゃ ヨ~ 浅間の エ~山に ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 今朝も ナ~ 三筋の ヨ~ エ~煙立つヨ~ ” 「はい、はい」 “ 浅間根腰の ナ~ エ~焼野の中に ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 菖蒲咲くとは ナ~ エ~しおらしや ヨ~ ” 「はい、はい」 “ ここはどこだと ナ~ エ~馬子衆に問えばぁ ヨ~ ” 「はい、はい」 “ ここは信州 ナ~ エ~中山道~ ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 浅間山から ナ~ エ~出てくる水はぁ ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 雨も降らぬに ナ~ エ~笹にごりぃ ヨ~ ” 「はい、はい」 “ あおよ啼くなよ ナ~ エ~啼くなよ ヨ~ ” 「はい、はい」 “ 森の中から ナ~ エ~灯が見える ヨ~ ” 「はい、はい」 湯が徐々に熱を持ってきたようで、みな上がってきた。 次郎丸と未雨(みゆう)はざんぶりと柄杓で頭から湯をかぶり半身を湯へ浸かった。 「おお、こりや熱いぜ師匠」 「一度沈んで出ましょうや」 湯番の先達が来て板の準備を始めた。 「何時も六つ半ころから熱くなるのかね」 「左様でございますよ。ここと御座の湯だけが、夜明け前は温(ぬる)く為るで御座います」 休んでいる爺さん婆さんに別れを告げて“ やまもと ”へ戻った。 五つ前に朝飯が出てきた。 棒鱈の軟らか煮、厚揚げと小芋のあっさり煮、高野豆腐の煮物、大根のはりはり漬け、味噌汁は豆腐。 「凍み豆腐とは噛みごたえが違う」 「紀州から来たものですよ。ひと手間余分に掛けるそうですよ」 食事が終わると番頭が帳面を持ってきた。 後から荷物が持ち込まれ、まず点検をしてくれと言うので自分の荷をそれぞれが改めた。 袱紗を包んだ渋紙の馬の毛は、乾いた飯粒で印の位置に狂いはない。 大野が「金も確認しておきなさい」と声を掛けた。 書付と狂いが無いというので番頭もほっとしている。 到着時に支払った金三分六百十六文。 大きなものは江戸へ送った分の四両二朱十六文、これには大野が気を配って白川の殿へ送った分、幸専様への土産、千十郎の土産の九百六十文も含まれている。 一日一人百二十文の持ち出しの清算、買い物の清算、すべてで八両二朱五十六文。 今朝の須賀尾宿“ しみづや治郎兵衛 ”、狩宿宿“
黒源 ”への飛脚便も入っている。 番頭が「差引七両一分二百四十文に為ります」と書付を大野に渡した。 大野が算盤で確認した。 支払いが済むと総額の受け取りが大野に差しだされた。 「一番の出費が荷の送る費用だ。土産も抜けばこれだけ贅沢して一人頭二分も掛かって居らんな」 大野の腹の内は未雨(みゆう)の心づけと同額くらいとはお主やるなと思っている。 幸専様への土産の確認も済んで荷駄へ荷を降り別け、四つ前(九時四十分ごろ)に“ やまもと ”を後にした。 女将と主の重右衛門が江戸木戸口迄見送ってくれた。 未雨(みゆう)の見送りに十人ほどいて、何やら話し合っている。 「大分んと此処も発句の連が多そうだ」 「師匠の直弟子がまだ大勢この付近に根を張って居りますので。あっしの弟子にしてくれなんて頓狂者まで居りました」 「したのかい」 「草津で二人、泊り客で藤岡の幸太郎と云う若い衆の三人受けました」 「おや。つながった」 「なんだお辰(おとき)」 「湯友達の一人さ、おっかさんたちと善光寺へ向かったよ」 「善光寺といやぁ、十返舎一九の続膝栗毛はいまだに到着していないぜ」 「何年かけても読んでくれるから版元は大儲けだ」 続膝栗毛は毎年正月に売り出される。 今年は第五編で大湫(おおくて)宿迄たどり着いた、木曽路はこれからになる。 「大久手宿」とも言われ江戸から四十七宿(しゅく)目、江戸まで九十里半、例によって夜這いの失敗談で大騒ぎ。 その一九、次郎丸に先だって信州へ入っていた。 此の二十八日は松本平を糸魚川(千国)街道で大町へ向かって旅立った。 長野原宿手前三十町ほど、勘木場村の休み茶見世で甘酒を頼んで一休みした。 大野は二人にそれぞれ百文の緡(さし)を二本ずつ駄賃に上乗せした。 長野原迄の一頭六百六十二文に上乗せだ。 問屋場で乗懸(のりかけ)が待っている。 須賀尾まで乗懸(のりかけ)でも五百七十八文。 次郎丸が乗り込むとお芳に「今何時」と聞かれ時計を見ると二時十五分、 此処から須賀尾宿まで三里足らず「暮れ六つには入れます」と馬方が言う。 須賀尾峠の休み茶見世で、大野は百文の緡(さし)を二本ずつ六人の駄賃に上乗せした。 “ しみづや治郎兵衛 ”には軒の提灯もぼんやりしている五時二十分に入れた。 部屋で飯前だというのに大野は南京豆を食べろとひと籠出してきた。 今日は甘酒二回で此処まで来たと理屈も捏ねている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“ しみづや治郎兵衛 ” 文化十一年八月二十九日(1814年10月12日)・須賀尾宿~狩宿宿 明け六つ(五時三十分頃)に“ しみづや治郎兵衛 ”を旅だった。 大野は荷駄二頭へ荷を乗せている。 喜んでいるのはちくまやの三人だ、軽い鋏箱を肩に最後を歩いている。 前にそれも馬に乗せたら歩きづらいとごねる始末だ。 宿を出ると大野は百文の緡(さし)を二本「駄賃のうわのせだ」と渡した。 次郎丸は五百七十八文が高いと言っていたくせにと可笑しかった。 万騎峠では風が強くて歩き辛く、思うより刻が掛かったが狩宿宿の追分に四つ(九時三十分ごろ)に到着した。 鐘が響く中“ 黒源
”へ入った。 「お早い御付で、雨は、濡れませんでしたか」 おしんたちが馬からの荷を受け取って来た。 「こっちは降ったの。峠では風が強くて難儀したけど」 時雨というには早いようだが、雨雲の切れ目が万騎峠だったようだ。 「昼は饂飩に山菜の天麩羅で良いでしょうか」 九つにはお出しできますという。 茶屋本陣で昼も出すとは大分新之丞の連絡で丁重に扱われている。 大野は問屋場で飛脚便“ つるや甚右衛門
”へ明日夕刻到着予定と書状を送った。 附いて来た未雨(みゆう)は借宿“ 黄檗ぬのや ”土屋作右衛門へ書状を送った。 部屋で寛いでいるとおしんが来て「もう大変よ。饂飩だけでなく蕎麦打ちまでするの。分家の旅籠で手が足りないと此処へ助けを求めて来たのよ」と右の肩を叩いている。 「蕎麦も打てるの」 「打つと言っても基本は同じ。ててが名人で見よう見まねで覚えたわ」 「違いは無いの」 「蕎麦は水気を控えめにが極意ね」 「ひとに話して盗まれない」 「いいのよ。親戚中で競い合ってるくらいだから、極意と言っても大したことないわ」 その日その日で水加減に、休ませる刻の掛け方がひとによって違うのだという。 「いくら上手な人でもお客様に合わなきゃいけないでしょ。私なんて名前のほうが売れて来たけどまだまだ未熟ね」 次郎丸が「それならこれからまだ上手に為れる余裕があるという事だね」と持ち上げた。 「そうなりたいわ。汁作りの名人にも為らないとね。女将さんの揚げる天麩羅は美味しいわよ期待してね」 仕事に戻って行った。 お芳は又時計の事を知りたがった。 江戸と信濃は同じ午の刻じゃないのは本当かという事だ。 「朝日の出る時刻には江戸とここらで十分は違うと聞いた。 「たったそれだけ」 「そうさこいつはその場所の九つに合わせるので毎日ずれてくるのさ」 「ふぅん。気休め程度なんだ」 「天文方の話しでは春分、秋分の日の午の刻でも正確な十二時ではないそうだ。明け六つと暮れ六つを京(みやこ)の時刻に合わせて作り出したそうだからね」 「なら京(みやこ)ならその時正確になるのね」 理屈上はそうだが計算が難しく暦の製作は大仕事になる。 「簡単には出来ないの」 「街に正確な時計の数が増えるまでは無理だよ。屋敷の二挺天符さえ俺には高すぎる」 「御大名道具ですもの高くて普通ですよう。お爺の自慢の二挺天符で三十五両ですもの」 夏と冬を明け六つ、暮れ六つで割るのが無理なんだよと教えた。 一日百刻の昼間の時刻は春分・秋分五十刻、冬至四十刻、夏至六十刻となる。 春分・秋分五十刻では一刻が十四分二十四秒に相当する。 四十刻の六等分に六十刻の六等分を足して一日では時計は意味がなくなる。 これに加えて明け六つ(日の出前二刻半・三十六分)、暮れ六つ(日の入り後二刻半・三十六分)が十五日周期で変化する。 日が出たら働く、日が沈んだら休む、この時代本当にそう働いたと思い込む人は多い。 「腹時計と言うのもあるわね」 「お腹がすいたのかい」 お辰(おとき)が訊いている。 「土間が賑やかだからもう直に九つだな。草津の昼九つに合わせて今二十分前そろそろ九つだ」 次郎丸は本当の時間と三十分はずれると聞いたら、お芳はどう思うだろうと可笑しくなった。 「なに思い出し笑いです若」 「お芳と同じ訊きたがりの“ なほ ”は甘いもの恋しくて泣いているかと思ってさ」 「まぁ、のろけてる」 お芳にからかわれた。 権太、介重、朗太の三人はお代わり自由とおしんに言われて饂飩のつめたで三鉢食べた。 幾ら旨くても量の食べられない次郎丸でもひと鉢で少し足りないと思うが、お代わりを求めるほどでもない。 食後未雨(みゆう)が手品のように瓦煎餅を持ち出した。 「昨晩見世を訊ねたら、焼いている最中で三十枚買い入れました」 片付けが終わったおしんを女将が「世話を焼いて来なされ」と送り込んできた。 いい幸いと次郎丸は追分を教えてくれとせがんだ。 「馬子唄と被るけど調子が座敷唄風ですだがや」 女将に頼んで三味を借りてきた、女将に主も付いてきた 「ア キタホイ」 “ 一に追分 二に軽井沢 三に坂本 ままならぬ ” 「ヨー ホイ」 “ 浅間根腰の 焼野の中で あやめ咲くとは しおらしや ” 「ア キタホイ」 “ 来たよで戸が鳴る 出てみりゃ風だよ ” 「オーサドンドン」 “ 浅間根腰の あやめが今はヨ 飯縄下町で 花盛り ” 「ア キタホイ」 “ 追分の枡形の 茶屋で ほろりと泣いたが 忘らりよか ” 「ハァキタホイ」 「此処からまた、調子がかわりますよう、嫌は嫌いという意味じゃないだ」 “ 嫌な追分 桝形の茶屋でヨ ホロと泣いたは 忘らりょか ” 「ヨー ホイ」 “ 吹き飛ばす 石も浅間の 野分と詠んでヨ 芭蕉翁は 江戸へ去る ” 「ハァキタ ホイホイ」 次郎丸は「草津ではじゃかじゃかした調子で教えるのを聞いたよ」と云うと、女将が三味で調子を取った。 「めた賑やかしょうか」 大袈裟な撥さばきに為った。 「そうそれそれ」 次郎丸に合わせてお辰(おとき)にお芳も歌いだした。 「追分に小諸に比べて草津は派手がん」 主はそういって別の調子、歌詞、間の手を替えながら唄った。 「ア キタホイ」 “ 一に追分~ ” 「ア キタホイ」 “ 二に軽井沢~ ” 「ヨー ホイ」 “ 三に~ ” 「ア キタホイ」 “ 坂本~ ” 「ア キタホイ」 “ ままならぬ~ ” 「ア キタホイ」 踊りたくなる調子に為った。 “ キクサのサンの字 ” 「ア キタホイ」 “ イネコのイの字は ” 「ホイ」 “ おやじのしるしだ ” 「ア キタホイ」 しんみりと語った。 “ 嫌な追分 身の毛もよだつ ” 「ホイ」 “ 身の毛どころか 髪の毛も ” 「オーサドンドン」 “ 碓氷峠の あの風車 ” 「ア キタホイ」 “ たれを待つやら くるくると ” 「こっちの嫌なは家業が嫌、おしんのは別れが嫌と同じものから出ても、人によって変化します。儂が子供の頃とは大分(だいぶん)と違ってきました。草津(くさづ)じゃ人寄せに都合よく変え始めました」 其々の仕事に三人は戻り朗太たちも二階の自分たちの部屋へ向かった。 お辰(おとき)未雨(みゆう)一家は茶の間脇に一部屋に与えられているので戻った。 三人は次郎丸の部屋で改めて善光寺までの確認をした。 大野が吾郎を呼びこんで話が弾んだ。 「此処の二階は五十人がとこ寝られますぜ」 「そういゃあ、のぞいてみないが権太がひとり一部屋は寝られない、何て贅沢いっていたな」 「前に三部屋あるからと一人一部屋で度肝を抜かれた良うでね、狭い六畳間に三人でくすぶっていますぜ。吹き抜けの隣で下から呼べば用が済みます」 下も殿居部屋がまだ空いている、殿居の間、上段の間の上は人が入れぬ造りだ。 二階の大広間は「百人詰め込んでも床が落ちません」と女将が自慢した頑丈な造りだ。 馬子唄が聞こえる、おしんが饂飩を踏んでいると分る。 「台所土間と板の間(茶の間)が続いているのが良い」と次郎丸はご満悦だ。 「そりゃ武家屋敷でそうは参りません」 忙しいだろうに女将と主がお辰(おとき)を連れて来た。 「娘さんから聞きましたが、女将さんは端唄上手だそうでぜひ最近はやりという物をお教え願えませんでしょうか」 「お芳が自慢などするものですから」 江戸も町中では長唄から端唄へ流行はかわってきた。 神戸節もちらほらつたわり、江戸は停滞期から抜け出している。 「分家した弟が太棹、中棹、細棹など二十本あまりも持っておりますのでお好きな物でぜひ」 未雨(みゆう)が了承して夕餉の後でと為った。 様々の端唄が披露され、中でも分家が「“ 桜見よとて ”を覚えたいので今一度」と強請った。 次郎丸がすぐに歌詞を書き写して渡した。 “ 桜見よとて 名をつけて まず朝桜 夕桜 よい夜桜や 間夫は昼廓へ エーどうなと首尾して 逢わしゃんせ 何時じゃ オヤ引け過ぎじゃ 誰哉行燈 ちらりほらり 金棒引く ” 「なぁ歌右衛門がはなれ駒長吉を中村座で演じた時だ」 「はい」 「伝手があって呼ばれたが、自作だという上方唄を聞かせてくれた。江戸端唄に取り入れらないのか」 「どんな歌詞でした」 “ 柳やなぎで世をおもしろう うけて暮らすが 生命のくすり 梅にしたがい 桜になびく その日その日の 風次第
” 「それだけでは色気がでませんよう」 “ うそもまことも 義理もなし はじめは粋に 思えども ” 間が空いたので「それでお仕舞ですか」と言われる始末。 「まてまて、今思い出す」 “ 日増しに惚れて つい愚痴になり 寝床の床の 浮き思い どうした日和の ひょうたんか あだ腹のたつ 月じゃえ ” 「これぎり」 「柳、梅、桜、月と揃いました。瓢箪は何の例えに」 「聞かなかったしもっとおぼつかない調子でも得意げだった。誰かに整えて貰えばいいものになるのに惜しいと思った」 分家が本調子で“ おまへあるゆえ世間の人が 実に粗末になるわいな そうぢゃないぢゃないか そうぢゃないか ”を披露した。 お辰(おとき)は「初めて聞きましたよ。潮来節に有りそうな調子ですよう」と言う。 “ 黒源
”事黒岩源右衛門が「誠に左様でございますな。追分、小諸も元は潮来節からもとられていましてな」という。 次郎丸が「“ 潮来出島の真菰(まこも)の中で 菖蒲(あやめ)咲くとはしおらしや
サテヨイヤ サヨイヤサ ”の事か」と尋ねた。 “ 浅間根腰の 焼野の中で あやめ咲くとは しおらしや
” 「どうしても似てくるのは仕方御座りませぬ。上方と江戸、人の往来が増えれば街道沿いに口伝えで広がってゆきます」 「そういえば東海道、日光、奥州と瞽女が多いがこの付近はあまり聞かないし、行き会わんな。流行には瞽女が敏感と聞いた」 「越後の瞽女様が来られますがこの辺りは六月に多くまいります。多くの唄が瞽女様によって伝わります」 「その内此方の節回しが越後を通じて広まるよ」 「こうなりゃ此方が本家と今のうちに言い広めておきましょう」 分家の主は締めにそういって手を叩いた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
“ 黒源
” 文化十一年九月一日(1814年10月13日)・狩宿宿~沓掛宿 “ 黒源
”の朝は鶏の刻を告げる鳴き声と、馬の立てるあがきで始まる。 明け六つ前、街道で馬子唄が唄われている。 “ ハイハイ さらしなは右 ヨ~ ホイ みよしのハ左にて ヨ~ ホイ 月と花とを ヨ~ ホイ 追分の宿~ ホイホイ
” 茶本陣の二挺天符は五つ(七時二十五分頃)、二頭の乗懸(のりかけ)が来て親娘を乗せて沓掛へ旅立った。 大野は朝出る傳馬に四十文を渡して分り茶屋へ伝言を頼んでいた。 「四つ時分には着くので十一人分のもり蕎麦を用意してほしい」 「九人じゃ」 「馬方も指咥えるのは拙いのでな」 其処まで義理堅く寄らなくてもと次郎丸は可笑しかった。 今日も茶屋の蕎麦は旨いと皆がほめた。 「おしんの打つ蕎麦も食べたいものだな」 「父親が見世を開いて居ると言っていました」 「ダメダメ。古宿は朝のうちに通過だ、いくら蕎麦が好きでも腹が持たない」 宿の朝飯を抜いても食いたいなんて言いだせない。 八つ前に沓掛の中山道の角へ出た。 沓掛宿“ つるや甚右衛門 ”では未雨(みゆう)と大野への置き手紙が幾つもあった。 この後の旅籠状況と繋ぎを上田で付けるという物で、稲荷山迄は確認済みと書かれている。 田中宿は九月二日、旅籠中屋源兵衛。 上田宿は九月三日、四日、井筒屋宋兵衛脇本陣。 鼠宿村は九月五日、鼠宿茶屋本陣。 稲荷山宿に九月六日、松木完司本陣。 八田の婿の辰三郎も、田中宿まで出向くと返事が来ていた。 借宿“ 黄檗ぬのや
”土屋作右衛門旦那は二日に追分までお供したいので家へ必ず寄ってほしいと未雨(みゆう)へ置手紙だ。 「もしかして上田も泊まると口を滑らしたので、諸先輩へ連絡付けたかも」 「上田に何かあるのか」 「わっちの師匠の生まれが上田で、直弟子の老人が大勢居ります] 「それだと師匠の句碑か、翁の句碑も有りそうだ」 「噂じゃ麦二師匠が白雄師匠の亡くなった後、信濃国分寺に翁の碑を、お建てに為ったと」 「馬鹿に丁寧な物言いだな」 「信濃のお弟子の中で最高峰とまで言われておりました」 「その言い様だと亡くなったか」 「四年前にお亡くなりに、鋳物師で近在の新造の鐘はこのお方に頼んだと聞いております」 “ はるの夜は さくらにあけて しまひけり
” 「此の句は翁を研究する人も年代や場所を調べても知れないと言われています」 「寄るか」 「見ものは八日堂という三重塔が有ると師匠から聞きました。本堂は無いと聞いた覚えが有ります」 「八日堂」 「正月八日の縁日が盛大に前夜から開かれるそうです。三重塔の中に金ぴかの大日如来が祀られているそうです」 此のところ昔の知り人に会い、記憶が蘇っているようだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・上野-沓掛街道~草津道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第八十六回-和信伝-伍拾伍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二部-九尾狐(天狐)の妖力・第三部-魏桃華の霊・第四部豊紳殷徳外伝は性的描写を含んでいます。 18歳未満の方は入室しないでください。 |
|
| 第一部-富察花音の霊 | |
| 第二部-九尾狐(天狐)の妖力 | |
| 第三部-魏桃華の霊 | |
| 第四部-豊紳殷徳外伝 | |
| 第五部-和信伝 壱 |
|
 |
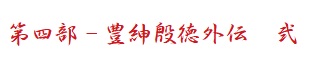 |
||
| |
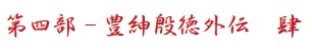 |
||
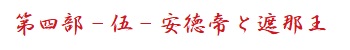 |
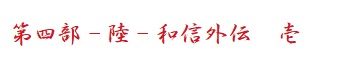 |
||
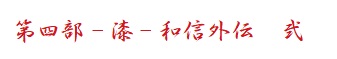 |
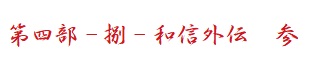 |
||
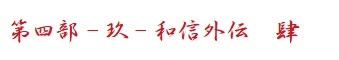 |
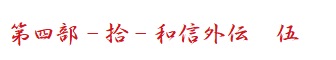 |
||