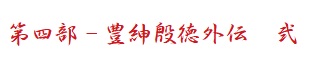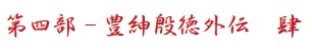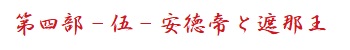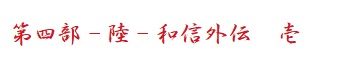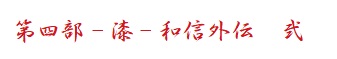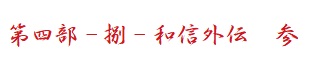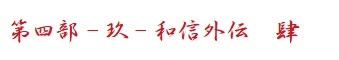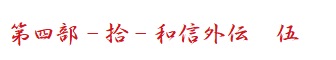|
“ 薬研掘 ”
文化十一年五月十三日(1814年6月30日)・薬研掘
卯の下刻前(午前五時前)、次郎丸は監物と忠兵衛を供に中屋敷へ向かった。
「定栄(さだよし)様、大殿は拝謁を許されますかね」
「監物見かけに因(よ)らず心配性だな。町の中では若さんで行こうぜ」
「私は監物でなく千十郎にしてくれますか。それと上屋敷、下屋敷では定栄(さだよし)様で無いとまずいので。お屋敷から出てからにしてください」
「それで宜しい千十郎殿」
「殿(どの)はいくらなんでも」
「儂より小姓のそなたのほうが実収は良いはずだ」
次郎丸は二百石程度の上士並みだと言う。
今年に入り給付はそれだけだが、四割支給での二百石だから苦しくはない。
「国元に一族が口を開けて餌を待っていますよ」
「そんなに親族が多いのか」
「ざっと二十人。無役席の領分はありもうすが」
「役に立ちそうなのは」
「男は弟二人。私の実入りはせいぜい七十五両。嫁は許嫁が来年輿入れ」
小姓で百石と云え支給は四十石、扶持米は無いという。
親は無役席千石だったが、惣領が収入の有る家は少ない。
「せめて三百両ないと嫁がボロを下げる様だな。殿は国へとは言わぬのか」
「若さんの付き人で在国、江戸住まい一緒ですよ。弟を養子に出せと大殿に言われます」
薬研掘の屋敷から横山町三丁目の突き当りへ出て左へ曲った。
一丁目の角見世が銭屋江戸見世と教えた。
もう小僧が見世の前の掃除をしている。
「吉よ。お前さんは城端へは行かないのか」
「若さん、おいら来年に為らないうちに手代にしてくれるそうで、江戸に残る事に為りました」
よく働けよと声を掛けて先の通塩町(とおりしおちょう)で緑橋を渡った。
橋の先が通油町(とおりあぶらちょう)、通旅籠町(とおりはたごちょう)先が日本橋大傳馬町(おおでんまちょう)二丁目、左手路地の先が猪四郎の酒井屋の有る堀留二丁目と教えながら歩いた。
本町三丁目で左へ行けば室町一丁目、日本橋川の日本橋。
橋の東側、本船町から本小田原町一帯は魚市場の喧騒で賑わっている。
橋の西側には品川町裏河岸、通称釘店(くぎだな)。
橋の向こうを左に折れた、万町、青物町先の楓川の海賊橋。
「昔は高橋と言ったそうだ。三代様の時に架橋され、後に向井将監忠勝様お屋敷を賜り、海賊取締りゆへ海賊橋の名が附いた。巷に九鬼家のお屋敷ゆへと噂有」
「どちらとも今に為っては判明しませんね」
四つ角まで進み右へ行けば九鬼家上屋敷、先に細川越中守下屋敷。
白銀町代地を挟んで白川松平家上屋敷。
掃除をしていた中間へ顔を見せて「築地下屋敷へ行くよ」と声を掛けた。
突き当りの八丁堀は左へ折れて中ノ橋で南八丁堀へ渡り。数馬橋で築地掘を渡ると南小田原町、前後に辻番小屋の有る三ノ橋で周って(まわって)来た築地堀を渡ると、その先右手が一橋(ひとつばし)様下屋敷、隣が白川藩下屋敷になる。
「此処から新しく手に入れた深川越中島の下屋敷へ船で通うと言っていらしたそうだ。まだ更地同然の地所を庭園にされるそうだ」
「此処の下屋敷も良いお庭とお聞きしています」
三人は薬研掘(元矢之倉)から一時間十分ほどで此処まで来た。
服部半蔵正礼(まさのり)が門内で待って居るには驚く次郎丸だ。
「正札殿、こちらへご用事でも」
「定栄(さだよし)様にお礼を言うために此処で待たせて頂き申した」
内玄関まで三人を案内して「そこな床几でお二人はお持ちくだされ」と次郎丸を書院へ案内した。
石町で辰の刻(六時三十六分頃)五つの鐘を打つ音が聞こえてきた。
正札は花月様の前で次郎丸に苦労の礼を述べて下がって行った。
「よくぞ手に入れてくれた。隠居では褒美もままならぬがそちが欲しがっておった相州正宗の小刀を遣わす」
殿と同じように煎餅の礼とは言わなかった。
相州伝五代綱廣が鍛えた物、刀身九寸五分“ 相州住伊勢大掾源綱廣 ”の銘が有る。
伊勢守を名乗る延宝六年以前の作という、大刀は秘蔵されて出てこない。
小姓の忠吉が小刀を、正札が大刀を持ってきた。
「その拵えは庄兵衛興正」
二尺三寸五分、二代長曽祢虎徹と言われた名工の鍛えた技物。
「そちが叶庸助と云う者の話をした時、所持しているというときの顔を忘れられぬ。儂が養子に出た時兄から頂いた物だ。奇しくもそちが養子となる故、我が形見として取らせる」
礼を言って両刀を受け取った。
「実は供の二人ですが。一人は真田のほうで指導役の付き人に選んでくれた二人のうち一人でございます。ぜひともお目通りの上お言葉をかけてくださりませんでしょうか」
「冴木から聞いた、矢澤監物であるか」
「左様でございます」
「これ、忠吉。内玄関へ出て矢澤殿を案内せい」
若いのうと正札と顔を見合っている。
「矢澤監物で御座ります。お引見あり難き幸せに候」
花月様、正札の二人から「よしなに頼む」と言われて「身に替えても」と息張って答えた。
忠吉が大小の刀が収まる木箱を用意して中へ納めた。
三本の飾り紐で飾られた木箱は、監物が持って辞去した。
三の橋から紀伊殿を回り込んで南本郷町で海辺へ出て明石橋へ出た。
八丁堀の南っ側に有る稲荷の橋を渡り、亀島川を高橋(たかばし)で渡り、越前掘の東湊町から白銀町の境の薬師稲荷で刀の礼を言った。
「何か霊験でも」
「霊岸島の由来の霊岸寺の境内に在った橋本薬師の後だよ。三河国鳳来寺由来で鳳来寺薬師ともいう。権現様にも関わる寺で、三代様が東照宮をお建てに為られた伝承がいろいろあるがその内に話すよ」
「短いのを一つ」
「権現様御誕生の時、寅の守り神である真達羅(しんだら)大将像が鳳来寺から消え去るという事が起きたそうだ。権現様がお亡くなりに為った後、元の所に出現されたという」
「真達羅大将とは」
「薬師如来の眷属、甲冑(かっちゅう)をつけ、忿怒の姿をとるという」
新川を二ノ橋で渡ると霊岸島の四日市町鹿嶋の前。
酒田屋に猪四郎の顔が見えたが知らん顔して三軒先の鴻池屋へ入った。
「お帰りなさい」
儀兵衛が笑った。
「可笑しいな、相州正宗は小刀だと聞きましたよ」
「養子に付御形見と思えと貰えた。庄兵衛興正だ」
仰け反っている。
「そりゃたしかに凄い話ですね」
忠兵衛に「草加煎餅を渡してくれ」と呼びこんだ。
猪四郎が居たから向こうへも顔を出してくると酒田屋へ向かった。
「なに通り過ぎるんですよ」
「土産の煎餅を渡してきた」
「昨日はごちそうさんでした。お由はあん位、歯ごたえがないと物足りないそうでね。瓦煎餅は風呂上りの口やすめだとぬかします」
千十郎の持つ木箱をみて「どこの土産です」と首をかしげた。
「鯨の土地の礼として、花月様養子の時に頂いた物を譲り渡していただいた」
「兄上様でなく花月様からですか」
「殿は塩饅頭を下されたよ」
「今ほかに一振り望むなら。誰が良いです」
「新刀で水心子正秀か若い大慶直胤。虎徹に一竿子だ」
「直胤さんは江戸のどこかに居るはずですが。殿様がまだ国元じゃないですか」
「出羽に居るんじゃないのか」
「買い上げたいのですか」
「勝手に使えるのはせいぜい五十両だ」
「そこまではしないでしょうが。買えるかどうか探してみましょう。それより一竿子忠綱ですがね」
「見つかったのか」
「無銘ですがね。若さんの大刀と同じ元禄のころのものだそうでね。一尺七寸八分半」
「無骨者らしい差料だ。一尺七寸九分の行光と変わらんな」
「三十両だそうですぜ。黒鞘に収まっています。何本あっても欲しいものですかね」
「そりゃそうだ。買い取ってくれ」
「龍の彫が有る大小揃いも有りますぜ」
「彫の有るのは百両以上と評判だぜ。俺にゃ無理筋だ。“ なほ ”の薙刀で百十五両した」
千十郎はそれほど興味がないのか出された茶を忠兵衛と飲んでいる。
「もし只なら貰いますかい」
「相手次第だ」
「龍と宝剣。梵字がね、大刀に有るのですぜ、なんと聖観音菩薩だ」
「聖観音と観音菩薩は同じで勢至観音は右に点二つ」
「聖観音と観音菩薩が同じなら問題は無いですがね。なぜ宝剣の上に彫るのですかね」
少し考えた。
「似ているのは大黒天か孔雀明王だな。観音と宝剣は意味が解らん。そいつは考え物だ。梵字無しなら欲しいな」
「梵字が無きゃ、俺とお由から養子成立の祝いなら受け取りますかい」
「二人からなら受け取る。嬉しいぜ。賄賂ととれる相手は困るけどな」
忠兵衛は「煎餅の礼が大小揃いですかい」と言っている。
「煎餅のお返しとは面白い」
千十郎まで話に乗っている。
刀剣好きの旗本、大名は多いが、金に困って売るのが放蕩息子たちだ。
お代替わりの家が狙い目の業者につけ込まれ、安く手放してしまう。
「千十郎は永代で戻るか」
「薬研掘で飯を食わせてくださいよ。御刀拝見をしたくてうずうずしているんです」
刀剣に興味が無いわけでは無さそうだ。
酒田屋を出て大川端で豊海橋を渡った。
北新堀町先の崩橋(くずればし・長さ十一間-幅四間)で渡ると小網町三丁目。
釜屋もぐさの看板が目立っている。
妻楊枝のさるや七郎兵衛も人の出入りが多い。
鎧(よろい)の渡し先一丁目で思案橋前、右へ折れると稲荷堀。
稲荷堀(とうかんぼり・とおかぼり)は松平越中守、酒井雅楽頭の中屋敷を囲んでいる。
幅は七間ほど有るが、行き止まりのせいで流れが無くなり、葭が茂り船は入れなくなっている。
「殿に花月様も蔵屋敷として使いたいようだが船が入れぬので困っておられる」
「何処かと交換してもらうようですかね」
「養子先へ移り住んだ後 “ なほ ”や“
つかさ ”これから生まれる子を此処へと話が出ているが、三千九百三十七坪も有るという。隅へ親娘の住まいを建てようと言っている。今度の金はそれに出る出費も有るので断れなんだ」
次郎丸は内心、白川藩への忠誠の人質かと心配もある。
石町の鐘が八つを告げている。
堀が広がる左前が甚左衛門町、堀の向こうに銀座。
「こんなところで銀貨を製造しておりますか」
「此処へ移って十四年たつ、儂が子供の頃引き移って来たそうだ。此のあたり蠣殻町だったので蠣殻銀座と言いだした人がいる」
住吉町から竈河岸を難波町(なにわちょう)へ出た、浜町河岸を左へ、浜町川には難波橋(なにわはし)、高砂橋(たかさごはし)次の富沢町の栄橋(さかえはし)を渡り、久松町へ入った。
突き当りを左へ行くと村松町の四辻へ出る。
右へ折れて右手先は若松町「此処は屋敷の富代の娘の小間物屋が有り、屋敷へ入れぬ鮨の担ぎを此処へ入れて女中たちが買に来る」と教えた。
鉤手(曲尺手・かねんて)で右へ出て、忠兵衛が怒るといけないので裏門前を通り抜け、薬研掘の表門から戻った。
「何時も両国橋か大橋で渡りますが、永代がこれなら思っていたより近こうあり申した。鉤手(曲尺手・かねんて)が多いので初手は一人では心もとうで御座りまする」
「魚市場へ出て思案橋で小網町と云うのも手だぜ」
「それで朝とは違う道で御座るか」
「今朝浜町川を渡った緑橋の三つ下流が栄橋だ、浜町河岸で横並びさ」
「なにやら簡単に聞こえました」
富代に三人分昼餉の仕度を頼み、大野たちを呼び寄せ首尾を話しながら、二振りの刀を披露した。
千十郎に負けぬくらい興奮しているのは大井源蔵だった。
皆が見ている間とよに「一竿子忠綱が三十両だそうだ」と話した。
「小刀ですか、お安いですね」
「一尺七寸八分半だそうだ」
「行光と同じくらいですね。お買い召されますか」
此の白川行き道中でも一竿子忠綱二尺四寸と藤原行光一尺七寸九分を無骨に差しての道中だ。
普段は打刀、脇差に肥前國忠廣五代忠吉二尺三寸五分に一尺七寸を差している。
旅に出る刀と長さがわずかに違うが、此方は柄巻師に月一度出して色に巻き片を替えさている。
一竿子忠綱と行光は諸捻巻(もろひねりまき)と云うのだと香佑氏(こうし)が言う。
「猪四郎の話しだ。物は無銘だがまがい物では無さそうだ。持ってきたら金を頼むよ」
鰻の煮こごりに鯵の押しずし、小肌の押しずし。
千十郎、忠兵衛も同じものを一緒に食べた。
「これで穴子でも出たら大騒ぎだ」
「予算が出れば用意しますよ」
富代と美代が千十郎に話している。
「これで一人前、いくらなのだ」
「今日は贅沢なんですよ。煮こごりは二十五人前で三百文、一人十二文に押しずし二切れで十六文の二十八文ですよ」
「小ぶりの卵二個より安いのか。築地の賄いを任せたい位だ」
千十郎も意外と世間に詳しい。
屋敷で一日九百文だが十日で均しているという。
「到来物が有れば贅沢できますのさ。お茶に菓子は買うことも少ないし。熱海の魚が月二度ほど市場へ出せない半端物を頂けます」
「そういやぁ千住の本陣でめじ鮪のねぎま汁が出た」
「本陣ですか。よく下世話な物を」
「喜連川の師匠が手紙で頼んでくれていたのだ」
「喜連川に居て千住の河岸の様子が分かるのですか」
千十郎が驚いている。
「驚くのは潮汁の椀だった。白いものが有ると聞いたら伊佐木の白子だ。五人前出すに幾匹必要だろうと考えてしまった」
「そりゃ若様、身は別の客人の腹の中でしょうよ。ここでも八月に入れば作らせますよ」
美代が「伊佐木は高いのですか」と富代に聞いている。
史代がでしゃばって「本陣ですもの高くて当たり前でしょうね」と言う。
「今の時期、十二文程度さ。でも白子は小さいし、育っている成魚を探すのが骨さね。片身刺身で片身煮付けにすれば白子が見つかりやすいのさ」
「でも若さんの言う、潮汁だと骨の出汁で使うので、煮付けが出来ませんよ」
「其処が本陣さ。良い料理人が控えているのだろうよ」
伊佐木の時期が来ればカワハギも旨くなるよと云う。
美代の実家は内藤新宿、家は魚があまり出なかったという。
十七歳でそろそろ嫁入るころだと“ なほ ”が気にしている。
とよに富代をはじめ深川へ幾人連れて行けるかも決まって居ない。
史代は今年春の出替わりで来たが、初めての奉公が屋敷勤めだという。
殿の暇前の忙しい中、薬研掘もいろいろと忙しくなってきた。
次郎丸と“ なほ ”の間には十月末には二人目の子が産まれる。
腰元のつや、華代(かよ)は二十歳に為っていて、暮れには嫁入りが決まって居る。
遅い位だが相手の家庭に事情が有り一年伸びた。
どちらも婿は江戸詰三十石三人扶持の軽輩だが、文化五年から花月様六園整備で小石川大塚上町の抱え屋敷に勤めている。
北に大悲寺、西に浪切不動が有る。
替わりに行儀見習いで十四の娘が二人、六月朔に遣ってくるという。
次郎丸は会っていないが“ なほ ”が大層気に入っているのだそうだ。
猪四郎の話しでは共に大きな商家の娘で、三年の約束だという。
大野と冴木が話しを進め、中屋敷へも“ なほ ”に付いてくれると決まったそうだ。
政(つかさ)の乳母のとりはもちろん、これから生まれる子の乳母も大野と冴木は見つけている。
次郎丸はとよがどうするか気がかりだったが、直枝を仕込んで金庫番へ育てるという。
最近知ったのは家が江戸の結の古株だそうだ。
鎌倉河岸に近い永富町一丁目に宝永七年青物問屋丸屋喜兵衛を開いたという。
多町丸屋十兵衛の別れだという。
連雀町、神田多町とともに青物三か町を為している。
合わせると青物問屋九十六、みずがし問屋が二十七と云う。
今年だと丸屋では十七人の売り子が町回りをしていると招かれた母親が話していった。
そのおっかさんの実家は京橋大根河岸(だいこがし)だが、おっかさんは“ だいこかし ”と言っている。
とよが期待する直枝はまだ十五歳だ、上に兄と姉が居る。
大野も無理して足軽二人を抱えていたが、深川持ちが決まりあと少しの辛抱だ。
大野玄太夫も四十一歳、息子は殿によって家督相続が許され稲荷堀(とうかんぼり・とおかぼり)中屋敷での二十石五人扶持が認められ、大野は薬研掘の持ちとされた。
殿と云うより、周りで冴木が根回しして居る様だ。
本堂治助、近井金治は大野の同輩の次男と三男で、深川持ちと云うよりは早急に薬研掘持ちと次郎丸は考えている。
大野は黙っているが先を見越し、儀兵衛が貸し出しをして居る様だ。
内々で養子入り前に領内巡遊を幸専(ゆきたか)様在国中にどうだと話しが有るようだ。
千十郎は鮭の話をして居ないという。
「どこから漏れるのかな。疑いだしたら限(きり)もない」
「大殿に殿もが若さんをお気に入りの様で。重臣の方々を牽制されるのでは」
「今なら本川次郎太夫は通用するかな」
“ なほ ”は“ つかさ ”に「又お留守になるとさびしいわね」と自分ではないように言っている。
「遅くも産まれる前にお帰り下さいませ」
十月十三日以降だろうと産婆は言っている。
「まだ範囲は二十日くらい幅が有るそうです。二百八十日前後だとは“ つかさ ”の時に教わりました。乳母は悪阻から見て二十五日以後でしょうと断定します」
「産婆は仕事に差し支えるから五月(いつつき)も前の断定は避けるさ」
|