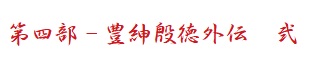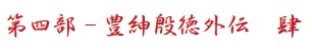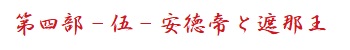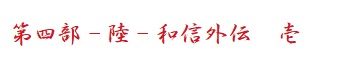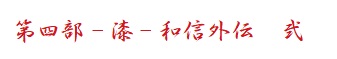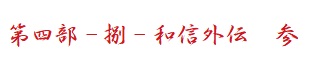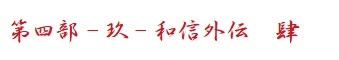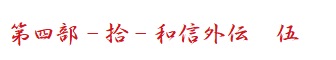|
文化十一年四月十一日(1814年5月30日)・江戸元矢之倉屋敷
定永は文化九年三月、定信の隠居により家督を継いだ。
この五月に初のお国入りを届け出て、五月二十六日に江戸を発つことが決まった。
忠兵衛を共に上屋敷へ出た。
「殿には少将任官のお祝いを申し上げます」
「これも大殿が房総警備のおかげをもってのことだ」
相州警備の松平容衆(かたひろ)は前年従四位下、侍従、肥後守となり釣り合いを取ったと評判だ。
昼に五つの小鉢で豆腐の料理が出た。
「定栄(さだよし)、頼みが有る」
来たぞと思った、普段しわい兄が次郎丸の好む豆腐料理で旅の疲れを労うはずもない。
「一つは父上の庭造りも一段落しそうになったが、作庭の為に国元へ行かせるわけにも参らぬ。三の丸に南湖は維持だけだが、江戸にもう一か所好きに出来る小庭園、いや火事や災害時の避難屋敷に船をつけられる土地が欲しい」
金の相談の様だ。
「初のお国入りともなればさぞかし物入りで正札殿も頭が痛いでしょう」
「忌憚なく言おう。そちの養子縁組は来年六月、儂と弾正忠殿が参府に合わせて行う」
「賜り申した」
「深川久右衛門町とかいう土地を手に入れてくれ。そちの養子縁組の後、父上に作庭指導という事で手を入れて貰うことにする」
俺に買わせて自分の名で大殿孝行を目論んだようだ。
「国元に中屋敷増設を打診したが酒井がよしと言わんそうだ。五百両の工面も付かんでお国入りは恥ずかしい」
「持ち主は」
「安房勝山鯨組醍醐新兵衛」
「知り合いです。参府までに手に入れれば宜しいですね」
「よそへ取られる前に手を打てるか」
「気の利いた者に使いを頼みます」
「二つ目」
おいおい、豆腐で五百両物にしたのにまだ有るのかと思った。
「国元で出立前に二千両工面してきてほしい」
「しかし殿、私めは一度も白川へは出むいておりませぬ、御用商人とも付き合いが有りません」
「房総警備で国元も不如意だそうだ。兄を助けると言ってくれ」
「その銀(かね)が無いと江戸を発てませぬのか」
「いや、国元での貧民救済を国入りに合わせて行う準備が整ったが、会計から不足を申し出てきた」
「抱屋敷は置き土産としても。二千両は借り入れで宜しいのでしょうか」
「上納金で始末は付かぬか」
「私の養子祝い金でも額が大きいでしょう。四半分は押し付けても千両は難しいと思います」
「正札(日記)は、二万両はそちが動かせると云うておる」
「動かすだけで自由に使えるわけではありませぬ。房総警備のお手伝いで銀(かね)が動いているだけです。戻らぬ銀(かね)を動かすものなどおりませぬ」
「そういうな。白川が無理なら柏崎へ頼むことに為るのだ」
「本川で出かけますか。誰かのお供として国元へ出ますか」
本川で出て三輪権右衛門と協力するように大殿の手紙を二通、冴木が持ち出した。
「十四日には発たれますよう。御供は川添殿へお申しつけ下されますよう」
川添は屋敷付の若侍、鴻池屋永岡儀兵衛の持ち家を店借している。
中間なり荷物持ちを何人か付けるのは構わぬと殿の仰せですという。
手紙のあて先は“ 待月へ ”“
良平へ ” の二通。
「待月は三輪権右衛門殿、しかして良平とは誰で御座ろうや」
「須賀川大庄屋でありもうす」
「国元の庭園などゆるりと御見物の上、殿の江戸旅立ち前にお帰りあれ」
八木助左衛門が傍から口を添えた。
「かしこまり申した。大殿の添え状が来ているとはお下屋敷へ行かずとも宜しいのか」
「定栄(さだよし)様には国元の庭園を見て戻られた後で、上方の土産話と共に聴こうと仰せでした」
質素倹約を言いながら、老中致仕後に何ヶ所もの庭園にのめり込み、相当の費用が掛かっているようだ。
上屋敷を辞去し、元矢之倉へ戻ることにした。
「忠兵衛、安房勝山まで出られるか」
「若様のお供ですか」
「いや俺は明々後日(しあさって)には国元へ行くように言われて別口だ」
「勝山といやぁ、鯨組ですかい」
「そうだ。船で行けば俺の出る前に戻れるだろうぜ。屋敷で手紙を書くからそうしたら新川で五大力を探してくれ。もし乗れそうも無きゃおしょくりぶねを雇ってもいい」
「仕立ては四人船頭でも二両は取られますぜ。その代り朝方には着くでしょうぜ」
「念の為さ。八丁櫓でも仕立てられる銀(かね)は預けるぜ」
「五両出してわし一人は気恥ずかしい」
「おしょくりぶねの八人乗合なら銀五十匁くらいか」
「船が居たらそれにします」
屋敷で一分判を二十枚二包と別に南鐐二朱銀六枚を持たせた。
とよは「そっちは使わない分は戻しとくれ、此の四文銭二十枚は団子代だ、好きにしていいよ」と渡した。
屋敷のお仕着せで颯爽と出て行った。
川添甲子郎は殿さまからの申しつけと言うと力んで「しっかりお供をさせていただきます」と答えた。
「わしゃ、また留守番ですのか」
大野はがっかりしている。
大野が一日十一里の予定なら、五日目の夕刻に白川へ入れるという。
甲子郎は「会津様に居る友人は六日で着いたと自慢しています」と言うがいくら陽の長い時期でも体が持たないだろう。
大野は「会津若松まで六十八里は有ると聞いているが」と思い出したようだ。
「松代は六日だと佐久間先生が言うとったぞ」
「白川まで四日は強いだろうな。我が藩の参勤は五日目の日暮れに入れるかギリだと聞いている」
藩が作らせた案内記を持ち出してみた。
一日目は日本橋から幸手迄十二里十丁。
二日目は幸手から小金井迄十里二十七丁三十間。
三日目は小金井から氏家迄九里十六丁三十間。
四日目氏家から越堀迄九里三十二丁三十七間。
五日目越堀から白川迄七里十二丁。
日本橋から白川四十九里二十六丁三十七間。
「二ヶ所の渡し次第で五日目の申の刻なら着くだろう」
後は天気と渡しで遅れても運次第だと大野も納得した。
「ま。四日目にもう一駅伸ばしてもすむことですな」
自分が行かないとなれば無理するのは若さま次第だという。
栗橋の関所は元対岸に有った中田関所で利根川房川船渡しに有る。
川原幅二百十四間、川幅四十間。
絹川の渡しの川幅は三十間、此処は冬場に仮橋と為る。
「荷物持ちに一人か二人連れて出るようかな」
「忠兵衛が戻れば弥助をお供に」
「あと一人雇うか」
「気心の知れたものが宜しいのでは」
「ちくまやに声を掛けるか」
介重達三人を大野は便利に使っている。
「忠兵衛が戻れば弥助と二人御供で、三人雇って庭の掃除に門前の掃除では」
ちくまやの娘もいっぱしに為って松代へ養子に入る次郎丸の屋敷中間、足軽まで送り込んでいる。
この年用人の大野は藩の財政とは別に足軽二人を入れ、自分の下役にしている。
介重達三人は小者として月の決まり日に雑用に出入りしている。
今は儀兵衛が持っているが養子縁組が本決まりに為れば他に出どこが必要だ。
その儀兵衛が客を連れて来たという。
「若様、国元へ御出でだそうで」
「早耳だな」
大野も呆れている。
「なに、出がけに忠兵衛さんに出会ったんですよ。船の手配の手助けをしながら聞き出しました」
「あのおしゃべりめ。内緒は腹に収められねえ」
「心配なんでしょうぜ。○○は簡単に出てきませんよ」
遅ればせながら長旅の無事のおかえりでと挨拶を始め、終わるとようやく連れを紹介した。
「松代の八田の婿殿です」
「先生が言っていた御用商人、八田嘉右衛門のことかね」
「七年前に婿に為りました、糸市手代の辰三郎で御座います」
新兵衛と違い実務を学ばせているようだ、歳は二十五に為ったという。
まだ会所組織は無いという、糸市が分散しているのでその調整を任されている一人だそうだ。
儀兵衛が言うには藩との調整が長引いて纏めきれていないという。
「なんで生糸まで儀兵衛が相談に乗るんだ」
「猪四郎は来ていませんか」
「こっちから帰着は教えていないよ。新兵衛が話しているはずだ」
「噂じゃ若さんたちは木綿の一貫生産に乗り出すそうで」
「どうやって知ったのか教えてくれ」
「尾州知多の醤油屋ですよ」
「そっちへも手立てが有るのか」
「大坂鴻池と間違って挨拶されて以来の付き合いでね」
下総流山の鴻池屋永岡儀兵衛は白川藩に食い込んで久しい。
浅草、深川、八丁堀の地に家作が有り、藩の妻帯者が借りて住んでいる。
表向きは抱え屋敷、川添もその一人だ、そうでもしなければ上士と言えど、六畳二間お長屋で我慢させるようだ。
「また抱屋敷を手に入れようという話が漏れてきましてね。若様に養子の引き出物ならぬ置き土産に買わせようと聞きましたが。本当ですか」
「忠兵衛に聞く前に耳にしていた様だな」
「へぇ。お上屋敷は最近話が駄々漏れですぜ。小石川に飽きたようで海辺にもう一屋敷、趣の替わった庭が欲しいとね」
「大殿は専ら息子たちへ作庭の手本を示そうというようだ」
辰三郎は養父の誓約書を持ってきていた。
“ 私儀若殿様御入用御用意致候此段誓約致候 知義 ”
「これでは俺と命運を共にすると言うと同じではないか」
生糸の商いを学んでいる“ 駆け出しでございます ”と言って指印を見せた。
「養父も結いの仲間かね。“ 流行りものには目がない ”俺に金を出して居ては際限もないぜ」
「若様に信濃の生糸を世に広めて頂く為にはまず松代からをお心にと言われてきました」
「聞いたところでは上田紬の名に勝る物なしという。製品では上田の名で出しても良いなら十年で三倍には出来るだろうさ」
「八王子付近に甲州が上田紬の名を使っていますが一段低く抑えられています」
生糸に為らない屑繭から真綿にする技術、それ自体に差が有るようだ。
「上田藩と揉めても困るしな、栄次郎殿は気骨者だぞ」
栄次郎は幼名、養子入りして忠学と名を改めた。
松平忠済(ただまさ)は六十四歳で隠居したが藩政を仕切っていると噂だ。
松平忠学(たださと)は分家から養子に迎えられ、二年前の文化九年に二十七歳で信州上田藩五万三千石の家督を継いだ。
次郎丸三倍と言い放ったが、養子の話が出てから松代周辺の情報は集めている。
上田は絹だけでなく木綿でも大きな取引が成立している。
「それに松代は先代、当代共にお健やかで養子に入っても当分は見習いで実権など何もないぜ。先物買で出すばっかりだ」
儀兵衛が「そういわずに先様お代わりで、私めは相談だけとさせて頂きます」と言っている。
盆を持って来てもらうと切り餅四つ風呂敷の紙箱から出して大野へ差し出した。
「当座のお屋敷費用にお使いください」
相当内情を儀兵衛が指導したようだ。
「路銀が出来ました」
四人で壱日壱分あれば余るのは確実、壱分判百枚の切り餅一つで贅沢が出来る。
「一つは甲子郎が道中の費用に預かるのだ」
そういって手渡した。
「切り餅持つなど初めてですが持ち重りしますね」
「後で小銭など“ とよ ”と相談して渡すから頼りにしているぜ」
「若様、大分四文銭で苦労しましたようで」
未雨(みゆう)たちが昨日旅の土産で面白おかしく喋っていった。
儀兵衛と辰三郎が辞去して間もなく新兵衛兄いが一人でやってきた。
「殿さまは何を馳走してくださいました」
「豆腐料理だ。まるで茶人さ。ところでいつ酒田へ旅立つのだ」
「明々後日(しあさって)に決めましたぜ。あいつら遊山旅の積りでいるので七つに出て初日は幸手だと脅かしておきました」
「おいおい、俺たちと同じ日だぜ」
「どこへ行くんです」
「白川常宣寺で墓参りしてくるように言われた」
「もう直に命日ですが、合わせないんですか」
実母貞順院は十四年前、寛政十二年六月二十二日、三十三歳で白川にて死去。
「殿の暇が五月二十六日なのでその前に戻れと言われた」
ひと月以上掛かるほど白川は遠くないと新兵衛兄いは笑っている。
「掛かるかも知れないのだ。金策を申し付かった」
「いくらで」
「二千両だが別に五百両出て行く」
「戻るかねなら江戸で間に合うでしょうに」
「五百両は深川に小さな屋敷を建てる金だ」
「若さんが入るので」
「いや殿の云うには下屋敷から大殿がさ。船で行くことが出来る屋敷だそうだ」
「売り物でも有るんですか」
「しんぺえの住んでた家だった場所だ」
「あれはしんぺえのおっかさんの持ち家、大島川の漁師町ですぜ。三千坪は有りますぜ。五百で売りますかね」
深川八幡の海辺、入舟町に佃町、秋葉社などが入り組んでいる。
「全部買って半分は売るつもりで忠兵衛を交渉に行かせた。殿は千坪あれば良いと言っていた」
仲介した者が細切れは困るというのを次郎丸に内緒にしたようだ、房総警備の視察の時鯨組の事を鰹の話としたので、安房勝山鯨組醍醐新兵衛と聞いてその事を思い出して押し付けてきたようだ。
「買い手の当てでも有るので」
「大名家に売り込んでも良い」
それで戻りのない二千は何の金ですかと聞かれた。
「殿の初のお国入りで貧民の救済だと聞かされた。俺の耳に心地良い言葉にしたようだ」
お代替わりでの善行は誰かの入れ知恵だろう。
病人、老人と赤子を対象に千六百人ほどだという。
領民は分領を除いても白川、岩瀬、石川、伊達、信夫、百七ヶ村。
越後は岩船、蒲原、三島、刈羽、魚沼、五郡二百二十一ヶ村に及んでいる。
合わせればおよそ十万人の領民が住んでいるのだ。
次郎丸が林松塢(はやししょうう)に聴くところによれば松代藩は十二万人ほどの領民が居るのだという。
赤子の間引きを防ぐための給付は、定信以前から行われていたが、定信は自分が持ち出して給付を始めたかのように、人を使って広めた。
質素倹約を金科玉条の如く唱えたが、国元江戸での様々な庭園の増設は何の倹約なのか納得は出来ない。
次郎丸は質素倹約も度が過ぎればただの吝嗇に過ぎないと思っている。
背伸びをしすぎない贅沢は、して当たり前だと思っている。
倹約して残した金で国防をしなければ急場に間に合わない、為ればこそ金を稼ぐ手段を模索している。
金持ちから金を吐き出させ、庶民に渡れば消費が伸びる、金持ちが遊行に金を使っても庶民にはなかなか回ってこない。
廻すのには産業育成への投資させることだ。
ただ建物を建てれば技術は伝承する、庭を作れば技術が残る。
そう思えば浪費とばかり言ってはいられないが、寺社の修復の御手伝いを言いつかる大名には大きな負担がのしかかる。
寺社の改築には物持ちは銀(かね)を出し渋るので、大奥へ働きかける寺社は多くなる一方だ。
「大野様。今度はご一緒されるのですか」
「わしゃ。留守番で若い者にお供させる」
「幾日で白川までの予定です。御一緒させて頂けますか」
先ほどの書付を大野が出した。
「五日ですか。一日平均十里、若さんらしくない道中だ」
参勤の道中は皆これくらいが普通で、中には駕籠を空にして急ぐ大名が増えている。
陸尺だって人が乗らなきゃ足も速くなる。
本陣は兎も角お供に割り振る小宿で、宿銭を値切る会計方が多いと聞いた。
そういう噂は街道を勝手に走っている。
「若さんも銀(かね)が入っても懐に留(とど)まらない人ですね」
「二万両持っていると殿に吹き込んだものが居る」
「松代様にもそういう噂が有るようですかね」
「兄いの来る前に儀兵衛が松代の人と来たが、何も言っていないぜ。それより今日から松代で勝手を預かりたいとさ」
あちらのご隠居が手を回したようだと大野が経緯を話してくれた。
兄いが笈摺(おいずる)から北齋漫画を三冊出した。
「全部呉れるのか」
「そうですよ。一冊は仕舞うため。一冊は誰か見せてくれと言うときの為、手垢がついても良い様にね」
「名古屋と昨日言っていたが、江戸でも売り出したのか」
「大野様これがわずか銀二匁八分、良い見世で鰻のお重より安いと来た」
銭換算でいくらですと若い栄吉が訊いた。
「上村様ここんところ銀一匁百十文、三百八文て所ですかね」
相変わらず計算が早い。
次郎丸だと三百三十文から二十二文をひくという数式が理解できず、同じような計算を出来るようになったのは新兵衛のおかげだ。
五枚の絵も板で挟んである厚紙の間から出して広げた。
「これは」
「用はないでしょうが、吉原の大籬の中はこういう風だと求めてきました」
北齋戴斗が文化八年に描いた吉原大籬扇屋図だという。
「よく行くのか」
「まだ大門潜ったことは無いですぜ大野様」
そういいながら写してきた聞き書きを大野に渡した。
一枚が尺二寸に幅九寸ほど有る「こんなに一時に人が集まるほどでもないそうですがね」と並べた。
おなじみ台所の柱に“ 火の用心 ”まで描いてある。
神棚の前に腕を揉ませている楼主に女主(おんなあるじ)。
小上がりの階段上にも女達が描かれている。
「七十人は描き込まれていますね」
栄吉は驚いている「こんなとこへ放り込まれたらどうしていいか迷います」と兄いに言いだした。
裏神保小路から小普請支配の八木但馬がやってきた。
八木但馬は代々十三郎を名乗っている。
次郎丸は別間へ誘って道中でしたためておいた報告書を渡した。
「お頭は御国もとで母君の墓参と聞き申した」
「さすが早耳ですな」
「報告書は明日例の手筈で稲垣様へお届けして置きます」
稲垣太郎左衛門は牧野忠精(ただきよ)家の江戸家老だ。
次郎丸は向こうから呼ばれればとも角、直に屋敷へ届けたりしない。
幾ら大樹、勝手掛老中、大目付と繋がると言えこちらは部屋住みでしかないのだ。
赤坂氷川町、長山直之へ帰着連絡を入れ、支配の八木十三郎が間をつなぐ役目だ。
直之は父親の代に八木但馬支配に入り、一時小笠原若狭支配へ組替えが有った。
「いやぁ、我が屋敷裏も広小路と言われて久しいが両国へ来ると違い過ぎていつも笑ってしまう」
十五分程度で口実の京(みやこ)土産“ 都名所図會 ”と一緒に包んで帰って行った。
部屋へ戻ると新兵衛は栄吉と二人で夕飯を食べている。
「若さんのは“ なほ ”様の部屋へ用意されるそうですぜ」
鰈の煮付け、山芋の千切りにとろろ汁、こういう時の飯は内三が決まりだ。
米三に麦七なら三倍飯が食えると大野も言っていた。
|