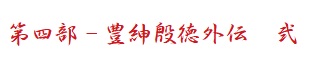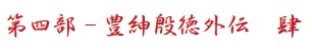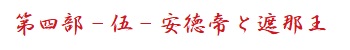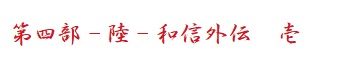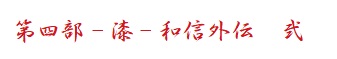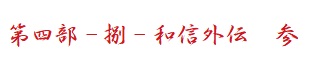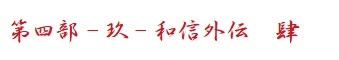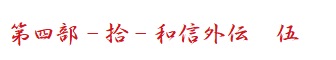|
“ 阿波屋五左衛門 ”
文化十一年九月十六日(1814年10月28日)・松代
朝は明け六つに一汁二菜の食事を食べた。
汁は蜆味噌汁
平に南京・氷豆腐煮物
皿にあまごの塩焼き
小皿は菜の湯掻き
飯
六つ半過ぎに一学先生の住む竹山同心丁へ向かった。
松代道を木町で右へ行くと堀の先に紺屋町。
「昔は此の辺り紺屋が多く住み着いていたそうですが。堀が汚れるというので染め物職人は、城下東の肴町や鍛冶町に移っていきました」
「それはどのあたりじゃろう」
「旅籠の裏の通りです」
右手の馬場への木戸前左の道へ入ると竹山丁で、右の横町先が竹山同心丁。
天池院の南が一学先生の道場と屋敷に為る。
道場から木剣の響きがする。
屋敷の玄関で「頼みますぞ」千十郎が声を掛けた。
「どうれ、どなたで御座る」
此の子が四歳の国忠(くにただ)であろうと「拙者奥州白河藩本川次郎太夫で御座る。一学先生にお目通りをお願い仕る」と礼儀を尽くした。
「そちらは」
「拙者奥州白河藩大野玄太夫に御座る」
「拙者信州松代藩矢澤千十郎にて候」
「都合を聞く故、道場前でお待ちあれ」
聴いていると正確に伝えている。
一学先生が迎えに出てこられ「まずは道場へ]と案内した。
「是、国忠、此の大きなお方が将来のお前のお殿様だ。御挨拶を」
「佐久間修理(しゅり)に御座ります。お引き立て願わしぅ存じ上げます」
こりや相手も驚くはずと三人が頷いている。
「将来儂の力の及ぶ限り後押しを約束しよう」
ごゆるりとなされと道場を出て行った。
「先生お久しぶりで御座います」
「昨日は上手く立ち回られたとお聞きし申した」
「二代養子となれば、思わぬ敵も出来るという事で有りましょう」
「御覚悟が出来ましたか」
「殿のように上手く立ち回れるかがまだ不安ですが、先はなごう御座ります」
師範代の谷口弥右衛門という若者が紹介された。
「卜伝流と小野一刀流の違いは何でしょう」
噂は聞いている様だ。
「兜を発ち割る胆力を練るのが卜伝流、相手の切り込みに乗じて先を取るのが私に教えられた一刀流。これがすべてに当てはめるのは無理とおおもいくだされ」
「兜割は業物次第ではないと」
「正宗を持てば名人に為れるわけでもありませぬよ。私の脇差は無銘ながら一竿子忠綱と伝わりますが、昨日の青竹三本で仔細に見れば傷がつき申した。これでは兜は無理と知れます」
しない打ち込みの剣術が盛んになれば、流派を超えた他流試合も解禁されるでしょうとの次郎丸の話しに一学先生も同意した。
「遅まきながら、善光寺土産の京菓子と草津の温泉の元、湯の花で御座る」
大野が草津で買い求めた湯の花の包を渡し、八ッ橋も二箱差し出した。
腰湯で浸かるくらいで六分目ほど、五右衛門風呂程度でひと包だと書付も渡した。
表で訪(おとなう)声がする。
谷口弥右衛門が出ると「拙者江戸より参った出口丈太郎で御座る。ぜひとも佐久間先生にお会い致しご指南を賜りたい」と大音声を上げた。
「先生老年故他流、同流を問わず門人以外とは殿のお許しを得ぬと立ち会えませぬ。どうぞお引き取りを」
道場破りか、本当の修行旅かは見分けが難しい、三人の名乗りが聞こえる。
「練塀小路中西一刀流出口丈太郎。卜伝流佐久間一学殿にご教授賜りたい」
一学が「若さんご存知かな」と聞く。
「覚え御座らんが中西先生の名を言うとは不審、先生ではなく儂が来ているのを承知で来たようだ」
「打ちのめして恐れ入ったと噂を流しますかな」
手も有るので道場へと次郎丸が言って大野にも指図した。
道場へ三人、皆大男で押し出しの良い男たちだ。
「拙者本川次郎太夫、ご貴殿と同じ一刀流で御座るゆえ一手ご指南賜りたい」
出口は〆たという顔だ、それを見て珍しく次郎丸は大太刀を選んだ。
下段付に構えたのを見て出口がぎょっとした顔を見せた。
木刀の先が触れた途端飛びさがって平伏し「参り申した。儂の及ぶところではござらん」とニコリとした。
大野がすかさず「これは修業の路銀になされ」と三宝(三方)に百文の緡(さし)二本と懐紙の上に南鐐二朱銀を乗せて差し出した。
大人しく三宝を受け取り控えていた男に渡した。
胸を張って道場を去る三人を道場の門人は大人しく見守っている、一学先生の躾が行き届いている証(あかし)だ。
「上手く負ける物ですな」
大野の言葉に一学もうなずいている。
「卜伝流の上を行く男たちですな。さて今日は蕎麦をうつで御座るでな。飛び切り辛い大根も買い入れてある」
大野がにっこりした。
「大野は辛味大根にぞっこんだ」
次郎丸の言葉に門人たちに笑いが広がった。
「本川様、打ち合わずに済むと見たのでしょうか」
谷口は其処が気になるようだ。
「一人ならともかく三人なら、金で方が付く連中と見もうしたで御座るよ」
武者修行の三人は天池社の前で話している。
「先生、なぜ打ち込みませんでした。片腕骨でも折らなきゃ金になりませんよ」
普段一撃必殺、確かな技の持ち主なのだろう。
「死ぬかと思った。打ち込めば俺の脳天にあの木刀が落ちて来るかと肝が冷えた」
誰かの差し金なのだろう、昨日の居合で後方の青竹にも水平に浅く筋が刻まれたのは、片づけた作事方の依田木工右衛門と目付横田助右衛門しか知らない。
次郎丸が一回りしたと見た御小姓が正しい目をしていたのだ。
此の三人もそこまでの情報は知らずに来たようだ。
四つの鐘で門人たちが新たに十人ほど遣ってきて、蕎麦の仕度が賑やかに始まった。
庭では竈に大釜が据えられ水を汲みいれている。
手慣れた様子に出てきた修理(しゅり)も笑いが止まらない。
八つの鐘に送られるように伊勢町へ向かった。
“ 阿波屋五左衛門 ”には辰三郎が来て未雨(みゆう)と話が弾んでいる。
「先ほど藤本善右衛門様と保右様が御帰りに為り無事取引の誓約書を交わし、こちらの希望の上物、並み物合わせて年二千疋の契約、松代紬との名称の区分けなど細部まで纏まりました」
前日から相談に松代へ親子で来ていたという。
上田紬と同等に織れるように織子への指導も行い、双方で機屋(はたや)を増やす費用は八田嘉右衛門が十年で千台まで持つとなったという。
「資金は必要なら結へ言うんだぞ、織機だけではないのだからな」
辰三郎へ念を押しておいた。
「稲荷山は来ませんね」
「慎重に下調べでもしているのだろうぜ」
夕飯は今日も豆腐が多めだ。
汁-巻き湯葉、しめじ茸の吸い物
皿-塩鰤の焼き物
鉢-里芋と南京の煮物
小皿-大根のはりはり漬け
小竹葉(おざさ)豆腐に振り掛け山椒
飛龍頭(ひりょうず)と蕗の旨煮
女郎花(おみなえし)田楽に胡椒醤油
餡かけ豆腐
飯
「蕗のほろ苦さと、染み出た牛蒡の旨味がたまらんな」
大野と未雨(みゆう)はお代わりが欲しい位だと褒めている。
主が家の料理人と豆腐屋の合作ですと二人を連れてきた。
大野が大層褒め、南鐐二朱銀を懐紙で二つ包んで、二人へ差し出した。
「おと、そんなに美味しいの」
「おめえの年でこいつが旨いと言われちゃこっちが心配だ」
中年男二人は大笑いだ。
「あたいはあんかけ豆腐が温くて旨いよう」
「娘さんえ、それならもう一品試してほしいのでお持ちしてよござんしょうか」
「試してみたいわ」
「そうだ、禁酒も解けたので酒も出してくれ。我らももう一つ二つ食べてみたい」
すぐに御仕度をと主も台所へ向かった。
「おっ、青海(せいがい)豆腐ではないか。一度しか食したこと無いぞ、よくぞ青のりが手に入った物だ」
葛湯で豆腐を煮、醤油をさし青のりを煎ってもんでふりかける物だ。
「あっちもこいつは旨いもんだと思いますね。葛餡かけもいいがこいつは堪らんね」
お芳は二人に先を越されて膨れている。
餡かけ豆腐を「これで最後ですよ」と出されて上機嫌に為った。
「お武家さま。豆腐百珍はお読みで」
「おお、試してみたいが全部は無理だな。信濃にいて良く青のりが手に入ったな」
「上総物が手に入らねえで作れませんでしたが、おとつい三河湾の“ あおさ ” が手に入りまして御座います」
|