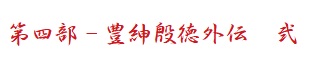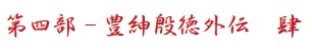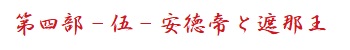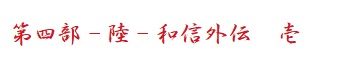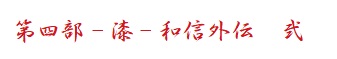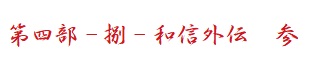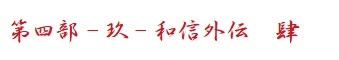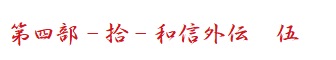|
文化十一年四月二十六日(1814年6月14日)・須賀川
卯の刻(四時)。
川添甲子郎が残って勘定をすると言うので六人で先へ出た。
道中記は笹川へ一里二十九丁だが、生沼文平は藩の記録に二里八丁とあるという。
「伊能様の記録が元ですからほぼ間違いないものと。笹川から郡山は一里九丁ですが道中記を足してゆくと一里二十丁と為っており申す」
郡山まで道中記で三里十三丁、藩調が三里十七丁。
多代女は「問屋場が三カ所あり間は五丁程、南黒門から北黒門の間は十一丁有ります」と言っている。
「一里塚でさえ一里とは限らない。伊能先生でも距離を測る基点が定まらなくてさぞかし困っただろうな」
「若さん、一里塚は間が一里じゃないんですか」
岩平は不思議そうだ。
「新兵衛兄いは郡山宿南手前、笹川宿南手前と白石坂南手前の三カ所に一里塚だと話していたよ。南黒門先の一里塚から計ればどのくらいか分かるだろうが計った記録を見た事無いそうだ」
「確かにそのようで御座る。作られたときの記録は江戸の道中奉行所なら、あるで御座ろうが、外には出て居らぬようでござる」
北町の黒門を抜け、坂を下った。
釈迦堂があり、釈迦如来坐像、庚申、大黒天が並んでいて、不動明王像の台座には文化八年の銘が有った。
釈迦堂川は往古に岩瀬の渡し場、今は中宿橋で渡ることが出来る。
此処からは越後高田藩領。
鎌足神社の前を抜けて上人坦に真新しい“ 二十三夜塔 ”昨年の建立だ。
下宿(しゅく)で川添が追い付いた。
隣の森宿(しゅく)は古代の東山道の磐瀬駅。
白石坂の登りへ入ると五十三番目一里塚。
白石坂を下ると供養塔がたくさん置かれている。
「筑後塚で御座る。守谷筑後守が此処で伊達によって成敗されたと伝わり申す」
他領でも知識は豊富のようだ。
滑川橋をわたり街道は十貫内(じっこうち)村へ入る。
五十四番目の一里塚は笹川宿の手前にある。
荒川を蛍橋で渡ると、笹川宿ここからが二本松領。
音無川の耳語(ささやき)橋を渡った。
「花かつみの伝説の地ですわ」
次郎丸は万葉と思い歌い上げた」
“ あさかやま かげさへみゆる やまのゐの あさきこころを わがおもはなくに ”
「そうではなく、翁がその花を探したという地の元の話しの地なのです」
“ 安積山 影さへ見ゆる 山の井の 浅き心を 吾思はなくに ”
“ 安積香山 影副所見 山井之 浅心乎 吾念莫国 ”
「見つからなかったと出ていたと思うが。万葉の前采女(さきのうねめ)が読んだ歌から様々な伝説が広まったという話だ」
「いくつくらいあるんです。須賀川では葛城王と春姫が此処で別れを惜しんだという話と春姫が采女に為るために奈良の京(みやこ)へ向かうとき、恋人と別れを惜しんだ話があります」
岩平は昔物語が好きなようだ、後を多代女が続けた。
「その後の二人が別れ別れになり恋人は山の井の清水に身を投げ、春姫は戻ってそれを聞くと山の井の清水へ身を投じたと伝わります。二人を憐れんだ村人が塚を作り祀ると塚の周りに薄紫の花が咲いたそうですわ」
翁は新古今の歌を頼りに探されたそうですわと多代女が言う。
「でも探したのは場所が今の安積山で此処とは違うのですわ」
“ みちのくの あさかのぬまの 花かつみ かつ見る人に 恋やわたらん ”
「細道に出ていたのは前に覚えたよ“ 等窮が宅を出て五里計 檜皮の宿を離れてあさか山有 路より近し 此あたり沼多し かつみ刈比もやゝ近うなれば いづれの草を花かつみとは云ぞと 人々に尋侍れども 更知人なし 沼を尋 人にとひ かつみかつみ と尋ありきて 日は山の端にかゝりぬ 二本松より右にきれて 黒塚の岩屋一見し 福島に宿る ”でいいのかな。翁は探し当てられないと書いているね」
「曽良さまは日記にかつみについて触れていませんの“
山ノ井清水 ”の事を書いて、その日の日記の締めくくりは“ すぐニ福嶋ヘ到テ宿ス。日未少シ残ル。
宿キレイ也 ”なんですの」
「翁は歌枕の花かつみを無視できないと押し込んだかな」
「まぁ、意地悪な言い方。伝承の奥まで掘るのですね」
「それが楽しみの一つさ。多代女さんの句の裏も探そうかな」
「しりません」
ぷっと膨れた顔で歩き出した。
岩平が聞こえない様に「若さんいいんですか。怒ったようですよ」と言う。
「翁の碑を見て呆れない様に予防線だよ」
「何かあるんですか」
「郡山とは無縁の句が彫られているそうだし」
「何か隠しているのですか」
「行けば分かるよ」
多代女が待っている。
「雨考さまが二十年前翁の百回忌を催しましたが。郡山でも記念した碑が善導寺に建てられたと云いますが、七年前の大火で失われたと云います。雨考さまはこの句も見ては居ないというのですわ」
“ 安積山 かたびらほして 通りけり ”
「雨考さまの云う通り、どこにもこの句が出てきませんの。露秀さまは善導寺に、ご自分の師である二代沾圃さまの顕彰碑をその十五年前に建てています」
安永八年二代沾圃(せんぼ)の七回忌だという。
「“ 安積山 ”(あさかやま)の碑が失われた年、露秀さまは亡くなれておりますわ」
次郎丸は翁伝説がこれからも増え続けるだろうと実感している。
日出山へ八丁あまり、次郎丸は多代女の足がきつそうなので、軽尻(からじり)を人馬継立で郡山迄雇った。
自覚はある様で大人しく馬へ乗った。
甲子郎が追分に“ 十九夜塔 ”を見つけた。
「なにやら懐かしい」
“ 従是磐城道 ”と道標も兼ねていた。
日出山から小原田へ十五丁。
小原田には本陣と高札場が有った。
五十五番目の一里塚は小原田宿の出口に有った。
郡山迄十五丁。
須賀川より郡山迄、生沼が藩の記録で三里十七丁と甲子郎とはなしている。
休息は殆ど取らず九時に桝形を抜けた。
上町の問屋場で馬を降り、堂坂妙音寺観音堂往復の軽尻(からじり)を雇った。
片道一里十八丁だという、往復七十六文だそうだ。
福原の馬継は中十日なので郡山で乗り換えなしで済むという。
帳付けは福原まで二十五丁で十九文だと多代女に話し、街道をそれるが道を知る者を選んでくれた。
上町“ ゑびや 横田冶右衛門
”で到着を告げると新兵衛兄いが出てきた。
「ずいぶん早いですね。こちらの面子は夜に揃う予定です」
「多代女さんが堂坂に有る芭蕉の碑を見たいというので早めに来たのさ」
「あれですか。良いんですかね」
「兄いが言うまでもない。見れば納得するさ」
次郎丸は兄いが今年見てきたことを未雨(みゆう)と話していたのを聞いている。
弥助と忠兵衛を兄いに預け、先に蝉塚へ向かった。
福原宿へは二十五丁。
会津街道追分に風化している道しるべが有る。
“ 右奥州街道 ”
“ 左會津街道 ”
下枡形先右手へ三春道の追分。
“ 従是三春道 ”
左手に御霊大明神が有る。
逢瀬川に架かる木橋を渡った先に藤屋本店がある。
「ここは藤乃井と言う酒蔵です。百年ほど前からこの地で酒造りを始めたと言います」
馬の上から脇を歩く次郎丸へ何かと話しかける、蝉塚が近づき、心が逸って居る様だ。
街道左手高台に鎮座する日吉神社は千年を越す古社だという。
左側にある無量山阿弥陀寺の鐘は江戸で鋳られて運んできたという。
「百年ほど前、享保二年の銘が有るそうですわ」
この付近の知識はあるようだが、来たのは俳句に目覚める前で、蝉塚へは行っていないという。
福原一里塚に福原宿南木戸が見える。
博労は右手の道へ入ってゆく。
「だんなぁ。この先が元の福原ですがな。西原の旧道いいます」
元西宿で此処の住民が福原に新道開設と共に移動させられたと言う。
阿武隈川の渡しを渡る、土手下は水田が広がっていた。
堂坂の妙音寺観音堂はひっそりとしていた。
多代女は堂守へ用意してきた紙包みを「供養料よ」と渡した。
門内に石柱がある。
“ 閑けさや岩にしみ入る蝉の声 ”
“ 佐々木露秀 不孤社中 ”
“ 寛政九年丁巳 建立 ”
「趣がないわ。石選びが間違っているわ。これでは蝉の声がしみいるのは無理筋だわ」
裏を見て何も言わずに門の外へ出て行った。
「あれほど期待してたのに。どうしたんでしょう」
岩平も裏へ回ってすぐ戻ってきた。
「どうだね」
「これでは句が泣きます。翁をたたえても逆に貶めてしまいます」
戻り道、次郎丸は馬脇へ岩平を付かせて先へ行かせた。
生沼文平と川添甲子郎も裏を見てきたが、何も言わずに後ろを歩いている。
問屋で馬からおり「団子か饅頭は何処が美味しいの」と聞いて、四文銭十枚ひとくくりを駄賃の上乗せと渡している。
「本陣手前の和久屋の茶見世が評判だね」
「有難う。寄ってみるわ」
饅頭は今蒸し(ふかし)てると言うので岩平が残って“
ゑびや ”へ運ぶことに為った。
足盥を運んできたのは幼い子供たちだ。
年増の女中が「脚絆はこの子たちが洗って火熨斗をかけて置きます」と言う。
“ ゑびや
”は奥が深い、裏庭の先に堀が有り向こう側が代官所だという。
生沼文平が「ここ郡山は大槻組、片平組、郡山組と三カ所の二本松藩の代官所が有り申す」と甲子郎と話している。
夕の食事が済むと兄いへ連絡が来た。
次郎丸と二人で筋向いの呉服屋へ入った。
六人の中年の男たちが談笑している。
「西小野屋の覚右衛門で御座います。お運び頂き“ ありがたやでございます ”」
次々名と三番指印に三番の合言葉「ありがたやでございます」を次郎丸へ告げた。
郡山、二本松、福島で呉服商の商仲間(あきないなかま)だという。
「“ 流行りものには目がない ”なり立てのほやほやだよ」
「御養子がお決まりとお聞きし、新兵衛さんからお近くへ御出でと言うのでご都合も構わず無理を言い、もうしわけも御座いません」
「結の人達は単なる知り合いではない。いつでも時間が有れば顔出しなど容易いものだ」
容易い(たやすい)と言う言葉に一同は感激している。
「福島は今年も六月十四日が生糸市です。多くの生糸が買いたたかれ江戸に京(みやこ)へと持って行かれてしまいます。新兵衛さんは地場で機織りを増やせば文字摺絹の名がよみがえると言います。値が上がらず多くの生糸が手に入れば土地に貢献できます」
「待ちなさい。生糸ではなく真綿取引は推奨した。京(みやこ)大坂、江戸に対抗しては取引が成立しない。買い取り商と争うべきではない。まして天王市相場は無視できない相談だ」
岡村熱田神社と長倉村八雲神社合同で行われる天王祭の市は、その年の取引値を決めたというほど大きな取引が有った。
では私らにどうしろと言うのかと紛糾した。
「六人力を合わせ、養蚕農家と真綿取引の安定をすること。買い取り商たちと争わずに差し値をすること」
「無理を言いなさる。買い取ったものをどう売れと」
「聞いていないのかね」
「知多木綿、上州絹布の事ですか。資金が有りません」
「昔の夢を捨て、やるなら織の指導職人を雇い、織子の腕を上げることから始める。いきなり良いものが大量に生産できるなど絵空事だ」
紬はどうだろうと兄いが下手に出た。
「信達(しんだつ)は奥羽内の半数の生糸が生産されると聞いた。されば屑糸の割合も増える。やる気が起きれば知多木綿に投じたのと同じ資金を結に呼びかけ、此処へも投資させる。農家で細々生産していては京(みやこ)、大坂の商人に対抗できるはずもない」
上州座繰り機の普及がこの地を救う筈だと兄いも強調した。
下総結城縞と高機(たかばた)の技術が知多木綿を成長させるとも話し、此方で種紙も優秀な種には一枚二朱を提示して良いと些細と思ったが伝えておいた。
資金は千両、織機十台単位で一組、大庄屋を説得して一村丸抱えの一貫生産を勧めた。
「もちろんの事、今ある機(はた)での生産は認めなければならぬよ。農家の臨時収入は村の財産だ」
「いくら結でも一組千両など無駄には出来ませぬ」
自分達の懐からも応分の出資と思って居る様だ。
「あにい、幸八たちと同じ仕組みは無理かな」
「幸八、藤五郎と同じ三十年元金均等返還、利無しですか」
六人が食いついた、尾張、紀伊では年利一割としてきたと説明した。
「利無しで三十年の均等返還をお許しに」
縮緬生産と京(みやこ)の買い取り商人と協調できる組を福島、二本松、郡山の三カ所、初年度織機十台単位で一組が三カ所、十年で五倍までは次郎丸の裁量で資本投下を約束した。
「紬で一反を三丈二尺、幅壱尺四寸、一疋が二反で六丈四尺ただし短いのと換算して値を決めよう」
幅広物でなければはいけませんかと言う。
「尺四寸物を一村でやるなら任せてみよう」
「誰に仕切らせます」
兄いは其処が肝心だと思っている。
「市原隆右衛門(りうえもん)に頼もう」
「須賀川ですか」
「あそこなら郡山へ連絡も取りやすい。戻りがけに申し入れておこう」
「お待ちください。仕事は此方、仕切は須賀川では困ります」
兄いがにゃつとした、良い食いつきだと次郎丸も安心した。
「ではこの六人の中で一人二番に推薦してくれるならその者に仕切らせる」
福島北南町の“ こうだや ”寺嶋喜二郎を五人が揃って推薦した。
「種紙ですが、一種に絞りますか」
「できれば三カ所別種からはじめたいが当てでもあるのか」
「白川様分領保原(ほばら)をご存知でしょうか」
「陣屋が有るとは承知しておる」
「“ さんと ” の名は御承知でしょうか」
蚕都(さんと)、鴻池屋永岡儀兵衛が連れてきた八田辰三郎が言っていた上田養蚕の種紙の事だ。
「聞いている。六十年以上各地で名をあげているとか」
「何年も十枚一両で苦しんでおります。一枚二朱で宜しければ買占めも可能です」
「だめだ。今六百四十文、高くとも七百四文までだ。結は前年他の取引業者へ渡した分以上の余分を買い取りはしても、買い占めての独占には金を出せない。相場を無理に上げても困る。種紙用の資金は面倒みるから独占しての相場崩しはしないでくれ」
白川藩、二本松藩、福島藩にまたがる紬生産の端緒が開かれるのも近い、元々幕府への冥加永で大きな特権を得ている地だ。
此の当時、種紙冥加永は伊達地方で二十両迄落ち込んでいて京(みやこ)では伊達の値段が高くなるのを警戒している。
生糸一箇(九貫六百匁)の取引値は三十五両から三十八両。
兄いが調べた京(みやこ)の引取り値が四十二両程度、荷づくりに二朱、送料一両が掛かるという。
「喜二郎さん。俺たち三人は明後日此処を発って、福島を経由して酒田へ戻る。福島で幸八たちも交えて話を煮詰めましょうや」
次郎丸が改めて“ こうだや ”寺嶋喜二郎の二番を確認した。
兄いは冬場酒田から福島まで八日、夏場は六日で戻れるそうだ。
“ ゑびや 横田冶右衛門
”へ戻ると皆がまだ起きていた。
「何の相談でしたの」
「しのぶもぢずりの相談さ。幸八と藤五郎に酒田で許しが出れば江戸で紬の見世を持つので、中通は福島が中心でやろうというのだ」
「しのぶずりは高価で織れる人も染める人も少ないとか」
“ みちのくの しのぶもぢずり たれゆゑに みだれそめにし われならなくに
”
「百人一首河原左大臣ですわ。難しいうたですわ」
「河原左大臣源融(とほる)は自分じゃないと言いながら見捨てないでくれと頼むようにしたと師匠は教えてくれた。古今では少し違う写本も残っている」
「どこが違うのですの」
“ 陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れむと思ふ 我ならなくに ”
「模様のように心が乱れると言うのでしょうか」
「伊勢物語は“ そめにし ”にしてあるよ。それより幸八と藤五郎は福島で紬に木綿の仕組み教えてやってくれ。六人いたが全員居る所で話すと面倒だから福島で話させると決めてきた」
兄いは二人に言い聞かせた。
「一度おさらいしておくといい。酒田で説明するのに話す手順も付くだろう」
「兄い」
「どうしました」
「今晩でかたぁついちまったぜ。明日はやることも無くなった。美味いもんでも食わせてくれよ」
「そうはいっても鰻に蕎麦切、川魚に鯉こくくらいですぜ」
思案していたが「福原の先二十丁ほどに佐世姫と大蛇の伝説がある蛇骨地蔵堂てえのが有りますぜ」と思いついたようだ。
「近くへはいきましたが、寄っては居ないのです。小娘の頃で怖らしく思って大蛇の骨の地蔵様は見ていないのです」
多代女は昔を思い出しているような顔を見せた。
「昨年ですがね。秘仏だそうで見せて貰えませんでしたよ。噂じゃ五尺七寸も有るそうでね」
「それならお堂の外で拝むだけで済みますわ。行っておきたいですわね」
岩平は母親の気まぐれはいつもの事だという顔だ。
「もちろん若さん暇ですから行きますよね」
蛇骨地蔵堂は東勝寺境内に有るという。
「高柴デコ屋敷も近いですぜ」
「ありゃ三春だろ。まごまごしてりゃ三春か本宮に出ちまうぞ」
わらっていやがる。
|