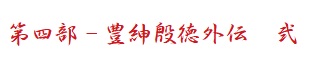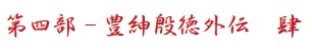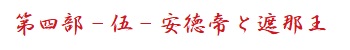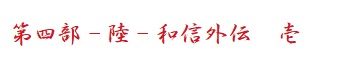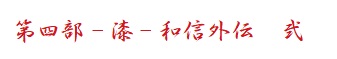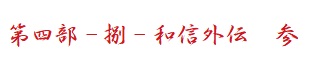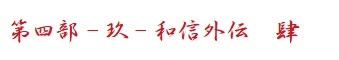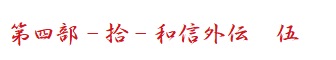|
“ 板鼻宿 ”
文化十一年八月二十一日(1814年10月4日)板鼻宿~沓掛宿
福田脇本陣は木島本陣より地面が多く取られている。
屋敷もわずかだが大きいそうだ、問屋は両家が半月交代で務め、今は福田脇本陣が問屋の当番に当たるという。
“ わくや小右衛門 ”は昨晩の内に当番の福田家問屋場へ六頭の乗懸(のりかけ)の手配をしてくれたので明け六つ前に馬方が表で準備している。
安中までは短いので乗懸(のりかけ)でも四十文。
戻りの道中も世話に為りたいので松代を出る前に書状で日時を知らせると約束した。
“ わくや小右衛門 ”を明け六つの鐘に送られて旅立った。
六丁目三軒先に福田脇本陣。
三丁目右手に木島家問屋場、木島本陣、向かいに当番の福田家の問屋場が有る。
高札場は左手に在り、斜め向かいに牛宿が有る。
牛宿に馬ばかりだは江戸もんの悪口だ。
板鼻宿京口木戸まで宿(しゅく)長十町三十間。
十四番目板鼻宿は高崎から一里三十町、安中宿まで三十町、
板鼻堰用水が街道右手に有る、宿の主が高崎で烏川へ落とすと教えてくれた。
碓氷川の木橋はさすがに馬から降りて渡った。
乗る前に大野は四文銭五枚括りを馬方の駄賃の上乗せと配った。
右手に御料傍示杭が有り、此処からが安中藩領中宿村となる。
碓氷川渡し場に冬場、土橋が許されたのが前橋藩から幕府領となる延享四年。
十八年後の宝暦二年には通年で仮土橋となり、今は木橋が架けられている。
二十七里目中宿一里塚は目の先に有った、左塚は民家の陰に為っていた。
高札場の間が追分、享和二年の庚申塔が有る。
初め不思議な常夜燈のように見えたので例によって次郎丸は降りてみている。
笠石が大きい屋根の様に感じた。
「まるで一人何役もこなす役者の様だ」
正面は“ 庚申塔 ”だ。
左面は上りの旅人の目に入る“ 從是 一宮 大日 街道
” と道しるべ。
「こりゃ貫前(ぬきさき)神社への道しるべで御座います」
馬子に教えて貰った。
碓氷川の上流が街道を横切り土橋が架かっていた。
此処も一同馬から降りて橋を渡った。
「大丈夫なのに、若さん慎重すぎる」
お芳の言葉に未雨(みゆう)が珍しく怒った。
「馴れぬ川を越えるに、流れがきつい場所では慎重になるのが大将の器だ。お芳は足軽でもほめ過ぎで権太以下だな」
「どうせ女は男以下だよ」
是には次郎丸も大笑いだ。
「師匠の負けだな。だが権太が一番下は可哀そうだ」
「どう見ても朗太(ろうた)より歳が上とは思えませんぜ。まるで十八、九の悪がきだ」
木戸の先が安中宿下木戸だと馬方が大野に教えた。
此処は安中藩三万石。
板倉勝尚(かつひさ)三十歳が治めている。
文化二年五月十二日、養父の死去により家督相続。
従五位下伊予守
文化七年九月、奏者番就任。
十五番目安中宿は板鼻から三十町
宿(しゅく)長三町四十四間と短い宿場だ
松井田宿まで一里三十町とまるで間宿(あいのしゅく)の様な感じだか、定式人馬の半減が認められ息を繋いでいる。
藩士を除けば男手が百五十を切るという助郷頼りの宿場だ。
右手の脇本陣は上の脇本陣金井家が間口十一間半、下の脇本陣須田家が間口八間。
向かいに伝馬町で本陣および問屋を営んでいる須藤家が有る。
大野が昨晩の内に手を回しておいたので馬は用意されていた。
此処は難所も有り百六文だという、六百三十六文にたいし大野は南鐐二朱銀を出すと釣りに四文銭で四十一枚出された。
大野は豆板銀をあまり使いたくない様だ。
安中も飯盛女を置けず、その分板鼻に茶屋が増えてきた。
安中城門口は右手の大手門へ登る大手坂、先に高札場。
明日は六斎市の立つ二、七の日。
松井田宿上木戸を出ると谷津の高札場、右へ街道がくねり上野尻にも高札場。
安中大木戸が出てくる、その先で人家が途絶え松並木が続いた。
「安中藩は此処までなの」
「松井田の先、御関所も御領内ですなぁ」
村境の先に人家が増えてきた、街道から奥に二十八里目原市一里塚が見える。
馬方によれば一里山一里塚だという、対角に街道からずれて見えた。
五町ほど坂を登ると原市村の集落。
「原市村に在ると言っても一里山のほうが一里塚の名にふさわしいな」
此処の村は絹買の商人が多く出入りしていると秩父の絹買が話していた村だ。
原市には茶屋本陣を五十貝(いそがい)家が受け持っているが、一行は訊いただけで通り過ぎた。
畑の中に大きな塚が有る、しかも街道の両脇だ。
「この方が一里塚だと通用するぜ」
「奥にもまだありますぜ旦那」
馬方が指差す先に小振りの塚が出てきた。
八本木立場に山田卯兵衛茶屋本陣が有るが、松代藩は景色を楽しむため野立をすると千十郎が話している。
捨て鐘が聞こえる、五つの鐘だが六時四十分くらいだ。
一行は小奇麗な“ あまざけ
”の暖簾の休み茶見世を選んだ。
大野は四文銭十枚括り六つを馬方に配った。
二十九里目郷原一里塚、江戸より是まで徐々に高みへ来ている。
「板鼻からでも五十丈は登ってるでなぁ」
馬方も賃銭の高いのをそのように説明している。
左の郷原の妙義道に真新しい常夜燈が有る。
「十年くれえ前に地の人たちが建てなされたで」
次郎丸は馬を止めさせ見に行った。
正面“ 白雲山 ”
東向き面“ 文化五年戌辰四月七日
”
台石西向き面“ 当所講中
”
台座に“ 是より妙義道
”
高さは二丈近くも有り、台座には多くの建立者名と石工向山民吉の名も見えた。
山道は下りで正面に妙義山が見える。
“ かうづけや はこその山の あけぼのに 二声三声 鳴くほととぎす
”
信生法師。
“ 草枕 夜やふけぬらん 玉くしげ はこその山は 明けてこそ見め
”
能因法師。
波己曽(はこそ)社は妙義神社の古名、白雲山は妙義山。
「良い声ですなぁ。お返しに馬子うたなど聞かしましょう」
“ 雨がふりゃこそ~~松井田泊まり~~降らにゃ越します~~坂本へ
”
「おれたちゃ降らないから峠越えだ」
権太めもう一度とせがんでいるうちに松井田の江戸口木戸へ着いた。
木戸内は両側に幅・深さ共に三尺の掘割が完備している。
街道右手字下町の徳右衛門脇本陣
街道左手の仲町金井藤右衛門本陣は壱百七拾壱坪あるとお芳が言う。
金井本陣の問屋場が月番で馬を乗り継いだ。
第十六番目松井田宿、安中宿から一里三十町。
宿(しゅく)長九町八間。
六斎市は三日と八日。
坂本宿まで二里十八町。
吾郎が「外郎が有りますぜ」と声を掛けた。
「善光寺にも似たものはあるだろうが少しは買っておこう」
「あっしが買い入れておきます」
吾郎が前の“ 諸国名産 頂透香 陳外郎 虎屋 ”の見世へ向かった
手持ちぶたさで次郎丸が台詞を詠んだ。
“ 親方と申すは お立合の中に御存知のお方もござりましょうが お江戸を発って二十里上方 相州小田原一色町をお過ぎなされて 青物町をのぼりへおいでなさるれば
欄干橋虎屋藤衛門只今は剃髪致して 円斎と名乗りまする ”
つい舞ってしまった。
「七代目の芝居はおっかさんと見に行ったわ。良い声だったけど若さんのほうが、張が有る」
「褒めてくれるなら何か買おうか」
「善光寺土産をたくさん」
「いいとも、背負えるだけ買ってやる」
介重が「持ちきれなきゃ俺たちも持ってやるぜ」と嗾けた(けしかけた)。
中間三人にとってお芳は妹のように思える様だ。
「坂本からは歩くというから、重いものは俺たち三人が分担するぜ」
千十郎が「若さん、良い事が有る。坂本からの峠越え、荷駄を二頭雇って身軽はどうです」と妙案を出した。
外郎店は天正の頃に店を設けたと未雨(みゆう)が聞いてきた。
道はきつくなるので乗懸(のりかけ)百二十三文の六頭七百三十八文。
大野は千十郎の意見に賛成した。
左へ入る道が有り、そこも榛名道だと大野は聞いてきている。
右手八幡への坂道の下が上町、松本駒之丞本陣壱百七拾四坪と問屋場。
先の左手に上町安兵衛脇本陣、さらに先の京口木戸手前に高札場。
馬方が「木戸先は新堀村でごぜえやす」という。
緩やかな上りが徐々に急になる。
大きく左へ曲ると一里塚が見えた。
三十里目新堀一里塚。
丸山坂を下りると茶屋本陣、お東とお西はどちらも中島家と云う。
八年前、文化三年に焼失、年内に再建されたという。
登り坂の途中に地蔵が有る。
「昔馬子が片荷の釣り合いに首を乗せて運んだそうじゃ。それも深谷じゃそうな。夜んなると“
五料恋しや ”と泣く声が聞こえてくるそうな、哀れに思った深谷の人がこん首を五料に届けてきて胴に乗せたそうな」
碓氷郷の産土神碓氷神社の前で峠越えの無事を祈った。
三十一里目横川一里塚、昔の街道に造られたがどこに有るのか判然としない。
「昔の東山道に近い場所らしい」
遠見番所が設けられた頃だと大野が言う。
百合若足跡石なる物が街道脇にあると馬方が言う。
板橋の先が横川村で、横川茶屋本陣と休み茶見世が軒を連ねている。
この付近はわらび餅が名物だという、力餅とわらび餅、好みを聞いて馬方へも振る舞った。
大野は四文銭十枚括りを太賃の上乗せに配っている。
次郎丸と未雨(みゆう)は通りかかる巡礼に四文銭五枚括りを「御報謝」と配りまわった。
山の方へ横川諏訪神社の参道が伸びている。
碓氷関所の東西の門は明け六ツに開き、暮れ六ツに閉じられた。
東門は安中藩が西門は幕府の管轄だった。
番所の前の石段を登り、おじぎ石に手をつくと、ひざまついてから手形を差し出した。
さすがに武士は藩名木札を見せるだけで通り抜けた。
お芳たち親娘は千十郎が付き添っていたので「草津の湯と善光寺詣で」と言うだけで女改めは無かった。
西門の先は下りで霧積川に架かる板橋先はまた上り坂に為る。
原村を抜けると坂本宿(しゅく)の江戸口木戸門は直ぐそこに見える。
木戸脇からの水路は宿場の中央を流れていた。
十七番目坂本宿は松井田から二里十八町。
宿(しゅく)長六町十九間。
軽井沢宿まで二里十八町。
下町先が仲町、右手に八郎兵衛脇本陣。
左手の金井三郎左衛門本陣と佐藤甚左衛門本陣。
本陣の隣が問屋場で金井本陣問屋場に佐藤本陣問屋場。
月番の佐藤本陣問屋場で荷駄(本馬)二頭をしつらえた。
さすがに峠越えともなれば一駄二百八文で四百十六文、四文銭の緡(さし)に四文銭四枚だした。
次郎丸が時計を見るとまだ十時二十五分。
用水の向こう側に永楽屋冨右衛門脇本陣、京口木戸門手前に坂本八幡宮への参道が有る。
登り坂の手前で立ち止まった。
「さていよいよ峠越えだが紀州で教わった滑り止めをして置こう」
権太が新しい手のごいを配っている。
「新しいのをどうします」
そういえば千十郎に話していない。
「古いのと交換だ。古いのを裂いてこうやりゃいい」
半分に引き裂くと軽く捩って(よじって)草鞋を包むように巻きつけた。
「少し指の根元の方へ付けたほうが歩きやすいぜ」
草鞋の鉢巻ですなと千十郎が珍しく冗談を言った。
「雪駄止めなら真田紐で踵だが、草鞋を守るとは初めてです」
「草鞋に手のごいの替わりは幾らでもある。足袋が擦り切れたら早めに替えぬと爪先をけがしてしまう」
馬方も手のごいを貰うと真似をし、馬の草鞋も替えている。
大野は早々と四文銭十枚括りを二人の馬方へ「駄賃の上乗せだ」と渡している。
次郎丸はどうやら軽井沢へ降りたらまた遣るのだろうと思った。
遠見番所までは難なく登れた。
吾郎と次郎丸が最後を歩いている。
「此の上に刎石坂と呼ばれている場所ですがね。あっしの師匠春秋庵白雄が選句をたのまれた翁の歌碑があるんですよ。あっしが弟子入りして二年目の春先でした」
「わざわざこの峠の先へかい」
「坂本宿(しゅく)の人たちでした。それほど記憶にない事ですが、刎石坂の上の四軒茶屋手前と覚えています」
「詳しく覚えていないという事は建てる方には師匠本人は拘らなかったのだな」
「その様です。字は師匠の書いた物を彫ってあるそうです。五尺も無い小さなものだそうです。詠んだ場所と違うのだと言って有るとは聴きました」
弘法の井戸はこの右手だと馬子が大野へ話している。
「此処の水で刎石茶屋(はねいしちゃや)は茶を入れる大事な井戸ですじゃぁ」
「その道を弘法大師も通られたか」
「水に難儀しとるを見かねて錫杖でついたら噴出したそうですらぁ」
刎石坂と呼ばれているところに芭蕉句碑が置いて有る。
“ ひとつ脱て うしろに負ひぬ 更衣
”
更衣はころもがえ。
未雨(みゆう)が話していたとおり小さな句碑で句の右手に芭蕉翁と彫り込まれていた。
「下から上げたようだ。周りの石とは大違いだ」
回り込んでみた。
「寛政二年か二十四年前だな」
「師匠がととにつれられて家に来た年だ」
お辰(おとき)は思い出したように微笑んでいる。
「おっかさんまだそんときゃまだ餓鬼だろうによく覚えているもんだ」
「初午の地口行燈(じぐちあんどん)の発句に狂歌を書きに来られたんだよ。手本も無しに二刻(とき・百二十分)もととと書きまくってた」
三十二里目刎石一里塚は岐蘓路安見絵図にはあるが見当たらない。
馬方は弘法の井戸の道に塚の跡に石組が有るという。
刎石茶屋(はねいしちゃや・羽根石立場)で力餅やわらび餅で一休みした。
茶屋本陣はどこかの姫様だろうか、御付の腰元六人に老女と言うには若い上臈が出てきた。
坂本を眼下に眺めていたが駕籠へ乗り込むと刎石坂を下って行った。
「駕籠のほうが大変そう」
「歩く方がいいか」
「この坂を馬に駕籠では疲れてしまいそう」
「よしよし、後の辛い坂もその調子で頼む」
時計は十一時三十五分。
下ってゆくと堀切と言う水場が有る。
その先は馬方が「座頭ころがしですだ」という隘路が続いた。
「まごめ坂」、「入道くぼ」という悪路が続いている。
山中茶屋へ着いた。
「若さんが脅かすほどじゃないわよっ」
一里近くの山道を六十五分で歩ききった。
馬方も褒めている。
大野も「道中記も此処で半道だ」と言うが馬方は後の街道は道幅も広くて楽だという。
三十三里目山中一里塚は左塚しか見当たらない。
「安見絵図から六十年、右塚は崩れたようだ」
大野が休み茶見世を選んで入った、丸屋六右衛門茶屋本陣をはじめ十五軒の茶見世が有った。
“ 羽根や
”という店は込み合っている、力餅やわらび餅で一休み、横川、刎石茶屋と来て今日三度目だ。
熊野大権現への参詣戻りの人が増えてきた。
馬方が言うには社家は三十家だという、参道前に上州、信州の国境標柱が有るという。
「吾嬬者耶(あずまはや)」
「若さん何の呪文」
「大昔日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が此処を越えるとき、辰巳の方角へ亡くなった弟橘媛をしのんで三度呼びかけたという伝承さ」
ついでのように「次はあんころ餅だ」等(など)と言ってみた。
坂を下り、しばらく行くとまた登りに為る、沢に土橋が架かっていた。
「茶見世に寄らぬ荷駄にはいい休み場所だな」
長さが五尺に満たぬ石橋が出てきた。
「足を濡らさぬのはあり難い」
「あっ」
「どうした。足をくじいたか」
手ぬぐいを見せて「切れた」という。
直ぐそこが熊野大権現「俺は参詣するので草鞋と足袋を替るけど。あと少しだ我慢しな」と励ました。
曽根茶屋本陣の前後に休み茶見世など十五軒ほどが客を呼んでいる、高札場脇の“ いせや ”を選んだ。
未雨(みゆう)が先に九両預かり、神楽奉納は出来るか聞き合わせに向かった。
次郎丸達は足袋と草鞋を捨て、新しく穿き直し、ちくまやの三人は馬方たちと此処に居させた。
五人で参詣に熊野大明神へ向かった。
国境の傍示杭から見ると鳥居の真ん中が目に入る。
最初の石段は十段、鳥居と次の石段前は石畳の道、古い形の狛犬が有る。
次の石段前に未雨(みゆう)が居てすぐに始まりますという。
旨い具合に神楽奉納が一段落した処へ、飛び込んで行った様だ。
手早く奉納者の名も書いて来たという「どうせ本名でも知らないだろう」と松平定栄としてきたという。
お辰(おとき)が「なぜここを特別に参詣されます」と不審げだ。
「社伝だが日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が八咫烏の導きで助かり、此処へ熊野の大神を勧請したとしてあるからさ」
五人の巫女に三人の楽人が奉納舞を始めた。
三十人ほどの参詣人が得したという顔で見いっている。
短く頼んだようで一刻(こく・十五分程)で終わり祝詞が奉じられた。
近くから鐘が鳴っている、八つだ、時計は二時八分。
本宮へ参拝し、那智、新宮と回り随神門 (
ずいじんもん )へ戻った。
馬方が教えてくれた風車(源氏車)を見て石段を降りた。
「此の狛犬見慣れない形ね。それと皆さま撫でさする様でつるつるだわ」
通りかかった禰宜が「四百年ほど昔の物だそうじゃ」と教えてくれた。
“ いせや ”という先ほどの見世へもどり、あんころ餅で茶を飲んだ。
吾郎はいつの間にか足袋草鞋を履き替えていた、素早い男だ。
大野は「あとは下るだけだが駄賃の上乗せをすると馬方を喜ばせ、思い切って十枚括りを与えている。
矢ヶ崎川二手橋で軽井沢宿の下木戸が見えた。
未雨(みゆう)が中宿左手、本陣問屋場を聞いて先に六頭の仕度を頼みに向かった。
中宿に入ると左手に脇本陣が三軒有る、用水路を跨いで高札場が在りその右手が佐藤市右衛門本陣。
問屋場も本陣が仕切っていて、脇本陣は分家だという。
十八番目の軽井沢宿は坂本から二里二十六町。
宿(しゅく)長六町二十七間。
沓掛宿まで一里五町。
乗懸(のりかけ)五十一文の六頭は三百六文、百文の緡(さし)三本と六文出した。
荷の積み替えが済むとすぐに沓掛へ向かった。
家の隙間に一里塚が有るときいていて大野は見に行ってきた。
三十四里目軽井沢一里塚は家の間から見えていて傍まで入れたという。
用水が右へ曲がり土橋が架けてある、その先に上木戸。
板橋が有る先へ行くと精進場川の野沢橋、街道右手は離山(はなれやま)。
街道を横切る小川が多く土橋が架けられていた。
「ねえ、おじさん」
「儂かい」
「熊野大明神から大分と坂を下って来たけどなんか高いどころにいる気がする」
「山中茶屋中りと同じだと客から聞いたことが有るだ」
「ええっ、あんな山の上と同じなの」
「そんだな、沓掛まで上りに下りで同じくらいなんだそうだぁ」
大野が昨晩広げていた安見絵図には川に架かる橋の右手に「八まん」、左手に 「一りつか 川向ひ古道」と有った。
馬方に聞くと「左浅間の手前で見えるで」という。
三十五里目宮之前一里塚が近いというので大野が遠眼鏡を取り出している。
馬方に四文銭五枚括りを「駄賃だ」と渡している。
大野は里程で渡す額を決めて居る様だ。
「なんで宮の前だね」
「昔は街道が川向こうの長倉様への参道じゃでね」
千年以上前からあると参詣の巡礼から聞いたという。
「祭神は」
「八幡様じゃ」
次郎丸は東山道の頃の古社だろうと納得した。
「あのあたり古道の跡だな」
そんな話をしていると街道が畝って本当に浅間は左側に見えるようになった。
湯川橋は木橋、陽は宿の向こうへ落ちてゆく寸前だ。
沓掛宿江戸口木戸を入ると用水路が街道の中から左手へ流れている。
用水路の右手へ入り土橋の先に市神の社が用水路の上にある。
そこで馬から降り、馬方とちくまやの三人は問屋場へ向かった。
未雨(みゆう)夫婦は市神鳥居前で拝んでいる。
問屋場では三人が荷物を降ろして待っていた。
隣は土屋本陣、この先追分も本陣は土屋家だ。
前に高札場が有り石橋が有る、それを渡ると今日の宿の“ つるや甚右衛門 ”脇本陣。
宿札が“ 白川藩本川次郎太夫様御宿 ”と出ている。
「お疲れですやろ。お風呂はすぐにでも入れます」
お芳と歳が同じくらいの女中が三人ほど率いて足盥を運んできた。
「皆様もお武家さまに女二人が混ざる旅でずら。四人さんで女二人と言う人は会いませんでしたか」
お辰(おとき)が「山中茶屋で見かけましたよ。今日は追分まで行くんだと先に出て行きましたよ。あたい等は熊野さんで大分差が出ていますので今時分ついてる頃だわ」と教えた。
「ありゃまぁ。見逃したかしんらね。二分儲け損なった」
「どうしたの」
「親戚の旦那が俳句好きで、今日明日にも来るはずだから来たら連絡をと頼まれたんですよ」
未雨(みゆう)は借宿の作右衛門旦那かと思ったが知らん顔で部屋へ案内された。
「飯の仕度はゆっくりでいいよ」
親娘で按摩を頼んでいる。
「女子しの按摩が二人居るで二人呼びますか」
「そうして」
吾郎は按摩が来ると次郎丸の部屋へ行った。
「本庄からばれたかな」
四人でなく九人と言いましたぜと言う。
「お客様ですよ」
未雨(みゆう)と同じくらいか小太りの男が遣って来た。
「おしんに二分やらずに済みました。明日狩宿宿へ頼まれて助に行きますんで土産を買う積りだったようでございます」
「どうして知れました。本川と知らせでも」
「いえ未雨(みゆう)一家とお武家が信濃へ向かったとは聞きました、春秋庵加舎白雄師匠に弟子入りした時からの付き合いでした」
「した」
「連絡も寄越さず信濃入りは呆れた所業。勘弁するには食事の後で一刻(百二十分)以上は茶屋でご詮議。本川様も付き合って下され」
笑っている。
承知した処へ食事の用意が出来たという「半刻後にお迎えを出します」と出て行った。
親子は別間で男は七人で食事をした。
おしんと言う娘は「九人さんとは聴かされていませんでした」と儲けがふいだと嘆いている。
未雨(みゆう)の事を知る江戸の者から「若さんと言う人のお供で草津と善光寺へ行くと聞いた」の話が先行したという。
“ 黄檗ぬのや
”とは遠い親戚だが、狩宿宿“ 黒源 ”黒岩源右衛門とも親戚、此処“ 鶴屋 ”とも親戚だという。
側の番頭が「取られたくは無いのですが“ 黒源 ”さんに家の旦那が頼まれまして」と口を利いた。
「こちらのおなご衆も軽尻(からじり)頼むので一緒にいくかい」
「付き合うべえ。くっちゃべる相手が居れば俺も飽きねえ」
上州弁に信州弁がまじゃるなどと言っている。
番頭に卯の下刻に出らるように軽尻(からじり)三頭の手配を頼んだ。
大野がいくらになると南鐐二朱銀を預けた。
「此のおしんの分は此方で」
大野は承知した。
“ ぬのや
”の使いが来て次郎丸は未雨(みゆう)と二人で附いて出た。
草津道の手前“ よしの
”という茶屋へ案内された。
留守の間に大野は宿から借りた案内記で道中の記録を千十郎と調べている。
沓掛街道
沓掛宿~五里二十六町十五間~狩宿宿
(狩宿宿~三里十三町・もしくは二里十八町~須賀尾宿)
(須賀尾宿~二里三十町四十間~長野原宿)
狩宿宿~六里七町四十間・五里十二町四十間(三十一町差)~長野原宿
長野原宿~三里十八町~草津
十五里十六町五十五間・もしくは十四里二十一町五十五間(三十一町差)
二人はこれで納得した。
「明日は鼻田峠の峰の茶屋の一休みで十分だな」
万騎峠越えで三十一町差が出るのは道が付け替わったのだろうと二人は話している。
お辰親娘の部屋にはおしんが羊羹と茶を持参して押しかけている。
「二番目の姉が小諸へ嫁いでいるんでね、土産にきのんもろただに、あんだら草津にいきんしゃるなら、一番目の姉が開いた湯宿にもあたいが元気だとつげんしゃい」
「なんという宿なの」
「広小路の“ やまもと
”のおつねと言えば判るわ、すぐ傍にわたの湯が有るから女は便利よ。十五年前麓の小雨村と言う冬住みの里へ嫁に入ったに、一昨年湯宿を頼まれて引き継いだのよ。十一を頭に三人子供がいるのに半年は会えないのよ」
「冬住みの里って何かしら」
「温泉は雪が深くなると湯治客もぐんと減るがね。一里も辰巳へ下って春まで支度をととのえるだに」
姉が五人、兄は一人の七人兄妹だと話した。
おしんは十三、なぜ引き合いが多いかと言えば信濃に珍しく饂飩踏みの名人だという。
「今度も半月狩宿宿の“ 黒源 ”さまへ頼まれただの、ごしたいなんど言わずにいくっかいかずっしょ」
こりゃお江戸の人には難しかろうと「疲れたと言わずに行こうという事」だと言い直した。
|