�����u�@��O���@�ېV
| �����u�@��O���@�ېV |
|
| �@�����u�|��\�ڎ��@�ېV�@2 | ���ݘa�Ö�(������) |
| ��ꕔ�ڎ� |
��ڎ� |
��O���ڎ� |
��l���ڎ� |
��ܕ��ڎ� |
�ڎ��̂��߂̖ڎ�-1 |
| ��Z���ڎ� |
�掵���ڎ� |
�攪���ڎ� |
��㕔�ڎ� |
��\���ڎ� |
�ڎ��̂��߂̖ڎ�-2 |
| ��\�ꕔ�ڎ� |
��\�ڎ� |
�ڎ��̂��߂̖ڎ�-3 |
| �c���S�N�Q���Q�P���@�|�@�P�X�U�W�N�R���P�S���@�y�j�� �@�ېV�@�|�@���� |
|
 ����͂����Ԓ����Ȃ�܂����`�`�B �����͔n�̖��O�Ǝ�����ɂ����ԗV�т�����l�Ł`�`���B �c���S�N�Q���Q�P���@�|�@�P�X�U�W�N�R���P�S���@�y�j�� �ېV�@�|�@���� �䎖�� �����ɂ���ăt�����X�l�̎��S��������Ă��܂����A�A�[�l�X�g�T�g�E�͂P�P�����S�i�����Q���A�s���s���V���A�����V���A�����A�҂T���Ə����̘A���j�Ə����Ă��܂��B �ɒB�@��Ə����ѓ����t�����X���g�ɎӍ߂ɖK��A�C�M���X���g�قɗ��Ă̘b�ł��̑����ɎQ���������͓̂y���ˎm�Q�O���A�̂��̂Q�O���Ƙb�����Ə����Ă��܂��B ���̎����͏����l�ɂ���Ă��ǂ���ɔ��邩���Ⴄ�p�x�ő����Ă��܂��B �ŏ��ɐX���O�́A��a������A���Ă����������̐w���ցA���l���삯����ŁA�`����t�����X�̐������㗤�����Ƒi�����B�t�����X�̌R�͍͂`����ꗢ����̉��ɗ��āA��\�z�̒[���i�͂����j�ɐ������ڂ��ď㗤�������̂ł���B�������̑������o���̗p�ӂ������Ă���ƁA�R�ĕ{����o���̖��߂��͂����B�����ɏo�����Č���ƁA�����͕ʂɂ���Ɖ]�������i���ǂ��j�����\�s�����Ă͂��Ȃ��B�������_�Е��t�i�Ԃ������j�ɕs�����ɗ�������B�l�Ƃɏオ�荞�ށB���q�𑨁i�Ƃ�j���ĝ����i���炩�j���B�J�`��łȂ���̒��l�́A�O���l�Ɋ���ʂ̂ŁA������i�����j��ē��������A�˂���ĉƂ��Ă���̂������B�������͗@�i���Ɓj���ďM�֕Ԃ����Ǝv�������ʕق����Ȃ��B��^���ŋA��Ɖ]���Ă��A��l�������Ȃ��B�����ő������w���ֈ������Ă��Ɩ������B��������߂ɂ��������𑨂��ē���|���悤�Ƃ����B�����͔g�~��������ē����o�����B���̈�l���A���Ƃ̌ˌ��ɗ��Ċ|���Ă�����������D���ċ삯�ĉ������B �ƌ������ɏ����Ă��܂��B ����ɔ����đ剪�����͍�`���Ύn���̒��Ŏ��̂悤�ɏ����Ă��܂��B �ߌ�R���t�����X�����悹�����z�̃{�[�g����`�ɓ��`�B�����ЂƂ͒��݁B�p���X�̏�����{�[�g�͑��ʊJ�n�B �S������y���˕��͒ʕ�㒼���ɏo���B���ʊĎ��̂��� ��������K�ɕ�����z�u�B �T������p���X���ʑ����C���ɏ㗤����̂��B ���@���ݑg�̂����̂ӂ���A�f�������ƃ����[�������ԑ��̐q�⒆�ɓˑR�� �S���͂���B ���S�҂�p���X���ʑD�Ɍ������C�A�Ə��͂��炩���߂��Ă������ƌ�����B �O����G�����镗���̏��a�����ɏ����ꂽ�����̎����͎����Ƃ������ꂢ�����̂����������Ă��܂������O�Ƒ剪���̏����ꂽ�����^���ɋ߂��̂ł͖����ł��傤���B �����̌����͂P�T���h���̔������ƂQ�O���̏��Y�Ō��܂����B ���b�V�����g���������ł̐ؕ��̌���ɗ���������̂͊ԈႢ�ł���ƃA�[�l�X�g�T�g�E�͏����Ă��܂��B �f�B���v���[���w�����g�D�A�[���卲���㗝�Ƃ��ėՐȁA�Q�O���̐ؕ��̗���n�܂������[��ꂪ�߂��A�͂��x���̂��C�����ĂP�P���̐ؕ����I������Ƃ���Ŏ���グ�Đ��~�����Ə����Ă��܂��B �i�f�B���v���[���ɂ��Ď��ۂ̒Ԃ肪�����莟��悹�܂��A�ǂݕ��͉p��ǂ݂���������A�W���v���[�E�f���v���[�ȂǗl�X�ɏ�����Ă��܂��j ���̓��ɁC�c�����������\����Ȃ��Ƃ����āC���̑�]���̏�őS���ؕ������L��������܂������^�U�̂قǂ͒͂߂Ă��܂��A�\�b�Ƃ��Ă������ł��낤�Ǝv���܂��B ���O�͎O������ɁA���Y��Ƃ��č����֎w�ԁi���������j���Ɖ]���B�����������A�Ə����Ă��̐�͖ƂɎ���܂ł������ɏ����ċ���܂��B �P�P���̈�͖̂������������̕��@�ɑ����A�y���\���m��Ƃ��ď��a�P�R�N�i�P�X�R�W�N�j���̎j�ՂɎw�肳��܂����B �܂��A��ɓ����@�Ƀt�����X���̈ԗ�肪��������Ă��܂��B |
|
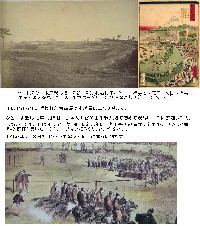 �����n�� �O�Ɏg�������Ƃ̂���摜�͂P�W�U�T�N�̎����n�̊G�Ɣ������܂����B ���߂ĉ摜���ڂ��Ă����܂����A�����ɂȂ��Ă���̃x�A�g�̎ʂ��������n��̎ʐ^�Ɖi�ѐM���̊G���ꏏ�ł��B ���ۂɖ{���̂悤�ȃ��[�X���s��ꂽ����������������܂��z���͊y�����������Ƃ��o���܂����B |
|
 �g�[�}�X Thomas�EThomas�͂P�W�U�P�N�P�X�̂Ƃ����l�ɗ��܂����B ���������Z�t����P�W�U�S�N���g�\������ɋ߂Ă����X�g���`�����Ƌ��ɃX�g���`�������g�[�}�X��ݗ��B �������̗A�o�ȐD���̗A���Ő����̌�A�ѐD���@�B�̗A�����肪�����A��`�����Ȃǂ��s���B �U�Q�ԂƂU�R�Ԃɏ���A�R��U�ԂɉƂ�����܂����B �O���l���H��c����A���n��̓��{���[�X�N���u�����ȂǗ�C�B �P�W�S�Q�N���܂�P�X�Q�R�N��k�Ђ̂Ƃ��ɉ��l�ŖS���Ȃ�B �R��O�l��n�S��ɉi�����Ă��܂��B �W���[�f�B�}�W�\�� ��Ԋق͎��͎O�Ԋقł����A�����n�P�Ԓn�ɂ���C�M���X�̖f�Տ��ЃW���[�f�B���E�}�Z�\������́A�g�[�����A�f���g�ɑ����u�p�O�ԁv�قł������n�Ԃ��P�ԂƂ���đ��̌�A�p��ԊقƏ̂��܂����B William Keswick�i�E�B���A���E�P�Y�B�b�N�j�͉��l�J�`�Ɠ��������ė��_�A�����n��Ԓn�̉p��ԊفA�Q�P�Ԃ̋�������A�Q�Q�ԊC�^�E�ی������L���鋐�古�ЂƂȂ�܂��B ���l�͂P�W�U�Q�N��C�x�X�Ɉڂ�A�P�W�U�W�N�ɂ͍��`�{�X�̍ō��ӔC�҂ƂȂ�A����ɂP�W�W�U�N�Ƀ����h���}�Z�\������̒��S�l���ƂȂ�P�W�X�X�N�ɂ͉��@�c���ƂȂ��Ă��܂��B �P�X�P�Q�N�������N�V�W�� ���q��JJ�E Keswick�ʼn��l�x�X���ߊO���l���H��c������߂܂����B |
| �c���S�N�R���P���@�|�@�P�X�U�W�N�R���Q�S���@�Ηj�� �ېV�@�|�@�w�L�� |
||
 �Y�t�摜�͐ԃ}�[�e���̉ƕt�߂���V���ƃW���p���u�������[���ʂ������������ł��B �c���S�N�R���P���@�|�@�P�X�U�W�N�R���Q�S���@�Ηj�� �ېV�@�|�@�w�L�� �w�L��̓w�N�g�iHegt�j��ō��̑㊯��ł��A���̓����͖��֍�ł�������ɓ������̃w�N�g�@��������ē����L�������ߒn���̐l���炻�̂悤�ɌĂ�Ă��܂����B �Ћg���v���o���Ȃ��������͓���w����ł��傤�A���̂����Z���g�W���Z�t�J���b�W�̖��O���v���o���č�̖����v���o���ł��傤�B �c���S�N�����ɃC�M���X�a�@������ꏊ���g���i���̙ԗt�w���j�ƌ������Ƃ܂ł͎v���o���Ă��܂��B �̃C�M���X�̌R�c�������Đw�����Ƃ��Ă��̖��O���c��܂����B �ŏ��A�����R�N�i�P�W�V�O�N�j�P�Q���U���ɎR����Hegt�ɂ���Č��Ă�ꂽ�Q�[�e���iGaiety Theater�j�͉��l�{���ʂ�U�W�Ԓn�ł����B ���S�P�R�u�A�Α��������ŁA���[�}�̐_�a���z���v�킹�錚�������������ł��B �����T�N�i�P�W�V�Q�N�j�P�P���ɃQ�[�e���̓p�u���b�N�z�[���Ɖ��̂���܂����B ���̌����͖����S�Q�N�i�P�X�O�X�N�j�P�O���Q�P���ɏĎ����܂����B �����P�W�N�i�P�W�W�T�N�j�S���P�W���ɎR��Q�T�U�`�Q�T�V�Ԓn�ɒn���P�K�n��Q�K���Ń����K���A���W�X�O�u�A���e�l���R�T�O�l�̃z�[�������݂��ꂽ�̂͌��݂̍`�̌�����u�����߂��̌��R�c�̂͂���ɂ�����ꏊ�ł��B ���̌������Q�[�e���ƌĂ��悤�ɂȂ����̂́A�����S�P�N�i�P�X�O�W�N�j�P�Q���ȍ~���Ƃ����Ă��܂��B ���̌������吳�P�Q�N�̑�k�Ђŕ��܂����B ���� Spring Valley Brewery��W�ECopeland����The Japan Brewery Company�i�i�فj���p�����Ă��܂����p�������͓̂y�n�ł����Đ��@�ł͂���܂���B �ٓV�\�t���ɂ̓r�[���̗��j���V���̃r�A�U�P�Ƃ��ĊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă���܂���������x�������Č��܂��B ���͑O��ŏ�����L�E�}�C���[���S�U�ԂŎn�߂��l�ɏ����܂������ǂ����r���Q���������悤�ł��B �k�E�}�C���[�A�W���p���E�u�������[ ���l�u�������[�i�W���p���E�u�������[�@����j�@ ������N�i�P�W�U�X�N�j�R��S�U�Ԃɒu���Ăf�E���[�[���t�F���g���h�C�c�lE�E���B�[�K���g�������Z�t�Ƃ��ăT���t�����V�X�R�Ō_��A�����n�̊O���l�����Ƀr�[���̏����̔����J�n�B G. Rosenfeld(t)�@ L. Klein�@�����l���̂̂͂��ߍl�ɂ̓��[�[���t�F���g�����L�҂Ƃ��Ă�����Ă���u�������[�����������Ƃ��̏��L�҂̓N���C���ł������Ƃ���Ă��܂��j �iEmil. Wiegand�o�o���ABavaria���܂ꁁ�o�C�G����Bayern�j�@�@ �����O�N���B�[�K���g���فB �����ܔN�i�P�W�V�Q�N�j�k�E�}�C���[�͎R��S�U�ԂɂčL�������l�����V���i����̖����V���Ƃ͕ʂł��j�ɍڂ���B�i�o�T�E���S���Łj �������N�i�P�W�V�S�N�j�ɔp�ƁB�@ J�E�w�N�g�@�w�N�g�E�u�������[ �����O�N�i�P�W�V�O�N�j�R��U�W�Ԃɂi�E�w�N�g�����B�[�K���g�̎Q���ăw�N�g�E�u�������[�������E�c�ƊJ�n�B �����ܔN�i�P�W�V�Q�N�j���B�[�K���g���فA���l�͈ꎞ���ė����A���A �������N�i�P�W�V�S�N�j���B�[�K���g�ė��_���ăo�o���A�E�u�������[�Ƃ��ăw�N�g������_�������Ōo�c�i�w�N�g�E�u�������[�͕��j�B W�E�R�[�v�����h�@�X�v�����O�E�o���[�E�u�������[ �����O�N�i�P�W�V�O�N�j �R��P�Q�R�Ԃ��܂ގl���Q�S�W�O�i������蒬�P���ځj���擾���ď������i�X�v�����O�E�o���[�E�u�������[�j���J�݁A�����͓V���r���U�P�Ƃ����Ă����B �������N�i�P�W�V�T�N�j �������אڒn�P�Q�P�ԂɃr���n�E�X���c�ƊJ�n�B ������N�i�P�W�V�U�N�j �U���P�T���t���W���p���K�[�b�g�ɍL�����ڂ��ă��B�[�K���g�Ƌ����ŃR�[�v�����h�����B�[�K���g�����ݗ������ƕB �R��U�W�Ԃ͍H��̈ꕔ�Ƃ��Ďc���B �����\��N�܂������B�[�K���g�͐܂荇���������Ȃ藂�����\�O�N�P�����U�B �R�[�v�����h�������ɂ���ɓ���ĉc�ƌp���B �����\���N�i�P�W�W�S�N�j �������ٔ��̏o��Ɉ���s�U��������ɕt�����B ���N�����Z�t�y�я����@�B�ꎮ���c�r�E�q��i�����{������j������Đ�c�������������J�݂��ꗂ�����P�W�N���甭�������B ���c�r�[���̓C�M���X���r�[����̔��i���Ђ͖����S�T�N�A�P�X�P�Q�N�p�Ɓj �R�[�v�����h�́u�X�v�����O�E�o���[�E�r���E�K�[�f���v�̌o�c���p�����܂����B �i�ٔ����@�W���p���E�u�������[�@ �����\���N�i�P�W�W�T�N�j ���`�Ђ�The Japan Brewery Company�i�W���p���E�u�������[�j�Ƃ��ĐV��Аݗ��B �R�[�v�����h�̏������Ղɖ{�Ђ�u���B �W���p���E�u�������[���ݗ��������L�����y�n�́A�P�O�T�a�A�P�Q�R�A�Q�S�O�`�A�Q�S�O�a�A�Q�S�O�b�̂T���i�y�n�������ɂ��Q�V�V�U�A���z�Z�t�_�C�A�b�N�̑��ʂł͂R�R�T�O�j�ŁA�A�{�b�g����w�����Ă��܂��B�@�@ The Japan Brewery Company�@����J.Dodds�@ ���{���T�O�D�O�O�O�h���T�O�O���@ ���N�l�@���S�ƂȂ����̂̓W���p���E�K�[�b�g�̃I�[�i�[��W.H.Talbot�i�^���{�b�g�j�ƁA�،��E����u���[�J�[��E.Abbott�i�A�{�b�g�j�ł����B Thomas Blake Glover�i�O���o�[�j���O���l�R�R���E����V�����{�l�P���i��ɑ������ɏa��h��A���c���ܘY�A���c�T�O�A�v�c�F�A�㓡�ۓ�Y�A��q�씪�Y�����Q���j�v�R�S���ł����B ������\�N�i�P�W�W�V�N�j �h�C�c��������Z�t�EH�E�w�b�P���g�������B �h�C�c��������ݔ������u�������[��{�i�I�ɍċ��B ������\��N�i�P�W�W�W�N�j �W���p���E�u�������[�ЁA�h�C�c�����K�[�r�[�����u�L�����r�[���v�u�����h�Ŕ����B�̔��͖��������ꊇ�i����A���l�������j�A��r�P�{�P�W�K�i�e�ʕs���E�U�R�R�~�����b�g������r�ƌ��߂�ꂽ�̂͏��a�P�W�N�j�B ������\�Z�N��r�P�{�P�S�K�A�����l�\��N�͑�r�P�{�Q�Q�K�ɒl�オ��B�i�����l�\��N���̓����ł͋����ꍇ�R�K�X�ЁE���苼���R�K�R�Ёj �����O�\��N�i�P�W�X�X�N�j �W���p���E�u�������[�E�J���p�j�[�����g���ă[�E�W���p���E�u�������[�ƂȂ����B �����Q�O�N�i�P�W�W�V�N�j�V�����疾���R�Q�N�i�P�W�X�X�N�j�S���܂ŏ����Z�t�߂��̂͂g�E�w�b�P���g�iHeckert�j�B�@ �J�C�U�[�iC.Kayser�j�͖����R�Q�N�i�P�W�X�X�N�j�U�����疾���R�T�N�i�P�X�O�Q�N�j�U���܂łŁA���̂��ƂɃA�C�w���x���N�iE.Eichelberg�j�������R�T�N�i�P�X�O�Q�N�j�V���ɕ������Z�t��菸�i���Ă��܂��B �����l�\�N�i�P�X�O�V�N�j �[�E�W���p���E�u�������[�̎��Ƃ������p���V��ЂƂ����i�ٔ���������Ђ��ݗ��A���`�Ђ�����{���ЂɕύX�B �~�n�͂Q�O���U�U�V�W�ɂ܂ōL�����܂����B�@ �吳�\��N�i�P�X�Q�R�N�j �X���P���֓���k�Ђɉ����Ė{�ЍH��͑S��B ���N���̓��m�����i�t�W�r�[�����E�̔��j�ƍ����B �吳�\�ܔN�i�P�X�Q�U�N�j �����H�ꌚ�݁B Willian Copeland�@ �R�[�v�����h�͌��̖������n���E�}���e�B�j�E�X�E�g�[���Z���Ƃ����ĂP�W�R�S�N�Ƀm���E�F�[�̃A�E�X�g�E�A�O�f���Ő��܂�܂����B �A�����_�[���E�u�������[�Ńr�[�������Z�p���w�ь�ɃA�����J�ɈڏZ���܂��B �������N�i�P�W�U�S�N�j���_�B �c����N�i�P�W�U�U�N�j�P�R�V�ԃW�F�[���X����i���l�q��E�^���Ɓj�̌o�c�ɎQ���B �c���O�N�i�P�W�U�V�N�j�S�����W�F�[���X������U�B �P�R�S�ԂɓƗ����ăR�[�v�����h����i�^���Ɓj�ݗ� ������N�i�P�W�U�X�N�j�R��P�Q�R�Ԃ��܂ވ�т����B |
||
| ��\���� | ��O������ | |
| ��ꕔ�ڎ� |
��ڎ� |
��O���ڎ� |
��l���ڎ� |
��ܕ��ڎ� |
�ڎ��̂��߂̖ڎ�-1 |
| ��Z���ڎ� |
�掵���ڎ� |
�攪���ڎ� |
��㕔�ڎ� |
��\���ڎ� |
�ڎ��̂��߂̖ڎ�-2 |
| ��\�ꕔ�ڎ� |
��\�ڎ� |
�ڎ��̂��߂̖ڎ�-3 |
| �����u�@��O���@�ېV | |||||
| ��\�ꕔ-1�@�ېV�@�P | |
��\�ꕔ-2�@�ېV�@�Q | |
��\�ꕔ-3�@�ېV�@�R | |
| ��\��-1�@�ېV�@�S | |
��O������ | |||
| �P | �@�K�u�쌈�� �| ���l�� | |
| �Q | �@�K�u�쌈�� �| ����q��@ | |
| �R | �@�K�u�쌈�� �| �V���{ | |
| �S | �@�K�u�쌈�� �| �������N |