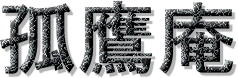令和4年9月 近畿旅行記 其の参(21日〜22日)
このページは、「令和4年9月 近畿旅行記 其の弐(19日〜20日)」の続きとなります。
●9月21日(水・休暇取得)
03:17 目覚める
広い駐車場で空いている区画ばかりなのに、すぐ隣に別の車が停まっており、違和感を感じる。
03:38 京丹波パーキングエリア 出発
03:49 走行中、今回の旅行での移動距離が1000キロメートルを超えたことに気づく(1005キロメートル)
後ろから猛スピードの車が接近してきたので、トンネル内の退避スペースで譲ってあげる。時間をおいてもう1台猛スピードの車が来たので同様に譲ってあげる。
04:13 京都府宮津市入り
04:17 宮津天橋立インターチェンジで高速道路を下りる
04:23 道の駅 海の京都 宮津 到着
ここまでの移動距離1044.8キロメートル。
ベッドで休まず、入浴もしていないためか、ふくらはぎが筋肉痛。
駐車場には何台か車あり。
仮眠する。
05:00過ぎ 起きる
夜が明けてきた。曇り。

道の駅 海の京都 宮津
06:25 道の駅 海の京都 宮津 出発
06:37 智恩寺有料駐車場 到着
適当な駐車場を探していたら、お寺が運営している(?)駐車場に入ってしまった。駐車場の受付の人はまだいない。
この智恩寺というお寺は参拝予定になかったが、せっかくなので参拝させてもらう。
朝のお勤め中だったお坊さんに駐車代金のことを聞いたら、「8時ころに係員が来て、駐車車両に代金の支払いをお願いする札を置いていくので、それで支払ってほしい。係員が来る前に駐車場を出ていくのならば代金はいただいてない。」と教えていただいた。
【智恩寺】(ちおんじ)
所在地・・・京都府宮津市
正式名称・・・天橋山 智恩寺
宗派・寺格等・・・臨済宗妙心寺派
本尊の文殊菩薩(秘仏・年間数日のみ開帳)は日本三文殊の一つとされている。切戸の文殊、九世戸の文殊、知恵の文殊とも言われている。

智恩寺 三門(黄金閣)

智恩寺 多宝塔

智恩寺 文殊堂
本尊・文殊菩薩
境内を出て、天橋立を歩いてみる。なお、この地区(天橋立南方)は「文殊地区」と呼ばれているらしい。
【天橋立】(あまのはしだて)
日本三景の一つ。全長3.6キロメートルの湾口砂州。宮津湾と内海の阿蘇海を隔てている。

天橋立 小天橋(廻旋橋)と
船を通すために橋が回転する構造になっている。橋が架かっているのは文殊水道(天橋立運河)。

天橋立内部
ここに生えている松は植林ではなく、大部分が自然発生的に生えたものらしい。
天橋立内にある天橋立神社へ。
【天橋立神社】(あまのはしだてじんじゃ)
所在地・・・京都府宮津市・天橋立内
社格等・・・不明
主祭神・・・伊弉諾命(いざなぎのみこと)
別名「橋立明神」とも言われる。なお、この神社には令和4年9月現在、御朱印は無いので注意。

天橋立神社 境内
境内で、右手に止まった蚊をつぶしてしまった。神社境内での殺生を反省。
天橋立神社の脇には日本名水百選の一つ「磯清水」がある。

磯清水

磯清水
周りを海に囲まれているのに真水が湧き出るという不思議な井戸。天橋立神社の手水として使われている。ただし、飲用は出来ないという注意書きがある。
天橋立神社参拝後、来た道を戻る。歩いて天橋立を渡ることも可能だし、レンタサイクルを借りることも可能だが、今回はやめておいた。
小雨。
遊覧船があったが、営業は午前9時かららしいので、今回はあきらめる。
再び智恩寺に来て、御朱印をいただく(この辺は記憶があいまいで、もしかしたら天橋立に行く前に御朱印はいただいたかもしれない)。
智恩寺をそのまま後にしようかと思ったが、智恩寺の授与品に「棒が付いた輪」のようなものが多いことに気づく。よく見ると「智恵の輪燈籠」という名所があるということを知る。智恩寺の女性職員に尋ねたところ、文殊水道にあることを教えてくれた。

智恩寺 智恵の輪燈籠
江戸時代に航海の安全を祈願して建てられたもの。
08:00ころ 雨がやや降ってきた
駐車場に戻ったら、駐車代金請求の札がワイパーに挿まれていた。
駐車場の受付で代金を支払ったら、係員に「魚釣り?」と言われた。
08:11 智恩寺有料駐車場 出発
雨、また止む。
天橋立北部(傘松地区)へ。
08:32 籠神社近くの有料駐車場 到着
前払いで700円。支払い時、100円硬貨を下に落としてしまった(回収済み)。
籠神社を参拝しようとしたら、表参道からではなく西口から入ってしまった。
境内をいったん抜けて、表参道から改めて参拝。
【籠神社】(このじんじゃ)
所在地・・・京都府宮津市
社格等・・・式内社、丹後国一之宮、旧国幣中社、別表神社
主祭神・・・彦火明命(ひこほあかりのみこと)
「元伊勢籠神社」と呼ばれる。伊勢神宮内宮の主祭神である天照大神が、伊勢に遷る前に4年間住まわれた場所と伝えられている。天照大神は伊勢に遷られる前は日本全国を旅しているので「元伊勢」と呼ばれる場所は他にもあるのが実情だが、「天照大神が伊勢神宮外宮の主祭神である豊受大神と一緒に住まわれていた場所」は、伊勢神宮を除くとこの場所だけになるらしい。

籠神社 参道

籠神社 神門
これより先は、撮影禁止。
御朱印をいただき、御守を授かる。なお、この後に行く眞名井神社の御朱印もここでいただける。

籠神社 西口
西口から出て、歩いて数分の距離にある眞名井神社(籠神社奥宮)に行く。
このあたりから、雨の心配は無くなる。
【眞名井神社】(まないじんじゃ)
所在地・・・京都府宮津市
社格等・・・籠神社の奥宮(境外摂社)
主祭神・・・豊受大神(とようけおおかみ)
「下宮」とする籠神社に対し、この神社は「上宮」と位置づけられる。伊勢神宮外宮の主祭神である豊受大神が伊勢に遷る前に鎮座していたとされる場所。

眞名井神社 参道入口

眞名井神社
これより先は撮影禁止。
なんとなく居心地が良い。不思議な雰囲気の空間。
なお、天橋立神社、籠神社、眞名井神社を参拝することを俗に「天橋立三社参り」という。これは昔から言われているわけではなく、2000年代以降に天橋立観光協会が企画した「天橋立三社詣ツアー」が発端らしい。
眞名井神社を後にし、徒歩で天橋立ケーブルカー等がある府中駅へ。
09:45 ケーブルカーで天橋立のビュースポット「傘松公園」へ

府中駅

府中駅内 天橋立ケーブルカー
【傘松公園】(かさまつこうえん)

傘松公園から見る天橋立
ここから見る天橋立は「昇龍観」と呼ばれ、右上がりに龍が昇っていくように見えることから縁起がいいと言われている。「股のぞき観」「斜め一字観」とも呼ばれる。

天橋立 昇龍観 股のぞき(単に画像を上下逆転させたのではなく、ちゃんと股のぞきの状態で撮影したもの)
傘松公園には遠足か何かの小学生の集団がいた。

傘松公園の一角
カワラケ(陶器のちいさな皿)を投げて輪を通すと運がいいという遊びをやる。3枚200円。5枚目で通した。通った時、ついつい大きめの声で「ヨシ!」と言ってしまった。
帰りは一人乗りのリフトで下る。
10:28 有料駐車場 戻り
10:32 有料駐車場 出発
次の目的地「成相寺」へ。
10:39 成相寺駐車場 到着
【成相寺】(なりあいじ)
所在地・・・京都府宮津市
正式名称・・・成相山 成相寺
宗派・寺格等・・・橋立真言宗

成相寺 本堂
本尊・聖観世音菩薩

成相寺 本堂内 左甚五郎作「真向の龍(まむきのりゅう)」
江戸時代初期の有名な彫刻職人「左甚五郎」の作と伝えられるもの。本堂内は撮影禁止だが、この真向の龍だけは撮影が許可されていた。
成相寺参拝後、成相寺駐車場から登っていけるパノラマ展望台へ車で行く。

成相寺 パノラマ展望台
晴れていれば稀に越前海岸や白山も見えるらしいが、この時はあいにくの曇り。ここでもカワラケ投げがあり、12枚買って10枚目でやっと輪を通せた。
11:16 パノラマ展望台 出発
パノラマ展望台を後にし、成相寺を出ようと思ったが、境内に五重塔や弁天山展望台があることに気づく。駐車場の受付の人にその旨を話したら、本来は地元の人用で使われている第三駐車場を使わせてもらえることになった。

成相寺 底なしの池(奇怪な話の底なしの池)と五重塔
写真中央が弁才天の祠。五重塔は夜間のライトアップが見事らしい。

成相寺 五重塔(弁天山展望台へ行く途中からの景色)

弁天山展望台
弁天山展望台でも、またカワラケ投げがあった。しかし、輪を通すというものではなく「カワラケに願い事を書いて投げて、遠くまできれいに飛べば願いが叶いやすい。投げたら池の弁才天に参拝するように。」という性質のものだった。3枚200円。3枚とも「国家鎮護」と書いて投げる。
弁天山展望台を下り、底なしの池に祀られた弁才天の祠に参拝。
11:42 成相寺第三駐車場 出発
再度、文殊地区方面へ向かい、天橋立ビューランドへ。
12:04 天橋立ビューランド付近 到着
観光客が多数おり、モノレール・リフト乗り場直近の駐車場は満車状態。近くの民家が経営している小さな有料駐車場(500円)に駐車する。
【天橋立ビューランド】

天橋立ビューランド モノレール・リフト乗り場
行きはモノレールで登っていく。

天橋立ビューランドから見る天橋立
ここから見る天橋立は「飛龍観」と呼ばれ、龍が天に舞い上がるように見えることから縁起がいいと言われている。

天橋立 飛龍観 股のぞき(単に画像を上下逆転させたのではなく、ちゃんと股のぞきの状態で撮影したもの)
ここにもカワラケ投げがあったが、ここではやらなかった。
カメラの充電が残り僅かになり焦る。
帰りは一人乗りのリフトで下る。
13:05 天橋立ビューランド近くの有料駐車場 出発
車内の充電装置でカメラの充電を行う。
13:12 道の駅 海の京都 宮津の隣にあるMippleという施設の駐車場に入る
次の目的地「白鬚神社」をナビに入力
13:16 Mipple駐車場 出発
13:18 ローソン宮津京街道店 到着
ここまでの移動距離1082.0キロメートル。
買い物&駐車場で遅い朝食(おにぎり、サンドイッチ、牛肉メンチコロッケ)
13:48 ローソン宮津京街道店 出発
13:51 宮津天橋立インターチェンジから高速道路流入
15:11 京都東インターチェンジで高速道路を下りる
15:48 白鬚神社駐車場 到着
【白鬚神社】(しらひげじんじゃ)
所在地・・・滋賀県高島市
社格等・・・旧県社
主祭神・・・猿田彦命(さるたひこのみこと)
全国にある白鬚神社の総本社とされる。「近江最古の大社」とされる。「白鬚大明神」「比良明神」とも称される。琵琶湖に浮かぶ湖中大鳥居で有名。

白鬚神社 拝殿

白鬚神社 拝殿から望む鳥居と湖中大鳥居

白鬚神社 湖中大鳥居
結構参拝客が多くて驚いた。湖中大鳥居を撮影しようとしている人でいっぱい。
湖中大鳥居の近くの岸に他の人の事を考えずに陣取ってタブレットを操作している女性がいて迷惑していた。
結局その女性も察したらしく、見えにくい位置に隠れた。
なお、社殿と湖中大鳥居の間には交通量が多い幹線道路があり、「横断禁止」の表示があった。
16:10 白鬚神社駐車場 出発
次の目的地「満月寺浮御堂」に到着するのは拝観時間ギリギリかも知れないとかなり焦る。
16:44 満月寺駐車場 到着
17時の閉院ギリギリで間に合った。
【満月寺】(まんげつじ)
所在地・・・滋賀県大津市
正式名称・・・海門山 満月寺
宗派・寺格等・・・臨済宗大徳寺派
琵琶湖に浮かぶように建てられた「浮御堂(うきみどう)」が有名。近江八景の一つ「堅田落雁(かたたのらくがん)」として知られる。

満月寺 浮御堂

満月寺 本堂(観音堂)
本尊・・・聖観世音菩薩
拝観料300円と御朱印代300円を間違えてしまい、御朱印をいただく時「もう御朱印代払いませんでしたっけ?」と大変失礼なことを言ってしまった。
帰る時には、一度締めた門を開けてもらうなど、迷惑をかけてしまった。

満月寺 山門
竜宮造という形の門。
17:08 満月寺駐車場 出発
17:20 雄琴温泉の歓楽街を通り過ぎ、その「いかにも歓楽街です」という状態に驚く
17:27 日吉大社水上鳥居があることに気づく
17:28 BわこRK園ホテルI筒 到着
チェックイン後、琵琶湖の写真を撮る。
このホテルは、京都の銘菓「八ツ橋」で有名なI筒グループの経営だとここで初めて知った。
18:10 車で外出
ファミリーマート大津唐崎店で夕食を買う(たらこスパゲッティ、クリームパスタ)。
18:40 ホテルに戻る
荷物のほとんどをホテルの部屋に持ち込み、再点検。
所在不明となっていた普賢院の御守を発見する。
客室(ツインルーム)は古く、冷蔵庫などの調度品も歴史を感じさせるものだが、とても広い。浴室も大きかった。
たらこスパゲッティを夕食で食す。
外は強い雨。
22時台には寝てしまった。
この日の教訓
・ 傘松公園と天橋立ビューランドは、数人で乗れるケーブルカー(モノレール)又は一人乗りのリフトで行き帰りとなるが、行きでリフトを使うと、乗っている最中に振り返って天橋立を見ることが難しいので、行きはケーブルカー(モノレール)、帰りはリフトがおススメ。行き帰りケーブルカー(モノレール)でもいい)。
・ 後で知ったことだが、天橋立は「四大観」と呼ばれる風景があり、傘松公園から観る「昇龍観(股のぞき観、斜め一字観)」、天橋立ビューランドから観る「飛龍観」、雪舟観展望所から観る「雪舟観」、大内峠一字観公園から観る「一字観」がそれにあたる。さらに最近は、丹後国分寺跡から観る「天平観」も含めて「五大観」とも言われている。もっとも有名なのは飛龍観だと思われるが、事前に五大観の事を知っていれば、旅行のコースも変わっていたかもしれない。
●9月22日(木・休暇取得)
02:45 目覚める
夜食にクリームパスタを食べようとしたら冷めて硬くなっていて、とてもじゃないが美味しく食べられない状態だった。
朝、明るくなったころにフロントに電話をかけ、電子レンジの有無を聞いたところ、厨房の電子レンジで温めてくれた。更におしぼりまで貰った。
温めてもらったクリームパスタで朝食。出発準備をしている時に寝不足からか軽い眩暈を起こす。
07:14 ホテル出発(このホテルには2泊予定なので、荷物は部屋に置いたまま)
台風15号の影響からか、今にも雨が降り出しそうな感じ。
本日のメイン目的地「比叡山延暦寺」へ。
07:26 比叡山ドライブウェイ料金所 通過
料金所通過後、すぐの所のガードレールに猿が座っていた。
雨、降り出す。
07:32 比叡山ドライブウェイ検札所 通過
07:39 比叡山延暦寺第一駐車場 到着
受付はまだ開いてなかった。
08:30 比叡山延暦寺東塔地域参拝受付開始
東塔地域参拝受付を一番乗りで通過する。
国宝殿は展示品入れ替えのため拝観できず。
【比叡山延暦寺】(ひえいざんえんりゃくじ)
所在地・・・滋賀県大津市
正式名称・・・比叡山 延暦寺(本来は“暦”は「木木」部分が「禾禾」である)
宗派・寺格等・・・天台宗総本山
天台宗総本山であるとともに、日本の仏教の各宗派開祖の多くがここの出身であることから、日本仏教に多大な影響を与えた場所と言える。「叡山」「北嶺(奈良・興福寺が「南都」と称されたのに対して)」とも称される。
延暦寺は東塔(とうどう)、西塔(さいとう)、横川(よかわ)の3エリアに分かれている。
【東塔(とうどう)地区】

延暦寺 大講堂
本尊・大日如来
霧に包まれた姿が神秘的。

延暦寺 根本中堂
本尊・薬師如来
延暦寺の中心。なんと、大改修中。

延暦寺 根本中堂(大改修のため工事用建屋に覆われている)

延暦寺 根本中堂 入口
両脇の白い部分は工事用の保護幕。
この先、少し行くと「撮影禁止」の看板がある。撮影禁止の看板の直前からは本堂内陣も僅かに撮影でき、開祖である伝教大師が灯して以来燃え続ける「不滅の法灯」も僅かに撮影できたが、ここで公開するのはやめておく。

延暦寺 文殊楼
雨は微妙に降っている。

延暦寺 大黒堂
本尊・三面出世大黒天
日本の大黒天信仰発祥の地と言われる。

延暦寺 万拝堂
日本全国の神社仏閣の諸仏諸菩薩諸天善神を勧請し、合わせて世界に遍満する神々を迎えて奉安しているという平成期に新設された建物。
再度、大講堂へ戻る。

延暦寺 開運の鐘
大講堂近くにある鐘。有料で鐘を撞くことができる。かなり勢いをつけて大きな音を鳴らしたら、近くにいた若い女性二人連れが小さく拍手してくれた。

延暦寺 大講堂
霧が晴れた際に再撮影。
大講堂を撮影していたら、年配の女性3人組に声をかけられ「大講堂をバックに自分たち3人の写真を撮ってほしい」と言われたので快く応じる。「大講堂全体を写すと人物が小さくなってしまうがどうするか?」と訊ねたら、「むしろ人物は小さく写してください。アップに耐えられないので(苦笑)。ここに来たことが分かればいいです。」と返されてしまった。

延暦寺 戒壇院
本尊・釈迦如来、文殊菩薩、弥勒菩薩
昨年(2021年)に伝教大師1200年大遠忌で特別拝観を実施したらしいが、それまで一度も公開したことが無く、もしかしたら今後も公開しないとされているらしい。

延暦寺 阿弥陀堂
本尊・阿弥陀如来

延暦寺 阿弥陀堂前 石庭
こういう雰囲気が非常に好み。水琴窟もある。

延暦寺 阿弥陀堂前 石庭

延暦寺 法華総持院東塔
本尊・大日如来をはじめとする五智如来
11:00 延暦寺第一駐車場 戻り
駐車場近くの売店で買い物をした後、車に乗って、念のため「延暦寺で貰える御朱印一覧」みたいな紙を見たら、延暦寺会館でいただける「正覚院不動」の御朱印を貰い忘れていたことに気づく。
受付に延暦寺会館まで行きたい旨を伝えたところ、「一般参拝者は車で延暦寺会館までは行けないが、歩いて15分程度である」と教えてもらい、再入場。なぜかこの時、ミラーレス一眼を車に残してきてしまう。そのため、延暦寺会館周辺の画像はiPhoneで撮影している。
雨は未だに断続的に降っていた。

延暦寺会館
宿泊施設であり、中学生か高校生と思われる団体が会館内にいた。
元々この場所は重要儀式が行われる道場があったが、その跡地に延暦寺会館が建てられ、更に延暦寺会館の前に祠を建てて「正覚院」に祀られていた不動尊を安置している。
フロントで御朱印をいただくと、延暦寺会館内の喫茶「れいほう」の10%割引券をいただいたので、「れいほう」で休憩する。

延暦寺会館内 喫茶「れいほう」 梵字カフェラテ
梵字は普賢菩薩の「アン」

延暦寺会館前 正覚院不動尊
本尊・不動明王
11:43 再度、延暦寺第一駐車場 戻り
11:47 延暦寺第一駐車場 出発
奥比叡ドライブウェイを走る。
このころになると雨が止む。
11:49 延暦寺西塔駐車場 到着
【西塔(さいとう)地区】
※ ただし後述の「浄土院」は東塔所属となる

延暦寺 椿堂
本尊・千手観世音菩薩
聖徳太子がここに椿の枝をさしたところ、根付いて枝葉が茂ったという伝説がある。
ちょうどこの時は、伝教大師1200年大遠忌記念・聖徳太子1400年御遠忌記念で、椿堂は特別御開帳が行われており、御本尊の千手観世音菩薩が特別公開されていた。

延暦寺 にない堂(左・常行堂、右・法華堂)
常行堂・・・本尊・阿弥陀如来
法華堂・・・本尊・普賢菩薩
武蔵坊弁慶が両堂をつなぐ廊下に肩を入れて担いだという伝説があるため、担い(にない)堂と呼ばれる。

延暦寺 転法輪堂(通称・釈迦堂)
本尊・釈迦如来
比叡山最古の建築物。元は園城寺(三井寺)の金堂だったが、1595年に豊臣秀吉が移築した。

延暦寺 浄土院(西塔地域寄りにあるが、東塔に所属している)

延暦寺 浄土院 伝教大師御廟
13:28 延暦寺西塔駐車場 出発
直で横川に向かうつもりだったが、途中で伝教大師像がある大きな駐車場を見かけ、立ち寄る。
13:33 比叡山峰道レストラン駐車場 到着

伝教大師像
せっかくなので、ここで昼食も食べることにする。

比叡山峰道レストラン 近江牛塩ラーメン(1300円)
正直、「観光客向けのレストランだしなぁ」と侮っていた。非常に美味で驚く。
食後、併設の売店で買い物。
14:00 比叡山峰道レストラン駐車場 出発
14:04 延暦寺横川駐車場 到着
【横川(よかわ)地区】

延暦寺 横川中堂
本尊・聖観世音菩薩
舞台造りと呼ばれる建築方式で、船が浮かんでいる姿に見えるのが特徴。

延暦寺 横川中堂

延暦寺 元三大師堂(通称・四季講堂)
おみくじを考案したとされる元三大師の居住跡と伝わる場所。
せっかくだからおみくじをやろうと思ったが、ここのおみくじは普通のおみくじとは違い簡単に引くような方式ではなく、「AとBでどちらを選ぶべきか迷っている。」というような真剣に迷っているようなことがある時にやるべきものらしい。しかも基本は予約制。
僕がおみくじをやろうと思って職員の方に訊ねたところ、説明を受けて「ああ、そういう迷い事がなく、おみくじを引く必要がないってことは、幸せな状態なんだなぁ」と納得した。

道元禅師得度の地
うちは宗派が曹洞宗なので、曹洞宗の開祖である道元禅師の得度の地があるということを知り、急遽来てみた。

延暦寺 根本如法塔
15:24 延暦寺横川駐車場 出発
次の目的地「西教寺」へ向かう。「もう今日は疲れたから、西教寺は明日にしようか・・・」という考えも頭をよぎったが、体力が残っているうちに動いた方がよいと思い、残りの体力をふり絞る。
途中、香芳谷展望台で1分程小休止。
15:36 仰木料金所 通過
15:52 西教寺駐車場 到着
【西教寺】(さいきょうじ)
所在地・・・滋賀県大津市
正式名称・・・戒光山 兼法勝西教寺
宗派・寺格等・・・天台真盛宗 総本山
聖徳太子が開基であると伝わるが、1486年に中興の祖とされる僧・真盛が入寺して以降栄えるようになった。
西教寺は1571年、織田信長による比叡山焼き討ちの際に焼失するが、明智光秀が寺の復興に尽力したとされ、今も明智光秀ゆかりの寺とされている。
天台真盛宗は、天台系ではあるが浄土教的色彩が強いとされている。

西教寺 総門

西教寺 本堂
本尊・阿弥陀如来

西教寺 大本坊
本堂裏の大本坊で御朱印をいただく。御朱印は5種類(令和4年9月22日当時)。なぜか善光寺御開帳記念の御朱印があり、最初はスルーしてしまったが、気になって後で職員の方に聞いてみたら善光寺と西教寺は縁があるということだった。職員の方に自分が長野県から来たことを告げ、善光寺御開帳記念御朱印も追加でいただく。

西教寺 大本坊庭園
江戸時代初期に造られた庭園。

西教寺 裏書院庭園
平成元年に造られた庭園。
17:01 西教寺駐車場 出発
17:06 セブンイレブン大津坂本3丁目店 到着
今夜の夕食、明日の朝食などを買い込み。セブンイレブンの店のカラーリングがやや地味であり、周辺の寺社に配慮したもののようだった。
17:20 セブンイレブン大津坂本3丁目店 出発
黄色点滅の信号が多いことに気づく(この後も、旅行中、滋賀県内は黄色点滅信号が散見された)。
17:26 宿泊ホテルBわこRK園ホテルI筒 到着
まだ陽が落ちるまでには時間があったため、すぐに徒歩で日吉大社の鳥居を見に行く。

日吉大社 七本柳鳥居

日吉大社 七本柳鳥居
近くに公園もあったので散策してみたら、この公園こそが明智光秀の居城「坂本城」の跡だったことが分かった。
小さな男の子と父親らしき人がサッカーボールで遊んでいた。湖岸では魚釣りを楽しむ人も散見された。

坂本城址公園

坂本城址公園 明智光秀像
坂本城は、1571年の比叡山焼き討ちの後、明智光秀が織田信長の命を受け作った平城で、比叡山の監視と琵琶湖の制水権が目的だったとされる。イエズス会宣教師のルイス・フロイスは「安土城に次ぐ豪壮華麗な城である」と記録している。
1586年、豊臣秀吉の命を受けた浅野長政が大津城を築城する際に坂本城は廃城となり、資材は大津城築城に使用されたことから、遺構はほとんど残っていない。
17:47 宿泊先のホテルに戻る
ホテルのコインランドリーを使用して洗濯。洗剤は備え付けのものを使用させてもらった。今回は充分乾燥機を使用し、完全に乾かした。
入浴中、右足親指にマメを発見。とりあえず放置。
夕食は、コンビニで買ったおにぎりと手巻き寿司。
正直、疲れのせいか「もう、長野に帰りたい」という気になってしまった。
多分、22時台に就寝。
この日の教訓
・ 御朱印は、どこでいくつ貰えるのかということをよく確認しよう。
・ 延暦寺はお土産・授与品のバリエーションが豊富。
・ 撮影対象はどこにあるか分からないので、ちゃんとカメラを持ち歩こう。
「令和4年9月 近畿旅行記 其の四(23日〜25日)」へ続く