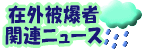 ― 在外被爆者に関するトピックスをいくつか抜粋して紹介します ―
― 在外被爆者に関するトピックスをいくつか抜粋して紹介します ―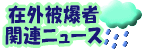 ― 在外被爆者に関するトピックスをいくつか抜粋して紹介します ―
― 在外被爆者に関するトピックスをいくつか抜粋して紹介します ―
| 2005年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2004年 | 9-10月 11月 12月 |
| ※(かっこ)内の日付はメディア等に報道・情報が公開された日です。 ※情報は上から [日付の新しいもの→古いもの] の順で並んでいます。 |
2005年11月
| (11月30日) | 在外公館で手当と葬祭料の申請受付 ついに開始! 厚労省、外務省 |
| (11月30日) | 葬祭料をめぐる在韓被爆者・朴さん訴訟 原告が訴えを取り下げ |
| (11月28日) | 在米被爆者の体験記を初収集 映像作家が聞き取り 国立長崎追悼平和祈念館 |
| (11月28日) | 事務次官会議、閣議で政省令改正を報告 在外公館での手当と葬祭料の申請受付に向けて 厚労省 |
| (11月23日) | 米国日系3世のドキュメンタリー監督が伊藤・長崎市長を訪問 原爆をテーマに制作中の作品を語る |
| (11月16日) | 在韓被爆者2名 訴訟の継続を主張 |
| (11月16日) | 5-6月実施の北米被爆者健診、結果まとまる 435人が受診 5人に2人は被爆者手帳を未取得 |
| (11月15日) | 「被爆者手帳の在外受付は引き続き検討」新任の麻生外相述べる 日韓外相会談 |
| (11月10日) | 被爆2世の元F1ドライバーが広島で慈善チャリティー ブラジルの英雄との交友写真も初公開 |
| (11月 9日) | 日韓被爆者による手工芸の合同作品展 韓国と広島市で開催 |
| (11月 2日) | イラクでの劣化ウラン弾被害を訴え、元米兵が広島で講演 |
| (11月 2日) | 長崎・高校生1万人署名活動実行委、来夏に向けて活動開始 |
| (11月 2日) | 被爆者手帳の在外公館での申請は「現状では困難」 新任の川崎厚労相 |
| (11月 1日) | 在外公館で手当と葬祭料の申請、11月下旬から可能に 厚労省 |
![]()
(2005年11月30日)⇒12月8日当HP掲載
![]() 【厚生労働省ホームページ】【外務省ホームページ】
【厚生労働省ホームページ】【外務省ホームページ】
〔在外公館で手当と葬祭料の申請受付 ついに開始! 厚労省、外務省〕
※11月1日付〔在外公館で手当と葬祭料の申請、11月下旬から可能に 厚労省〕の続報
本日30日、私たち在外被爆者の大きな願いの一つ=「居住国の大使館、領事館での各種手当と葬祭料の申請受付」=がついに開始されました!
30日付「厚生労働省ホームページ」「外務省ホームページ」に以下の告知がされました。
|
※ 外務省ホームページ2005年11月30日掲載「お知らせ」より抜粋
在外被爆者へのお知らせ ・これまで、在外被爆者(被爆者手帳を有する者)は、被爆者援護法に基づく健康管理手当等各種手当及び葬祭料の支給申請については、日本で行わなければならないこととなっていましたが、平成17年11月30日よりこれらの支給申請をお住まいの地域を管轄する在外公館その他最寄りの在外公館経由で行うことが可能となりました。 ・詳細は、厚生労働省ホームページをご覧下さい。 ・また、不明な点は最寄りの在外公館等にも御照会いただけます。 |
|
※ 厚生労働省ホームページ2005年11月30日掲載「報道発表資料」より全文を抜粋 被爆者援護法に基づく手当・葬祭料の国外からの申請の受付開始について 日本国外にお住まいの被爆者の方々(被爆者健康手帳をお持ちの方)について、被爆者援護法に基づく手当の認定申請や葬祭料の支給申請を国外から行う際の手続等に関し、本日をもって、関係法令が改正され、各国に設置された在外公館において、本日より申請の受付が開始されましたのでお知らせします。 申請手続きの詳細な内容は別添資料をご参照下さい。 なお、別添資料については、現住所が判明している方々についてダイレクトメールにより配布するほか、厚生労働省ホームページや在外公館のホームページへの掲載、在外公館窓口での配布、各国の被爆者協会等を通じた広報などを行うこととしております。 手続きに関し不明な点は、厚生労働省健康局総務課又はお近くの在外公館までお問い合わせ下さい。
|
……
→ 申請手続に関する資料は「厚生労働省ホームページ」内「日本国外にお住まいの被爆者の皆様へ~日本国外からの手当・葬祭料の申請手続について~」に掲載されています。
→ 在外公館に問い合わせ等をする際の連絡先は「外務省ホームページ」内「在外公館リスト」でご確認できます。
![]()
(2005年11月29、30日)⇒12月8日当HP掲載
![]() 【長崎新聞】〔葬祭料をめぐる在韓被爆者・朴さん訴訟 原告が訴えを取り下げ〕
【長崎新聞】〔葬祭料をめぐる在韓被爆者・朴さん訴訟 原告が訴えを取り下げ〕
※2月9日付〔韓国人被爆者への葬祭料 長崎県が遺族の申請を却下〕
7月15日付〔在外被爆者「葬祭料」訴訟 韓国の遺族が新たに提訴 全国で5件目〕― の続報
29、30日付『長崎新聞』によると、被爆者援護法に基づく葬祭料の支給申請を却下されのは違法として、広島で被爆した韓国人女性の遺族が、国と長崎県を相手取り、処分の取り消しなどを求めた訴訟で、原告側は29日長崎地裁での第2回口頭弁論で訴えを取り下げました。
原告は、韓国在住で昨年10月に亡くなられた故・朴畢順さん(享年75、広島被爆)の長男、李在榮さん(56)。李さんは昨年12月、葬祭料を県に申請しましたが、県は1月、死亡場所が長崎県内でないことを理由に申請を却下したため、7月に長崎地裁に提訴していました。
しかし、「長崎在外被爆者訴訟」(9月26日福岡高裁判決)の判決確定(原告・崔季澈さんの遺族に葬祭料支給が認められた)に伴い、県は10月、李さんへの却下処分を取り消していました。
原告側は「海外で死亡した在外被爆者への葬祭料支給にめどがたち、訴訟の目的を達成した」としている、ということです。
→ 詳細は『長崎新聞』11月29日付、同30日付 をご覧ください。
![]()
(2005年11月28日)⇒12月8日当HP掲載
![]() 【長崎新聞】〔在米被爆者の体験記を初収集 映像作家が聞き取り 国立長崎追悼平和祈念館〕
【長崎新聞】〔在米被爆者の体験記を初収集 映像作家が聞き取り 国立長崎追悼平和祈念館〕
28日付『長崎新聞』によると、長崎で被爆した在米被爆者の被爆体験記が、このほど国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館に収められました。同館には現在、約160件の体験記が永久保存されていますが、在外被爆者の体験記は初めてになるそうです。
この在米被爆者は米国サンディエゴ郊外在住のすえ・カーペンターさん(71、旧姓藤原)。11歳の時に爆心地から1.3㌔の工場寮で被爆。後、横須賀に移り、1966年米海軍士官と結婚し渡米されたそうです。体験記には、後遺症に苦しみながら被爆者であることを隠して生きてきたことや、夫ロニーさんの献身的な支えなどが克明に記されているそうです。
体験記の聞き取りをしたのは、米国に住み在米被爆者の取材に取り組むドキュメンタリー映像作家、竹田信平さん(26、大阪府出身)。今夏、サンディエゴの地元紙に発表した英文記事が基になっているそうです。竹田さんは「被爆者の話を直接聞くことができる最後の世代として、この歴史を受け継ぎたいという思いに駆られた」と語ったそうです。
→ 詳細は『長崎新聞』11月28日付 をご覧ください。
![]()
(2005年11月25日、28日)⇒12月8日当HP掲載
![]() 【厚生労働省ホームページ】〔事務次官会議、閣議で政省令改正を報告 在外公館での手当と葬祭料の申請受付に向けて 厚労省〕
【厚生労働省ホームページ】〔事務次官会議、閣議で政省令改正を報告 在外公館での手当と葬祭料の申請受付に向けて 厚労省〕
※11月1日付〔在外公館で手当と葬祭料の申請、11月下旬から可能に 厚労省〕の続報
25日更新の『厚生労働省ホームページ』によると、24日の事務次官等会議で、在外被爆者への諸手当と葬祭料を支給するための政令、省令の改正が報告されました。
また28日更新の『厚生労働省ホームページ』によると、25日の閣議でも、この政令の改正が話されました。
![]() なお閣議後の記者会見で、川崎二郎厚労相は、日本国外からの被爆者健康手帳の申請について、改めて現状では実現困難との判断を示しました。
なお閣議後の記者会見で、川崎二郎厚労相は、日本国外からの被爆者健康手帳の申請について、改めて現状では実現困難との判断を示しました。
→ 戸苅利和厚生労働事務次官の定例記者会見における説明内容(概要)はこちら
→ 川崎厚労相の閣議後記者会見における記者との質疑応答の内容(概要)はこちら
![]()
(2005年11月23日)⇒12月8日当HP掲載
![]() 【長崎新聞】〔米国日系3世のドキュメンタリー監督が伊藤・長崎市長を訪問 原爆をテーマに制作中の作品を語る〕
【長崎新聞】〔米国日系3世のドキュメンタリー監督が伊藤・長崎市長を訪問 原爆をテーマに制作中の作品を語る〕
※6月9日付〔原爆投下60年 海外メディアの取材 相次ぐ〕の続報
23日付『長崎新聞』によると、米国の日系3世でアカデミー賞を受賞したドキュメンタリー映画作家・スティーブン・オカザキ監督(53)が22日、長崎市に伊藤一長市長を表敬訪問し、広島、長崎の原爆をテーマに制作中の作品について語りました。
オカザキ監督は現在、大手ケーブルテレビの依頼で、広島と長崎の原爆投下後の状況などを伝える長編ドキュメンタリーを制作中。2007年に完成、米国で放映される予定だそうです。
『長崎』紙によれば、オカザキ監督は「原爆に関する作品はこれまで多く作られてきたが、政治的メッセージを主張するものが多い。私は、被爆者の声を中心にした作品で米国の視聴者に伝えたい」と話していたそうです。
オカザキ監督は1991年、第2次大戦中の日系人強制収容を描いた「待ちわびる日々」でアカデミー賞を受賞しています。
→ 詳細は『長崎新聞』11月23日付 をご覧ください。
![]()
(2005年11月16日)⇒12月8日当HP掲載
![]() 【中国新聞】〔在韓被爆者2名 訴訟の継続を主張〕
【中国新聞】〔在韓被爆者2名 訴訟の継続を主張〕
※李さん=6月15日付〔被爆者手帳の代理申請が却下 在韓・李さんが広島県を提訴へ〕
9月29日付〔在韓・李さんが病身押し訪日、被爆者手帳を取得〕 ― の続報
※朱さん=10月26日付〔手当申請を却下された在韓被爆者の逝去が判明〕の続報
16日付『中国新聞』によると、被爆者健康手帳を韓国から申請して却下された韓国在住の李相燁さん(82)と、健康管理手当の支給申請を却下された朱昌輪さん(7月に逝去、享年82)が国や広島県、市に処分の取り消しと慰謝料を求めた訴訟の口頭弁論が15日、広島地裁でありました。
李さんは3年前に脳内出血を発症。訪日が困難なお体のため、昨年、代理人を通じて広島県に手帳を申請しましたが、今年1月、県がこれを却下したため、6月に却下処分の取り消しなどを求め広島地裁に提訴しました。しかし裁判の長期化を懸念した李さんは9月、車いすに乗り会話が困難な状態ながら、医師の許可を得た上で「無理して」長男の付き添いのもと訪日し、長崎市で無事に手帳を取得しています。
しかし15日の口頭弁論で、代理人は「却下した広島県の処分自体は取り消されていない」として引き続き争う考えを主張したようです。
また朱さんについては、10月に広島市は却下処分を取り消し申請の実質審査を始めていましたが、同月に支援者が訪韓したところ、ご本人が7月に亡くなっていたことが判明しました。
口頭弁論で、代理人は「まだ手当は支給されていない」として、同じく訴えを継続する意向を示したそうです。
→ 『中国新聞』11月16日付 をご覧ください。
![]()
(2005年11月16日)⇒12月8日当HP掲載
![]() 【中国新聞】〔5-6月実施の北米被爆者健診、結果まとまる 435人が受診 5人に2人は被爆者手帳を未取得〕
【中国新聞】〔5-6月実施の北米被爆者健診、結果まとまる 435人が受診 5人に2人は被爆者手帳を未取得〕
16日付『中国新聞』によると、広島県医師会は、5~6月に実施した北米での被爆者健康診断の結果をまとめました。受診者数は435人(前回比18人減)で、平均年齢は73.1歳でした。
北米での健診は、1977年から同医師会が隔年で実施しています。15回目になる今年は、米国シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ホノルルの4都市で行われました。
受診者のうち、何らかの症状が認められた比率は86.7%。高血圧51.8%、悪性腫瘍19.6%、糖尿病12.8%だったそうです。
また今回の健診では、広島、長崎両県、市の職員が相談会を開き、146人から207件の相談を受けました。主な内容は▼被爆者健康手帳の新規取得(53件) ▼渡日治療(39件) ▼医療費助成(38件)― などでした。
![]() 受診者のうち手帳を取得している方は6割弱(58.9%)でした。4割の方が未取得ですが、相談者のうち10人前後は「体調不良で、手帳取得のために訪日するのは困難」と訴えられていたそうです。
受診者のうち手帳を取得している方は6割弱(58.9%)でした。4割の方が未取得ですが、相談者のうち10人前後は「体調不良で、手帳取得のために訪日するのは困難」と訴えられていたそうです。
訪日できないために手帳を取得できない人、の救済 ―― 。まだ私たちに課題は残されています。
→ 詳細は『中国新聞』11月16日付 をご覧ください。
![]()
(2005年11月15日)⇒12月1日当HP掲載
![]() 【外務省ホームページ】〔「被爆者手帳の在外受付は引き続き検討」新任の麻生外相述べる 日韓外相会談〕
【外務省ホームページ】〔「被爆者手帳の在外受付は引き続き検討」新任の麻生外相述べる 日韓外相会談〕
15日更新の『外務省ホームページ』によると、麻生太郎外相と韓国の潘基文(パン・ギムン)外交通商部長官が14日会談しました。
潘長官からは、在韓被爆者による被爆者健康手帳の在外申請について積極的対応を求める要望があり、これに麻生外相は「被爆者手帳の在外受付は、被爆者の高齢化という事情を踏まえ、支援のあり方を引き続き検討する」旨応じた模様です。
会談は、韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会合に先立って行われました。日韓外相会談は先月27日にも行われましたが、31日に第3次小泉改造内閣の発足で外相が交代したため、両者による外相会談は初めてとなりました。
麻生外相は自民党衆議、当選9回(福岡8区)。経済財政担当相、党政調会長、総務相を歴任。学習院大政経卒。65歳。
→ 日韓外相会談(概要)の内容はこちら(クリック!)をご覧ください。
![]()
(2005年11月10日)⇒12月1日当HP掲載
![]() 【中国新聞】〔被爆2世の元F1ドライバーが広島で慈善チャリティー ブラジルの英雄との交友写真も初公開〕
【中国新聞】〔被爆2世の元F1ドライバーが広島で慈善チャリティー ブラジルの英雄との交友写真も初公開〕
10日付『中国新聞』によると、自動車レースF1の元ドライバー鈴木亜久里さん(45)によるサイン入り商品のチャリティーオークションが13日、廿日市市の中国新聞広島制作センターで開かれました。亜久里さんの母・敏江さん(68、東京都在住)は広島での被爆者で、「ふるさとへの恩返し」として提案し、実現されたそうです。売上は中国新聞社会事業団を通じて交通遺児たちへの基金に充てられるということです。
会場では写真展も開かれ、被爆2世と、私たちが暮らすブラジルの英雄との、自動車レースを通じた交友 = 17歳の亜久里さんがカートを通じて親友だった故アイルトン・セナさんと並ぶ記念写真 = も初公開されたそうです。
敏江さんは、爆心地から約2.5㌔の広島市三篠本町(現在の西区)で被爆。その記憶を封じてきましたが、「60年目の節目を迎え、ふるさとのために何かしたいという気持ちが強くなった。亜久里も同じ思い」と同紙に話した、ということです。
→ 詳細は『中国新聞』11月10日付 をご覧ください。
![]()
(2005年11月9日)⇒12月1日当HP掲載
![]() 【中国新聞】〔日韓被爆者による手工芸の合同作品展 韓国と広島市で開催〕
【中国新聞】〔日韓被爆者による手工芸の合同作品展 韓国と広島市で開催〕
9日付『中国新聞』によると、広島と韓国の被爆者が制作した手工芸の合同作品展が、韓国と広島市で開かれました。
韓国ではすでに10月に開催され、広島市では8日~11日に原爆養護ホーム「倉掛のぞみ園」(安佐北区)で入所者向けに展示されました。また11~13日には広島原爆被爆者療養研究センター「神田山荘」(東区)で一般にも公開されたほか、9日から原爆養護ホーム「舟入むつみ園」(中区)でも入所者向け展示がされました。
「倉掛のぞみ園」の展示会では、双方の被爆者施設の入所者たちによる約500点が出品されたそうです。
広島市では1999年から韓国の施設職員を研修に受け入れています。交流が進む中、施設の入所者が相互に理解を深めるため、作品の合同展が今回初めて企画され実現した、ということです。
→ 詳細は『中国新聞』11月9日付 をご覧ください。
![]()
(2005年11月2日)⇒12月1日当HP掲載
![]() 【中国新聞】〔イラクでの劣化ウラン弾被害を訴え、元米兵が広島で講演〕
【中国新聞】〔イラクでの劣化ウラン弾被害を訴え、元米兵が広島で講演〕
2日付『中国新聞』によると、劣化ウラン弾による健康被害を訴えている元米兵ジェラルド・マシューさん(31)の講演会が3日、広島市の原爆資料館で行われました。主催は市民団体「劣化ウラン弾禁止(NO DU)ヒロシマ・プロジェクト」と「核兵器廃絶をめざすヒロシマの会」。
同紙によれば、マシューさんは2003年4月クウェートに派遣され、イラク南部の基地から使用済み兵器を回収するなどの業務に携わりました。間もなく頭痛や顔のむくみがひどくなり、9月に帰国。尿検査でウラニウムが検出されました。04年6月に生まれた長女には身体障害があり、マシューさんは劣化ウラン弾の被害を訴える活動を始めたそうです。
講演会には妻ジャニスさん(31)も参加し、健康被害の実態を伝えるほか、米政府に補償を求める取り組みへの支援も訴えるそうです。
「ヒロシマの会」共同代表によれば、マシューさんがいた場所の近くで自衛隊が活動しているそうです。
広島、長崎であれ、米兵であれ、イラク国民であれ…、放射能を受けた苦しみは人種、国籍を問いません。
→ 『中国新聞』2日付 をご覧ください。
![]()
(2005年11月2日)⇒12月1日当HP掲載
![]() 【長崎新聞】〔長崎・高校生1万人署名活動実行委、来夏に向けて活動開始〕
【長崎新聞】〔長崎・高校生1万人署名活動実行委、来夏に向けて活動開始〕
2日付『長崎新聞』によると、長崎の「核兵器廃絶を訴える高校生一万人署名活動」実行委員会が、来年夏に向けて6回目の活動を開始しました。
同紙によれば、同実行委は2001年にスタート。毎年8月、国連欧州本部を訪れる「高校生平和大使」に署名簿を託しています。昨年11月からの5回目の署名活動では、過去最多の約9万1,000人分が集まったそうです。
私たち在ブラジル原爆被爆者協会のもとにも7月、同実行委からメンバーの松尾美咲さん(長崎女子高3年)が派遣され、サンパウロで8,500人分の署名を集められました。また10月には当協会からブラジルでの追加署名3,500人分も届けさせていただきました。
若い皆さんの平和を願う心に、ブラジルの人々の平和への思いが少しでもお役に立てたことを、嬉しく思います。
→ 詳細は『長崎新聞』2日付 をご覧ください。
→ ブラジルの高校生も活動中!「サンパウロ事務局だより」12月1日付〔①〕も併せてご覧ください。
![]()
(2005年11月2日)⇒12月1日当HP掲載
![]() 【厚生労働省ホームページ】〔被爆者手帳の在外公館での申請は「現状では困難」 新任の川崎厚労相〕
【厚生労働省ホームページ】〔被爆者手帳の在外公館での申請は「現状では困難」 新任の川崎厚労相〕
2日更新の『厚生労働省ホームページ』によると、在外被爆者が居住国の大使館や領事館を通じて被爆者健康手帳を申請することについて、川崎二郎厚生労働相は1日の厚生労働記者会共同会見で「現状では困難」との認識を示しました。
地方公共団体から専門職員を在外公館に派遣するのは「現状ではなかなか難しい」、といった趣旨の発言でした。ただ、地方からの職員派遣について「やはり一度ご協力いただければありがたい」と、検討の余地も含ませていました。
川崎厚労相は、10月31日第3次小泉改造内閣の発足で新しく就任した大臣です。自民党衆議、当選8回(三重1区)。郵政政務次官、運輸相、衆院議運委員長を歴任。慶大商卒。57歳。
→ 川崎厚労相の厚生労働記者会共同会見における記者との質疑応答の内容(概要)はこちら
![]()
(2005年11月1日)⇒12月1日当HP掲載
![]() 【共同】【中国新聞】【長崎新聞】〔在外公館で手当と葬祭料の申請、11月下旬から可能に 厚労省〕
【共同】【中国新聞】【長崎新聞】〔在外公館で手当と葬祭料の申請、11月下旬から可能に 厚労省〕
嬉しいニュースです!10月31日『共同通信』が配信、11月1日付『中国新聞』『長崎新聞』ほか主要紙が報道しました。
厚生労働省は10月31日、在外被爆者が居住国の大使館や領事館を通じて各種手当と葬祭料を申請することについて、11月下旬をめどに受け付けを開始することを明らかにしました!
対象となる手当は①健康管理手当②保健手当③医療特別手当④特別手当⑤原子爆弾小頭症
―― の5種類。④特別手当以外の申請には、厚労省が指定した現地の医療機関の診断書が必要となります。
葬祭料は過去5年間に亡くなった方にも支給されます。
申請するのは原則本人ですが、病気や高齢で大使館、領事館に行くことができない場合は、代理人による申請ができます。パスポートなど身分を証明できるもので本人確認し、書類は日本国内で最後に住んでいた都道府県か広島市、長崎市が審査します。
以上が報道された内容です。
……
これで私たち在外被爆者も、手当を申請するために、高齢で病気がちの体を押して「命がけ」で訪日する「危険」を冒さなくても済むようになります。葬祭料も頂けるようになります。
手当と葬祭料に関しては、ようやく被爆者援護法に定められた援護、すなわち日本国内の被爆者と同等の援護を受けられる日が来たのです。
これもひとえに、長年にわたり運動を続けてこられた各国の在外被爆者の皆さまと、私たちを支援してくださった市民の皆さま、在外被爆者訴訟で公正な判断を下された司法の皆さま、このたび決断を下された厚労、外務両省の皆さまのおかげです。ここに心から篤くお礼を申し上げます。
また今回の決定に直接的な影響を与えた「長崎在外被爆者訴訟」(9月26日福岡高裁判決)の原告で昨年亡くなられた崔季澈さんのご冥福を、改めて深くお祈り申し上げます。
あと私たちに残された願い ―― それは、現地の大使館や領事館を通じた「被爆者健康手帳の申請」の実現、です。
→ 詳細は『中国新聞』『長崎新聞』1日付、ほか主要各紙 をご覧ください。
![]()