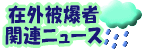 ― 在外被爆者に関するトピックスをいくつか抜粋して紹介します ―
― 在外被爆者に関するトピックスをいくつか抜粋して紹介します ―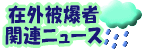 ― 在外被爆者に関するトピックスをいくつか抜粋して紹介します ―
― 在外被爆者に関するトピックスをいくつか抜粋して紹介します ―
| 2005年 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
| 2004年 | 9-10月 11月 12月 |
| ※(かっこ)内の日付はメディア等に報道・情報が公開された日です。 ※情報は上から [日付の新しいもの→古いもの] の順で並んでいます。 |
2005年9月
![]()
(2005年9月30日)
![]() 【中国新聞】〔救護、看護活動に従事した「3号被爆者」 認定求め提訴 広島在住の7人〕
【中国新聞】〔救護、看護活動に従事した「3号被爆者」 認定求め提訴 広島在住の7人〕
日本国内の話題ですが、在外にも救護・看護活動により被爆された方がおられるので掲載します。
30日付『中国新聞』によると、被爆者の救護、看護活動に従事した「3号被爆者」として被爆者健康手帳の交付を広島市に申請したが却下された方々が29日、却下処分の取り消しなどを求め、市を相手取り広島地裁に提訴しました。弁護団によると、3号被爆者認定をめぐる訴訟は全国でも初めてということです。
原告7人は広島市内在住の62~74歳の男性3人と女性4人。原爆投下直後の8月、被爆者の救護・看護活動に従事したり、救護所で看護する親に背負わされたりしていたそうです。7人はそれぞれ1996年2月~2004年2月、市に被爆者健康手帳の交付を申請しましたが、02年8月~05年1月、救護などの活動をした事実が確認できないとして却下されてしまいました。
原告団長(64)は「同じ場所にいた兄弟(姉妹)でも認定されたり、されなかったりするのは納得できない」と訴えておられる、ということです。
→ 詳報は『中国新聞』9月30日付 をご覧ください。
![]()
![]() 【長崎新聞】〔在韓・李さん=代理申請めぐる裁判の原告=が病身押し訪日、被爆者手帳を取得〕
【長崎新聞】〔在韓・李さん=代理申請めぐる裁判の原告=が病身押し訪日、被爆者手帳を取得〕
※6月15日付〔被爆者手帳の代理申請が却下 在韓・李さんが広島県を提訴へ 代理申請をめぐる初の裁判に〕の続報
29、30日付『長崎新聞』によると、広島県を相手取り被爆者健康手帳の「代理申請」をめぐる初の裁判を起こしていた韓国在住の被爆者・李相燁さん(82)がこのほど、手帳を取得するため病身を押して急きょ訪日し、27日長崎市から手帳の交付を受けました。
李さんは3年前に脳内出血を発症。右半身がマヒし会話や歩行が不自由になり、訪日が困難なお体になりました。
そのため昨年、韓国で被爆確認証を取得した後、「被爆者健康手帳」の取得を目指し、ご自分の意志で手帳の申請書類を代筆で作成。昨年11月、これを李さんの代理人である広島弁護士会の足立修一弁護士を通じて広島県に申請しましたが、今年1月、県がこれを却下したため、6月に却下処分の取り消しなどを求め広島地裁に提訴していました。
しかし裁判は、いつ決着がつくかわかりません。
関係者によれば、李さんは裁判の長期化を懸念し、医師の許可を得た上で「無理して」訪日を決めたようです。
車いすに乗り、会話が困難な李さんに付き添う長男・蓮熙さん(56)は28日長崎市内で「周囲から無理してでも行ったほうがいいと勧められた。こんな体でここまで来なければいけないことにがっかりしている」と話したそうです。
なお裁判について、足立弁護士は29日『長崎』紙の取材に対し「国家賠償請求など検討するべき点がある」として訴訟継続を検討する意向を示した、ということです。
→ 詳報は『長崎新聞』9月29日付、同30日付 をご覧ください。
![]()
(2005年9月26日~29日)
![]() 【長崎新聞】【中国新聞】【共同】【時事】
【長崎新聞】【中国新聞】【共同】【時事】
〔在外被爆者への手当、葬祭料認める 初の2審判決 福岡高裁〕
〔上告断念の方針固める 厚労省〕
〔日本国外からの手当、葬祭料申請認める方向へ 日本政府 細田官房長官が談話〕
※2004年10月10日付(①健康管理手当)、
2005年3月15日付、同3月17日付(②葬祭料) ― の続報
在外被爆者援護に、大きな動きがありました!以下、26~29日付『長崎新聞』『中国新聞』、『共同』『時事』配信、ほか主要各紙が一斉に報じたニュースです。
在外被爆者が日本国外から〔①健康管理手当などの各種手当②葬祭料〕を申請、支給できるとする、初の高裁判断が下されました(26日
福岡高裁)。
厚生労働省はこの判決を受け、最高裁への上告を断念する方針を固めました(27日)。
また日本政府も、国外からの①各種手当②葬祭料の申請を可能にする方向で在外被爆者援護制度を見直す考えを表明しました(26日
細田博之官房長官 記者会見)。
……………
◆ この裁判は、韓国在住で昨年7月に亡くなられた故・崔季澈さん(享年78)と遺族が、長崎市を相手取り提訴したものです。原告の訴えは、被爆者援護法に基づく①健康管理手当と②葬祭料の支給申請を同市が却下した処分の取り消しを求めたものでした。
この裁判は①健康管理手当については昨年9月、②葬祭料については今年3月、いずれも長崎地裁が原告勝訴の判決を下しました。しかし被告である長崎市は、国の意向を受け、福岡高裁に控訴していました。
この2審判決が26日、福岡高裁で言い渡されたのです。
判決で石井宏治裁判長は「不支給は違法」と述べ、いずれも1審長崎地裁判決を支持、市側の控訴を棄却しました。つまり原告の主張が全面的に認められたのです!
(以上、共同、時事26日付より)
◆ 今回の福岡高裁判決を受け、細田博之官房長官は同26日午後の記者会見で、日本政府として日本国外からの申請を可能とする方向で在外被爆者援護制度を見直す考えを表明!「高裁判決を受け止め、外務省、厚生労働省で知恵を絞ってもらいたい」と語りました。
(以上、共同26日付より)
◆ 一方、尾辻秀久厚生労働相は判決について27日閣議後会見で「国にとって大変厳しい判断。長崎市や法務省と協議して上告するかどうかの結論を出したい」と述べていましたが、厚生労働省は同日、上告を断念する方針を固めました!
(以上、共同27、28日付より)
→ 詳細は『長崎新聞』『中国新聞』26~29日付、ほか主要各紙 をご覧ください。
→ 続報はこちら(10月7日付)をご覧ください。
![]()
(2005年9月6日、29日)
![]() 【長崎新聞】【中国新聞】〔海外原爆展 パリ市が初主催 30日まで〕
【長崎新聞】【中国新聞】〔海外原爆展 パリ市が初主催 30日まで〕
6日付『長崎新聞』によると、核保有国フランスの首都パリ市が初めて主催者に加わった「ヒロシマ・ナガサキ原爆展」が5日から30日まで、パリ市庁舎展示ホールで開かれました。
海外原爆展は広島市、長崎市が毎年、米国などの地方都市で開催しています。今回はパリ市のドラノエ市長が昨年、広島市を訪問した際に開催を要望し、このたび実現したということです。
内容は写真パネル48点、被爆資料20点、またパリ市が希望した「はだしのゲン」など原爆を題材にした漫画作品などが展示されるそうです。
29日付『中国新聞』では、フランスを訪問した広島市の秋葉忠利市長が「子どもの来場が多かった。ヒロシマの歴史を感じ、未来を創造する力を身に付けてくれただろう」と同展を振り返っていました。
なお『毎日新聞』9月25日付日曜版(「日曜くらぶ」)掲載の連載コラム「欧州的成熟ライフ」に、同展の開催と、近年のフランス社会の原爆に対する反応の変化が書かれています(タイトルは「パリで初の原爆展」)。興味のある方はご一読ください。著者の木立玲子さんはパリ在住のジャーナリストです。
→ 詳細は『長崎新聞』9月6日付
『中国新聞』9月29日付 をご覧ください。
![]()
(2005年9月1日)
![]() 【読売新聞】〔健康管理手当 在外公館での申請が年末にも実現へ 日本政府が方針〕
【読売新聞】〔健康管理手当 在外公館での申請が年末にも実現へ 日本政府が方針〕
※8月7日付〔在外公館での各種手当申請に前向き姿勢 ただし被爆者手帳交付は否定 尾辻厚労相〕の続報
1日付『読売新聞』が、嬉しいニュースを掲載しました!同紙によると日本政府は、在外被爆者による健康管理手当の申請を在外公館でも受け付ける方針を固めました。
記事によれば、政府は被爆者援護法施行規則を改正し、年末をメドに在外公館で受け付けを開始する意向だそうです。
申請に必要な医師の診断書については、居住地の医療機関を事前に指定することが検討されている、ということです。
![]() ただ一方、被爆者健康手帳の取得申請については「在外公館での手続きは難しい」(政府筋=同紙より)とされているようです。
ただ一方、被爆者健康手帳の取得申請については「在外公館での手続きは難しい」(政府筋=同紙より)とされているようです。
被爆地にいたことの証明が在外公館では困難、というのが理由だそうで、手帳取得は従来どおり「訪日が条件」との方針を見直してはもらえないようです。
専門職員を在外公館に派遣するなど、実現への方法はあると思うのですが…。
→ 詳細は『読売新聞』9月1日付 をご覧ください。
![]()
(2005年9月1日)
![]() 【中国新聞】〔“一部の人の特殊な問題” 在外被爆者援護の論戦なく 衆院選〕
【中国新聞】〔“一部の人の特殊な問題” 在外被爆者援護の論戦なく 衆院選〕
11日投票の衆議院議員総選挙を目前に、「在外被爆者援護」をめぐる議論はほとんど聞かれない ― 1日付『中国新聞』は「在外被爆者の声どこへ」と題し、そんな今回の選挙戦のありようを描きました。
「在外被爆者問題の重要度が低く、一部の人の特殊な問題とされている」。
「在ブラジル・在アメリカ被爆者裁判を支援する会」代表世話人の田村和之・龍谷大法科大学院教授は語り、選挙戦で議論が盛り上がらないことに危機感を募らせているといいます。
記事によれば、マニフェストで在外被爆者問題の解決を公約したのは民主、共産、社民の3党。しかし被爆地・広島でも選挙戦で「議席を回復して救済を」と訴えたのは社民党元職の候補だけで、「小泉改革の是非に注目が集まる中で、かき消されがちだ」という状況のようです。
記事は、「訪日できない被爆者は放置されたままだ」と、いまだ援護の手から置き去りにされた人々がいることを指摘。にもかかわらず、在外被爆者援護対策に「腰が重い」国の姿勢を憂えるトーンとなっています。
→ 内容は『中国新聞』1日付 をご覧ください。
![]()