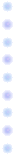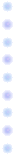結果を聞きに行く前の晩、家族でよく行ったジャズのライブハウスで息子と
彼の数人の友達と落ち合った。夫は、二晩とも友達の家に泊まった息子とここで
初めて顔を合わせたのだが、一年前と比べて自信に満ちている息子の様子に満足そうだった。
別れ際、息子と握手をした。何年ぶりだろう。彼の手は温かくてやさしかった。
翌日、J病院にひとりで結果を聞きに行った。
待合室で待っている間、「乳腺症でしたよ」と言われて、
「やっぱりね。また思い過ごしだった」と安心する場面を想像した。そうなりそうな気もした。
大して緊張もせず、備え付けの乳癌のパンフレットに目を通したりしていた。
「もし癌だとしたら、大きさからいったらⅡ期。5年後の生存率は・・」
大変なことのはずなのに、まったく他人事のようで実感が湧かない。
不思議なほど静かな気持ちで名前を呼ばれるのを待っていた。
呼ばれて診察室のドアを開けると、机に向かってカルテを見ていた先生が顔をあげ
「あ・・おひとりでいらしたんですか?」
と言った。困ったな・・と言いたげな声音で、もう決まりだ、ということがわかってしまった。
重大な場面なのに、おどけてのけぞってみせ
「出ましたか、やっぱり」
と笑いながら答えた。笑い事じゃないのにお腹の底から、笑いたいような何かがこみ上げてきていた。
椅子に座りながら机の上のカルテを覗きこむと、細胞診の結果の票に「・・・・多数の異型細胞が見られ・・・」と書いてあるのが読み取れた。テレビなどで時々見る、顕微鏡の中で元気に蠢いて増殖している癌細胞が目に浮かんだ。不思議な事に、恐怖は全く感じなかった。むしろ、元気な癌細胞がわたしの体の中にいるんだ、という実感が湧き、これは本気で腹を決めてとりかからなければ、と力が湧いてきた。
先生が困ったような顔をしていたので
「わたし、大丈夫ですから、全部言ってください。覚悟して来ましたから。
入院、手術のスケジュールがはっきりわかった方が仕事の段取りをつけやすいので」
とこちらから申し出た。
「そうですか、それでは・・」と言って先生は説明を始めた。癌である可能性のレベルがⅤ、
つまり、灰色ではなく、間違いなく100%癌だ、ということ、癌の大きさから言って、
ぎりぎりだが温存の範囲内にあること、温存か全摘かは最終的には患者本人が決めるということ、
温存と全摘それぞれの治療法の違い等、わたしの質問にも丁寧に答えて下さった。
「再発や転移の可能性がなるべく低い方を選びたいので、全摘でお願いします!」
と意気込んで言うと
「ちょっ・・ちょっと待って下さい」
と先生が慌てた。
「いやぁ、患者さんから先にそこまで言われるとは・・」
「え?普通の人はそうじゃないんですか?」
「いや、普通は、癌だと言われたら泣き出したり、呆然として無言になって、出なおしてきます、と言って
帰ってしまったりしますよ」
「へぇー、そうなんですか」
テレビドラマの癌告知の場面は、なにかわざとらしくて大げさだなぁ、と思っていたのだけれど、
ほんとうにそういう人も多いのか・・、と妙に納得した。
悪いものは早く取ってしまいたい、と思い、なるべく早く入院、手術が出来るように頼んだ。
手帳を見てスケジュールを決めながら思いつく質問を次々すると、先生は一生懸命答えて下さった。
「そこまで前向きな患者さんなら、僕、全力を尽くしますよ!」
傍で先生とわたしの対話を聞きながらカルテにメモをとっていた年配の看護婦さんが
「先生、嬉しそう!」と笑った。
その場で、翌週入院、翌々週手術、というスケジュールを決め、次の来院日を決めて帰る時に
「信頼できそうな先生だから、あとはとにかく早く手術をして癌を取ってしまいたい」という一心で
「セカンドオピニオンも考えていたんですが、もう、先生にお願いすることに決めます」
と言うと
「セカンドオピニオン、どうぞどんどんやってください。カルテも資料もどんどん貸しますよ。
手紙も書きます」
と言って下さった。
医学の世界もずいぶんオープンになったんだな、とその時は思ったのだが、
ほんとうに誠実な良いお医者様だった、ということらしい。
検査をする為に移動する途中で夫に電話を入れた。
夫も覚悟していたのだろう、驚いた様子は無かったが、病院も日程もすでに決めてしまった、というと
少し心配そうな声になった。
冷静でいるつもりだったが、実はかなりパニックになっていたに違いない。
手術をすることも日程も、夫に相談せずに決めてしまったことを、この時は変だとは、全く思わなかった。