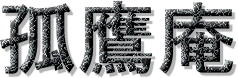小諸城址 懐古園 +α(夏)
平成24年9月22日、夏から秋に変わりゆく季節の懐古園を訪れました。
気温も30度を超えることはなくなってきたので、「夏の懐古園の風景を撮影できるのはこれがラストチャンスかもしれない」と思い、愛機である一眼レフカメラ(ニコンD80)をぶら下げて散策してみました。
当日朝は曇りだったのですが、午前11時ころには晴れ間も出てきました。猛暑ではないものの、それなりに暑く、ライトグレーのポロシャツがところどころダークグレーになるくらいに汗をかきました。

三の門(重要文化財)
寄棟造りの門の代表的なものとして有名で、小諸のシンボルでもあります。ちなみに「三の門」とは、本丸から数えて3番目にある門という意味だそうです。

三の門を横から見たところ(右側が正面)

三の門料金所を過ぎたところ
右側の石垣は二の丸跡で、かつてはここに、渡り矢倉の「二の門」があったそうです。

二の丸跡(正面の階段がある石垣)
右側の石垣は南丸跡

黒門橋
渡りきったところに、かつて「黒門」があったそうです。黒門は現在、小諸市八幡の正眼院という寺院に移築されています(後述)。

黒門橋を渡りきったところ
左へ行くと本丸跡・懐古神社等、右へ行くと水の手展望台等があります。基本的には懐古神社への参道となる左へ行く順路がよいでしょう(右回りで行くと懐古神社へは裏から入ることになるため)。

懐古神社 鳥居
ここから小諸城本丸跡に入ります。

懐古神社脇の食事処

懐古神社 本殿
明治13年(1880年)、小諸城本丸跡に祀られました。

本丸跡の池
本丸跡・懐古神社を通過し、谷に沿って千曲川方向に行きます。

富士見台
天気の良い日は富士山が見えるそうです。

馬場
春には桜の名所として賑わいます(懐古園は桜名所百選の一つです)。

藤村詩碑
小諸にゆかりの文豪・島崎藤村の作品「千曲川旅情のうた」の詩碑です。

水の手展望台
千曲川が見渡せる展望台です。

水の手展望台から望む千曲川
東京電力西浦ダムが見えます。

武器庫(復元)

武器庫前の東屋(あずまや)

天守台の石垣

天守台の石垣

画面中央の、石垣と石垣の間に僅かに見えるのが黒門橋です。これで黒門橋先の分岐から左回りで一周したことになります。
とりあえず、これで懐古園をあとにします。なお、懐古園内には長野県最古の動物園である小諸市動物園、児童遊園地、藤村記念館、等の施設も多数ありますが、今回は割愛しました。
ちなみにこの日は、観光客もちらほらといたのですが、うまく「人が入らない写真」を撮ることができました。
以下はおまけ的な要素です。
小諸城の門は、現存しているものは4つあるのですが、三の門を除く3つは懐古園の外にあります。

大手門(重要文化財)
もともとは小諸城の正門です。現在、懐古園からは僅かに離れたところにあります。小諸城本丸から数えて4番目の門だったことから「四の門」、三河から運ばれた瓦を用いていたことから「瓦門」とも呼ばれていたそうです。東日本の初期城郭建築の中でも代表的な城門とされています。明治維新後、一時は民有となって「門」としては使われない時期もあったようですが、平成3年4月に小諸市に寄贈され、平成20年3月に大修理が完了し、元の「門」としての姿を取り戻しました。
小諸駅から徒歩1〜2分程度。

足柄門
もともとは小諸城の三の丸(大手門の西側?)にあった門です。現在は移築され、小諸市荒町の浄土宗寺院「光岳寺」の総門となっています。「高麗門」と呼ばれる門の形です。ちなみにこのお寺、僕の子供の頃の遊び場でした。
小諸駅から徒歩10分程度。

黒門
もともとは小諸城の本丸付近にあった門で、「一の門」とも呼ばれていました。現在は移築され、小諸市八幡の曹洞宗寺院「正眼院」の山門となっています。
小諸駅から自動車で15分程度。
小諸は北国街道小諸宿として栄えた場所で、今でもその名残を見ることができます。

旧小諸本陣(重要文化財)
本陣とは、大名や公家の休泊施設の事です。この建物は北国街道の小諸宿の本陣兼問屋場(といやば)です。小諸の名所の一つとされています。
小諸駅から徒歩8分程度。
この年(平成24年)は小諸を舞台にしたアニメも放映されたことから、記念ページというか御祝儀ページというか、そんな意味合いでこのページを作ってみました。ギリギリ夏の風景として写真に収められたかな、と。
ちなみに翌日から急に寒くなり、小諸の夏は終わりを告げました。