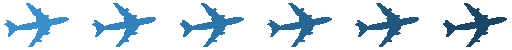
| 本部町 沖縄本島沖縄本島北部東支那海に突出した本部半島の西半を占め瀬底、水納、両離島を含む東北部は今帰仁村に面し西方海上には伊江島、北方海上には伊是名、伊平屋の両島を望み南東部には名護市に接しております。八重岳、本部富士などの比較的高い丘陵が海浜まで裾野を広げ、近隣の名護、今帰仁との境を分けており、平地には満名川が流れています。その昔は豊富な水量を利用した稲作地帯が広がっていましたが、現在は水イモ栽培が盛んに行なわれています。そのような変化に富んだ地形の中
で、花卉、サトウキビ、パイナップル、果樹、野菜などの農業から、有名なカツオ漁などの漁業、砕石場などの工場まで、様々な産業が営まれています。1975年には沖縄海洋博の会場となり、その跡地には国営沖縄記念公園として美しく整備されました。(もとぶ町観光協会HPより) 今回は、沖縄美ら海水族館と備瀬のふく木並木を訪れました。 今帰仁村 今帰仁村は、沖縄本島北部、本部半島の北東部に位置し、那覇市から北へ約85km。東から東南部にかけては名護市、南西部から西は本部町、北は東シナ海に面し北東約1.5kmには古宇利島があります。 村の南側は、乙羽岳(標高約275m)を中心に、山並みがほぼ東西に延びています。その山麓から北および東に向かって緩傾斜地となり、さらに平坦地が広がり、耕作地は集落を中心に広がっています。 今回は、今帰仁城跡と古宇利大橋を訪れました。 |
|||
 |
 |
||
| 沖縄美ら海水族館 平成14年に新しくオープンした沖縄美ら海水族館は、世界一の「アクリルパネル」と世界初の「生きた珊瑚の大規模飼育・ジンベエとマンタの複数飼育」がここにあります。海洋文化館、エメラルドビーチなどの施設をもとに、沖縄郷土村やおもろ植物園、熱帯ドームセンターも整備され、一般公開されています。(もとぶ町観光協会HPより)入場料は、1,800円です。割引があります。) | エメラルドビーチから伊江島を望む。 | ||
 |
 |
 |
 |
| アデヤッコ | ナンヨウハギ(沖縄名:ジュリグヮークスク) | イトヒキテンジクダイ(沖縄名:ウフミー)、黄色い魚はニセネッタイスズメダイ | アカマツカサ(沖縄名:ミンタマアカイユー) |
 |
 |
 |
 |
| オオテンジクザメ(沖縄名:タコクワヤー) | タマカイ(沖縄名:アーラミーバイ) | アオウミガメ(沖縄名:ミジガーミー) | 縦縞がツノダシ(沖縄名:ハタムチ) |
 |
 |
 |
 |
| 後ろの黄色がヨスジフエダイ(沖縄名:ビタロー) | ?? | ギンユゴイ | ドクウツボ(沖縄名:ウナジ) |
 |
 |
 |
 |
| コブシメ(沖縄名:クブシメ) | ハナゴイ(沖縄名:ジュリグワーイユ) | チンアナゴとニシキアナゴ | トビハゼ |
 |
 |
 |
 |
| タツノオトシゴ | ??クマノミ | ??ウナギ | ハマダイ(沖縄名:アカマチ) |
 |
|||
| 黒潮の海と称した巨大水槽(水量7,500㎥のアクリルパネル)の中を、ジンベエザメやマンタなど大型の魚がゆうゆうと泳いでいます。感動です! | |||
 |
 |
 |
 |
| ジンベエザメ(沖縄名:ミズサバ) | オニイトマキエイ(沖縄名:ガマーカマンタ) | オニイトマキエイ(沖縄名:ガマーカマンタ) | ヒョウモンオトメエイ(沖縄名:カマンタ) |
 |
 |
 |
 |
| マダラトビエイ(沖縄名:フェンサー) | マダラトビエイ(沖縄名:フェンサー) | タマカイ(沖縄名:アーラミーバイ) | ロウニンアジ(沖縄名:カマジャー) |
 |
 |
||
| オオメジロザメ | アメリカマナティー | ||
 |
 |
||
| 備瀬ふく木並木 備瀬区は本部半島の先端部に位置し、北緯26度42分、東経127度53分にある。村落は弓形になった延長1,100mの海辺に沿った砂丘の上に形成されていて、起伏の少ない珊瑚礁の村落である。また、備瀬の土壌は、主に珊瑚石灰土壌(マージ)であり、村落内は砂土となっている。沿岸は屈曲に富んでいるが、周辺は遠浅であり珊瑚礁をもって囲繞されているためイノウ(湾)は至って穏やかである。しかし、備瀬崎と伊江島に迫るこの海峡は、黒潮で洗われた三十尋を超す海溝があり潮流の激しいことで知られている。また、備瀬は、南西から北東にかけて海に巻かれているため、気象の変化が激しい。夏は砂地による輻射熱で日中は焼けつくように暑いが、夜は海風が吹き寄せて涼しい。(説明板より) | 福木の説明 フク木(方言名プクーギ) Garcinia subelliptica Merr オトギリソウ科 原産地:フィリピン 推定樹齢:250~300年 樹高:15~20m 胸高直径:70~100㎝ 実径:2.5~3㎝ 特徴:雌雄異株 花 帯黄白色 防潮、防砂、防風、防火など沿岸屋敷林として最適 用途:屋敷林、建築用材、染料(樹皮) ※備瀬区のフク木並木は昭和58年に「沖縄の自然百選」に選ばれ、県内最大規模のフク木ロードが見られます。(説明板より) | ||
 |
 |
||
| 備瀬公民館の向かいにある拝所(説明板には御嶽(ウタキ)ではなく拝所とありました。)。 | 地元の人が、なにやらお参りの準備をしていました。 | ||
 |
 |
||
| 今帰仁城跡 今帰仁城跡と今帰仁村歴史文化センターには、入場券が必要です。400円でした。 | 今帰仁城跡屋外模型 今帰仁城跡の縄張り、城の周囲に点在する遺跡の様子を確認することができます。(パンフより) | ||
 |
 |
||
| 外郭です。立派な石垣です。 | 平郎門 本門で、現在見る門は昭和37年に修復されたものです。門の両脇には狭間があって門番が見張りするところです。(パンフより) | ||
 |
 |
||
| 平郎門から大庭へ続く石階段です。パンフには「旧道」と書いてあります。大庭(ウーミャ)を囲むように正殿(主郭)、北殿、南殿の建物が配されていたと考えられ、行事等に利用された重要な広場です。(パンフより) | 主郭 本発掘調査によって築城から廃城までの時期変遷を確認することができました。場内でもっとも中心的な建物があった場所です。(パンフより) | ||
 |
 |
||
| 主郭から志慶真門郭へ下る門です。特に説明はありません。 | 志慶真門郭へ下る道です。ここには城主に仕えた身近な人々が住んだと考えられます。発掘調査によって4つの建物があったことが分かっています。(パンフより) | ||
 |
 |
||
| 大隈 戦時に備え馬を養い、兵馬を訓練した場所として伝えられています。もっとも高い石垣が築かれた堅牢な城郭です。(パンフから)御内原(ウーチバル)からの眺めです。雨模様ですが、海はコバルトブルーです。 | 主郭から北側の展望です。遠く古宇利島が見えます。手前の石垣は、志慶真門郭の城郭です。 | ||
 |
 |
||
| 日本一早い桜祭りが1月21日~2月6日で始まっていたのですが、今年はだいぶ遅いようです。それでも場内で咲いている寒緋桜を見つけました。 | 今帰仁村歴史文化センター 今帰仁城跡をはじめ今帰仁の歴史と文化を紹介しています。今帰仁城跡から出土した陶磁器などの資料も展示しています。(パンフより) | ||
 |
 |
 |
 |
|
第一展示室 今帰仁の歴史 今帰仁グスクから発掘された中国製の陶磁器をはじめ、今帰仁按司と関わる大北墓や百按司墓などを紹介し、今帰仁グスクをめぐる歴史を展開。山北監守と関わる阿応理屋恵の勾玉や水晶玉(ガラス)を展示してある。グスクから出土した銭類も展示してある。(今帰仁村歴史文化センターHPより) |
今帰仁城跡の模型がここにもありました。 | 第二展示室 今帰仁のムラ・シマ ムラ・シマ(村落)の集落の形態には碁盤型や分散型などがある。ここでは今泊の集落をモデルとして今帰仁グスクや御獄や水田や馬場跡など、昭和30年代の様子を描いてある。そこにはムラ・シマを構成する家や神ハサギや田畑や湧泉(カー)や生業など様々なキーワードがある。(今帰仁村歴史文化センターHPより) | 第三展示室 今帰仁の生活と文化 ムラ・シマで生まれ暮らし、そこで日々使ってきた人々の生活道具や芭蕉布、豊年祭や神アサギなどを展示。旧暦をサイクルとしてきた人々の生活リズムや知恵を生活文化として描いてある。失われかけているシマの人々の農耕を中心とした潜めている感性を呼び覚ませてくれる。(今帰仁村歴史文化センターHPより) |
 |
 |
||
| ワルミ大橋 2010年12月18日に開通したばかりの「ワルミ大橋」です。今帰仁村から名護市の屋我地島の間のワルミ海峡に架かる橋で、橋長は315m、工事費用は45億円でした。元々、2005年に開通した古宇利大橋とセットで計画されていたらしいのですが、用地問題で遅れたそうです。 | この海峡は、運天港への航路のため、クリアランスの高さは37.2mあります。道理で橋が高いわけです。古宇利大橋も見えて、景色も満点です。今回は、時間があまりなかったのですが、この橋が開通したおかげで、古宇利大橋の観光が間に合いました。 | ||
 |
 |
||
| 古宇利大橋 当初は2002年に開通予定だったが、建設工法の難しさから3年遅れ、2005年2月8日にようやく開通したそうです。それにしても、不思議な景色です。 | 橋の一番高いところです。この橋は、現在沖縄県内の離島架橋ではもっとも長く、通行料無料の橋としては日本一長いそうです。 | ||
 |
 |
||
| 車から降りて古宇利島を踏みしめてきました。 | 小雨が降っているのに、何ときれいな海の色でしょうか! | ||