⇒ (補足説明):疑問にお答えします…①
困ってます!②
困ってます!③
![]()
![]() (補足説明): 疑問にお答えします - ①
(補足説明): 疑問にお答えします - ①
8月某日、当ホームページ「困ってます!①」をご覧になった東京のある新聞記者の方から、ホームページ管理者のもとに、次のようなご指摘をいただきました。
![]()
「今年10月から在外被爆者への医療保険制度が始まるのですが、ご存知でしたか?
その制度とは、訪日できない被爆者のために、日本に来なくても現地で医療費が支給されるというものです。
この制度によって在外被爆者の医療費の問題は解決されるのではないですか?!」
![]()
この記者の方は、手当を受給できない在外被爆者について関心を示され、取材の問い合わせをして下さったのです。ところがその後に“10月にスタートする医療保険制度”のことを調べてお知りになったようで、少々きつい口調でこのようなお電話を下さいました。おそらくは「これなら記事にする必要はない。時間のムダだった」とお腹立ちになられたことと思います。
ホームページでの説明に不足な点がありましたことをお詫びしますとともに、読者の方々への誤解を防ぐため、ここではご指摘の点について改めて補足説明させていただきます。
| ※ なお、ご指摘いただいた医療保険制度とは、厚生労働省の「在外被爆者保健医療助成事業」のことで、10月のスタートは延期となることが決まっています → 詳しくはこちらをご覧下さい(クリック!) |
(以下、補足説明)

日本国内であれば、広島、長崎で被爆した被爆者は、被爆者健康手帳を持っていれば
◆ 医療の給付+医療費の支給
◆ 各種手当の支給
を受けることができます。
この〔医療の給付+医療費の支給〕と〔各種手当の支給〕は別のものです。
ご指摘いただいた医療保険制度(在外被爆者保健医療助成事業)は医療費の支給にあたります。
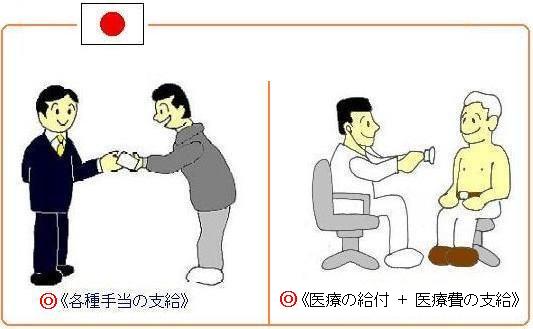
医療の給付+医療費の支給に関しては、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(通称「被爆者援護法」)第3章第3節に記されています。
この中には医療の給付とあわせて、たとえば虫歯など明らかに被爆と因果関係がないと思われる疾病・傷害を除いては、国が被爆者の医療費を負担しましょう、という内容が定められています。
一方、各種手当の支給に関しては、同法第3章第4節に記載されています。
ここには、被爆状況や疾病の内容により、「医療特別手当」「特別手当」「保健手当」「原子爆弾小頭症手当」「健康管理手当」といった各種の手当を国が被爆者に対して支給しましょう、という内容が定められています。
国による医療の給付+医療費の支給は1957(昭和32)年に制定された「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」(通称「原爆医療法」)に、
国による各種手当の支給は1968(昭和43)年に制定された「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」(通称「原爆特別措置法」)に、
それぞれ定められました。
この〔医療の給付+医療費の支給〕と〔各種手当の支給〕は、1994(平成6)年に制定された「被爆者援護法」に引き継がれ、今日まで続いています。
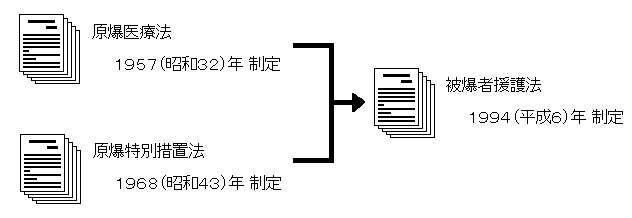
※ なお原爆特別措置法が制定される以前の1960(昭和35)年、医療法改正により医療手当の支給が定められましたが、これは対象者が限られたものでした。

(?国はなぜ被爆者にだけ〔医療の給付+医療費の支給〕や〔各種手当の支給〕をするの?
→ と疑問を持たれた方は、ここをクリック!)