

2004.02.28
根室本線漫遊(富良野−新得) 路線図を表示
綾小路さんは旅行が好き・・・、もとい大好きである。
というか、ほとんど生きがいでもある。
みなさんにも、すでにお分かりいただけていると思う。
しかし、旅行の計画を立てるのも好きなのである。 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
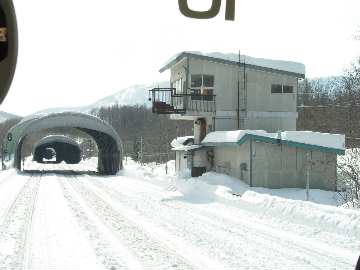 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
綾小路さんは旧線に乗車した事はなかったが、過去に何回か路線跡を探索した事があった。
その時に残されていた遺構が、頭の中に浮かんできた・・・。 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 トップ |
 鉄道 |