1-1.トェンティクロス ハイキング
神戸三の宮の布引の瀧 から
トェンティクロス を経て神戸市立森林植物園 に行ってきた。同行者はいつもの3人、田村、新郷、塚田の各君で、示し合わせて皆が中山8時前の電車に乗車。三の宮には9時頃ついた。
天気は文字通り五月晴れでいうことなし。
布引の瀧
阪急三の宮から新神戸駅まで歩くことにした。 久し振りに加納町辺りを目の当たりにし、ビルが立ち並びすっかり都会の様相を呈しているのに感心した。ブラブラ歩きになり、布引の瀧方面の入り口を探したりして、結局30分くらいかかってしまった。
久し振りに加納町辺りを目の当たりにし、ビルが立ち並びすっかり都会の様相を呈しているのに感心した。ブラブラ歩きになり、布引の瀧方面の入り口を探したりして、結局30分くらいかかってしまった。
新幹線の駅の地下一階の奥の方に瀧方面のトンネルのような道があって、それをたどっていくとやや急な登りにになり、ラジオ体操の会場に良く使われているという見晴らしの良い広場にに出た。眼下に神戸港が一望される。
一休みして又登っていくと、程なく大きな瀧の音が聞こえ始め、すぐ目の前に迫力のある瀧が現れた。布引の雌瀧である。
後から分かったのだが、他の夫婦、鼓、雄の3つを加えた4つを総称して布引の瀧というらしい。
それにしても見事な瀑布だ。たまたま水量が多かったとは思うが、4つとも、姿形が予想をはるかに越えていた。日本の3大瀧の一つらしいが、納得した。(これから出てくる写真や画像は、どれもその上に、ポインターを持ってきて一呼吸おくと、説明文が出てきます。)
全体に瀧壷が小さめなのか、眼前に水が轟音と共に落ちてくる様は本当に迫力がある。他の3つについても同じ印象であった。上の写真は鼓瀧を横から撮ったもの。
トェンティクロス
瀧の流れに沿って登っていくと神戸市の水甕といわれる布引貯水池に出た。明治に出来たものでダムの表面は小さな石を貼り付けたように見え、昭和以降と工法が違い時代が感じられ、風情がある。丁度土砂の浚渫とダムの補強工事中で大きな干上がった底で数台の重機が動いているのが小さく見えた。
目にまぶしいくらいの新緑を楽しみながら、しばらく緩やかな登りの山道を行くと、一寸した休憩ができるところに出た。今日は閉まっていたが茶店やトイレがある。市が原という場所らしい。この辺りは六甲山縦走路の一部に当たるらしく、その標識が立っていた。直ぐその標識とは外れ左の方に進む。いったんは川の流れから遠ざかったと思っていたら、又まもなく文字通り渓流に直面した。生田川であり、トェンティクロスの始まりであった。
ここ数日来の雨で川の水かさが増えているとは予想していたが、初めての瀬の渡り(クロス)を見てこれは、少し危ないな!と感じた。川幅は10mは軽くあり、それを横切る形で大小の岩が並んでいる。
その中ほどのかなり大きい石の上を、水が流れているのが分かったからだ。他の者も一様にそう思ったらしい。自分がたまたま先頭を歩いていたので、そのまま用心しながら渡り始めた。オーバーフロウしている石に靴を乗せると当然水に半分くらいつかってしまった。だが慌てず普通の速さで残りの岩もそのまま渡りきった。
靴の中がてっきり濡れたものと思っていたが、足先もヒモの部分も完全に遮断出来ていて全く濡れずにすんだ。なかなか造りの良い靴だと感心した。最初がこんな様子では先が大変だと思ったが、結局ここと最後が難関でほかは問題なかった。名称から20も瀬渡りがあるのかと半ば期待もしたが、数えてみるとせいぜい8,9箇所で、危ないところは前記のとおり二箇所だけだった。そこも普段は全く楽に歩けるとのことらしい。でもやはり終わりの所(上の写真の手前側)で、一人が滑って川にはまってしまい、大分濡らし大変だった。自分も以前似たような場所で滑って転んだことがあるので、やさしい箇所でも細心の注意を払った。
川の水は多くてしかも綺麗だった。正直なところ 生田川 は地名とばかり決め込んでいて、迂闊にも、こんな清流が気持ち良く流れているとは、ついぞ知らなかった。時間にして約3,40分の距離だと感じたが、十和田湖の奥入瀬の流れに似ているところもあった。神戸という都会の直ぐ側にこんないい流れがあるとは・・・。感激の面持ちであった。でもこの川は街に入ってどこをどう流れているのだろか?詳しい人に聞いてみたい。
昼飯は河原の少し広がったところで取った。ローソンの握り飯だったが、本当に美味いと思った。
神戸市立森林植物園
小1時間の昼食休憩後、再び歩き出してすぐにまたクロスの箇所になった。結果的には先に書いた一人が流れに落ちたところだが、それを越えるとすぐに植物園の東口があった。従ってトェンティクロスは自動的にここで終わりとなったが、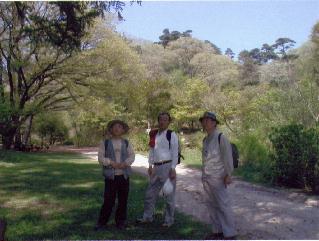 この川の上流がこの後どうなっていくのか非常に興味を持っているが、当然分かっていない。
この川の上流がこの後どうなっていくのか非常に興味を持っているが、当然分かっていない。
東口には門だけで人はおらず、入園料300円を南にある正門で頂きますとあった。そのまま道なりに登っていくとやがて大きな池に出た。
周囲は綺麗に手入れされたここの中心になる長谷池である。辺りの風情を楽しみながら遊歩道を半周してしばらく行くと、正門があり側の休憩所でコーヒーを取って一服した。その後唐松の林や石楠花の群などの花を愛でつつ西門にでた。広い園内は一通り見るだけで恐らく丸まる1日いやそれ以上かかるだろう。今回1時間ほど歩いただけだがそうする価値が充分にあると思われた。神戸市もなかなかやるな・・・。
位置的にここは六甲山の西方で、山上のドライブ道が続いており、宝塚からは簡単に来れる筈だ。いずれ一度試してみよう。
この後は学習の森、再度公園、大竜寺、再度谷、市章山、諏訪山神社を経て神戸の街中に戻ってきた。道中殆どひたすら歩くだけで、寄り道や見学などはせずだったが、それでも午後4時半を廻っていた。総歩数34000歩の、かなり重いハイキングであったが、丸一日非常に楽しかった。
以 上


1-2.大船山に登る
 H15.5/4(日)に大船山(三田市 653M)に登ってきた。午前中は薄い雲がかかり山登りには持って来いの日よりだった。
H15.5/4(日)に大船山(三田市 653M)に登ってきた。午前中は薄い雲がかかり山登りには持って来いの日よりだった。
何時ものように十倉の公民館の広場に駐車させてもらう。他には1台もなかった。そこから慶長寺というお寺の前を上がっていく。程なく山道が始まる。少し登ると池が三段構えで順番に現れる。いずれも一方がダムのように堰き止められた溜め池である。池の色は、土砂の関係からか鮮やかなコバルトブルーで、一見すると生き物はいないような感じを持つが、オタマジャクシの大きいやつが沢山いた。
いよいよ山道に入る。植林された杉林で木が高い為殆ど日は射さないが、それでも湿気があるのだろうか、かなり暑かった。後から分かったのだが、この山の特徴は頂上まで平坦な道はなく、かなりキツイ坂ばかりであることだ。足元はやや大きめの石がゴロゴロしていて歩きにくい。雨のたびに土砂が少しずつ流されていく為だろう。そのせいで一部脇に新道ができているところがある。前回の時それに入り損ね、歩きにくくて難渋した。
途中山桜とおぼしき大樹があり、印象に残った。30分ほどで波豆川バス停方面の道標のある分岐にきた。少し開けたところでベンチもあり一息いれる。すでに背中は汗でぐっしょり。頂上まであと870m、ここまで1560mのサインが出ていた。
再び歩き出す。最初のうちは緩やかで5分くらいで又分岐がある。大舟山寺跡、バス停方面となっている。前回の時帰途をこの道にとって見たところ、波豆川バス停には割りに早く行けたものの、そこから車を停めている公民館まで遠くて、うんざりさせられたことがある。
ここで今日初めて人に出会った。自分と同じ年頃の男性の二人ずれだった。それを先にやり過ごし、ゆっくりしたしたペースで登っていく。
かなりの急坂が最後まで続き、中程にはロープの張られたところもある。登りは時々前の岩などに手を付いたりしていくが、下りの時は、脇の木を掴んで体を支えていくことになる。頂上まであともう数分と思われる足場が少し広い所で、アンダーシャツを換えた。上がってしまうと他に人がいるとの理由で、桂子が嫌がる。
気持ち良くなって最後の坂を上がりきった。11時20分ごろだ。案の定、三つあるベンチは先客でふさがっていたので、東面した適当なところにシートを広げて少し早いが昼食にした。頂上は狭いがほぼ360度の眺望が楽しめる。特に東方向は眼下はるかに朝通り抜けてきた道が見え、その向こうには名前は定かではないが、山並みが重なり合っている。それらを眺めながらのお握りはいつものことだが、いかにも美味い。更に甘いものを楽しみ、何となく体は充実感で満たされる。
食事を済ませ、周囲の展望を堪能して、12時30分頃下山開始。登りより下りの方が怖いので、廻りの立ち木を順にしっかり握り、足元に注意しながら慎重に行く。最初の10分間位が一番滑りやすい地帯だ。案の定、桂子が二回ほど尻餅をついた。落ち葉が多いのと土の表面が乾燥していて滑りやすいのだ。軽い転びなのでケガにはならず、ほっとする。

その内初めの分岐にきた。ここからはさほど問題になるようなところはない。殆ど一気に下りていく。主としてヒノキや杉の林で山道はしっかりついているものの、眺望は全くきかない。その為か一息入れるに都合の良い場所が見当たらず、疲れも出ていないのでそのまま例の青い池のところまで来てしまった。
朝ここを通る時から戻りには、ここでわらびを探したいと云っていたので、約束通り一服することにして、早速自分用にシートを広げ場所を作った。それからすぐゴロリと横になり暫しの居眠りを楽しんだ。20分ほどもまどろんだろうか、その後ミカンで喉を潤したりしてから立ちあがった。
桂子も結局あまり戦果はなかったようだった。
(右上の画像は、頂上より遥か彼方に池田の五月山を見る。画像のリンクスポットで青い枠が出でいる見本。)
帰宅途中、つくしの里に立寄り野菜を物色、ついでにコーヒーを飲む。ここのコーヒーには何故か、つまみにアツアツの草餅がつく。なかなかうまい。ただ出てくるまでに相当時間を要するのが難。
今日は終日好天気であった。こんな日の山歩きは本当に楽しい。良い一日を過ごせ、幸せである。
以 上
(追記)
H15.7.27(日)曇り
又、登ってきた。梅雨の雨で、下は相当軟らかくなっていたので、石や根っこは滑りやすく、充分な注意を要した。
しかし下りは乾燥している時よりも、いくらか降り易いように思えた。
何時もと同じく日差しが樹で遮られていて、暑さは比較的凌げる。風もやや冷気を含み、気持ち良かった。
池の色は、今日は青ではなく、緑色をしていた。山道が全般に、枯れ木などが新しく処理され、手入れがされているようだった。頂上は他に人はおらず、小1時間独占して楽しむ。
(11時45分入山、15時25分下山。) 以 上
(追記2)
H15.11.14(金)晴
今や恒例となった三下会の連中とのハイキングで、ルートを変えて登った。カナディアン大磯からで十倉方面からの合流点までは比較的楽に行ける。そこまでは幅のある、傾斜も緩い山道で、のんびり上がって30分程度だった。落ち葉で覆われていて時として思わぬところで滑るので、少し注意が要ったが。その後はいつもと同じ道となる。尤も車でいくと駐車場までかなり狭い道を行くので、対向車が来たりすると少々面倒。
この登山口の近くにある大舟寺(だいしゅうじと読む)は、文字通りの古刹で風情があり、良い雰囲気を醸している。大きな道から少し入っているので、これまでなんとなく敬遠してきていたのだが、今度初めて訪ね感心した。 以 上
|
1-1.トェンティクロスハイキング | 1-2.大船山に登る に戻る

