







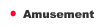

最強の剣豪は誰か
宮本武蔵の巻(2)
比較しやすいからだ。「誰が最強か」は比較のうえに成り立つから比較できる対象があるほうが考えやすい。
柳生宗矩の弟子の渡辺幸庵は、武蔵は柳生宗矩に比べて囲碁でいえば井目置くほど強いと証言している。
井目というのは囲碁で力に大差がある場合ハンディで九つの黒い点に先に石を置くことだが、プロとアマチュアくらいの差だ。
しかし、比べるのが柳生宗矩というのは、なかなか微妙である。
柳生宗矩の強さがよくわからないのだ。逸話も示唆的なものが多く、それほど壮絶なものがない。
というか、初めてこの話しを知ったとき柳生宗矩は、それほど強くないという印象しか残らなかった。
神谷伝心斎は宮本武蔵の評判を聞き、「武蔵といえども鬼神ではない。必ず打ち込む隙がある」と広言していた。
これを聞いた師の小笠原源信斎は、「そのほうの技量で武蔵を評することは僭越だ。慎むのがよかろう。」と諭した。
それでも伝心斎は納得がいかないので、源信斎は二刀の形を使って伝心斎の腕を試すことにした。
この師弟対決は伝心斎が勝った。
小笠原源信斎は人から武蔵の強さを訊ねられて「宮本武蔵は名人である」と答えたところ、
弟子の一人が「恐れながら、宮本武蔵は、手ごろのものを打ち、投げ、自分の剛強を恃むところがあります。
名人ではありません」と言ってのけた。そして、この弟子に極意印可が与えられた。
これらは、武蔵非名人説によく使われる逸話だが、しかし、これは、武蔵批判ではない。
宮本武蔵は細川家の客分であり小笠原家の家老の養父だ。批判は両藩に失礼だろう。
これらは、「宮本武蔵」自体が、強さの指標に使われているだけなのだ。
とにかく、机上でもいいから武蔵と比較し、武蔵より上ならば一等ということなのだ。
逸話に武蔵を登場させるのは、武蔵の強さの裏づけと言ってよいだろう。
しかも、塚原卜伝、上泉伊勢守や伊藤一刀斎のように剣術の創生期ではなく完成期での評価だ。
尾張の逸話で、柳生兵庫と歓談しても剣技には触れなかった。お互いに技量が分かっているからだ、と。
この挿話では、柳生新陰流二世の柳生兵庫と互角と言っているのだが、
柳生兵庫を賛美するのに武蔵を引合いに出す必要があったのだ。
長野五郎右衛門が兵法三十五箇条を書き損ないと断じ、武蔵に後悔千万である、と言わしめるもの同様であろう。
渋川伴五郎時英は塚原卜伝を飯縄使い(妖術使い)、宮本武蔵を幻術師と評した。
ともかく、この二人は魔法を使っているように、滅法強いと評したのだ。
では、武蔵と卜伝のどちらが強いか。


