







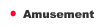

巌流島決闘の仮説
佐々木小次郎の正体(1)
ちなみに、この頃、細川忠興が兵法指南に選んだのは、上泉伊勢守門下の四天王の一人、疋田文五郎である。
岩流の正体をめぐって議論されるが、なかなか実像がつかめない。
岩流の実像を追うなら、関ヶ原合戦以前の地図で実施したほうが良いかもしれない。
「丹治峰均筆記」では津田小次郎であり、長府の人か?とある。「江海風帆草」では上田宗入とある。
岩流の決闘時の年齢は「丹治峰均筆記」によると武蔵に対して若輩者と呼んでいるので壮年くらいか。
「佐々木小次郎」という名はキーワードになるのだろうか。「佐々木小次郎」とは「二天記」の脚注に記述されているが本文にはない。
一般的なイメージである前髪姿の長身の美剣士で背中に長刀を背負っている風貌は吉川英治氏の創作である。
富田勢源の門弟で小太刀に対する打ち太刀をつとめた結果、長刀有利と悟るに至り、通称物干し竿で燕返しの秘剣を操る佐々木小次郎とは、架空の人物であろう。
鈴木家所蔵「岩流剣術秘書」には岩流という流派は伊藤左近祐久によって興され「風車」「虎切」などの剣技を編み出したとあり(「丹治峰均筆記」では水車という技で戦うとある)、 また、宮本武蔵が岩流の遣い手多田市郎を謀殺したと記されているとのことである。
富田勢源の弟子筋というのは伊藤左近祐久から伊東一刀斎を連想したのではないか。
「旧山陽道行程記」(寛保二年)に巌流島の名の由来が記録されていて、長門の眼竜という棒の名人と豊前の弁という太刀の名人が決闘したからとある。ここでは棒術の名人である。 「二天記」で描写されている小次郎の長刀は棒がモデルだったのかもしれない。物干し竿である。
岩流は、巌流、岸流、岸柳、眼竜などの記述があり、流派なのか名前なのかも不明である。
− 参考 −
・佐々木小次郎よ、永遠に


