







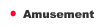

巌流島決闘の仮説
巌流島決闘の仮説
「丹治峰均筆記」の記述が正しく、慶長七年に決闘があったと考える。
岩流と武蔵が舟島で戦ったのは、慶長七年の十月である。慶長十七年は誤りである。
武蔵が十九歳のときのことで、吉岡一門と決闘する前のことであり、本格的に武者修行に出るまえのことであった。
試合経過は「丹治峰均筆記」に詳しい。その後は、「沼田家記」の通りである。
「二天記」に記述されている試合経過は、故意か思い込みかは不明だが、結果として誤った記述である。
巌流島の決闘は、武蔵が十九歳のときの仕合である。二十九歳のときではない。
もし、「二天記」が正しいとするなら、記述されている年月の問題を改めるか、あるいは試合の直後に無二が豊後にいたことを証明し、
「沼田家記」その他の文献にある刻限遅れや見物人などの記述が誤っていることを証明しなければならないが、
現在発見されている資料だけで証明することは出来ない。
しかし、「二天記」の資料としての価値は否定しない。
岩流との仕合模様が誤った記述と考えるだけで、他の箇所まで誤っているとは言い切れない。
佐々木小次郎に関しては、例えば、富田勢源の弟子筋であったことを否定するものは、今のところ推測以外ない。
「小倉碑文」に、その後、岩流島と言うようになった、とある。
武蔵の顕彰碑にしては無意味なこの一文を挿入するくらい、その死を惜しまれたのである。
試合の模様が細部まで記憶される立会いであったのだ。
武蔵は遅刻の常習者ではない。また、策を弄するような卑怯なことはしていない。
尚、武蔵は天正十二年生まれである。
− 参考 −
・巌流島決闘後に試合を申し込んだ相手
・武蔵が五輪書序文に岩流の仕合を記述しなかったわけ


