







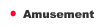

巌流島決闘の仮説
「丹治峰均筆記」の信憑性(4)
「二天記」が正伝で「丹治峰均筆記」が誤伝である理由はない。資料の価値は同等である。
しかし、少なくとも巌流島の決闘の記述は「丹治峰均筆記」のほうが状況証拠としての他の文献に符合するのだ。
さて、「二天記」では長岡佐渡が関わっていることになっており、松井家に伝わる巌流島の決闘時の木刀のレプリカもあることから、松井家は武蔵の試合に何らかの関係があったかもしれない。
実際に、三尺余りの長刀を使う武芸者に対して四尺の木刀で戦った試合があり、その相手が佐々木某であったかもしれない。
巌流島の決闘が二回あったとまでは言わないが、このような試合が、後世、混在して伝わった可能性は否定できない。
武蔵が三十歳を超えて試合することをやめたことは「五輪書」序文から分かるが、十八年間の六十回以上の全ての試合経過が正確に弟子達に伝わってはいないだろう。
いずれにせよ、武蔵が最大のライバル小次郎と試合をしたのを最後に試合をすることをやめたという通説は、あやしい。


