|
◇ 雑学手帳 その33 ◇
 
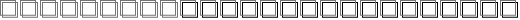
 ① 日本で最初に始まった縁日は ① 日本で最初に始まった縁日は
鎌倉時代・観音様の【18日】であった。
 【○】 【○】
 ② 《家紋》は元々、墓地を間違えないようにと ② 《家紋》は元々、墓地を間違えないようにと
【墓石】に彫られたことに起源がある。
 【×】 【×】
《紋》の始まりは、平安時代中期の貴族社会。
自家用の礼服に入れたのを始め、
乗り間違えないようにと《自家用の牛車》にも、
その柄を大きくして入れたそうです。
 ③ 《物見遊山》の【遊山】とは、もちろん、 ③ 《物見遊山》の【遊山】とは、もちろん、
【山登りに出掛け、山を楽しむ】
・・・ことを意味している。
 【×】 【×】
《遊山》の【山】とは、【お寺】のことで、
本来は《他の山》、つまり【他の寺】へ修行に
出掛けることを意味したのだとか。
 ④ 《地道に暮らす》の《地道》。 ④ 《地道に暮らす》の《地道》。
当然、【地に足をつけ歩いていく】
・・・を、表した言葉である。
 【×】 【×】
この《地道》とは、【馬術】で使う言葉で、
速歩の《かけ》、駆け足の《のり》に対して、
【並足=最も基本的な乗り方】を表すことから、
《手堅く物事を着実に進めること》を
意味することになったそうです。
 ⑤ 相手を影から《糸を引く》。 ⑤ 相手を影から《糸を引く》。
【納豆の糸】のように、粘り気(ネバネバ)を持って
操ることから、生まれた言葉だ。
 【×】 【×】
《操り人形》を【操る糸】に由来するそうです。
 ⑥ 政治家などでもお馴染みの《演説》だが、 ⑥ 政治家などでもお馴染みの《演説》だが、
実はこの言葉、【お釈迦様の説法】
・・・を、意味していた。
 【○】 【○】
《よく説明をする》という意味があったようですね。
 ⑦ 《おかめ》と《ひょっとこ》。 ⑦ 《おかめ》と《ひょっとこ》。
もちろん、【夫婦】である。
 【×】 【×】
違うんですって。
ふ~ん、そうなのか・・・
 ⑧ とっても忙しい《かき入れ時》。 ⑧ とっても忙しい《かき入れ時》。
お金や運を、【かき集める】・・・ことから
生まれた言葉である。
 【×】 【×】
お金や運ではなく、《帳簿》、すなわち帳面に
【書き入れる】=お金の出入りが激しい時期を
《かき入れ時》と呼ぶようになったというのが正解です。
雑学手帳のページへ
トップページへ
|