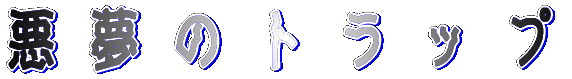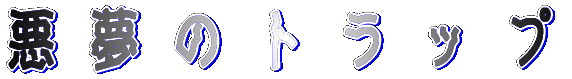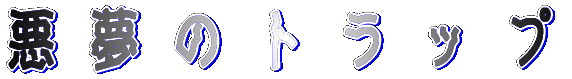
(3)
夜のパトロール中に謎のピエロと遭遇して捕らえられたバットマンは、薬品とベインの
マッサージによって足に力を入れることが全くできなくなってしまった。両手と尻だけで
何とか移動を開始するも、足が完全に機能を停止しているため、殆ど思うように行えてい
ない。そうこうしているうちに再び扉が開き、誰かが入ってきた。ドアに背を向けていた
バットマンはその音に振り返ろうとしたが、振り返る前に入ってきた者達の手で目隠しを
され、両腕を後手に縛られてしまった。
「けっけっけ、あのバットマンがこうも簡単に捕まえられるとはな!」
気味の悪い笑い声が室内を響き、傘を床につく音が聞える。声の主の正体はすぐにバッ
トマンの脳裏に浮かび上がった。
「ペンギンか……、何をする気だ!!」
「そう怒らんでもよいだろう、ちょっとした散歩だよ。けっけっけ……」
ペンギンは嫌らしい声で笑うと、部下に命じてバットマンを持ち上げ、何処かへと座ら
せた。椅子のような何かに座らせられると、両手を縛ったロープを外されたが、すぐにそ
れぞれの手を椅子の手かけに縛られてしまう。ロープを腕から指先まで手かけに巻き付け
ていくのがスーツ越し、グローブ越しに分かる。両足は動かないことが分かっているのか、
全く縛られなかった。バットマンはその間も両足に力を込めていくが、立ち上がることさ
えもできない。ただ、足の感覚が無くなっていないため、かかとが触れている感覚で足が
ついている場所が床ではないことが何となく分かる。そして車輪の音が聞え、自分の座る
椅子がゆっくりと動き出したため、自分が座っているのが車椅子であることが分かった。
「バットマン、今から散歩の始まりだ。逃げることができないとはいえ、お前は野生の蝙
蝠だから、ちゃんと首輪をつけてやるぞ」
「何だと……っ!!」
ペンギンの言葉と共に首の周囲に何かが嵌められ、カチリと音が聞えてくる。ここで目
隠しが外され、バットマンは自分の姿を鏡で見せられた。バットマンは車椅子に両手を縛
り付けられた状態で座り、番犬用の大きな首輪がつけられている。首輪には鎖がついてお
り、その鎖の先はペンギンが握り、車椅子はペンギンの部下が動かしていた。この状況か
ら逃げ出そうと身体を動かすも、後ろにいるペンギンの部下が肩を抑えるだけで身動きが
取れなくなってしまう。足は全く動かず、両腕は指の先まで念入りに縛り付けられたため
にこちらも動かせない。
「逃げることを考えるのは無理だと考えるがいい。バットマンは翼のないこうもりのよう
なもの、足が動かせない今、もしこの車椅子を奪ったとしてもそれは不可能な行為なのだ
からな。けーけっけっけっけ……」
ペンギンは高笑いをしながら鎖をおもむろに引っ張り始めた。バットマンはそれを引っ
張り返そうとするが、足に力を入れられないために踏ん張ることができず、逆に身体ごと
鎖で引っ張られてしまう。縛られている腕だけが動かずにいるため、腕に痛みが走ってい
た。腕の捕縛が唯一、バットマンを車椅子から落下させないための装置になっている。ペ
ンギンと部下は一定のペースで歩いており、バットマンだけが腕に痛みを受けながら、ペ
ンギンに遊ばれていた。
「くっ……、や、やめろっ!! やめるんだ!!」
バットマンは必死に叫ぶが、ペンギンは全く聞く耳を持たない。彼らはそのまま建物の
外に出た。バットマンは周囲を見渡すが、見たことのない庭園が広がっている。周囲は森
が生い茂っているようで、都会の明かりは全く見えない。自分が今何処にいるかさえも知
ることができないまま、ペンギン一行は別の建物へと入っていった。扉を入ってすぐの部
屋はテーブルが置かれているだけで、赤いじゅうたんが敷かれ、普通に明るい電気が灯さ
れている。バットマンは車椅子ごとテーブルの前へと連れて行かれ、テーブルの前で車椅
子を固定されてしまった。そのうえ、両足にはそれぞれ鉄球までつけられている。ただ不
可解なのは両腕が自由にされたことだった。
「疑問を感じていることだろうな、バットマンよ」
「……今から何をするつもりだ」
「まぁ、ここにいれば分かるが教えてやる。お前には今から出される料理を食べてもらう。
残さず食べれば両足が動けるようにしてやるぞ」
ペンギンはニヤニヤした笑みを浮かべている。その異様に気持ちの悪い笑みを睨み付け
ながら、バットマンは内心、嫌な予感を感じていた。残さず食べればということは、自分
が出てきた物を食べることができない仕掛けがしてある可能性があるということだ。それ
に食べ残しを行えば何らかの行為を行ってくることだろう。ここは慎重に彼らの出方を見
なければいけないと、バットマンは表情を硬くする。そこへ一人のウェイターが身なりの
いい燕尾服姿でやってくる。手には湯気が出ているジョッキと氷が詰まったバケツが載っ
た盆があるが、彼の表情は完全に怯えと恐怖で入り混じっている。
「ごっ、ご主人様っ、お飲み物でござっますっ」
ウェイターは言葉を詰まらせながらボトルとバケツをバットマンの前に置いていく。汗
を滴らせ、顔面蒼白で、手を震わせながらの動作にバットマンは嫌な予感を感じていた。
その横ではペンギンが楽しそうに立っている。彼が足早に部屋を出て行くと、ペンギンは
楽しそうな表情を崩すことなく話しかけてきた。
「バットマン、今のウェイターが気になっただろう。はっきり言ってしまえば、お前に食
事を与えるために某ホテルからウェイターやシェフを何人か連れてきたのさ。少々強引な
手を使ったが、怯えてはいるが全員最高級クラスの手腕の持ち主ばかりだ。そのような者
達がお前のためにわざわざ食事を出してくれるのだ。ありがたく召し上がるんだぞ」
ペンギンはそう言い残すと、そのまま部屋を後にした。ペンギンの部下も一緒に出て行
ってしまい、部屋にはバットマンが残された。足は動かないが、腕は使えるので車椅子は
動かせる。ベルトからバットラングを取り出すことも可能なため、逃げようと思えば逃げ
ることもできる。だが、自分のために誘拐されてきたウェイター達がいると知れば、自分
が逃げたことで彼らが被害を受ける可能性も高い。今は食事を食べつくす以外に方法はな
く、バットマンは知らぬ間に食べること以外の選択肢を消されてしまっていた。
「これは水の代わりに出してきたと考えるべきだろう。しかし、わざとお湯を出し、しか
も氷を出してきたということは、この氷に何か仕掛けがある可能性が高い。冷めるのを待
つとするか……」
バットマンはバケツの中の氷を見て、中心に白い塊が入った氷であることに気づいてい
たその白い塊の正体が分からないが、お湯に氷を入れることでお湯にとんでもないものを
混ぜさせようとしているとペンギンの様子から想像し、喉の渇きを感じたが、彼は敢えて
飲み物にまだ口をつけないようにしていた。しばらくすると、今度は数人のウェイターが
何かを運んできた。大きな皿を4人がかりで運んでいる。さらには大きな銀の蓋が置かれ
てあり、全く中が何の料理か見ることが出来ない。ウェイター達も顔面蒼白だったり顔を
引きつらせたりで、誰もバットマンと目を合わす事さえ行わない。ただ一人、マネージャ
ーと思われる男が彼らとすれ違いに入ってきて、バットマンを見た。
「料理の紹介をさせていただきます。これを残した場合、あなたがペナルティを受けるだ
けでなく、私どもにも制裁が行われることを知っていただきたい。あなたが捕まらなけれ
ばこのような事にならなかったことにも。あなたのせいでこの料理が生まれ、うちのシェ
フはシェフであることをやめようとしています。ウェイター達も元の生活に戻れたとして
も、この業界を生きていけないでしょう。では、失礼します」
マネージャーと思われる男は嫌味ったらしくバットマンを睨み付けて言う。彼やウェイ
ターやシェフはペンギンに捕まり、よほどヒドイ目に遭っているようだ。その怒りの矛先
がバットマンに向いているに違いない。その証拠にバットマンの動かせない足を見て鼻で
笑ったほどだ。足を使用不能にされたことを聞いているのか、その時点でバットマンに対
する信用も彼の中では消えているに違いない。バットマンは彼の言葉を聞いてショックを
隠しきれず、何も言えずに俯いていた。だが、マネージャーが蓋を開けた直後には目を見
開いて驚いたまま硬直していた。
「ホワイトソースで絡めた冷やしサラダパスタの男盛でございます。この男性はご主人様
が路上で捕まえてきた制服警官を陵辱し、射精寸前の限界で薬を与え、一時的に放出を止
められた状態にあります。急がなくてはこのサラダパスタは男汁風味になるでしょう。で
は、ゆっくりお召し上がりください」
マネージャーはそう言うと、バットマンを嘲笑うような表情で出て行った。彼やウェイ
ター、シェフたちは多分、バットマンが自分達のために食事をすると期待している半面、
バットマンのせいで捕まえられているわけだから、バットマンが屈辱を受けることに関し
ては嬉しく思っているのだろう。さて、お皿の上にはズボンと下着が足首に留まり、制服
の前をはだけられ、帽子をかぶったままの状態で猿轡をはめられ、手足を固定された制服
警官が乗っており、彼の股間周辺やおなかの上、太股の間などに所狭しと大量のサラダパ
スタが盛り付けられていた。かなりの量であり、全てが真っ白いホワイトソースで絡めら
れている。制服警官の肉棒周辺は完全にパスタ等で隠れ、影も形の見られなかった。そし
てその警官もまた表情を赤く染めたまま、バットマンを酷くにらみつけていた。ただ射精
寸前で止められているのか、身体を震わせているのも事実だった。早く食べなければ彼が
射精を迎えてしまうのも事実。バットマンはフォークを探そうとしたが、その時に気づい
た。食べるためのナイフやフォークが置かれていないのだ。ウェイターもマネージャーも
それらを一度も持ってこなかった。
「……そういうことか」
バットマンはこの理由を早々に察した。つまり、犬食いをしろということだ。テーブル
の高さはバットマンの腹の辺りにあり、テーブルに手をついて体を固定しながらかがめば
ちょうど犬食いができる。無論、手を使って食べることもできるが、犬食いをしなければ
いけない部分もある警官の身体の反対側は手で触って探すよりも覗き込んだ方が好都合だ
し、パスタの切れ端などはグローブで掴むのは困難なのだ。数分前まで全く考えもしなか
った事態にバットマンの顔も引きつり、屈辱が彼を覆っていく。でも、これをしなければ
いけない。たぶん自分が食べなければ、目の前の警官も解放されないだろう。どういう理
由でペンギンが自分に食事を与えるのか、はっきりと分かっていなかったが、これでよう
やく分かった。彼はバットマンを貶め、屈辱を与えたいのだ。夜の騎士と呼ばれ、それな
りに気高く紳士的なヒーローにそうではない行為をさせることで、バットマン自身の気持
ちを貶めたいということだろう。
「私が不甲斐ないために申し訳ない……」
バットマンは悔しさに震えながら、両手を使って警官の上に乗ったサラダパスタを掴み、
貪るように食べ始めた。グローブやスーツ、ベルトやタイツの上にホワイトソースが滴っ
ていき、黒い身体を白く汚していくが、バットマンは手を休むことなく動かしてサラダパ
スタを掴み、ドンドン口の中に押し込んでいく。咽かけることもあったが、お湯には手を
つけず、無理やり飲み込み続けていた。苦しさで吐きそうになっても、両手で口を押さえ、
必死に耐えていく。彼は自分自身がホワイトソースでぐちょぐちょに汚れていくことを気
にせず、食べ続けた。そして半分ほど食べきったとき、ドアが開き、ペンギンと部下が戻
ってきた。
「バットマン、そんな汚い食べ方をしているとは行儀が悪いぞ。それにお前は野生のコウ
モリだ。手づかみではなく、野生らしい食べ方が必要だ」
ペンギンはそう言うと、部下に指示を出し、バットマンの両手をテーブルに固定してし
まった。これで倒れこんだり姿勢を崩して車椅子から転落することはない。だがその代わ
り、今からはずっと犬食いをしなければ行けない。少し頭を下げて向こう側を覗き込んだ
りする程度の犬食いで何とかなると考え、少しでも自分に対する屈辱を免れようと考えて
いただけに、バットマンはさらに顔を引きつらせる。ペンギンは最初から犬食いをさせる
つもりで、バットマンがどう動くかを見るためにわざと自由にさせていたのだ。そのうえ、
ペンギンはさらにバットマンを追い込む行動に出た。残っているサラダパスタに唐辛子の
粉を大量にかけたのだ。ホワイトソースは真っ赤な粉でピンク色に染まっていく。自分の
身体に唐辛子をかけられた警官は痛みで身体を身震いさせ、涙を流していた。
「さあ、早く食べるといい。野生らしく、犬のようにな」
ここまでされて食べられないとはいえない。犬食いをすれば、制服警官の身体を舐める
ことにもなり、彼を追い詰めることにもなる。自分自身も唐辛子の辛さでお湯を欲するこ
とにもなるし、屈辱で顔を埋めることにもなる。でも、もう逃げられない所まで追い詰め
られた。息をゴクンと呑み、さあ食べるぞとバットマンが思った瞬間、ペンギンに頭をつ
かまれ、そのまま制服警官の太股の間に顔を押し込まれてしまった。
「ぐふっ……、ぅがっ……」
制服警官の皿の向きを変えたらしく、バットマンの頭が制服警官の股間に突き刺さるよ
うな態勢で顔を太股の間に押さえ込まれている。顔を必死に上げようとするが、ペンギン
が力任せに押さえつけており、全く頭が上がらない。太股の間に挟まるように詰まってい
たサラダパスタがべったりと顔に張り付き、無理やり口を動かして食べるしかない。だが、
股間の間の男臭にまみれていたせいか生臭さが鼻腔をつき、思わず吐きそうにもなる。そ
れを必死に堪えながら食べ進めるバットマンだが、不意に後頭部に暖かい液体が降りかか
ってきたことを感じた。唐突な出来事だったが、バットマンはすぐ察した。制服警官が射
精を遂げてしまったようだ。そして肉棒から飛び出た精液がバットマンの頭に降りかかっ
たのだろう。バットマンの頭による電気あんまが制服警官に限界を与えたと思われる。よ
うやく太股の間の料理を食べきって顔を上げると、そこには完全に果ててしまった制服警
官の姿があった。その顔は力をなくし、自分を睨みつける事もなく、射精に満足し、官能
に酔いしれる表情へと変貌している。
「バットマン、制服警官が精液ドレッシングをかけてくれたぞ。残りのサラダパスタは味
わって食べるんだぞ」
ペンギンは再びバットマンの顔を掴み、制服警官の身体へと押し付けてくる。その横で
は彼の部下は大きなフォークを使って残りの料理を股間周辺に集めて盛り付け、精液と絡
めていく。それをバットマンは何度も顔を押し付けられる形で無理やり食させられていっ
た。何度も吐きそうになり、それに耐え続け、唐辛子の粉に目や鼻腔をやられて涙を流し
続けた。だが、ペンギン達はバットマンに起きている被害を無視したまま、顔やスーツを
汚しながら食べ進めるしかない。精液ごとサラダパスタを、制服警官の身体にかぶりつく
ようにして食べ、舐めていく。どれだけ抵抗したいと思っても、食べないことはこれを作
る羽目になった、運ぶ羽目になったシェフやマネージャー、ウェイター、そして生贄にさ
れた制服警官を犠牲にすることになる。自分がこれを食べきることがすなわち、彼らを助
けることになる。だからバットマンは食べ続けるしかなく、喉をこみ上げてくる吐き気を
何度も飲み込みながら、必死に食べ進め、1時間以上をかけてようやく食べ終えることが
できた。その時にはバットマンの身体はホワイトソースと精液によって真っ白に汚れ、顔
も白い液体でグショグショに汚れ、威厳も何もなくなってしまっていた。
「バットマン、口直しにそれでも飲んだらどうだ?」
ペンギンは未だに湯気を立ち昇らせているお湯を指し示した。実はバットマンが食べ続
けている間にお湯を交換されてしまったのだ。そのため、冷めかけのお湯は捨てられてし
まっていた。バットマンが首を振ってそれを拒否すると、ペンギンは残念そうに進めるの
をやめている。ただ、表情は残念そうにしているものだったが、その目にはまだ怪しげな
笑みが潜んでいるように感じられた。そこへ扉が開き、複数のウェイターが入ってくる。
彼らは快感に酔いしれた警官と真っ白に汚れたバットマンを目にして笑いを抑えているよ
うな表情を浮かべている。だが、その中の一人がペンギンと目を合わせてしまったらしく、
恐怖で顔色を変えると、他のウェイターを促して早々に警官を運び出していった。その際、
今度は普通の大きさのステーキ皿を置いていった。これが次の料理らしい。マネージャー
は来なかったが、元々普通の料理なのだろう。ペンギンたちもバットマンの両手を解放し、
部屋から出て行ってしまった。だから仕方なく、バットマンは蓋を開けてみた。
「普通のステーキだな……」
先ほどのようにとんでもないものが入っているのではないかと不安を抱えながら開けて
みたが、皿に乗っていたのは普通のビーフステーキで、どこにも変な様子はない。精液や
糞を混ぜたんじゃないかと考えてしまいかけたが、それを行った様子も見られない。それ
にせっかくの料理であり、匂いも食欲をそそる物だった。これだけ見事な物を疑ってしま
ってはいけないし、先ほどの口直しにもなる。バットマンは腕で顔を拭い、バットラング
を取り出してステーキを切り分けると、そのうちの1つに突き刺し、ゆっくりと口に運ん
でいく。口に入れた瞬間、肉の見事ですばらしい味が口内に広がった。
「上手い!!」
思わず声を出してしまうほど、先ほどのサラダパスタと違いが大きく現われるほどのう
まみを感じられる。先ほどの料理が途中から生臭く、吐き気を催すものだっただけに、バ
ットマンの口が動くのは早くなり、みるみるうちにステーキが消えていく。熱かったが、
それでもその旨みを我慢することはできず、数分後には完食しており、バットマンは満足
そうな表情を浮かべている。さらにお湯にも手を伸ばし、それをゆっくりと飲み干してい
った。ステーキで熱さ慣れをしたからか、お湯であっても関係無しにバットマンはそれも
飲み干してしまったのだ。
「見事な食べっぷりだったね」
バットマンがホッと一息つくと、そこにペンギンが入ってくる。多分他の場所でずっと
バットマンの様子を監視していたのだろう。
「全部食べたぞ。早く捕まえた人々を解放するんだ。それに私の足を治す約束だったな?」
バットマンは入ってきたペンギンを睨み付けて言うと、ペンギンも忘れたという顔はせ
ず、うんうんと肯いて答えてきた。
「確かに食べきったな。先ほどの警官やレストランの連中は約束どおり、解放してやろう。
これを見るといい」
ペンギンが近くの壁に触れると、そこには厨房と思われる様子が浮かび上がる。そこに
は先ほどの制服警官やウェイター達の姿があったが、ペンギンの部下達によって誘導され
る姿が映っていた。映像は途中で切り替わり、彼らが外へと連れて行かれ、解放される様
子も映っている。途中途中の移動の映像が切り替わりによって分からなくなることもあっ
たが、それは多分、バットマン自身を簡単に逃がさないためにやっているのだろう。バッ
トマンは彼らがゴッサムシティの外れのゴミ捨て場付近に出られたところまで映像で確認
した。制服警官に関してはお皿ごとウェイター達が運んでいたが、彼らが無事に外に出さ
れたためにバットマンはつい安心してしまっていた。
「次は私のあ……」
バットマンはペンギンの方を向こうとしてそのまま意識が遠ざかるのを感じていた。ペ
ンギンが手にしているスプレーを吹きかけられ、そのまま意識を失ってしまったのだ。映
像に集中しすぎてペンギンが準備していることさえも気づけなかったらしい。バットマン
は再び車椅子で何処かへと運ばれていくかと思われたが、ここで新たな映像が浮かび上が
ってきた。解放されたと思われたウェイター達が全員、ペンギンの部下達によって薬品を
かがされ、縛られて陵辱を受けている映像が。そして、バットマンがゴミ捨て場と思われ
た場所も、単なる地下室の一室をそう見えるように作っただけの場所だったことも分かっ
た。全てはバットマンをわざと安心させて油断させるためだったのだ。その罠に見事に嵌
まったバットマンは、車椅子から下ろされ、突然床にあいた穴に投げ落とされていた。
「さて、私の出番は終わった。バットマンをここまで屈辱で煽ることが出来て光栄なこと
だ。そのうえ、新たに私の部下となる人間を大量に仕入れることもできた。満足なことだ」
ペンギンは一人、部屋で映像を見ながら笑い続けていた。