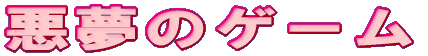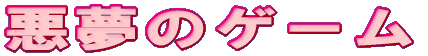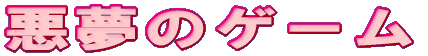
(2)
座ることも両膝に手をつけて休むことも首輪の鎖に阻まれたまま、レッドホークは立ち
続けている。疲労もさらに現われていたが、ふと気づけば目の前で奇妙な現象が起こり始
めていた。目の前や周囲の景色が変化し始めたからだ。自分と背後にある壁を残して周囲
の景色が工場から海辺へと変わっていく。地面は真っ白な砂浜に、目の前には何処までも
広がる青い海に、空は太陽が照りつける雲ひとつない青空に変わっていた。ふと背後を振
り返ると、壁もなくなっている。だが、背後には十字架が立っており、十字架の棒に首の
鎖が繋がれている。足の鎖も十字架を固定する台から伸びている状態に変化しており、鎖
は依然としてレッドホークを拘束し続けていた。
「周囲は砂浜と海のみ……、こんな場所に残してどうするつもりなのか」
何処を見渡しても海と砂浜しかなく、建物や森も崖も何もない。太陽から降り注ぐ熱と
周囲の温度は熱帯にいると感じさせるほど熱いが、これらは戦闘スーツを身につけている
ため、並大抵の温度での活動が可能になっていることから耐えられるが、それでもヘルメ
ットのバイザーを通して光が入るのを感じ、眩しさから無意識に暑さを感じてしまってい
るような気もする。少しずつ蓄積されていく疲労がそう思わせているのかもしれない。そ
う思おうとし、無意識に額に生まれた汗を拭うように腕を上げた。ヘルメット型マスクを
しているためにそんなことをしても無駄に等しいが、暑さを光で感じて、つい無意識に動
かしてしまったようだ。だがその直後、上げた腕は強い力で背後に向かって引っ張られて
いた。力を抜いていたため、対抗する暇もなく、腕は背後の十字架の枝に張り付いてしま
った。何が起きたのかと驚いて、もう片方の腕で引っ張ろうとするも、こちらの腕も持ち
上げた瞬間、反対の枝に引っ張られてしまった。十字架の両枝に腕が張り付いてしまうと、
どれだけ頑張っても腕が離れることはない。手首や手は動かせるし、肘もかすかに動かせ
る感覚があるため、腕だけが張り付いているようだ。
「あ、あの鉄輪……。……この十字架は磁石なのか」
レッドホークは腕に何もされなかった代わりにつけられた鉄輪が十字架に吸い寄せられ
たのだと察した。あの時、何も異常はないと判断していたが、最初から十字架に腕を貼り
付けにさせるために敢えて鉄輪をつけさせただけだったのかもしれない。油断したと後悔
しても遅く、これで全く動けなくなってしまった。首と足を固定する鎖も壁についていた
時よりも若干短くなったようだし、戦闘スーツや装備品がひきつけられているのか、身体
も思うように動かせなくなってきている。動かせるのは頭と手くらいだった。レッドホー
クは完全に固定されたことを察し、油断していた自分を情けなく感じている。今この状態
では敵以外の誰かに助けを求める以外に手段がない。もしくは敵に命乞いをするより手が
ないのかもしれない。
想像もしたくなかった姿をうっかり脳裏に浮かべてしまい、レッドホークは頭を強く振
った。何とかする手段を考えなければと必死に脳を動かすも、今この状態では不安の方が
生まれてしまう。強くジェットマンであること、この状態を脱することを考え、精神を集
中してかつてのように奇妙な空間から脱出しようとも思うが、一度不安が生まれてしまう
となかなか上手くいけない。もしかしたらこのままなのではとか、敵にどう命乞いをしよ
うかということをも考えてしまう。
レッドホークは苦悩のせいか、砂浜から出現し始めた存在には気づけていなかった。白
い砂浜の中から大きなイソギンチャクが姿を見せ、ゆっくりと十字架の台に近づいている。
イソギンチャクは十字架の背後に隠れ、触手を残して身体を砂浜の中に隠すと、触手をゆ
っくりと十字架に絡めながら伸ばし始めていた。レッドホークの身体は十字架にピッタリ
と貼り付けられているわけではなく、左右に広がる枝に腕が張り付いているようなだけだ。
そのため、レッドホークに気づかれないうちに、十字架の柱全体にイソギンチャクの触手
が絡み付いていた。だが触手が動き出す様子は見られず、それらが動きを見せる前に人影
が姿を現した。
「無様な姿だな、レッドホーク」
十字架が触手に覆われたことに全く気づかず、苦悩し続けるレッドホークに声がかかる。
声に反応して顔を上げると、そこには仲間の凱の姿がある。変身してブラックコンドルの
姿になっているようだが、レッドホークを助ける様子はなく、腕組みをしてレッドホーク
を眺めているようだ。
「凱……なのか……?」
「そんな状況に陥れば、仲間も疑いたくなるよな。だが、俺は本物だ」
凱は自信たっぷりにそう言いきるが、近づいてくる様子もなく、澄ました様子でいつも
のように腕組みをして立っているだけだった。いつもピンチになれば、なんだかんだ言い
ながらも凱は仲間を助けようとする。自分の性格に合わないとか言いながらも、すぐに助
けようと向かってくるはずなのに、凱はレッドホークを助けようとはしなかった。
「本物なら助けてくれてもいいんじゃないか?」
「……悪いが、俺はお前を助けることはできない。お前が思い出して、そしてお前が乗り
越えれば助かる」
「どういう意味……、凱っ!!」
レッドホークは凱の言葉の意味を理解できなかった。助けることができないといわれた
レッドホークは凱の言葉もそこそこにショックで目をそらしてしまい、裏切られたと感じ
たのか悲しく俯いた。そして再び顔を上げ、凱を見ようとしたのだが、レッドホークの感
情は悲痛から驚愕に変わっていた。目の前にいた凱の姿が石像に変わってしまったのだ。
「凱っ!! どうしっ、んぁあっっ!!」
思わず身体を必死に動かして凱の元に向かおうとしたレッドホークだったが、その瞬間、
太股に何かが群がったのを感じた。さらに何かが背後から身体に絡みつき始めてくる。目
線を下に向けたレッドホークは、身体中に触手のようなものが群がり、絡み付いているこ
とに気づいた。細長い無数の触手はレッドホークの脇腹から太股、腕や足、首等にドンド
ン絡みつき、ゆっくりと身体を撫で回すように蹂躙していく。おぞましく、何ともいえな
いくすぐったさで身体を蝕まれる感覚を覚え、全身に鳥肌が立つ。必死に身体を動かそう
とするが、身体をなぶられる感触が集中しようとする意識を邪魔し、レッドホークの抵抗
を許さない。
「なっ……、やめっ……、はぁんっ……、あぁぁ……」
身体中をゆっくりと撫でられ、弄られていくその感覚に鳥肌が立ち続けるが、されるが
ままにしかなれず、必死に耐える以外にないが、脇腹や脇の下、太股や背骨の真上に当る
部分等、触れられると股間へ臀部以外の敏感になりやすい場所を集中的に狙われ、同時に
身体中を弄られ続ける状況は少しずつレッドホークの忍耐力をも蝕んでいく。だが、レッ
ドホークから抵抗というものが消えにくいと感じたのか、触手はさらなる攻撃に移った。
「そ……、そこあぁぁぁ……っ!!」
数本の触手の先が太股を覆うタイツ型スーツと臀部を覆う赤いスーツの間へと食い込み、
ゆっくりと赤いスーツの中に入り込み始めたのだ。先ほどまでその部分を敢えて避けてい
たらしく、赤いスーツの中に入り込んだ触手は中で先端からさらに細く長い触手を出し、
スーツの中に隠れていた男の象徴に巻きついた。流石にスーツを貫通することはできなか
ったようだが、男の象徴から、根元から奥の穴へ続く道、根元に垂れ下がる袋までをスー
ツ越しに群がり、絡みつき、ゆっくりと蠢いていく。
「ぁぁっ……、うぅ……っ、あ……っ、あ……ぁぁ、……んぁぁっ」
赤いスーツの中で男の象徴である肉棒から袋、蟻の門渡りに至るまでが無数の触手によ
って撫で回され、触れられ、わざと感じるように時には刺激していき、レッドホークの意
識を抵抗ではなく、快感へと導かせていく。肉棒に巻きついた触手は肉棒を扱くかのよう
にゆっくりと蠢き、亀頭には数本の触手の先が触れるか触れないかの際どいギリギリの部
分を刺激し、思考さえも狂わせていた。レッドホークが少しでも耐えようとすれば、別の
刺激を行い、彼を弄び続けていく。
「こ……っ、こんなこ……っ、で……、……負け……っ……、たま……、……かあぁぁぁ
っっ!?」
それでも必死に耐え、必死に抵抗しようと、冷静さを取り戻そうとするレッドホークは、
手足に力を込めようとし、さらなる刺激に襲われた。身体に絡みついた触手が身体を締め
付けるようになり始め、太股を締め付けながらもその肉体をゆっくりと擦りあげて刺激を
与え、スーツ越しに筋肉や骨格の溝から形状に至るまでを嘗め回すように愛撫していく。
中では無数の触手が1本に戻り、肉棒を激しく扱き始めていた。それらはレッドホークが
再び意識を呑まれても続き、レッドホークを狂わせ続ける。だが、根元に別の触手が絡み
つき、きつく締め付けることで刺激の末の射精を封じており、どれだけ絶頂に向かいかけ
てもそれを封じられてしまう。そればかりか、レッドホークが絶頂になりかけると、全て
の愛撫をとめてしまうのだ。わざとじらしているらしく、彼の身体も徐々に刺激がなくな
るとそれを求めてしまいかけている。愛撫による刺激がなくなったときに抵抗すればいい
のだが、絶頂に行きかけているために身体はかなり敏感になっており、刺激の影響が強す
ぎて動けないのだ。
「も……う、駄……、っ……目……」
それが何度も続き、流石に10回を越したくらいだったろう。レッドホークの意識はゆ
っくりと闇の中に落ちていき、身体の力はスーッと抜けていってしまった。その間も触手
が彼の身体をなぶり続けていくのだが、それでも意識が戻る様子はなく、意識を失った身
体はその後も触手に愛撫されていった。