







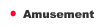

佐々木小次郎よ、永遠に
「巌流島の決闘」史料
しかし、決闘の描写の最後に「故に俗舟島を改めて岩流島と謂う」と書かれているが、
地元民にしてみれば、それは周知の事実だから、この一文は不要である。
では、何故、この一文が書かれたのか。
それは、地元民は、島の名の由来が負けた武芸者にちなんだことは知っているが
勝者が宮本武蔵であることを知らなかったからだ。
現代人は勝者が宮本武蔵であると知っているが、当時の地元民は知りえるはずが無い。
なぜなら、「丹治峰均筆記」では武蔵が十九歳のとき、「江海風帆草」では十八歳のときの決闘とされているが
地元民は、この若者が後に古今無双の兵法家に成長するとは知り得るはずがないからだ。
「小倉碑文」の記述は、勝者が宮本武蔵であることを知らしめるために必要だったのだ。
熊本の春山が書いた碑文に対し、小倉に住む伊織が巌流島エピソードを付け足したのではないかと思うのはこの点だ。
春山が下書きをしたときに沼田家の情報を知っていたとしても、あえて捻じ曲げず書かなければよい。
伊織は、春山から届いた碑文になかった伝承で、地元民の間で「岩流島」と呼ばれるようになった決闘の当事者で
しかも、勝者は、実は宮本武蔵であると伝えておきたかったのではないか。


