







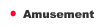

佐々木小次郎よ、永遠に
「巌流島の決闘」史料
おそらく「江海風帆草」も同様に地元の伝聞である可能性が高い。
しかし、当日の事件現場に野次馬の見物人はいたのだろうか。
野次が飛んでいるから見物人はいた。
沼田延元がいたのは確かと思うが、野次は全て沼田延元のものかもしれない。
「丹治峰均筆記」「江海風帆草」は、見物人の証言だけで構成されていない。
当日の服装や誰が先に島に着いていたかなどは野次馬の証言かもしれないが、
決闘に至る経緯や弁助(武蔵の童名)の年齢などは当事者でなければ分からないはずだ。
小次郎の太刀が青江刀であると、素人が遠目で見ただけで分かるはずが無い。
「丹治峰均筆記」は、単なる挿話集のようなもので信憑性は低く明らかな誤り(弁助の年齢)があると評されてきた。
その評は今でも変わらないのだが、なぜ信憑性が低いのかというと、情報源がはっきりしないからだ。
しかし、柴任三左衛門から聞いた話しとなっており、特に柴任は武蔵と接触があったかもしれないので
信憑性に関しては認識を改めるべきだが、しかしながら、やはり巌流島決闘は柴任三左衛門から聞いた話ではなく、
「二天記」同様に取材源は地元民である。つまり、柴任三左衛門は知らなかったのだ。
史料の成立は、「丹治峰均筆記」よりも「江海風帆草」のほうが早いが、それでも決闘から約100年後のことである。
100年と言えば、1910年 大逆事件、1912年 乃木希典殉死 くらいの時間的距離感である。
(1909年松本清張生誕、1911年岡本太郎生誕と考えると距離感がぐっと縮まるが。)
地元民が決闘描写を覚えていたとは思えない。
たとえ弁助が宮本武蔵という有名人にならなくても、あるいは、「小倉碑文」が無くても
舟島を岩流島と呼ぶようになった理由が語られるならば、伝承は残ったかも知れない。
しかし、何故、決闘描写は語られ、登場人物は記憶されなかった。
岩流島と呼ぶようになった当の本人である小次郎のことは記憶されなかったのだ。
それは、巌流島決闘の物語が創作されて記憶されたからではないだろうか。
人は理解できるのものを記憶する。というか、理解してから記憶する。
個々の伝聞の不十分な部分があったとしても、そこは推理して補い、まとまった内容にしてから理解し記憶する。
人物の素性は、この物語の理解に必要なかったのだろう。
地元民は武芸者の決闘に興味があったろうか。
おそらく、プロの兵法者に喧嘩を売った馬鹿な若者が無残に殺されるのを見たかったから野次馬ができたのだ。
向島を舟の形に似ているから舟島と呼び、さらに、武芸者の名にちなんで岩流島と呼んだ。
しかし、岩流の素性は記憶されなかった。
(つづく)


