







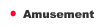

佐々木小次郎よ、永遠に
「巌流島の決闘」史料
小次郎は仕合に敗れたが息を吹き返したところ、武蔵の弟子達が打殺した、という記述で有名になった書き物だ。
この「沼田家記」というものは、武家によくあるもので、当主の武勇伝や美談などを子孫に残すために書かれたものだから
第三者に関する記事は嘘を書く必要がないから信憑性は高い。
「沼田家記」は二部構成になっていて、第一部が沼田延元の誕生から死去まで二十九ヶ条にわたった一代記で、
ほぼ年代順に編纂されているものの、年月日を特定しない中に巌流島決闘の記事がある。
しかし、当時の事件の記録集ではなくて、延元の記録だから、ここで著者(子孫)が言いたいのは、
稀代の剣の名人である宮本武蔵がまだ若いころ決闘した相手の弟子の報復に困り、延元を頼ってきたので、延元はこれを請負い
宮本武蔵を助け豊後の宮本無二に無事に届けたのでことなきを得た、という延元の「手柄」を書き残しておきたいのだ。
他のことは、その原因となった事柄として書かれているだけだ。
豊田正剛は「武公伝(二天記)」の元になった記録を集めたていたときに、この情報を掴んでいたはずだ。
しかし、「武公伝(二天記)」を企画したとき、これは武蔵の英雄談には書ける内容ではないと判断した。
「武公伝(二天記)」は巌流島決闘の描写を下関の商人である村屋勘八郎から聞いて書いた注釈にある。
おそらく「武公伝(二天記)」の豊田父子は、内容の信憑性を高める効果を狙って、この注釈を入れたのだろうが、逆に言えば
外部の者に頼ったのだから、熊本には巌流島の決闘に関する伝聞が無かったことになる。
熊本は宮本武蔵の終焉の地で二天一流が伝わった土地だから武蔵に関する伝承が多いだろうと推察できるが、
しかし、巌流島の決闘に関して言えば、熊本(細川藩)では、ほぼ誰も知らなかったのだ。
今では、巌流島決闘物語は非常に有名な出来事で、その内容が「二天記」から採用されていると知っているため、
ある程度の改竄や創作は認めたとしても、熊本に伝わった基本となる伝聞があって、それに肉付けしていったと思いがちだが、
あれは、白紙の状態からの創作だったのだ。
豊田父子は、「沼田家記」の記述が後世に打ち消されるほどに、「武公伝(二天記)」で宮本武蔵の英雄伝として飾り立てた。
だから、あれほどに長編でドラマ仕立てになっているのだ。
今日では、熊本の顕彰会本や吉川英治の「宮本武蔵」などで、先に「二天記」の描写が有名になって、
「沼田家記」の記録は、その裏話しとして紹介されるから、武蔵は卑怯などと言われるのだ。当時と逆転したのだ。
余談ながら、「武公伝」でもうひとつ有名な長編ドラマがあって、それは、どじょう伊織といわれるもので、小倉の宮本伊織は
武蔵が常陸を旅しているときに拾った子供で後に小笠原家で家老になったという物語だが、これは「武公伝」の記述の前後関係からして
巌流島決闘を伝えた下関の商人の村屋勘八郎が語ったものであると思う。


