







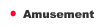

佐々木小次郎よ、永遠に
「巌流島の決闘」史料
「二天記」によると伊織は銘を熊本時代に武蔵と昵懇だった春山に依頼したとある。
春山は、おそらく下請けの誰かに依頼したのだろうが、碑文の内容自体は、熊本の伝聞をまとめたものということになる。
このことの真偽はここで論じないが、それにしても「小倉碑文」の巌流島決闘の描写は、どうもしっくりこない。
現代人の先入観や刷り込みも多少はあるだろうが、この記述だけ後から付け加えたような感がある。
あるいは、伝聞自体を捻じ曲げたというか、全く臨場感が無いのだ。
ところで、巌流島決闘に関して、下関から遠距離にある熊本なら伝聞の伝播に歪みや劣化が生じやすいと思いがちだが、
もちろん、下関の伝聞が、口伝えに遠路はるばる熊本まで伝播されたのではない。
伝播なら同心円状に広がるであろうし、街道沿いに伝わってもよさそうだが、岡山や広島では語り継がれてなく、
その土地で不要であれば消えてしまうはずだ。
巌流島の決闘の伝承は、熊本という土地よりも細川藩内の伝聞として論じられるべきだ。
決闘があったと推察される時期が、細川藩が小倉を治めていた時期と重なるので、最も近い位置にいたからだ。
熊本(細川藩)でまとめたものとして有名な「二天記」がある。
そこで記述されたものと「小倉碑文」の記述は量も内容も全く異なるのは何故だろうか。
これは、「小倉碑文」の巌流島決闘の記述は、春山が書いた熊本の伝聞に、後で伊織が加筆したものと考えればどうか。


