







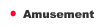

佐々木小次郎よ、永遠に
「佐々木」姓の信憑性
というか、出てくれば史料の信憑性が落ちるという始末。
今日、もっともよく知られた巌流島決闘の描写が「二天記」によるもので、そこの注釈に書かれた名前が今日広まっているのだ。
宮本武蔵の周辺史料で出てくるのは、ここだけ。
なぜ、「佐々木」姓が信憑性が低いかと言えば、江戸時代中期以降に成立する人形浄瑠璃や歌舞伎や文学のみで使用される名だからで、
同じように江戸時代中期以降に成立した「二天記」は、娯楽物の伝聞を借用したのではないか、と。
娯楽物の特徴は、小次郎を近江の佐々木六角氏と結びつけ、観音寺城主の六角義賢(あるいは義治)の御落胤とする傾向が
あるということで、また、小次郎の幼名を久三郎、諱を義高としているのが多い。
宮本武蔵の周辺史料では、佐々木小次郎のほかに「丹治峰均筆記」の「津田小次郎」、「江海風帆草」の「上田宗入」がよく知れる。
しかし、「江海風帆草」の場合、「(此名不分明)」と告白されており、実際のところは名前は知らないようだ。
但し、明らかに茶人を意識しているはずだ。
当日、着用した服が八徳(直綴みたいなもの)としており、安芸で上田宗箇流が栄えたからだ。
「津田」、「上田宗○」とくれば、その中間的な名前で「津田宗及」を連想する。
津田宗及は、千利休・今井宗久とともに茶湯の天下三宗匠と称せられた。
この今井宗久は、堺の茶人でるが、祖は近江佐々木氏の末裔で近江国高島郡今井市城を領したので今井とした。
今井宗久の初名は久秀。ここで「佐々木」姓が登場する。
「佐々木」姓は、今井宗久からヒントを得たのではなかろうか。
六角氏の御落胤で「佐々木」姓を名乗ることはないと思うが、今井宗久の隠し子?
小次郎の幼名を久三郎を設定しているから、まるで久秀の三男のようだ。小次郎は次男の名と思うのだが。
決闘当日は、直綴みたいな服装をしているし、剃髪していたかもしれない。茶人でなくどちらかといえば僧。
宮本武蔵の周辺史料の「巌流島の決闘」は大阪あるいは京は意外と重要な場所で、武蔵が決闘を決意する場所として登場する。
人形浄瑠璃などの場合、興行が大阪で行われたこともあろうが、淀川の砂洲が決闘の場に設定されることが多い。
「丹治峰均筆記」に出てくる小次郎の仕込み剣は、堺の鍛冶職人の作ったものかもしれない。
大阪は摂津なので、「丹治峰均筆記」の「津田小次郎」も、「摂津の小次郎」ではないだろうかと思えてくるのだ。
「津国ノ小次郎」が「津田小次郎」に誤伝したのではないか。
「津国ノ小次郎」や「(此名不分明)」を前提に考えてみると、
宮本武蔵の周辺史料に「佐々木」姓が出てこない、というより「姓が出てこない」、と言ったほうが適切。
舟島を「岩流島」と呼ぶようになったのは、負けた岩流(小次郎)にちなんだものとされるが、
例えば、「袖錦巌流島」では、岩流がこと切れるときに「なにとぞ、その所を岩流島と名づけたまわれ」と言い残したので
「岩流島」というようになったと設定している。
意外と、このように小次郎の遺言で島の名が残ったのかもしれない。
はたして小次郎は姓を名乗ったのだろうか。
そもそも名乗る姓があったのだろうか。


