







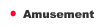

巌流島決闘の仮説
「丹治峰均筆記」の信憑性(3)
このことから、小次郎のキリシタン説、暗殺説などが推測されている。 しかし、暗殺で記録されるべきものでなかったなら、家臣の沼田家が延元の当時の行動を記録に残したことの解釈がつかない。 また、細川藩に関わりのある「二天記」作者が巌流島の決闘を記述するのに外部の人間に取材するほど熱を注いだことも理解できない。
ならば、細川藩は全く関わっていなかったと考えたらどうか。細川忠興が小倉に入国するのは、慶長五年十二月である。
慶長五年十月に試合があったなら、細川藩に資料など残っていようはずがないのだ。
あるいは、細川藩に記録がないことは、単に細川藩の公式仕合ではなかったという理由だったかもしれない。
他藩の領地で行われた仕合なので公式仕合ではない。他藩のことゆえ関心がなかっただけかもしれない。
そもそも、岩流が細川藩の兵法指南役であることを前提にした場合の細川藩記録云々である。
記録がないなら、岩流は細川藩の兵法指南ではなかったのだ。岩流を細川藩兵法指南とした「二天記」の誤りである。
「沼田家記」では沼田延元は門司城代のころとある。「丹治峰均筆記」でも名前は失念としているが門司城代の者が登場する。
しかし、慶長五年十月は、まだ門司城代としての沼田延元は居なかった。
沼田延元が武蔵を親の元へ送り届けたのは、保護者の親元に送り届けた行為ではないだろうか。
二十九歳の武蔵ではなく、若輩者の弁之助を親の無二の元へ送り届けたのではないか。
また、「沼田家記」の延元が「門司城代になられしとき」という記述は、門司城代になりたてのころとも読み取れる。


