







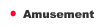

巌流島決闘の仮説
「丹治峰均筆記」の信憑性(1)
到着順は、小次郎が刻限に遅れたのではなく、武蔵が刻限よりも早く島に到着していただけだ。刻限通りに開始されたのだろう。
試合を申し込んだのは、岩流という説と武蔵という説があるが、おもしろいことに、両方とも矛盾せず、うまく収まる。
また、他の資料に記述されている見物人がいたことも符合する。「沼田家記」の弟子同士の師の兵法自慢も、 「本朝武芸小伝」の船頭が小次郎に向かって武蔵には弟子が沢山いるから早く逃げなさい、と言った挿話も無理はない。
「二天記」は、このようにうまく符合しない。
では、年齢の問題はどうか。
「丹治峰均筆記」では、巌流島の決闘のとき武蔵十九歳とある。「二天記」には武蔵二十九歳とある。
これは、次の理由により、「二天記」の誤りと考える。
「二天記」では試合のとき、小次郎十八歳としている。
これは、「武公伝」で越前一乗谷の生まれの富田勢源の弟子の小次郎が師に勝って岩流を開いたとき十八歳だった、 とあるのを小次郎は越前一乗谷の生まれで富田勢源の弟子となり船島で武蔵と戦ったときは十八歳だった、と変更したものだ。
なぜ、「二天記」作者は、このように変更したのか。
岩流との試合が、十代のころの決闘と記録されていたと考えられ、それを、武蔵ではなく小次郎のほうとし、そして、武蔵二十九歳のときと判断した。 二十九歳の時の決闘とは「武公伝」にも記述されており、それに倣ったものだが、「武公伝」は十九歳を二十九歳と誤った。
なぜなら、「小倉手向山武蔵顕彰碑(小倉碑文)」の記述が、二十一歳のときの吉岡一門決闘の記述の後に、 巌流島の決闘の記述があるので、作者は巌流島の決闘を二十一歳以降のことと思い込んだのだ。


