







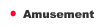

巌流島決闘の仮説
「丹治峰均筆記」と「二天記」(2)
ある日、無二は岩流から試合を申し込まれたが岩流が仕込み剣を使うので断った。すると、不評がたったので、代わりに弁之助(武蔵の童名)は自分が戦おうと考えた。弁之助は岩流から試合を申し込ませようと、門弟の前で岩流を挑発した。岩流は挑発に対し怒って、弁之助に試合を申しこんだ。試合場所では弁之助が先に着いていた。周りには見物人が集まっていた。しばらくすると、岩流が家人を一人伴いやってきた。岩流は船から飛び降りるとき、飛び損ねてこけるのを見て見物人は笑った。岩流は、そばに門司の城代が槍を持った家人を連れていたのを見て不信に思い、一体誰かと問い掛けると、我々は弁之助と親しき者で見物にきた、その方には関係ない、血迷ったか、うろたえ者め、と怒鳴り返された。岩流は鞘を海中に捨て武蔵と戦って、弁之助は膝上の袴を三寸ほど切られた。弁之助は岩流の頭を砕いたので船に戻って去っていった。その後、岩流は両目をくわっと開き、水を求めたが倒れた、というものである。
「丹治峰均筆記」「二天記」の描写の共通点は、武蔵と岩流が舟島で戦い武蔵が勝った。その決闘では、両者の到着時刻は待っているほうが欠伸をするほど間があった。岩流は直前に何か言われて、うろたえた。岩流は真剣で、武蔵は櫂で作った木刀で戦った。岩流の剣は特殊なものであった。岩流は鞘を捨てて戦った。岩流が倒れながら刀をはらい、武蔵は膝上の袴を三寸ほど切られた。岩流は頭を打たれ倒れた。共通項は決闘場面だけに限られ、決闘に至る経緯は全く異なるのだ。
「二天記」では、巌流島の決闘の描写は、主筋の長岡興長と正徳二年(巌流島の決闘から百年後!)に武蔵が 決闘前日に宿泊した廻船問屋の主人の小林太郎左衛門の親族である村屋勘八郎が、当時の棹人から聞いた話しを元にして書いたとあって、 確かにこの者たちの知っていることしか書いておらず、武蔵の視点は入っていない。
一方、「丹治峰均筆記」は丹治峰均自身がその場にいて見てきたように書いてあるが、基本的に武蔵の視点で語られている。
武蔵の知らないことは、岩流が最後に水を求めて果てたことくらいだ。ここの部分は、見物人の伝承によるものか、あるいは創作と考えるしかない。(これ下の関辺にて語り伝ふる処なり、と土地の人の岩流評を記述しているので伝承だろう。)
「二天記」の語りの中に武蔵の視点がなく、現場にいた周辺の人に取材したということは、巌流島の決闘の経緯は、武蔵の語ったものとして記録された覚書きを所持していなかったことを意味し、従って岩流と試合をする原因は記述できなかった。
「二天記」は、吉岡清十郎の試合も試合に至る原因、経緯は記述していない。
しかし、「丹治峰均筆記」は吉岡清十郎の仕合も岩流の試合とも原因、経緯を記述している。
つまり、遅参の話しは、本来、吉岡清十郎との試合の話しとして語られてあったものを、「二天記」作者は、巌流島の決闘に用いたとしか考えられないのだ。


