







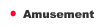

武蔵随想
どじょう伊織
このどじょう少年は、13、4の少年とあり、伊織の生年は1612年だから、1625、6年のころのことだと分かる。
このとき武蔵は何をしていたかというと大阪で江戸から戻ってきた造酒之助と酒を飲んでいたらしい。
造酒之助の殉死は1626年とはっきりしているからだ。
この話しは、「二天記」の中では、名場面の一つといってもよいくらいの量が割かれている。
では、なぜ、このどじょう少年の話しが語られたのか。
「武公伝」を整理して「二天記」になったとき、「武公伝」から捨てた記事がある。
このどじょう少年のすぐ後にある伊織に関する記述も捨てられている。
伊織は由比正雪が謀反を起こす前年に会っていて、謀反を起こすであろうことを事前に察知していたという話しである。
伊織の不思議人としての超人的な挿話は「鵜の真似」などにもある。
手品師は伊織の前では仕事にならなかったとか、通行人を見ただけで火事が起きることを察知したなどである。
つまり、このどじょう(=なまず)少年の話しは伊織には予知能力があったという、単なる枕話しではないか。
造酒之助は馬に縁があるのだろう。武蔵が語ったものだ。
なぜ、武蔵が語ったものかというと、「丹治峯均筆記」の造酒之助と出会う場面と似ているからだ。
両方とも、武蔵が旅の途中の出来事である。何かしら動物が登場する。
武蔵が少年の行動を不信に思い、理由を訊ねると、その返答が立派だった、いう具合である。
同じ書物に記述されているなら、その作者の創作かもしれないが異なる書物である。
構成が同じなのだから同一人物が語ったものだろう。
伊織は小笠原藩の家老である。
造酒之助は本多家の家臣である。
この二人に対して、このような話しができるのは、当時は武蔵しかいなかったはずだからだ。
伊織の話しが「二天記」ルートに流れ、造酒之助の話しが「丹治峯均筆記」ルートに流れたのだ。


