







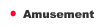

武蔵随想
吉岡一門との決闘
無二斎と先代の吉岡憲法が仕合して無二斎が勝ったからリベンジだったのだ、が通説である。
この無二斎が吉岡憲法と仕合をしたという伝承は武蔵周辺からしか出ていない。
とすると、武蔵が語ったものが残ったのだろう。
吉岡清十郎との試合は相打ちだったという伝承がある。
これは武蔵の存命中からの風聞であったらしく、志水伯耆というおっさんがいて、
あの仕合は相打ちだったのでは、とよせばいいのに余計なことを上座から言ってしまって、
正月というのに皆の前で武蔵から、むちゃくちゃ怒られたという挿話がそれである。
この話しは、「二天記」では巌流島の決闘のときとなっているが「武公伝」では吉岡清十郎の仕合になっている。
「二天記」によると、武蔵は、清十郎と伝七郎の試合のときは遅れていき、一乗寺下り松のときは早く行った。
武蔵は、「五輪書」の中で「山海のこころ」という言葉で戦術を教えている。
これは、同じ手段は二度までは許されるが三度はいけない、というものだ。
武蔵本では、この吉岡一門の決闘がそれにあたると述べられていることがある。
三度目の一乗寺下り松のとき、逆に吉岡が真似て遅れてきたら逆効果になってしまうじゃないか。
一乗寺下り松の決闘は、清十郎と伝七郎の試合と明らかに異なる。
場所が蓮台野ではなく、一乗寺下り松と変更され、しかも多勢になった。
蓮台野は西ノ桐院からは比較的近いが、一乗寺下り松は遠い。
あえて、この土地を吉岡が選んだとするなら、通説通り戦闘を意識しているのだ。
吉岡にしてみれば武蔵を門弟含めて一網打尽にすることを狙ったものと考えたほうが自然だ。
「二天記」では、武蔵が語ったとして、多勢に対し一人で戦ったことになっている。
早めに着ていたのが吉岡にとって意外であったのではなく、一人で来ていたほうが意外であったのではないだろうか。
早めに行ったのなら、意外性を狙ったのではなく、吉岡の陣形が整う前に勝負を決めようとしたのだろう。
ちなみに「丹治峯均筆記」では、多勢対多勢である。


