







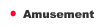

武蔵随想
敵討ち!宮本武蔵
しかし、全く根拠のないところから創作はできないだろうから、多少は事実を反映していると考えたほうがよい。
事実と虚構を見極めたら少しは武蔵の実像も分かるかもしれない。
例えば、講談本では武蔵は無二斎の仇として巌流を討つことを決心する。
巌流は仕込み剣を使い武蔵を傷つける。武蔵は加藤清正の家臣といった設定である。
「丹治峰均筆記」では無二斎の無念を晴らすため巌流に仕合を申し込む。
巌流は仕込み剣を使い、武蔵は肩を斬られる。この辺りの筋書はよく似ている。
また、武蔵は晩年は熊本で過ごしているから加藤清正とは印象の上ではつながる。
渡辺幸庵の証言や「丹治峰均筆記」などから、武蔵は風呂に入らなかったらしいが、
講談本では武蔵は風呂でひどい目にあう。
講談本では武蔵は、突然、意外な場所に現れる。
例えば生駒の信貴山である。これは無二斎が兵法を指導していた場所である。
突然、津山で子をつくり、その子をそのままおいて旅に出る。
この津山においてきた子は八五郎という名だ。伊織の童名と同じである。
武蔵と巌流が決闘する場所は舟島ではなく灘島であり、この島の命名など容易に明石を連想する。
しかし、田原というキーワードはでてこない。
講談本では政名という名だ。母と言われる於政からの連想だろうか。
全く偶然かもしれないし、あるいは、講談本は意外と事実に基づいた創作物かもしれない。
有馬喜兵衛や吉岡が登場するから、意外と下調べはやっているようだ。
しかし、どうやって調査したのだろう。
調査した結果で物語りを書いたとしたら、江戸時代は武蔵関連資料は意外とオープンだったかもしれない。
口承の類が、まだ残っていたのだろうか。
吉川英治本は、まだ講談本の影響が随分と残っている。
例えば、少年のころ「たけぞう」と名乗っていたことや、千年杉や、お杉婆の風呂の件や、
巌流との決闘をハイライトにもってきていることや、秘剣燕返しなどである。
お馴染みの巌流島決闘で武蔵が飛ぶのは塚原卜伝直伝である。
(注)本物の江戸期の講談本を読んだわけではありませんので、内容は多少、異なっているかもしれません。


