







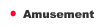

武蔵随想
無二斎が弁之助に向かって小刀を投げた話し(改)
こんな話しだ。
弁之助は幼年から父の無二斎の兵法を見ていたが、しだいに批判がましくなった。
ある日、無二斎が楊枝を削っていると、弁之助が一間隔たところに座った。
すると、突然、無二斎は、楊枝を削っていた小刀を手裏剣にして弁之助に向かって投げつけた。
しかし、弁之助は面をかわしたので、小刀は背後の柱に突き刺さった。
無二斎は、甚だ怒って、「日ごろからわが兵法を誹謗するので、手裏剣で耳の端を切って思い知らせてやろうと
手裏剣を投げたが、面をそむけて難を逃れる。お前は、近頃、様子がおかしい。」
と勘当し、家を追い出した。弁之助が九歳の時のことである。
この逸話はよく紹介されるが、武藏考証でよく使われる「伝わった年の誤差」は聞いたことがない。
例えば、平田武仁の没年は天正八年ではなく天正十八年の誤りだ、とか、
小次郎は決闘時は十八歳ではなく七十八歳の誤りとか、である。
このときの弁之助は九歳ではなく十九歳とすれば、まあ、あり得るかも。
このエピソードは、一体、誰が語ったのかといえば、武蔵か無二斎しかいない。
その場に、二人のほかに誰もいないからだ。あるいは、後世の創作か。
意外と、弁之助の指摘は的を得ていたのではないだろうか。
的外れなら五月蝿いと怒るだけでよい。勘当の必要はないだろう。
当時は、(特に黒田家では)現在より無二斎の武名は有名だったろうが、
それを早熟な武藏が九歳にして超えた、という単なる暗示なのだ。
無二斎の異常さ、親子の情の薄さや、不遇な少年時代の背景によく使われるが、はたして、そうだろうか。
親子の情が薄いというのは、現在人の武蔵のイメージから来る印象だ。
武蔵は、幼少のころに父母をなくし天涯孤独で暮らした、という設定を作ってしまったからだ。
むしろ逆だろうと思う。
幼児虐待やDVが普段からされている家庭なら、子供が親に向かって批判がましいことを言うはずがない。


