







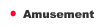

宮本武蔵参考文献
虚像と実像を語られる時代
これが後の正月の10時間時代劇ドラマのきっかけになる。
吉川英治版「宮本武蔵」が英訳、仏訳され海外に紹介される。
NHK大型時代劇「宮本武蔵」が役所広司主演で放映される。
こうして武蔵ブームがおこった。
この頃の武蔵研究本は、吉川英治版「宮本武蔵」は虚構で実像はこうだった、とする本であふれた。
そうした内容であるためか、武蔵の人格批判をする研究本が多い。
曰く、武蔵は当時の江戸にいた剣豪列伝中の剣客と立ち会わず弱い者ばかりを相手にしていた。
武蔵は策を弄するので卑怯である。どこにも仕官が出来なかった。
晩年、細川藩に仕官できたものの禄高は低く不幸な晩年を過ごした。
「五輪書」序文では過去の自慢ばかりしている。
遅れてきた剣豪であった。
大体、このような内容である。
元々、吉川英治本が直木説に対する回答であり、吉川英治本に反論するなら直木説の系譜になってしまう。
というか全く同じで進歩がないじゃないか!
武蔵の少年時代を垢まみれの薄汚い格好をさせ大人をにらみつけるようにしたのは、このころ作られた映像イメージだ。
親子の愛情に乏しい不幸な少年時代を過ごしたと設定されていた。
とにかく武蔵の一生は、少年時代は母親が既になく父から愛情を受けず、青年時代は殺人剣にあけくれ、壮年時代は仕官の口がなく、
晩年は不幸であったとされていた。
世間がバブル景気で浮かれている割りには、むちゃくちゃな設定である。
この時期に生誕400年を迎えた。


