







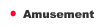

娯楽
五輪書序文
修得したことを五巻の書に遺さんと思い、
岩戸山にて書き初めるもの也。
我こそは、新免武蔵玄信、播磨出身、六十歳。
我、年少の頃から兵法の道を志し、兵法勝負の機会を窺う。
初体験は十三歳。その相手、有馬喜兵衛。これを投げ飛ばし打ち勝つ。
十九歳にて下関の小島で岩流小次郎をぶちのめす。
廿一歳のとき、室町将軍指南の吉岡兵法所をぼこぼこにし、
その後、諸国を遍歴し、柳生の剣士を投げ飛ばし、槍の宝蔵院に打ち勝ち、
伊賀で鎖鎌の兵法者をけちらし、天下諸流の兵法者に行き合ふこと六十余度、
しかれども勝利を得ざると云ふ事なし。
兵法勝負は、年十三より廿八、九迄のこと也。
三十を越えて振り替えるに疑念が湧く也。
諸国諸流の兵法者に打ち勝つが、
それは我の強さが絶対的なものなのか
それとも相対的なものか。
絶対的な兵法を得んと朝鍛夕錬し、ついに天地間の道理を得る。
我五十歳の比也。
其よりは、尋ね入るべき道なくして道楽を送る。
万事にわたって兵法の心をもってすれば、諸芸諸能において我に師匠なし。
此一流の見たて、実の心を顕す事、朝日を拝み、書初るもの也。
・・・・・・・
あ〜、めんどくせぇ〜。
春山め、添削を断りやがった。
なんで、わしが自分で添削をやらにゃならんのだ。
そんなの意味ないじゃん。
まったく、もぅ。
わしは忙しいのじゃ。
しかし、しかたあるまい。
それでは、気を取り直して、と。
えと、
ま、出だしは、まずまずってとこか。
あ、日付が漏れてる。
寛永二十年神無月のころ、っと。
次は、自己紹介じゃ。
我こそは、ってのは、ちと、大げさかな。
消そ。
新免武蔵玄信、播磨出身、六十歳。
えと、何か漏れているような。
住所、氏名、年齢、職業・・・
あ、職業だ。
播磨生まれの新免武蔵玄信、六十歳、武芸者。
何か拍子が悪いなぁ。
武芸者ではなくて身分をあらわす武士にしよ。
播磨生まれの武士、新免武蔵玄信、六十歳、っていうのはどうじゃ。
次。わしの経歴。
えと、
おいおい!これは、いかん。
初体験は十三歳。その相手、有馬喜兵衛。
やだぁ、武蔵ったら。バカバカ。
まぎらわしい!
十三歳で初めて兵法仕合をす。その相手が有馬喜兵衛だ!
でも、有馬喜兵衛だけでは、その凄さが分からんな。
なら、神道流って付けとこ。
はい、次。
十九歳にて下関の小島で岩流小次郎をぶちのめす、か。
これって、後世の人は分かるかなぁ。
天才的な演出家が芝居でも書いて興行で成功を収めないかぎり
岩流って残らんのではないか。どうだろう。
下関の小島と岩流を書いておけば、岩流小次郎って想像もつくか。
今なら岩流島って呼ばれているからな。
でも、後世では、壇ノ浦と結び付けて巌流島って呼ばれるかもな。
岩国小次郎って書けばどうだろう。
って、誰だ、それ。
やっぱ、消そ。
おっと、これでは、十三歳から廿一歳まで、ずいぶん空くじゃないか。
なら、ちょうど真ん中の十六歳ってとこで、何か入れよ。
十六歳にして兵法達者に打ち勝つ、と。
でも名前が無いのは、ちと問題じゃ。
何にしよ?
岩戸山、辺りを見渡せば秋の山、か。
おお、名前は、秋山にしよ。
そういえば、十六歳の頃、どこにいたのじゃ。
あ、親父殿と丹波にいたのじゃ。
丹波の秋山某に打ち勝つ、と。これでよし。
はい、次。
室町将軍指南の吉岡兵法所をぼこぼこにし、か。
これは、また、物議をかもしだす表現じゃのう。
ま、ぼこぼこにしたのは、吉岡だけではないのだ。
京に上りて名だたる兵法者に打ち勝ち、だ。
柳生の剣士を投げ飛ばし、
槍の宝蔵院に打ち勝ち、ってのは
これも、ちと、表現がやばいか。
考えてみれば、むちゃ、やばい!
鎖鎌や、宝蔵院はともかく柳生はまずいなぁ。
なんか、うまい表現はないものか・・・
やっぱ、消そ。
う〜、でも柳生をぼこぼこにしたのを入れたいなぁ。
そうじゃ、名案!
さっきの秋山。丹波をやめて、隣の但馬にしよっと。柳生但馬守だ!
十六にして、但馬の秋山に打ち勝つ、と。
次。えと、
う〜ん、難しいのぉ。
絶対か相対か、って言ってもな。
詳しくは五巻の書参照じゃが、それじゃ序文にならんし。
目次じゃないんだからね。
要するに、自分が強いのか相手が弱いのかを
うまく書けばいいのじゃ。
打ち勝ってきたのは、自分が兵法達者だからか、たまたまか。
ま、三十歳くらいで反省した、ということだ。
三十を越えて振り替えるに、我、兵法達者にして勝にはあらず、
おのずから器用にて、天理に合っていたためか、
あるいは、相手の稽古不足なるとことか、だ。
道楽ってのはどうだぁ。
光陰をおくる、のほうがいいか。
此一流の見たて、実の心を顕す事、朝日を拝み、書初るもの也。
ここで、序文をかっこよく最高潮に達しないといけないな。
ということは、もう少し、修辞が必要か。
ま、先に、孫子や韓非子、今昔物語など参考にしてません、って断っとこ。
此書、孫子や韓非子、今昔物語などもちいず、と。
あ、やっぱ、古き軍記・軍法をもちいず、だ。
神に誓って、じゃなくて、天道に誓って、と。
古き軍記・軍法をもちいず、実の心を顕す事、天道に誓って、か。
やっぱ、天道に誓って、はよくないな。
あ、観世音だ。観世音を鏡として、だ。
神無月上旬、卯の刻に書き始めるもの也、と。
卯の刻、って、やけに可愛いな。
これは兵法書だからな。
もっと、何かこう、強そうに聞こえるようにしたいな。
寝丑寅卯辰巳・・・と。
あ、前と後ろが、竜と虎じゃないか。
辰の刻か寅の刻、か。
寅の下刻にしよ。
ふぅ〜、疲れた。
また、明日にして、今日は、疲れたから、もう、寝よ。
・・・・・・
その後、また、見直し、ついに完成させた。
兵法の道、二天一流と号し、数年鍛錬の事、初而書物に顕さんと思ひ、
時に寛永二十年十月上旬の比、九州肥後の地岩戸山に上り、
天を拝し、観音を礼し、仏前にむかひ、
生国播磨の武士新免武蔵守藤原の玄信、年つもって六十。
我、若年のむかしより兵法の道に心をかけ、十三歳にして初而勝負をす。
其のあいて、新当流有馬喜兵衛と云ふ兵法者に打勝ち、
十六歳にして但馬国秋山と云ふ強力の兵法者に打勝つ。
廿一歳にして都へ上り、天下の兵法者にあひ、
数度の勝負をけつすといへども、勝利を得ざると云ふ事なし。
其後国々所々に至り、諸流の兵法者に行合ひ、
六十余度まで勝負をすといへども、一度も其利をうしなはず。
其程、年十三より廿八、九迄の事也。
我、三十を越て跡を思ひ見るに、兵法至極にして勝にはあらず。
をのづから道の器用有りて、天理をはなれざる故か。
又は他流の兵法、不足なる所にや。
其後なをも深き道理を得んと、朝鍛夕錬してみれば、
をのづから兵法の道にあふ事、我五十歳の比也。
其より以来は、尋ね入るべき道なくして、光陰を送る。
兵法の利にまかせて、諸芸・諸能の道となせば万事に於て、我に師匠なし。
今此書を作るといへども、仏法・儒道の古語をもからず、軍記・軍法の古きことをもちひず、
此一流の見たて、実の心を顕す事、天道と観世音を鏡として、
十月十日の夜寅の一てんに、筆をとって書初るもの也。


