







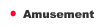

娯楽
新二天記
生涯の勝負、歳十三から二十八、九までに六十余度。一度もその利を失わず。流書に曰く、三十を超えて跡を思いみるに兵法至極にして勝つには非ず、自ずから道の器用ありて天理を離れざる故か、或いは他の兵法不足あるところにや。その後も尚も深き道理を得んと朝鍛夕錬し、兵法の道に遭うこと五十歳のころなり。それよりは光陰を送る。兵法の理に任せて諸芸諸能の道と為せば、万事において師匠なし、と書せり。
書に曰く、村上天皇の皇子具平親王の後胤、播磨国佐用の城主赤松二郎判官則村入道円心の末葉也。故有て外戚の氏姓宮本に改む。又兵法書等には新免と書せり。
武蔵が生年諸説あり。在る説に曰く、武蔵「五輪書」序文に寛永二十年に書物に顕さんとしたとき年つもりて六十と書せり、因て天正十二年であると。又養子伊織が系図に天正十年とあるを真と説く者、近年多し。世上天正十二年説多し。此記それに従ふ。
生誕地諸説あり。美作国吉野郡讃甘村宮本に武蔵幼少のころの伝多し。他に聞かず。又播磨国揖東群鵤庄宮本村こそ真であると「播磨鑑」にあり。証拠有りと云えども焼失せり。或いは、伊織系図に因り、播磨国印南群河南庄米田村とも云えリ。武蔵自ら「五輪書」序文に生国播磨の武士と書せり。論盛んとなりしが今だ決着つかず。
武蔵が幼名弁之助と云。老年に至り二天道楽と号す。
武蔵が父は新免無二の介信綱。当理流、十手二刀の達人也。新免の姓は自ら剣術を修し得て新免と改むと云。扶桑第一剣術者吉岡憲法と将軍義昭の御前で勝負を決し、憲法が一度勝ち無二は二度勝つ。此れに因り日下無双の称号を賜う。又此時から改むとも云えリ。不詳。
新免無二は、実父ではなく養父であるとする説あり。伊織が系図に武蔵は伊織祖父家貞の次男と書せり。新免無二之助一真の養子になると見えたり。
武蔵、弁之助と呼ばれしころ父が兵法見こなし、常々誹謗す。無二、一子たりと云へども其のことによつて心に不叶。或時無二、楊枝を手づから削る。弁之助、また一間余りを隔てて座せり。無二、小刀を以て手裏剣にうつ。弁之助、面をそむく。則ち座する所の後の柱にしたたかにうつ。無二、甚だ怒りて曰、「平日わが兵法をさみす。手裏剣を以て左の耳の端を二三歩打切り、思い知らせんと思ひしに面をそむけ難をのがる。近頃、奇怪の由にて家を追」
十三歳のとき初勝負をす。その相手新当流有馬喜兵衛に打勝つ。「丹治峰金筆記」にその談あり。「二天記」曰く、有馬喜兵衛は播州の剣術者也と。或いは「佐用郡誌」に曰く、新当流遣い手なるも博徒にて蛇蠍の如く嫌われし者なりと。
十六歳のとき、但馬の国強力の兵法者秋山某に勝つ。不詳。
十七歳のとき関ヶ原合戦に参戦し武蔵の働き群を抜くと「二天記」に云えども他の文献に見当たらず。不詳。西軍より参戦したとする者多し。
二十一歳のとき、京で吉岡憲法の嫡子清十郎と洛外蓮台寺野で勝負をす。清十郎は真剣、武蔵は木刀。これに打ち勝つ。その後、弟の伝七郎とも洛外で勝負を決す。伝七郎は五尺の太刀、武蔵はその太刀を奪つて一撃で倒す。この後、吉岡門弟は清十郎の子又七郎と組し数十人で一乗寺下がり松で勝負を決せんと約す。然るに武蔵門弟来たり告ぎて云う「又七郎は父叔父の仇とす。清十郎以来の門弟大勢引卒し挟み討ちて仇を報せんと企てる由を聞ぬ。死地に着く也。誠に危き所也。願わくば我々も相従いて倶に之を拒まん。」武蔵云う「各数輩を引出て戦闘に及ぶは徒党を結んで戦を催すなり。公儀の固く禁止する所也。慎ますんば有るべからず。若し一人も従い来るものあらば却つて我を罪に陥るゝにあらずや。思うに渠か賊術奈ぞ懼るに足らん。」門弟を返す。清十郎及び伝七郎と会せしときは期に遅れ凝滞して之に勝つ。這回は是に引き替え先達て行へしと。鶏鳴より独歩し洛を出る路に八幡の社あり。因て思う「我幸いに神前に来れり。正に勝利を祈るべし」と。社殿に至りて慎みて鰐口の紐を把て将に打ち鳴らさんとす。忽ち思う「我常に神仏を信仰せず。今此難を憚て祈るとて神夫受めや。吁怯し」と。慙愧汗流して踵に至る。暫く有りて又七郎数十人引卒し燈を提て来り云「定て武蔵又遅滞して期に遅れんこと必せり」とて、松根に近くとき、武蔵待得たりと高声に呼びて大勢の中に切入る。又七郎抜合わんとする所を又七郎を真二つに斬殺す。徒党の者切懸かる。或いは槍を以て突き懸かり、半弓にて射る。その内矢一筋袖に留るのみにて、幸いにして疵を蒙らず。前後左右の者どもを斬り崩し追い立てれば、大勢崩れたる息に踏留る者なく狼狽し、武蔵全勝を得たり。此段「二天記」に依るもの也。
吉岡、無名の武蔵と仕合うこと不可思議と説く者多し。父憲法無二に負けたることを報いんとする説あり。「丹治峰金筆記」に廻国修行は吉岡が免符必要なりと、武蔵此期に吉岡と仕合を願うと見えたり。
同年槍の宝蔵院覚禅坊法胤胤栄の弟子、奥蔵院と立ち会う。武蔵は短い木刀で立会い、二度勝つ。武蔵の技量を感嘆し夜が明けるまで饗応す。
伊賀国宍戸という鎖鎌の達人と野外で立会う。武蔵は短刀を抜き宍戸の胸を打貫く。宍戸の門弟が連れ合て斬懸かる所、武蔵が追い崩せば四方に逃走す。
波多野二郎左衛門宗件と云う者、一伝流の遣い手也。武蔵に教えを請ひて後、技を改て一転流と号す。
柳生流の士に大瀬戸隼人、辻風某と云う強力の者あり。武蔵江戸に在りしとき勝負を挑むも立所に仆る。
夢想権之助、武蔵に勝負を挑む。武蔵は楊弓の細工中で割木で立ち向かう。武蔵一撃で倒す。権之助閉口して立ち去る。「二天記」「海上物語」「武芸小伝」の其の談見ゆる也。
武蔵が門弟に幸坂甚太郎と云う者あり。奥義許されしも辻斬りをすること武蔵聞き及ぶに至り之を破門されし。
佐々木小次郎という剣客あり。越前宇坂の庄、浄教村の産。富田勢源が家人にて幼少より稽古を見覚え長ずるに及んで勢源が打太刀を勉む。小次郎常に大太刀を持ち勢源が短刀に対してその技能あり。尚鍛錬して勝利を弁するに高弟達小次郎が大太刀に及ぶ者なし。勢源が肉弟治部右衛門と勝負して之に打ち勝ち、勢源が許を欠落して自ら一流を興し巌流と号す。その法術奇なり。諸国廻国し豊前小倉に至る。細川三斎翁忠興公聞き召し、小次郎を停め置き玉う。門弟できて指南あり。慶長十七年四月、武蔵都より小倉に来る。長岡佐渡興長は父無二の門人なり。その故に因て来るなりと。興長に請いて曰く「巌流小次郎今此地に留りぬ。その術奇なりと承る。願わくは手技を比べんことを。」興長応諾ありて武蔵を留め忠興公御聴に達し、その日を定め、小倉の絶島に於いて勝負を決せしむ。向島とも船島と云。後年巌流島と云へり。前日府中に触有て、この度双方勝負の贔屓、遊観禁止あり。興長武蔵に曰く「明朝辰の上刻、向島にて巌流小次郎と仕合致すへき由を諭す。小次郎は忠興公の船にて、武蔵は興長船にて渡るべし也。」武蔵喜色面に顕れ願望達せしことを謝す。然るにその夜武蔵去て迹なし。皆云う「逗留の内、小次郎が技芸妙術なることを聞き及び臆して逃げたり」興長も如何とも為かたなく茫然と臍を噛む。興長家士に命じ「武蔵懼れて逃げるならば何ぞ今日を待たん。察するに何ぞ心持有ことならん。先の日下関に着て翌日ここに来れり。下関に至りそれより向島に往んこと必せり。急ぎ飛脚を立つべし」と。飛脚下関に至り見れば、果たして問屋小林太郎左衛門と云う者の所に在り。武蔵書を呈す。その文に、此回小次郎と私は敵対の者にて御座候。小次郎は忠興公御船にて被遣、私其許様御船にて向島に被遣の由、御主人様へ被対、如何敷奉存候。明朝は爰許船にて向島へ渡候、と。翌朝にになり日高なる迄、武蔵起きず。亭主太郎左衛門「辰の刻に及ぶべし」と起こし告る所に小倉より飛脚来り、船渡の由を武蔵に告る。武蔵程無く参る由返答し、手水し飯を仕廻い、亭主に請いて櫓を以て木刀の大きさに削る。その内又飛脚来り、早々に渡るべし由告る。武蔵は絹の袷を着て手拭を帯にはさみ、その上に綿入を着て小舟に乗て出る。船中にて紙縒りをして襟にかけ綿入れを覆て臥す。島には検視警固の者差し渡さる。号令厳重也。巳の刻過ぎに武蔵向島に到る。武蔵綿入を脱ぎ短刀を腰に差し裳を高くかかけ木刀を掲げ素足にて舟より下りる。手拭を以て一重の鉢巻にす。小次郎は猩々緋の袖なし羽織に染革の立付けを着し草鞋を履み三尺余りの刀を帯す。甚だ待ちつかれ武蔵か来るをはるかに見、憤然として進みて水際に立て云う「我は先達て来れり。汝何ぞ遅するや。ああ臆れたるか。」武蔵黙然と応えず。聞かさるか如し。小次郎霜刃を抜きて鞘を水中に没、水際で武蔵を迎う。武蔵、にこりと笑いて剣豪決闘史上最高の名台詞を発す「小次郎敗れたり。勝者なんぞその鞘を捨てん。」小次郎益々怒りて刀を真甲に振りたて武蔵が眉間を打つ。武蔵同じく撃処の木刀、小次郎が頭にあたり立所に仆る。小次郎が打ちし太刀の先、武蔵が鉢巻の結び目にあたりて手拭分り落つ。武蔵木刀を掲げて暫く立ち、又振り上げて撃んとす。小次郎、伏ながら横にはらう。武蔵が袷の膝上三寸切りさきぬ。武蔵、小次郎か脇腹横骨を撃折て小次郎気絶す。口鼻より血流れ出つ。暫く有て武蔵木刀を捨て、手を小次郎か口鼻に覆い、顔を寄せて死活を窺うこと漸暫也。而して後、遥かに検使に一礼し、起きて木刀を把り元の舟に飛び乗り、自らも共に棹さして行事速やか也。佐々木小次郎、此時十八歳の由なり。英雄豪傑の人なりて武蔵も是を惜しむと也。此段、「二天記」に依るもの也。
巌流島決闘、細川家家臣沼田延元が日記に後日談有り。双方共に弟子壱人も不参筈に小次郎方は如兼約、弟子壱人も参らず。然るに武蔵方弟子共数人参る。小次郎蘇生致しとき武蔵が弟子共参合し小次郎を打殺す。小次郎が弟子、此聞き及び武蔵を打果たさんとす。武蔵、難遁れるため門司に到る。門司城代沼田延元、城中に召し置くに付き、恙無く運を開く也。その後、豊後に送届け、武蔵が父無二に相渡す也と。
巌流こと諸説あり。富田勢源が弟子なれば此時老年の筈也と。或いは鐘巻自齋が弟子也と。岩国の産也と。豊前岩石城佐々木一族の者也と。佐々木小次郎が伝甚だ少なし。此仕合、多くの文献に書せりと雖もその談甚だ異なること不可思議也。又細川家公式記録に見えず。因りて小次郎殺害のため仕組まれた仕合也と説く書近年に多し。「二天記」の筋、老若男女に至るまで人気を集めること吉川英治氏の筆に依ること大なり。近年巌流島観光地になる程也。武蔵が生涯最大の仕合と云う者多し。然れども、その談虚構の疑い濃いと云う者これ又多し。武蔵遅滞の伝、卑怯なりと評する者、後を絶たず。之、武蔵を嫌悪する者の根也。「二天記」作者、流祖英雄談を世に遺すに努めると云えども効果逆さになること此時知る由もなし。
慶長十九年のとき大坂の陣に参戦す。軍功証拠ありと「二天記」にあり。此れ「水野勝成覚書」他にも伝えるところなり。
在る年、武蔵尾張に到る。徳川光友公、武蔵武芸を見て曰く、凡庸に非ず、妙神に入る。仕を勧む。武蔵肯かず。客遇し留る三年。之に依り、円明流尾張に広まる也。
武蔵、尾張に在るとき路上にて一人の偉丈夫を見かけ、当地にて初めて活きた人物を見た、柳生兵庫助殿ならんと傍らの門弟に云う。兵庫助も又相手の非凡の風貌みて、これぞ武蔵なるべし、と。互いに名乗り合い兵庫助宅で歓を尽くすと云う。名人が名人を知る話し也。
松平出雲守直政公、家士随一の剣術者を武蔵に立ち合せること思し召す。その者歯が立たず。直政公武芸自慢にて御自ら立ち合うこと三度。御勝利することなし。木刀折れ天井を突き破ると云う。直政公、此ときより武蔵が門人になられたと云う。
姫路に在りしとき、姫路城西の丸庭園の作庭をする伝あり。誠に美しき庭園なり。
本松寺、円覚寺の造園の伝あり。美しき趣にて静かなるが平成の大地震のさい土塀が崩れたると聞き及ぶなり。
小笠原忠政公、明石城御築城の折、武蔵町割りに参画す。
姫路城主が木下家定の頃、天守閣に妖怪が出没すると云う噂広まる。武蔵に退治を命ずる。武蔵明け方まで番をするに美しい姫が現れ云う、自分は刑部明神なり。武蔵の武勇により妖怪が逃げ去ると。明神喜び、その剛勇をたたえ郷義弘の銘の刻まれし宝剣を授けしとする伝あり。しかるに講談の類なること云うを待たず。又武蔵天守閣に幽閉されしとき万巻の書を読むの伝、吉川英治氏の創作也。
三宅軍兵衛と云う者、姫路随一の剣術者なり。武蔵に勝負を挑む。武蔵二刀で応ずる。武蔵、軍兵衛が頬を突き鮮血流れる。武蔵薬を与え布切れを渡し静かに控えたと云う。此れより軍兵衛、武蔵の門人になりにけり。軍兵衛、生涯に恐ろしいと思ふこと二度あり。一つは大坂の陣殺気の中で静まり返る時、尚一層は武蔵二刀掲げて現れしとき也と。
宮本造酒之助、武蔵の養子也。当世の美少年、二刀剣術優れたると伝あり。本多忠刻公に仕える也。小姓頭七百石。忠刻公病にて御逝去の折殉じ遂げる也。「丹治峰金筆記」に馬子なりと見える。真実と云い難しの説多し。
宮本伊織貞次、武蔵の養子也。小笠原忠真公に仕え、子孫存続す。知行四千石、家老也。「二天記」に泥鰌少年とされるが此れも虚構の説多し。
宮本三郎九郎景貞、武蔵の養子と伝ありしも不詳。
豊前細川越中守忠利公へ肥後国を賜う。その跡を小笠原右京太夫忠真公へ賜う。寛永十一年、武蔵小倉に至る。忠真公篤く遇し賜う。之に依り、武蔵小倉に滞留す。
高田又兵衛吉次、宝蔵院流槍術名人、天下無双の者也。武蔵小倉に在りしとき正月、忠真公の命にて双方御前で相対す。三合、一進一退の後、又兵衛槍を投げ出し「参つた」と。又兵衛曰く「槍は長く剣は短きものなり。槍七分の利あるにかかわらず勝利得ることなし。負けなり」と。
寛永十四年、肥前島原の城に切支丹一揆楯籠る。忠真公出陣、武蔵相従う。
寛永十七年、忠利公の招きによつて肥後に至る。小倉より肥後に向かうとき、城外の山に寿蔵を建てる。その後、伊織が承応二年四月に石碑を建て、その銘を春山和尚に請う。その銘伊織自身の作と云う説あり。
武蔵、忠利公より十七人扶持、現米三百石賜り、御客分にて座席は大組頭の格合なり。居宅は熊本千葉城に屋鋪あり。武蔵平居閑静にして、或いは連歌、茶、書画、細工等にて月日を過ごす。書画の評価甚だ高し。平日共廻りは侍六人程也。門弟は諸士千人に及ぶ。
忠利公の御前にて、柳生流氏井弥四郎と手技を比べる。両人木刀を以て立会うこと三度、弥四郎に勝利なし。武蔵、御前ゆえ強く打つことなく、唯技を押えて働かさせず。忠利公、柳生但馬守より柳生流相伝し奥義を極められるなり。御工夫を回され御自身が立ち会うとも御勝利なし。甚だ驚き玉いて、それほどの者とは思い召されざりしと感称し玉う。それより二天一流を御修行あり。
塩田浜之助と云う者、棒捕手の達人なり。或るとき武蔵に相手を請う。武蔵直ちに短刀を持て対す。浜之助六尺八寸の棒を持て立向かう。武蔵、浜之助が棒を振り出さんとする頭を押え働かさせず。又振り出す後を打つ。武蔵曰く「吾無手にて居るべし。吾間のうちに足踏み入れば浜之助勝ちとする」と。浜之助大いに怒りて棒を捨て手捕りにかかる。武蔵間の外より突き倒す。よつて間の内に寄り附くことならず。浜之助門弟に成らんことを願う。武蔵則ち門弟とす。浜之助棒捕手の達人なるを以て門弟に習さしむ。世に武蔵流の棒とは浜田流のことなり。
或る晩、武蔵に闇討ち仕掛ける者あり。武蔵之を押さえつけ叱りつけると、其の者過ちを詫び命乞いをす。武蔵訳を質すと其の者、刀鍛治なれど其の切れ味試すためと云う。その鍛刀なかなかの業物故、武蔵之を褒め此れよりその者武蔵の門弟になりにけり。河内守永国と云う刀鍛治なり。
或る年正月三日の晩、御花畠に於いて御諷初のとき各座列にて武蔵も在り。志水伯耆上座より武蔵に曰く「貴方先年巌流と勝負ありし時、巌流先に打たる由風説あり、その通りの様子にてありしや」と。武蔵とかくの言なくて立て燭台を取り伯耆の膝元につかと座し「我幼少のとき蓮根という腫物致し、その痕有て月代を剃ること難なり、惣髪なり。巌流と勝負のときは、巌流は真剣我は木刀なり。真剣にて先を打たれしならば疵痕あるへし。御覧あれ」と左の手にて燭台を取り右の手で髪を掻き分け頭を顔に付き麗る。伯耆後に反りて「疵見えず」と。「諚と覧有るへし」と云う。「成る程、得と見届け申したり」と。その時に立て燭台を直し、元の席につき髪掻きなで自若として在り。真に一座の諸士手に汗を握り鼻息するものもなく見えたり。
寛永二十年十月、武蔵、兵法が真髄を書に遺さんと思い岩戸山霊岩洞に籠りて書きはじめられる。地火水風空の五巻の書也。後年「五輪書」と云えり。稀代の名著なること疑うこと知らず。然るに武蔵自筆による原著見当たらず。「丹治峰金筆記」に曰く、江戸大火のさい焼失する也と。近年「五輪書」よく書きたる書多し。その数浜辺の砂の如し。商いの上手ならんとする者皆愛読す。其れに因てか異国本に翻訳せしり。効果のほど如何。橋本某、首相なられしとき、仏国大統領が「五輪書」のこと尋ねられしと談あり。未詳。
正保二年、武蔵疾病なり。霊岩洞に至り静かに終命の期を了せんとす。然るに世上に奇怪の浮説ありと。寄之聞にし召し、鷹狩に託して岩戸に至り、武蔵を諌めて誘い千葉城の宅に帰りぬ。
同五月十二日、寄之友好へ鞍を譲り、寺尾勝信に五輪の巻、同信行に三拾五箇条の書を相伝なり。自戒の心にて書せらる。独行道十九箇条也。二十一箇条とも云う。
同五月十九日、千葉城の宅にて病没す。年六十二。武蔵遺言にまかせ、甲冑を帯し六具を固めて入棺也。兼ねて約なれば泰勝寺春山和尚導師にて飯田群五丁手永弓削村の地に葬す。此春山和尚誤りの説多し。大淵和尚であると伊織の書簡に見える也。引導終わると斉しく、一天晴れたるに雷鳴一つあり。諸士の下部とも驚き、葬場大いに騒動すと云えり。豪傑の死去葬礼にはこの事有りと云えリ。


