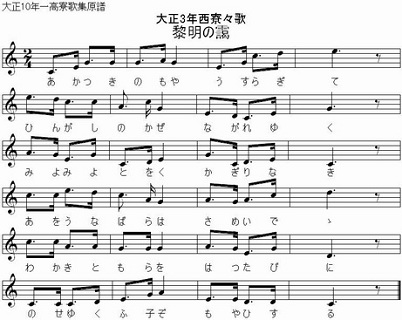| 語句 |
箇所 |
説明・解釈 |
| 黎明の靄淡らぎて 東の風流れ行く 見よ見よ遠く限なき 蒼海原は醒め出でゝ 若き友等を初旅に 乗せ行く船ぞ舫ひする。 |
1番歌詞 |
夜明けとともに、立ち込めていた靄が晴れ、東の風が靄を運んでいく。見る見るうちに、すっかり明るくなって、どこまでも遠く広大な青海原が眼前にその姿を現した。この春、向陵を離れ、世間の荒波の中に初めて船出する卒業生を送るために紀念祭の準備をしよう。
「東の風」
春に東から吹く季節風。朝靄を吹き飛ばす風、また船出のための順風をいうのであろう(朝凪の後は、海風が陸に向かって吹く。太平洋岸では一般に東風である)。
拾遺1006 「東風吹かばにほひおこせよ梅の花 あるじなしとて春を忘るな」
「蒼海原は醒め出でゝ」
「醒め出でゝ」は、眠りから醒める。すっかり明るくなって。昭和50年寮歌集で「醒め出でて」に変更された。
「初旅に 乗せ行く船ぞ舫ひする」
「初旅」は、一高を卒業し、向陵を離れ初めて世の荒波の中に旅立つこと。「舫ひ」は船と船を繋ぎ合わせることだが、そうすることによって、多くの船を碇泊させること。紀念祭を催して、卒業生を送る準備をすること。
|
| 橄欖の森柏葉下 語らふ春は盡きんとす 嗚呼紅の陵の夢 其の香其の色永劫に 旅行く子等の胸に生き 強き力とならん哉。 |
2番歌詞 |
香ばしい橄欖の花が咲き、綠もぞ濃き柏葉が繁る向陵で、友と語ろうにも別れの春は、すぐそこにやって来た。今振り返って見る時、あゝなんと素晴らしい夢のような向陵の生活であったろうか。橄欖の花の香に酔い、綠もぞ濃き柏葉の蔭に旅寝した三年の春の思い出は、生涯、旅立つ一高生の胸に生き、長い人生を渡る上で、強い力となるであろう。
「橄欖の森柏葉下」
向ヶ丘の一高キャンパスで、あるいは寄宿寮で。橄欖は一高の文の、柏葉は一高の武の象徴。
「嗚呼紅の陵の夢」
あゝなんと素晴らしい夢のような向陵生活であるか。陵は向陵。
|
我等を守る星の運 其の武運こそ拙くて 矢叫びの跡風吹けば 野花白うして草亂れ 友の血潮の紅に 夕日淋しく映えんとす。
|
3番歌詞 |
栄光の歴史と伝統を有する一高運動部も、ついに武運に見放されたのであろうか。野球部は早慶に連敗し、陸運も駒場運動会・帝大運動会で敗北、さらに雪辱に燃え必勝を期して仙台に遠征した柔道部も北の豎子二高に無念の涙を飲んだ。勝利の桂冠を得べく全寮挙げて応援し、選手は血の滲むような猛稽古に励んできたのに、敵との壮絶な戦いに刀折れ矢尽き、我が一高は敗北した。炎と燃えた友の勝利への執念と情熱も今はむなしく、捲土重来を誓う友の顔に、沈む夕日が淋しく映えるばかりである。
「その武運こそ拙くて」
同年東寮々歌「彌生が岡の夕まぐれ」で既述のとおり、大正2年から3年初め、一高運動部は野球部が早慶に連敗し、陸運も駒場運動会・帝大運動会で敗北、さらに柔道部も対二高戦で敗北した。運動部のこのような相次ぐ敗北・不振をいう。
「矢叫びの跡」
戦場跡。「矢叫び」は、戦いの初めに両軍が遠矢を射合う時、互いに高く発する声。
「野花白うして草亂れ」
「白」は負け、悲しみを、「亂れ」は戦いの凄まじさを表す。
「友の血潮の紅」
炎と燃えた友の勝利への執念と情熱。戦いに敗れた後では、「夕日淋しく映えんとす」である。
「不幸我大將、敵の副將と引分けとなるや一同無念の涙を飲み選手の奮戦の目覺ましかりしを賞揚しつゝ之を擁して歸りぬ。あゝ豎子再び名を成せり。意氣感激に生くる向陵健兒三度起ちて捲土重來せば榮冠何ぞわが頭上に輝かざるべけんや。」(「向陵誌」大正3年対二高柔道戦)
|
| されど望は盡きざりき 紺碧の空白銀の 文運の星瞬けば 今六寮の若き血は 燎原の火の行く如く 亂れし世をば燒き果てん。 |
4番歌詞 |
さりながら悲観ばかりするでない。天下に覇を唱える我が一高の望みが尽きたわけではない。天下に一高文芸部・弁論部ありと、久米正雄、芥川龍之介、菊池寛、矢内原忠雄、土屋文明などが若くして文壇・論壇に彗星の如くデビューし大活躍しているではないか。炎と燃える一高健児の若き血は、ペンの力で以て、この乱れた世を燎原の火の如く焼き尽くそうとしている。
「紺碧の空白銀の 文運の星瞬けば」
「紺碧の空」が昼間の空であるとすれば、「文運の星」は白く輝く太陽であるが、夜空であれば白鳥座のデネブ、こと座のベガ、わし座のアルタイル(以上夏の大三角形)、オリオン座のペテルギウス、こいぬ座のプロキオン、おおいぬ座のシリウス(以上冬の大三角形)などの白く輝く星が考えられる。後の句の「燎原の火の行く如く 亂れし世をば燒き果てん」に相応しいのは、光輝全天随一で、ギリシャ語で「焼き尽くす」の意味のシリウスとなろう。白銀の星を「銀河の星」(こと座のベガは、おりひめ星として有名)とロマンチックに想像するのもよいが、「燎原の火の如く・・」にはあたらない。
「虹霓の意氣文はなる」(明治40年「朝金鷄たかなきて」3番)
「天狼(シリウスのこと)凍る霜の朝 正義に燃ゆる皇国の 降魔の劔今ぞ鳴る」(昭和17年「寒風颯々」1番)
「当時の『文運』隆盛を物語る事例としては、文芸面における久米正雄、秦豊吉、倉田百三、藤森盛吉、菊池寛その他の活躍があり、弁論部その他の面で矢内原忠雄、安井英二、青木一男、柳田誠二郎、芥川龍之介、石田幹之助、土屋文明などの名が挙げられる。」 (一高同窓会「一高寮歌解説書」)
「向陵誌」(第1回)が大正2年6月に刊行された。また、関係ないかも知れぬが、岩波茂雄(明治34年入学、一高中退)が岩波書店を大正2年8月5日に開業し、翌年夏目漱石の「こゝろ」を出版した。
「燎原の火」
野原を焼く火。転じて、火が野原に燃え広がるように、勢いがさかんで防ぎとめることができないさまの形容。
|
|
短かゝりしよ其の三年 麗しかりし其の夢よ 今し船出の餞別に 二十四年の追憶を 語り明かすも感激に 若き心の躍る哉
|
5番歌詞 |
素晴らしい向陵生活、三年は夢のように短く、あっという間に過ぎてゆく。紀念祭の今宵、卒業・去寮にあたり、栄光の一高寄宿寮24年の歴史を語り明かす感激に、若い一高健児の多感な胸は躍るのである。
「短かゝりしよ其の三年 麗しかりし其の夢よ」
夢のような向陵生活、三年はあっという間に過ぎる。向陵は、若き三年を過ごした短くも麗しい夢の旅路であった。
「短かゝりし」は、昭和10年寮歌集で「短かりし」に変更された。
「三年の春は過ぎ易し」(明治44年「光まばゆき」4番)
「丘の三年はひたすらに 吾等が夢の住むところ」(大正2年「ありとも分かぬ」4番)
日本武尊 「倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山こもれる 倭しうるわし」
「船出の餞別に」
卒業・去寮の記念に。船出は一高卒業・寄宿寮去寮のこと。「餞別」は、旅立つ人の馬の鼻を行くべき方向に向けて見送った習慣による。
「二十四年の追憶」
24年の寄宿寮の歴史。 |