フロイト・コンプレックス
〜ドイツ表現主義映画〜
ドイツ映画「カリガリ博士」(1919年)
ヴェルナー・クラウス(左)とコンラート・ファイト
(「カリガリからヒトラーへ」より)
20世紀最大の発明とは、「映画」、「ファシズム」そして「精神分析」の3つと言われることがある。ドイツは、この3つすべてに大きく関わった国である。1895年11月1日にエミール(1863〜1939)とマックス(1859〜1945)のスクラダノフスキー兄弟によってベルリンで初公開された「ビオスコープ」は、フランスのリュミエール兄弟による「シネマトグラフ」よりも2ヶ月近く早い偉業であった。ファシズムは言うまでもなくアドルフ・ヒトラー(1889〜1945)率いるナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)の専売特許みたいなものだし、厳密にはオーストリア出身だが、精神分析の創始者ジークムント・フロイト(1856〜1939)はドイツ語を喋っていた。フロイトの亡くなる1年前の1938年にオーストリアはナチス・ドイツに併合されるが、ユダヤ人であった彼はすぐにイギリスに亡命してしいる。
映画は、ファシズムとも精神分析とも少なからぬ関わりを持ったものである。ナチス・ドイツとヒトラーが映画を有効な宣伝手段と考え、「意思の勝利」(1934年)や「民族の祭典」「美の祭典」(共に1938年)といったプロパガンダ映画を作り出していったことは、いずれまた別の機会に述べることにしよう。フロイトの代表作は「夢判断」(1899年)であるが、彼は精神分析において「夢」を重視した。夢は潜在的願望の現れであり、目覚めている時には認めたくない欲求や隠している野心が出現してくるものなのだそうだ。それにしても、この夢というものと映画とは実に良く似ている。
夢は基本的には寝ている間にしか見ることができない。映画もまた、映画館のスクリーン、あるいはブラウン管の前にいる時にのみ観ることが可能である。また、夢を見ている時、大抵自分が夢の中にいるということに気づかないが、映画を観ていて主人公に感情移入してしまい、映画の中に入り込んでしまったと錯覚することも決して珍しくはない。さらに、夢の内容は朝起きたらほとんど覚えていないものだが、観終わったばかりの映画の細部を正確に思い出すことも実は難しい。僕もこのエッセイを書くに当たって昔観ているはずの映画を確認のために何度もビデオで観直している。70年以上も昔に観た映画を昨日観たかのように語る淀川長治さん(1909〜98)の記憶力はホントうらやましい。
「夢」という言葉には今あげた幻覚の一種である夢の他に、「将来実現したい願い。理想。」(「広辞苑 第三版」より)という意味があるが、映画はまさしくそうした「夢」を描いたものに他ならないではないか。
それにしても、フロイト自身は映画について語ってはいないそうである。彼自身は新興芸術の映画にさほど興味を持っていなかったのであろうか。
精神分析の父
ジークムント・フロイト
(「フロイト―無意識の扉を開く」より)
そこで、そのフロイトを生んだドイツの映画について見ていきたい。本来ならオーストリアを含めた“ドイツ語圏”の映画を見ていくのが妥当なのだろうが、いかんせん現在観ることの出来る映画は限られている。残念なことに僕は1910、20年代のオーストリア映画を一本も観たことがないので、ここでは省かざるを得ない(*1)。
さて、第一次世界大戦で戦場となったヨーロッパの映画界は、大きな打撃を受けたが、中でも敗戦国であるドイツの受けたショックは大きかった。だが、ドイツ映画はその後奇跡的とも言える大発展を遂げる。イタリア映画が長く低迷していったのとは正反対である。1920年代は、ドイツ映画の黄金時代であった。
*1 ちなみに僕が観ることのできた最も古いオーストリア映画は1933年ドイツと合作の「未完成交響楽」。それに1934年の「たそがれの維納」である。
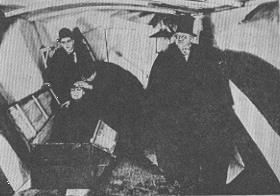
「カリガリ博士」(1918年)
ヴェルナー・クラウス(右)
(「映画芸術の社会学」より)
この時期のドイツ映画で、フロイトの影響を受けたであろうと思われる作品に、1919年に発表されたロベルト・ヴィーネ(1881〜1938)監督の「カリガリ博士」がある。主人公のカリガリ博士(ヴェルナー・クラウス)は催眠術師で、眠り男チェザーレ(コンラート・ファイト)を意のままに操り犯罪を行なう。だが、その正体こそは精神病院の院長であった。しかし、この物語自体も精神病患者の見た幻想であったのだ。なるほど、確かに精神分析的な要素を持ち合わせている。
また、悪魔的な人物によって操られる男、という主題は、すでに「プラーグの大学生」(1913年)に見られ、後には「ドクトル・マブゼ」(1922年)でも繰り返される。そもそも、悪魔との契約という主題からして、ゲーテ(1749〜1832)の「ファウスト」を挙げるまでも無く、極めてドイツ的なのだろう。
「巨人ゴーレム」(1920年)
パウル・ヴェゲナー
(「カリガリからヒトラーへ」より)
「カリガリ博士」を筆頭に、この時期のドイツ映画の秀作の多くは怪奇映画や幻想映画であった。人間心理の襞に触れるということは、こうした暗部を描き出すことにつながっていくのだろう。「プラーグの大学生」はドッペルゲンガーを主題としていたが、ここで主役を演じたパウル・ヴェゲナー(1874〜1948)は後に「巨人ゴーレム」(1920年)を監督・主演している。これは、土から作られた巨人が、圧政に苦しむ民衆を救うために立ち上がるという、民間伝承に基づいた映画。巨人といっても「大魔神」(1966年大映)のように巨大なわけではなく、大男であるだけ。巨人が女性に恋するあたり、「フランケンシュタイン」(1930年米)や「キング・コング」(1933年米)を思い起こさせる。
「吸血鬼ノスフェラトゥ」(1922年)
マックス・シュレック
(「映画芸術の社会学」より)
さて、1920年代のドイツ映画界をリードしていたのは、F・W・ムルナウ(1888〜1931)と、フリッツ・ラング(1890〜1976)であったが、2人共怪奇映画や幻想映画を数多く手がけている。
ムルナウは1922年に「吸血鬼ノスフェラトゥ」を発表。これは、ブラム・ストーカー(1847〜1912)の「ドラキュラ」(1897年)を世界で最初に映画化したものである。ストーリーはストーカーの原作にかなり忠実であるのだが、版権を取っていなかった関係上、「ドラキュラ」の名前が使えず、主人公はオーロック伯爵となっている。もっとも、現在ビデオ化されたものの字幕は、元通りドラキュラになっているのであるが…。ストーカー未亡人フローレンスの訴えにより、1925年ドイツの裁判所は全てのプリントの廃棄を命ずる。本来なら今日我々が観ることはできないはずなのだが、映画のドラキュラ同様にしぶとく生き残り、きちんと観ることができる(*2)。その辺の事情は、本編以上に興味深いことである。また、ムルナウは「ファウスト」(1925年)も映画化している。言うまでもなく、主人公ファウストと悪魔との契約の物語だが、ほんの一瞬ホムンクルスなるバイオテクノロジー(?)による人造人間も姿を見せる。
一方のラングは、出世作「死滅の谷」(1921年)で死神を取り上げている。落語の「死神」と同じく、人間の生命が燃えるロウソクに準えられているが、これは洋の東西問わず同じことなのらしい(*3)。また、「メトロポリス」(1926年)では人造人間を、「ドクトル・マブゼ」(1922年)では変装と催眠術を操る犯罪王を描いてみせた。
*2 仁賀克雄「ドラキュラ誕生」182〜183ページ
*3 西本晃二「落語『死神』の世界」(2002年11月青蛙書房)によると、落語「死神」は落語中興の祖と言われる三遊亭円朝(1839〜1900)が明治20年代にオペラ「クリスピーノと代母」もしくはグリム童話「死神の名付け親」をヒントに作 ったものとのことである。(2009年1月24日追記)
「朝から夜中まで」(1921年)
エルンスト・ドイッチュ(左)
(「世界映画全史10」より)
先にあげた「カリガリ博士」には美術・装置担当として、ヘルマン・ヴァルム(建築家/1889〜)、ヴァルター・レーリヒ(画家/1887〜1945)、ヴァルター・ライマン(画家)の三人が参加している。彼らは当時ドイツを中心に盛んに行なわれていた芸術運動「表現主義」のグループ「シュトルム」に参加していた芸術家であった。
表現主義の美術は、極端なデフォルメ、原色の使用、激しいタッチを特色としているが、「カリガリ博士」の極端に歪んだ街路や、斜めになった煙突にこうした表現主義が見て取れる。映画史の文献をひも解くと、この時期のドイツ映画の総称として「ドイツ表現主義映画」などという名称が用いられていることが多々あるが、厳密に 言えばそれは正しくない。明らかに表現主義の芸術を取り入れて製作された映画というのは、「カリガリ博士」の他には「朝から夜中まで」(1921年)など数作品に過ぎない(* 4)。「朝から夜中まで」には、黒地に白ペンキで塗られたような背景が用いられていた。
*4 小松弘(1956〜)によれば「Torgus」(1921年)「ゲニーネ」(1922年)「月の家」(1923年)「罪と罰」(1925年)「裏町の怪老窟」(1925年)を加えた全7本とのこと(早稲田大学文学部「映画史」授業より)
「メトロポリス」(1926年)
(「映画芸術の社会学」より)
しかし、表現主義映画をあげるまでもなく、当時のドイツ映画の舞台装置・美術の見事さは、目立って素晴らしいと言える。
ラングは、「メトロポリス」で近未来の管理社会を描き出したが、その冒頭には高層ビルの乱立する大都会を映し出した。手塚治虫(1928〜89)の初期の作品に同じタイトルの「メトロポリス」(1949年)がある。近未来の大都会メトロポリスを舞台に、人造人間のミッチィが活躍するこの作品とラングの映画の関係 はなかなか興味深いところであるのだが、意外にも手塚はこの映画を観ていなかったとのこと。手塚自身によると、彼は人造人間マリアの誕生シーンのスチールを観ただけで、インスピレーションを膨らませたという。ちなみに大友克洋(1954〜)が脚本を執筆した映画版「メトロポリス」(2001年METROPOLIS製作委員会/手塚プロダクション)は、ほとんどオリジナルともいえるストーリー。だが、機械によって仕事を奪われた貧困層が都市の地下に追いやられるというメトロポリスの抱える社会的矛盾の設定に、ラング版からの影響が感じられる。
「ニーベルンゲン」第一部「ジークフリード」(1924年)
パウル・リヒター(右)
(「カリガリからヒトラーへ」より)
ドイツ映画はこうした人造の建造物に限らず、森や湖といった自然までもセットで表現してしまっている。例えば、ラングの「ニーベルンゲン」(1924年)がそうである。ロケーションを効果的に利用したイタリア映画とはこの点でも対照的と言える。
だが、ドイツ映画のセットの用い方は、必ずしもリアリティを追求するためというわけではない。しばしばセットでもって人間心理を表現しようとする。「カリガリ博士」の歪んだ街路が、精神病患者の妄想を表していたことは言うまでもない。ムルナウの「最後の人」(1924年)の倒れ掛かってくるホテルは老人の不安感を、「ニーベルンゲン」第一部「ジークフリード」の髑髏に変化する木は死の予感を暗示する。「ヴァリエテ(曲芸団)」(1925年)の空中ブランコを見つめる人の姿が巨大な目玉と化すのは、主人公の気の迷いを表していた。こうした、セットと人間心理を結びつけるということを指して「表現主義」的であると言うことは可能であろう。
「喜びなき街」(1925年)
(「カリガリからヒトラーへ」より)
さて、同じくセットを重視しながらも、ラングやムルナウとは別の方向に向かった映画作家がいる。G・W・パプスト(1885〜1967)は徹底したリアリズムでもって映画を作り上げた。彼の出世作「喜びなき街」(1925年)は、第一次大戦直後の貧困にあえぐウィーンを舞台に、荒んだ人々の姿を描き出す。渡米前のグレタ・ガルボ(1905〜90)が可憐でみずみずしい演技を見せているのが印象的であった。また、「パンドラの箱」(1929年)は、男たちを次々と破滅に導く悪女ルルの愛憎を描く。黒髪のオカッパ頭と、素肌をさらす大胆な衣装でルルを演じたルイーズ・ブルックス(1906〜85)の官能的な魅力が最大限に発揮されている。
「パンドラの箱」(1929年)
ルイーズ・ブルックス
(「週刊THE MOVIE 70」より)
ところで、サイレント期のドイツ映画の特徴が、深刻で暗い内容だというのは、もちろん一面的な見方にすぎない。それは僕も重々承知している。実際には、底抜けに明るい映画だって作られているのだ。だが、そういった映画を実際に観るのは難しい。何しろ、この頃のドイツ映画でビデオ化された作品は、アメリカ映画に比べると極端に少ない。だいたい、アメリカ映画を10回に渡って述べて来たのに、ドイツ映画はたった1回で済ませてしまうのだから、いかに僕の観た作品数が少ないか解るだろう。もっともそれは、これから述べるフランス映画やソ連映画にも当てはまることではあるが。ともかく、僕が今までに観た中で、能天気なドイツ映画(サイレント)はと言えば、エルンスト・ルビッチ(1892〜1947)がドイツ時代に製作した「牡蠣の王女」と「花嫁人形」(共に1919年)ぐらいなもの。これでは何も言うことが出来ない。ちなみに後者は人形劇そのままのようなセット美術がドイツ映画らしかった。
「最後の人」(1924年)
エミール・ヤニングス
(「世界映画全史10」より)
トーキーに入ってからも、「会議は踊る」や「制服の処女」(共に1931年)など、ドイツ映画は傑作を次々と生み出していく。だが、その栄光は長くは無かった。1933年に政権を握ったヒトラー率いるナチスは、思想の弾圧を行ない、ユダヤ人を迫害した。その結果、映画界からも多くの人材がドイツを去っていくことになる。ナチスを嫌ったパプスト、ユダヤ系であったラングは共に1933年にドイツを抜け出し、フランスを経てハリウッドへ渡る(パプストはすぐにドイツへ帰国)。すでに1923年にルビッチが、1926年にはムルナウがハリウッドに渡っていた。「結婚哲学」(1924年/ルビッチ)、「サンライズ」(1927年/ムルナウ)、「暗黒街の弾痕」(1937年/ラング)など、彼らのハリウッドにおける活躍を考えると、ドイツ映画界の受けた打撃がいかに大きかったかがわかる。
二つの大戦の狭間に一見華やかに咲いたかに見えたドイツ映画の栄光。その中に、次々と現れた名作の多くが暗いものだったのは、その後の暗い時代の訪れを予感していたのだろうか。「カリガリ博士」におけるカリガリ博士と無力な眠り男チェザーレが、ヒトラーに操られるドイツ大衆の姿を予言しているのだと言う人もいる(* 5)。そう考えてみると、「吸血鬼ノスフェラトゥ」で、右手を高くあげた「ハイル・ヒトラー」のポーズのまま朝日の中に煙と消えていくオーロック伯爵の姿(写真下)が、何とも象徴的に思えてくる。
*5 ジークフリート・クラカウアー/丸尾定訳「カリガリからヒトラーへ」73ページ
(2003年4月18日)
(参考資料)
ジークフリート・クラカウアー/丸尾定訳「カリガリからヒトラーへ」1970年11月 みすず書房
クリスチャン・メッツ/鹿島茂訳「映画と精神分析/創造的シニフィアン」1981年7月 白水社
ミヒャエル・ハーニッシュ/平井正監訳/瀬川裕司、飯田道子訳「ドイツ映画の誕生」1995年3月 高科書店
ジョージ・A・ヒュアコ/横川真顕訳「映画芸術の社会学」1985年4月 有斐閣
「映画100物語/外国映画篇」1995年7月 読売新聞社
仁賀克雄「ドラキュラ誕生」1995年9月 講談社現代新書
ジョルジュ・サドール/丸尾定、小松弘訳「世界映画全史10/無声映画芸術の成熟」1999年4月 国書刊行会
明石政紀「フリッツ・ラングまたは伯林=聖林」2002年11月 アルファベータ
ピエール・ババン/小此木啓吾監修/小林修訳「フロイト―無意識の扉を開く」1992年11月 創元社
ジークムント・フロイト/金森誠也訳「夢と夢解釈」2001年9月 講談社新書
「現代芸術事典」1993年7月 美術出版社
手塚治虫「メトロポリス/手塚治虫漫画全集44」1979年1月 講談社
ブラム・ストーカー/新妻昭彦、丹治愛訳・注釈「ドラキュラ 完訳詳注版」2000年4月 水声社
目次に戻る
サイレント黄金時代(12)「第三の天才」へ戻る
サイレント黄金時代(14)「芸術映画の都〜アベル・ガンスとフランス芸術映画〜」へ 進む