Scratch Noise 「始まり2」
「獣人の扱いが酷い町だったな」
町の出入り口に立って、昨日の事をまるで遠い昔のような表情で語るアヴェルス。
その言葉の通り昨日はいろんな事があった。夕食の時には、獣人には食わすものはない。と言われたり、その後の宿では、お断りだと追っ払われた。今までにも差別的な事は、何度かあったが、これほどまで直接的に言われる事はなかった。嫌な顔をされたり、何かと理由をつけて断られたりする事が多かった。
「嫌な町だったな。獣人の事、とことん嫌ってる奴ばっかだ」
「ん、そーだね」
自分の事だというのに、やはり気に留めていない様子で、その場にしゃがみこんで一生懸命地図とにらめっこをしているカプリスに、アヴェルスはため息をついた。昔から知っている仲、つまり幼馴染という種類に分類される2人だが、未だにカプリスの読めない性格に、アヴェルスには悩まされ続けている。
「今度はどうした?地図なんか普段見ないだろ?」
「うーん」
アヴェルスがしゃがみこみ地図を横から覗き込むと、カプリスは顔を上げた。
「ねぇ、アヴェルス。風の神殿って知ってる?」
「は?」
「風の神殿だよ。知ってる?」
「…… いや、聞いた事ないけど、それがどうした?」
「ふぅーん」
「ふーん…… って、俺の質問に対する答えはないのかよっ!」
知らないという返事が返ってきたせいか、カプリスはつまらなさそうな顔をして、また地図に視線を戻した。普段地図なんか見ないカプリスが探しているものは、きっと先程の言葉にあった『風の神殿』なのだろう。昔から、自分が気になった事には、とことんのめりこむタイプのカプリス。風の神殿というものが、実際に存在するのかどうか解らないが、どっちにしろ彼自身の答えを見つけない限り終わる事はないだろう。
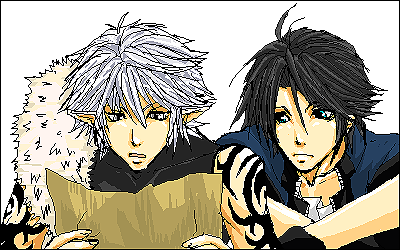 「…… 昨日さ。風の神殿に来いって言われたんだよね」
「…… 昨日さ。風の神殿に来いって言われたんだよね」
「誰に?」
「知らない」
「はぁ?」
会話が成り立たない状態にアヴェルスは、表情を歪めた。
「だって誰かわかんないんだからしょーがないだろ。最初は、何も思わなくて今朝気になってきたんだからさ。昨日は、お腹空いてたし」
「あのさ、全然意味解んねぇ」
「聞こえたんだよ、声が…… 」
静かに昨日の出来事を話すカプリスに、アヴェルスも耳を傾けた。言葉を飛ばす。昨日カプリスの身に起こった事は、遠くから言葉を飛ばし、それを特定の人物に送るという事。果たしてそんな事が出来るのだろうか?
エレメンタルの力は、基本的には四大精霊の力である、火、水、風、土の4つを物質化するもの。例えば、水の精霊であるウンディーネの力を借りると、何もなくとも水をその場に湧かせる事が出来る。力には個人差があるが、強い者であれば、それを気体にも固体にもでき、それ以上の事も可能だそうだ。
「言葉を飛ばすなんて無理だろう」
「でも、聞こえた。で、最後にこう言ったんだ。『はやくきて、ウンディーネのししゃ』って」
「ウンディーネっていう事は、四大精霊が絡んでるのか?風の神殿って事は、シルフ…… 」
「うん。きっとオレは、ウンディーネの生まれ変わりなんだよっ」
「え?」
地図を強く握り締め、立ち上がったカプリスの瞳は、何かを決意したような強いものだった。
「ちょ、ちょっと待てって。どこをどうしたらお前が生まれ変わりになるんだよ」
「え、だって死者だろ?死んで、生まれ変わり?」
あまりにも真剣に話す様子に、アヴェルスは本日何度目かのため息をつきながら、立ち上がると、カプリスの肩を軽く叩いた。
「死んだ者の死者じゃなくて、使いの者の方の使者だろ」
「…… 使いの者?」
「普通に考えれば解るだろ」
カプリスは、地図を握り締めたまま目線を空へ向け数秒考えると、何事もなかったかのような表情で町へと戻り始めた。
「風の神殿に行くよ」
「話、だいぶ飛んだぞ……。まぁ、それはいつもの事だからいいとして。そんなあるのかどうかわからない所―― 」
「あるよ。神殿はある。オレは、四大精霊のウンディーネ様の使者だよ?」
「もう様付けかよ」
何か文句でも?といった表情でアヴェルスを見ると、くるりと方向を変え町へと戻るカプリス。一度その気になったカプリスは、もう誰にも止められないのだった。
「……しょうがねぇなぁ」
「で、ここでその声が聞こえたと」
「そう、風の神殿へ来い。ウンディーネの優秀な使者の力が必要だってね」
「だんだん話が飛躍してってねぇか?」
「してないよ。いちいちウルサイなぁ」
「なんだと?」
昨日と同じ通りでまたしても同じ人間と獣人が言い争いをしているということは、周りの住人からしれみればあまりいいことではないようだった。実際には、獣人という事だけが引っかかるのかもしれないが、2人の様子を誰もが冷たい目で見ていた。
獣人がよく思われていない事は、確かにある。しかし、それほどまでに人間から迫害されているわけでもない。実際には、地位も権力も持ち合わせている獣人もたくさん居る。この2人の故郷では、獣人と人間は、普通に仲良く暮らしている。この町が異様に獣人に対しての目が厳しいのだ。それには、きっと何か理由があるのだろう。
「お前は、そうやっていつも、訳解らん事ばっか言いやがって」
「オレは聞いたんだよ!風の神殿へ来いって」
「どうだかなぁ。寝ぼけてたんじゃねぇの?」
「聞いたんだ!寝ぼけてない。お前それ以上言うとキレるよ」
「ほぅ、やれるもんならやってみろよ」
カプリスは、グッと奥歯をかみ締め睨みつけると、手にエレメンタルの力を溜めはじめる。それに対してアヴェルスも、腰にある1本の剣に手をかけ、一歩後ろに下がり僅かに鞘から剣を浮かせるとすぐに、カプリスの手のひらに青白くエレメンタルが集まり始めた
「ここでそんな物使うんじゃないよ」
カプリスは、言葉と共に右手首を掴まれると、それに気を取られてエレメンタルの力も姿を消した。
掴まれた手首を見ると、皺の多い小さな手だった。そして、その先に視線を移すと、手と同じように年をとった老婆の姿があった。
「そっちの剣士さんも、剣を納めるんじゃな。おぬし等の話に出てきた場所教えてやっても良いぞ。ついておいで」
ニヤリと笑った老婆は少し不気味だったが、風の神殿について何の手がかりもない今、この老婆の言葉を信じるしか道はないだろう。2人は、口論していた事も忘れて顔を見合わせると、先に歩き始めた小さな背中を追った。
「おばーちゃん、どこまで行くの?ってかココどこ?」
「本当に、あるのかよ。そんな神殿」
「だから、あるって言ってんじゃん!」
「五月蝿いねぇ。ちょっとは静かについて来れんのか」
歩き始めて2時間ほどは経つだろうか。町の裏手の小さい出口から繋がる大きな森へ入った。滅多に人が通らないであろうその森は、草木が生い茂り歩くのも困難で、いわゆる獣道といってもいいものだった。そんな道とはいえない道を掻き分けながら前に進む老婆は、一体何者なのか。若い2人でさえ、少々疲れの色が見え初めているのだが、老婆にはそんな様子は窺えない。
「なぁ、カプリス。このばぁさん、ちょっとおかしくないか?普通じゃねぇよ」
「うーん。じゃぁ、ついてくのヤメる?でもココまで来たんだから、もう今更って感じじゃない?」
「それは、そうだけどさ」
「あ〜、アヴェルス前!」
「うわっ!」
カプリスに言われ前を確認すると、老婆が足を止めており、あやうくぶつかるところだった。驚いたアヴェルスもぶつからなかった事に胸をなでおろす。
「ここじゃ」
ここと言われ辺りを見回してみるが、神殿どころか小さな建物すらない。今まで歩いてきた森と何の変わりもない様子に2人して顔を見合わせる。
「ココってどこ?何もないじゃん」
「あるじゃろここに」
老婆はそう言いながら、草を掻き分けて進むと2人に手招きをした。不安に思いながらも、近づき指差す方を覗き込むと地面に直径50センチ程の石版が埋まっていた。
「石版?」
「おばーちゃん。オレら探してるのは、神殿だよ。解る?シ・ン・デ・ン」
「そんな事は解っておる。石版をよく見てみろ」
石に刻んである文字は、古代のものなのか読み取る事は出来ない。丸い石版の淵をなぞる様に複雑な形がいくつもならんでおり、その中心には絵が刻み込まれていた。ふんわりと優しい横顔の少女。緩くウェーブのかかった髪は長く、彼女の足に絡みながらその最後を宙に浮かせていた。そして、その背には羽が生えている。
「シルフじゃよ。おぬし等が言っておった風の神殿を守るものじゃ」
「これがシルフ…… 四大精霊の1つ」
「でもばーちゃん。神殿に来いって言われたんだけど、どうすれば行けるの?」
「四大精霊の使者。そして、化身ならおのずと道は開かれる―― 」
老婆の言葉と共に、まばゆい光を放ち始める石版。そのあまりにも強い光に2人は、目を細め光をさえぎるように手をかざした。



|