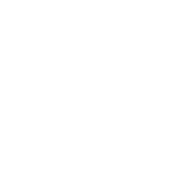<><> SUMIO'S HOME PAGE <><> |
| のが正直なところである。若し読んで頂ける方がおれば恐縮至極で心からお詫びするが。) ということで本当は大分迷ったが、冒頭の題のように主題を多少ずらして綴って見ることにした。もっとも自分は芹など山菜を採るという趣味は生憎持ち合わせていないのだが、山の神の一言で付き合いをさせられたので、それをいいことに材料に使わせて貰う次第だ。 10時前に阪急と能勢電を乗り継いで妙見口に着いた。天気は気持ちのよい五月晴れだ。周りの山々の瑞々しい新緑が目に入る。新緑といってもよく見ると実にさまざまの色合いがあって複雑な斑模様を呈している。この季節ならではの色彩の競演で、ここを初めとしてこの一日いろいろな新しい芽吹きをも色で堪能した。 駅前の通りを右に取り暫らく行くと直ぐに田園風景の真っ只中になる。畑の作物は未だ小さいが田んぼは水が満々と張られているか丁度田打ちをして水を引き入れる寸前のところと半々だ。作業中の農家に聞くとこれから田植えにかかるといっていた。満水状態の田が鏡のように何 |
 (ボタンをクリックすると、残像を残しつつ画像が切り替わる。) |
枚も続いているのは壮観である。水は濁っているが向いの山の新緑が綺麗に写っていた。 山に向かって進むと初谷渓谷コースという標識が出てくる。それに従い進むと直ぐにアスファルト道路が終り山道にかかる。樹木に覆われた林道で幅は広く轍がはっきりとついている。右側は初谷川で、この道は殆ど終りまでこの川というか渓谷に沿って登っている。しばらく行くと一寸した川原状の空間に出た。見ると車が数台止まっていて辺りにはテントが何張か張られている。キ |
ャンプを楽しんでいる一団らしい。その中には赤ん坊を抱いた人もいて今時の若い人の行動力に感心しながら通り越していく。次第に林道も狭くなっていって車が無理なところまできた。杉や檜の林が多く、日が遮られ中の道は適度な涼風が通り汗ばんだ肌に何ともいえず心地よい。夏場までのここ当分は快適なハイキングが出来る貴重な期間である。  歩き初めて30分程で又所どころに小さな川原状の空間が出てきた。その一つを選んで降りて見て周りを探す。まず三つ葉 歩き初めて30分程で又所どころに小さな川原状の空間が出てきた。その一つを選んで降りて見て周りを探す。まず三つ葉  数回繰り返して次第に奥に登って行く。途中で山肌が大きく崩れ落ち林道を覆い隠して通れず、川原の方に新しく道をつけかえたところがあったりした。 数回繰り返して次第に奥に登って行く。途中で山肌が大きく崩れ落ち林道を覆い隠して通れず、川原の方に新しく道をつけかえたところがあったりした。狙い目の  直ぐ上が頂上に通ずる車道に近い杉林で遂に終着点だ。芹や三つ葉を探しながら登ってきたので思いの他時間が過ぎて気が付いたら正午も大分廻っていた。それでこの林で昼食を取ることにした。 林は割合と高木が並び文字通り木漏れ日が少しだけ射し込んでいる。風もないので丁度良い気温で握り飯をほお張りながらゆっくり休んだ。 直ぐ上が頂上に通ずる車道に近い杉林で遂に終着点だ。芹や三つ葉を探しながら登ってきたので思いの他時間が過ぎて気が付いたら正午も大分廻っていた。それでこの林で昼食を取ることにした。 林は割合と高木が並び文字通り木漏れ日が少しだけ射し込んでいる。風もないので丁度良い気温で握り飯をほお張りながらゆっくり休んだ。小1時間後の午後1時30分山頂に向かう。杉林の急な坂を登りきると車道に一旦出て直ぐまた山道に入る。又ここも根っこの露出した急坂である。2〜300mを上がるとやがて頂上で妙見の本殿やお堂が並びその奥に星嶺と名付けられた超近代的な信徒会館が現れる。本殿やお堂には手をあわせたが、信徒会館は以前中に入って分かっているので、わざわざ靴を脱ぐのも手間に思い省略する。ただ 脇の展望台からの眺めがいいので暫らく展望を楽しむ。 その後参道を下りていくと大鳥居があって大きな駐車場に出るが、ここが先程の車道の終点で、正確には多分こちら側が正門なのだろう。人影が断然多くなっていた。鳥居の右手に帰り道の新滝道コースの階段が始まっている。下山のもっとも近道だが石段が多くて非常に歩きにくい。殆どコンクリートで固められている上、  歩幅にあわない高さ、長さになっているからだ。更に西向なのか太陽が正面から差してくるので、暑い上に眩しい。午前の気持ちのよかった渓谷沿いの上りとは大違いだ。それでも途中シャガ(射干)の花が沢山咲いていて幾らかでも慰められた。主に半日陰の斜面や木の下などに群生していて、白い小さな花が印象的だった。よその山でも時々見かけるがこれほどの群落(畳数枚分の広さ)
があちこちに見られるところは初めてだ。 歩幅にあわない高さ、長さになっているからだ。更に西向なのか太陽が正面から差してくるので、暑い上に眩しい。午前の気持ちのよかった渓谷沿いの上りとは大違いだ。それでも途中シャガ(射干)の花が沢山咲いていて幾らかでも慰められた。主に半日陰の斜面や木の下などに群生していて、白い小さな花が印象的だった。よその山でも時々見かけるがこれほどの群落(畳数枚分の広さ)
があちこちに見られるところは初めてだ。
途中で休もうと思いつつも適当な場所がなくとうとうケーブルの駅まで来てしまう。時間は下り始めてから約50分程かかっていた。駅に人気のないことを幸いにベンチで一服させてもらう。そのあと車道をのんびり妙見口駅へと向かった。その道中が又所謂里山そのものの風景を見せてくれる。昔風に言うと端午の節句のこの日、まさしく鯉幟が5月の薫風に吹かれて気持ち良さそうに泳いでる。この情景は何時見ても我々日本人の原点のような気がする。毎年見慣れているというものの初夏を彩る素晴らしい風物詩だ。鯉幟に見とれつ田舎道を下ると程なく出発点の妙見口駅に着いた。駅前の食堂で冷たいもので喉を潤し、朝買い求めて預けてあった筍を引き取る。 かくして収穫はさほどではなかったものの一応の目的は達成できた妙見山行になったので、二人とも機嫌よく家路についた。 「 見惚れおり 風満腔の 鯉幟 」 純 風 以 上 |