<><> SUMIO'S HOME PAGE <><>コース 白馬八方(タクシー)→猿倉→白馬尻小屋(泊)→大雪渓・小雪渓→葱平→村営宿舎→白 馬山荘(泊)→白馬岳山頂→三国境→小蓮華山→白馬大池→白馬乗鞍岳→天狗原→ 栂池自然園→(ケーブル・ゴンドラ)栂池高原駅 HSC歩こう会の特別例会として計画された白馬岳(2932m)登山は7月18日〜20日に実施され、成功裏に無事終った。参加33名の大部隊で当初は事の成行きが懸念された面もあったが、31名が怪我もなく予定コースを踏破し天下の名峰のトレッキングを堪能した。  (惜しむらくは1日目の山小屋での一寸したアクシデントがもとで女性1名がリタイヤとなり、リーダーの一人ががそれに付き添って下山の止む無きに至ったことであった。ただ結果的には大事に至ることなく、帰途は同じバスで全員33名が揃って元気に戻ってきた。) (惜しむらくは1日目の山小屋での一寸したアクシデントがもとで女性1名がリタイヤとなり、リーダーの一人ががそれに付き添って下山の止む無きに至ったことであった。ただ結果的には大事に至ることなく、帰途は同じバスで全員33名が揃って元気に戻ってきた。)自分もこれに参加し、3 日間にわたって多くの感動感激を味わうことが出来た。 以下に今回の山行きの顛末を簡単に記しておく。 第1日目(7月18日 (月)) 大阪(バス)→白馬八方(タクシー)→猿倉→白馬尻小屋(泊) 午前7時前の集合時間には遅れるもの一人もおらず全33名が梅田のバスタ−ミナルに揃った。名札や班区分のリボンを各自つけ貸切バスに乗車、直ぐに一路白馬村(長野県北安曇郡)に向け出発。上々の空模様で互いに幸運を喜び合う。名神などいくつかの高速道を走り抜け午後1時半頃白馬八方に到着。タクシーに乗り換え猿倉に向かう。 程無く今回の白馬岳トレッキングのスタート地点の猿倉に着いた。改めて身支度を整え装備を点検し、勇躍1日目の宿泊地の白馬尻に向けて歩き出す。すぐ山道に入るも林道のような歩きよいところだ。次第に坂を上っていくが左程急ではない。ただあれだけ良かった空模様が少しずつ変わって時折小雨がぱらつくようになる。  正面に名は分からないがかなり高い山が見え、明日はあの程度のところまで登るのだと思うと何となく武者震いが出てしまう。 正面に名は分からないがかなり高い山が見え、明日はあの程度のところまで登るのだと思うと何となく武者震いが出てしまう。約1時間20分ほどで目的の白馬尻小屋(1560m)に到着。目の前に広がる大小の雪渓風景に圧倒される。特に翌日登る大雪渓はここからの眺めではかなりの急勾配がついていてとても人が登っていくところには見えなかった。最初はもっと緩やかな幅広い別のところをいくものとばかり思っていた。周りの人に教えられ初めて間違いなくそこを登ると分かり、内心非常に驚いた次第だ。下から大雪渓を見上げるのだが、当初予想していたものより幅狭く山と山との間の沢の大きな残雪 といった風景にしか見えなかった。後から分かったことだがこれらは相当の距離がある為スケールが大きく縮小されて見えていた訳だ。実際に歩いてみると幅はかなり広く勾配は驚くほどでもなかった。 
小屋の前が一寸した広場になっているがそこに座り、この景色を眺めつつ生ビールを味わう。なんとも表現がしにくい程美味しい。夕方5時に夕食、山小屋の食事にしては随分と立派なのに感心した。 部屋は売店食堂などとは別棟で、団体のせいか3階の大部屋の半ば屋根裏をあてがわれた。天井が低くて梁に直ぐぶつかる。午後9時の消灯後は懐中電灯頼りに手洗いなどに降りるが、時々誰かしらが頭をぶつけ、この構造をなじる声がした。聞くとこの建屋は雪の為毎年立て替えるらしいが、それにしては少々知恵のない造作と呆れた次第。ただ10数人が思い思いに場所を占めて横になるだけの広さは充分にあった。2階の小部屋がその日は他の利用がないと分かって数人が移っていったせいもある。 布団の上に寝転がると雪渓から流れ出ている谷川の音が改めて大きく聞こえてくる。水量が多くしぶきをあげて流れているから当然だが、夜中ふと目が覚めた時は瞬間まるで土砂降りの雨と錯覚した。 第2日目(7月19日 (火)) 大雪渓・小雪渓→葱平→村営宿舎→白馬山荘(泊) 6時出発に備え、早々に起き出し食事や身支度を整え小屋の前の広場に出る。気がかりな天候はうす曇のようだ。軽く体操をした後出発。しかし生憎直ぐに雨がぱらつき出す。15分ほど山道を辿ると大雪渓の左下端に出る。 そこでアイゼンを手早くつけいよいよ雪渓に乗り出した。初めの20分も行ったところで記念の集合写真を撮る。それから約2時間半、途中2、3回の小休止はあったものの、ゆっくりではあったが雪の上を歩き通しだった。  雨は一時やや強くなったが雪渓の後半くらいからまた幸い次第に上がり、少し出ていたガスも登るにつれ同時に消えていってくれた。大雪渓は初めはほぼ真っ直ぐに進み、三分の二位で左に曲がりそして最後に右へ戻って終わりとなる。下から見ていると直線的に進むところまでが直接目にすることができるようだ。 雨は一時やや強くなったが雪渓の後半くらいからまた幸い次第に上がり、少し出ていたガスも登るにつれ同時に消えていってくれた。大雪渓は初めはほぼ真っ直ぐに進み、三分の二位で左に曲がりそして最後に右へ戻って終わりとなる。下から見ていると直線的に進むところまでが直接目にすることができるようだ。
雪渓は一般的にザラメ状で固まっている。そして良く見ると小さな波型の紋状になっていて、その少し窪んだところを選んで足を運ぶのがコツみたいだ。又所々が凍結した氷で、うっかり足を置くと滑って転びそうになる。表面は近くで見ると長時間に埃や粉塵がついたのかかなり汚れていて見苦しい。思えば六甲山よりはるかに標高はあるのに風で遠くから運ばれてきた塵埃なのであろう。 又休憩は雪の上では安全上出来るだけとらないようにといわれているが、歩きにくい雪の上でかつ坂で、小雨もぱらついているとそう長時間は持たない。やはり小さな休みがどうしても欲しくなる。今回はかなりスローペースではあったが、それでも一息入れたいと感じる場面が一度ならずあった。 大雪渓を登りきりアイゼンを外すと足もとが急に軽くなる、と同時に心底ほっとした。ここで何気なく携帯の自宅を押してみたら繋がったのには驚く。直ぐそばで話をしているようにはっきりと聞こえた。この後は下山するまでどこからも繋がらなかったことからするとここが電波の状況が最も良かったのだろう。大雪渓を足下に見下ろしながらの報告は一寸乙なものであった。 そこからしばらく急坂になる。この辺りから一帯が葱平(注 文末参照)と呼ばれていて、白馬岳との中間だ。  急坂が終わると小雪渓のトラバースが始まる。アイゼンを再び付けて7,80mの雪渓を殆ど真横に横切る。道がついていて坂でもないので楽に進む。
急坂が終わると小雪渓のトラバースが始まる。アイゼンを再び付けて7,80mの雪渓を殆ど真横に横切る。道がついていて坂でもないので楽に進む。そのあと再び急坂があった後今度は緩やかで道幅の広いところに出た。道の両端にロープが張られ歩くところが制限されている。所謂お花畑である。低い這松の間にかわいい花をつけたいろんな高山植物が点々と眺められた。ひとつづつ写真を撮り名前を確認できると楽しいだろうがとてもその余裕がない。 時間はいつの間にか12時近くになっていた。それで風が出てきていたがお花畑の大きな標識の前で昼食となった。山小屋調製の弁当だがおにぎりではなく箸を使う普通のほか弁スタイルである。内容は悪くはないが強い風にあおられて非常に食べずらい。こんな時こそ握り飯と思うのだが、出してくれる方はどんなことを考えているのだろうといささか不思議に思った。 お花畑が終わってからしばらく登ると上方に小屋の屋根が見えてくる。  村営の頂上宿舎である。最初はそこが本日の泊まり場所と思いこんでいたので、案外早く辿りつけたなと内心喜んでいた。ところがだんだん強くなる風の中をようやく上がりきり小屋の中に入ってみて、そこからまだ先に行かないといけないことが分かる。かなり大きな山小屋で出て行く時に、そこの係の人から上の白馬山荘まではガスと風が更に強いので行けなくなったら戻って、ここで泊まるように勧められた。 村営の頂上宿舎である。最初はそこが本日の泊まり場所と思いこんでいたので、案外早く辿りつけたなと内心喜んでいた。ところがだんだん強くなる風の中をようやく上がりきり小屋の中に入ってみて、そこからまだ先に行かないといけないことが分かる。かなり大きな山小屋で出て行く時に、そこの係の人から上の白馬山荘まではガスと風が更に強いので行けなくなったら戻って、ここで泊まるように勧められた。一服した後改めてスタート。目的の今夜の山小屋の白馬山荘に向かう。さっきの人がいっていた通り進むにつれ風が更に強まる。おまけにガスがかかり前方が殆ど見えない。後から分かったのだが広い原っぱ状の稜線で風が通りやすくて余計に強く吹くらしい。濃いガスと風の中をゆっくり行く。少し遅れがちな人を見守りながらだったのでいつの間にか自分たち2〜3人になってしまう。30分程進んだところで突然ガスが晴れて、前方に山小屋にしてはかなり立派な大きい建屋が忽然と現れたのには驚くと同時に嬉しかった。目指している白馬山荘だった。これに元気付けられそれからはやや早足になってしばらくの後、午後2時ごろになっていたが、やっとそこに着いた。他の人達は全員既に山荘の中にいて遅れがちだった人が先頭になってそこに入っていくと一斉に拍手で迎えてくれた。 割り当てられた部屋は4畳半位で5人の相部屋、旧館らしく天井は普通の高さがある以外は前夜のところとあまり変わらず、ここに登ってきた時見えた立派な外見の割には貧弱でいささかがっかりする。本来ならばいったん荷物を置いてから程近い山頂を往復するはずであったが 風とガスがあるので中止となる。その後夕食までリュックの中を整理したり下のロビーのようなところでビールを飲みつつ数人で雑談したりして過ごす。角の部屋のせいか窓を打つ風の音がけたたましい。2重窓になっているが内側も外も隙間があるようだった。あまりにひどいので紙をパッキン代わりにして挟んで少しは静まる。夕食の後は今日の疲れが出たのかそのまま寝入ってしまう。翌日の食料(朝・昼食)を貰う為起こされるまで知らず、その後も又直ぐ寝てしまった。立付の悪い窓は結局一晩中鳴り通しだったらしい。 (注1 承前) 報道によれば、H17.8.11にここ葱平で崩落事故が発生し犠牲者が出たようだ。詳細はリンク先の新聞記事の通り。 (注2 承前) H20.8.19にも同様の崩落事故発生。詳細リンク記事の通り。 第3日目(7月20日 (水)) 白馬岳山頂→三国境→小蓮華山→白馬大池→白馬乗鞍岳→天狗原→ 栂池自然園→(ケーブル・ゴンドラ)栂池高原駅→(バス)大阪 午前3時に誰からともなく起きだし出発の用意にかかる。天気が気になるが雨ではないようだ。だが相変わらず風が吹きまくっていて窓を大きく鳴らしていた。こんな状態で頂上にいけるのかと内心心配していた。  きっと寒いだろうと昨日の雨でも使用しなかった雨具の下も取り出ししっかりと着込む。
きっと寒いだろうと昨日の雨でも使用しなかった雨具の下も取り出ししっかりと着込む。4時過ぎいよいよ山頂に向かう。風は確かに強いが歩けない程ではなく、寒さも着ているもので丁度良かった。勿論風の為顔や指先はかなり冷たい。星は見えないが薄明かりがあり照明なしで何とかいける。ガレ場というのだろうか手の平大の石で埋まった道がついている。あまり急坂ではないので登るのに難渋するといったことではなかった。右側が切立った断崖になっているので左寄りに慎重に上がっていく。かれこれ20分程でこの道を登りきると白馬岳2932mの頂上だった。コンクリートで固めた標識が目に入った時はやはり「やった!」という達成感を覚えると同時に感動した。  ご来光はほんの数分前までは雲の切れ間から次第に明るくなっていく状況がはっきりと見えていたのだが、いよいよこれからが本番という瞬間に突然すっと隠れてしまって、薄明かりの中に幾重もの山塊が雲の間から頭を覗かせているだけになってしまう。誠に残念であった。  記念の写真を撮ったりしてから5時に頂上を離れ、右手の山稜にはっきりと見えている道を次の小蓮華山に向かう。これからしばらくは稜線を伝って上がったり下がったりを繰りかえす。高木がない為どこでも見晴らしが利いて楽しい。岩陰に入るとそれまで強く吹いていた風がピタッと止まる。その違いがあまりにはっきりしているので驚く。  やがてやや盆地状になった窪地の真ん中に立つ三国境の標識につく。頂上から45分のところだ。文字通り三国 長野、富山、新潟の境らしい。頂上からかなり下ったという気がしたが実際はまだ標高は2751mもあると出ていた。この分岐を小蓮華山の方にとる。この辺りの地形は二重山稜といって二本の稜線が平行して走って舟窪地形になっている、と後になって解説書を読んで知った。そういえばそこだけが周りの地形とは少し異質との印象を受けていたがその訳が分かった次第。 5分ほど休んで歩きだす。先程と同じような稜線を辿る。風が依然として強いが雨の心配はなさそうで、足元に注意をしながらかつ周囲の移り行く山々の様子を楽しんで進む。30分ほどで稜線の一箇所で左側が岩で少し小高く壁になったところに出た。例によってとたんに風がなくなる。絶好の休憩場所だ。午前3時の起床から朝食をとらず既に3時間以上経っていたのでさすがに空腹を覚えていたところだった。夫々適当に腰を下ろし昨夜配られた例の山小屋製ほか弁を食べた。遥かかなたに微かにあがる噴煙でそれとわかる浅間山や右にやや間をおいて黒いシルエットの八ヶ岳を眺めながら、又右手にはたった今通って来た白馬岳がその堂々たる雄姿を見せていた。ところがこのほか弁は昨日の昼と比べるとご飯がいかにも不味い。炊き方が下手で折角の朝食も食欲が少し萎えてあまり箸が進まなくなった。座って体の動きが止まって寒くなってきたこともある。 朝食休憩を終え再び動き出す。それから白馬大池までの約2時間がおそらく今回の白馬トレッキングのハイライトであろう。小蓮華山(2769m)を間に挟み長く続く稜線を辿るコースは素晴らしい眺望の連続である。と同時に高山トレッキングの醍醐味を満喫させてくれる。 栂池スカイラインコースと名付けられているが文字通りであると思った。  約40分ほどで小蓮華山に着く。風は変わらずに吹いているが寒さは左程感じない。ややとがった角ばかりの大小の岩だけで形ずくっている山頂で写真だけ撮ってすぐ先に進む。このあたりから右下の遥かかなたに昨日泊まった小屋が雪渓の端っこに見えてきた。最初は気がつかなかったのだがいくつもある雪渓を目で追っていく内にあの小屋の屋根に気がついた。それでこれまでの辿ったコースの概略が頭の中で描けて一気に理解できたように思った。また振り返ると白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳などがその威容を現わしていていつまで見ていても見飽きがしない。それから次第に下っていくと前方遥かのやや下方に白馬大池が美しい形を見せていた。そのうち稜線伝いから左側に回り込みややなだらかな坂になってくる。雷鳥坂といわれる山のお腹に当たるところの下りである。途中急坂もあるものの次第々々に池に近付き8時50分に白馬大池(2380m)に到着した。白馬岳頂上から約4時間を要していた。午前3時に起き4時ごろから歩いているだけにさすがに少し疲れを覚える。下ってきて気温がかなり上り汗を掻いたせいもある。早速セーターや雨具を脱ぎ、下のシャツも着替えて
すっきりさせた。
約40分ほどで小蓮華山に着く。風は変わらずに吹いているが寒さは左程感じない。ややとがった角ばかりの大小の岩だけで形ずくっている山頂で写真だけ撮ってすぐ先に進む。このあたりから右下の遥かかなたに昨日泊まった小屋が雪渓の端っこに見えてきた。最初は気がつかなかったのだがいくつもある雪渓を目で追っていく内にあの小屋の屋根に気がついた。それでこれまでの辿ったコースの概略が頭の中で描けて一気に理解できたように思った。また振り返ると白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳などがその威容を現わしていていつまで見ていても見飽きがしない。それから次第に下っていくと前方遥かのやや下方に白馬大池が美しい形を見せていた。そのうち稜線伝いから左側に回り込みややなだらかな坂になってくる。雷鳥坂といわれる山のお腹に当たるところの下りである。途中急坂もあるものの次第々々に池に近付き8時50分に白馬大池(2380m)に到着した。白馬岳頂上から約4時間を要していた。午前3時に起き4時ごろから歩いているだけにさすがに少し疲れを覚える。下ってきて気温がかなり上り汗を掻いたせいもある。早速セーターや雨具を脱ぎ、下のシャツも着替えて
すっきりさせた。
30分の休憩の後9時20分に最後の行程に入る。出発に際しリーダーからも話があり、そこからは完全な下りでごく楽にいけるものとばかり思いこんで気分も軽く歩き出した。ところがこれが大間違いだった。高いところのつらい歩きとは又別の少し危険でなお体力もいるという今回のトレッキングのなかでも最も面倒な場面が待っていた。 白馬乗鞍岳(2450m)までとそれから少し先の大小の丸みを帯びた岩ばかりの道(岩の上を次に足を置く岩を選びつつバランスを取りながら歩いていく)。そのあとの小雪渓をアイゼンなしでの横断やロープを使っての降下。栂池自然園に近づいたところでの足元のすこぶる悪い山道(相当昔に整備されたものが今や痛みがひどく、そのせいできわめて足元を悪くしている)などなど。標高の下がったことから急に湿度を伴っての暑さも加わってこの最後の行程はかなり応えた。 ただこの途中で一つだけ非常に心和む光景を偶然にも眼にすることが出来た。それは5匹の子を連れた雷鳥を3〜4mの至近距離で見ることが出来たことだ。遊んでいるのか餌をさがしているのか6匹全部が岩から岩にゆっくり移りながらしばらく姿を楽しませてくれた。まるで絵のようとはこのような場面をいうのだろう。5匹の子雷鳥が何とも愛らしかった。人間慣れしていない為か直ぐに逃げる素振りはまったくなく、特に親鳥はこちらをしばしじっと見ているようで、そしてやがて岩陰の草むらに静かに消えていった。保護色だろうが岩の上に並んでいるのが 岩に溶け込んだようで最初は見落としそうだった。 栂池自然園に着いた時(午後1時半頃)にはいい加減くたびれ、そのピークにきていた。白馬大池から約4時間、早朝4時からの歩きを加えると9時間以上になり、さすがに心地よい疲れではなく、ぐったりというのが正直な感想だ。そこで直ぐ使わせて貰った洗面所の冷たくて豊かな水は格別で、思わず何回も顔を洗ったことだった。更に汗みずくのシャツを代えたりしていたら時間を取ってしまい昼食が半分も食べられずに時間になり、ケーブルの駅に急いだ。それからはさらにゴンドラを乗り継ぎ、あっという間にバスの待っている高原ターミナルに着く。 その後近くの温泉「岳の湯」につかり汗と疲れをとり文字通り生き返ったようになって白馬村を後にした。 以上が2泊3日にわたる今回の白馬トレッキングの概要であるが、結論は本当に楽しくかつ感動を貰った最高の山行きであった。当初年寄りの冷や水といわれかねないと懸念していたが、そんなこともなく無事に戻れたことを心から有難いと感謝している。 以 上 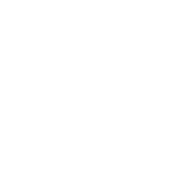 |