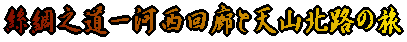
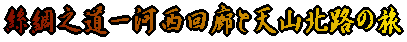
1992・8/3〜8/14

敦煌・鳴沙山
中国文学の世界に足を踏み入れた者の憧れの的シルクロードの旅が実現した。古くは法顕や玄奘、またマルコポーロの歩いたロマンと苦難の道を訪ねてみた。
中国東方航空で2時間、上海に到着。中国資本の5ツ星ホテル新錦江大酒店に宿泊。翌朝、西安に飛ぶ。そして郊外の「乾陵」を訪れた。
 ここには中国至上唯一の女帝則天武后の陵がある。「無字碑」が並んでいるが、首がない。陪葬墓の一つ「永泰公主墓」にも立ち寄った。
ここには中国至上唯一の女帝則天武后の陵がある。「無字碑」が並んでいるが、首がない。陪葬墓の一つ「永泰公主墓」にも立ち寄った。
そして帰路、漢の武帝・劉徹の墓である「茂陵」、 その陪葬墓の「霍去病墓」にも寄った。
その陪葬墓の「霍去病墓」にも寄った。 ホテルは西安賓館で、周りには夜店が並び、薄暗い中、火鍋の辛さで汗だくになった。
ホテルは西安賓館で、周りには夜店が並び、薄暗い中、火鍋の辛さで汗だくになった。
 一夜明け、西安市内観光で、玄宗皇帝と楊貴妃のロマンスの舞台「華清池」を訪ねた。
一夜明け、西安市内観光で、玄宗皇帝と楊貴妃のロマンスの舞台「華清池」を訪ねた。 「兵馬俑抗」は2・3号墓が公開されていた。
「兵馬俑抗」は2・3号墓が公開されていた。
「秦 始皇帝陵」は正直言って、ただの山であるが、この墓を作るために、当時は70万人が動員されたということだ。
始皇帝陵」は正直言って、ただの山であるが、この墓を作るために、当時は70万人が動員されたということだ。
 夕刻の「大雁塔」はいにしえ唐の都を彷彿とさせ、南門には「大唐三蔵聖教序記」の碑がはめ込まれている。その拓本を購入した。652年、玄奘三蔵の訳した仏典を納めるために建てられた64メートルの塔。最上階からの西安の街並みが見渡せる。
夕刻の「大雁塔」はいにしえ唐の都を彷彿とさせ、南門には「大唐三蔵聖教序記」の碑がはめ込まれている。その拓本を購入した。652年、玄奘三蔵の訳した仏典を納めるために建てられた64メートルの塔。最上階からの西安の街並みが見渡せる。
黄河のほとりの蘭州へ。金城賓館に泊まる。そばの夜店のハミ瓜はみずみずしい甘さで、いよいよシルクロードの景物に出会うことになる。またここで食べた牛肉麺の味は未だに忘れられない。澄んだ塩味のスープの味は最高であった。 「白塔山」からは黄河が見下ろされ、吹く風は実に快かった。
「白塔山」からは黄河が見下ろされ、吹く風は実に快かった。 しばし黄河遊覧としゃれこんだ。
しばし黄河遊覧としゃれこんだ。
本来なら、ここから列車の旅となるはずであったが、変更で飛行機で酒泉までひとっ飛び。太陽が沈むのを追いかける形の列車の旅を期待していたが、残念だった。長城賓館という嘉峪関を模したホテルであるが、砂漠の中にあり、周囲には何もなかった。往時の旅人たちの心細さを身にしみて知った。 市の中心に三層の「鼓楼」がそびえ、雄渾な門額が掛けられている。
市の中心に三層の「鼓楼」がそびえ、雄渾な門額が掛けられている。 近くには「酒泉公園」があり、湧水がある。
近くには「酒泉公園」があり、湧水がある。
 万里の長城の最西端、「嘉峪関」がそびえている。楼上からは、長蛇波打つように続く万里の長城が眺められ、
万里の長城の最西端、「嘉峪関」がそびえている。楼上からは、長蛇波打つように続く万里の長城が眺められ、 西には烽火台が眺められる。
西には烽火台が眺められる。
市 の東北20キロには、「魏秦壁画墓」があり、地下は外の40度近い温度に比べ、ひんやりとしていた。当時の農耕・狩猟・宴会などの生活ぶりが紅色を基調とする単純な彩色で生き生きと描き出されていた。
の東北20キロには、「魏秦壁画墓」があり、地下は外の40度近い温度に比べ、ひんやりとしていた。当時の農耕・狩猟・宴会などの生活ぶりが紅色を基調とする単純な彩色で生き生きと描き出されていた。
一路敦煌に向けて熱砂のアスファルトの道を車はひた走る。アスファルトも溶け、フロントガラスを叩く。 途中烽火台の名残が点在する。敦煌は海抜1200メートルの砂漠のオアシス。
途中烽火台の名残が点在する。敦煌は海抜1200メートルの砂漠のオアシス。
 まず、「鳴砂山」を駱駝の背に揺られて登る。おだやかなスロープを観光客のキャラバン隊が列をなして登っていく。背後から陽を受け、砂丘に駱駝と人の影が映し出される。異国情緒も満点だ。
まず、「鳴砂山」を駱駝の背に揺られて登る。おだやかなスロープを観光客のキャラバン隊が列をなして登っていく。背後から陽を受け、砂丘に駱駝と人の影が映し出される。異国情緒も満点だ。
 そして下りきると「月牙泉」があり、青々とした水をたたえていた。3000年以上涸れたことがないという。中国では三日月のことを「月牙」という。
そして下りきると「月牙泉」があり、青々とした水をたたえていた。3000年以上涸れたことがないという。中国では三日月のことを「月牙」という。

 憧れの敦煌にやってきてアクシデントに見舞われた。ホテルが変更になったことと、昨夜クーラーに当たりすぎて体調を崩してしまった。「莫高窟」を参観中、どうも調子がおかしい。ホテルへ帰ってから下痢と嘔吐。午後からの参観は取りやめにしてホテルで過ごすことにした。しかし、午前中に見た45窟は盛唐の中でも最も美しいとされる窟で、人物は腰をひねり、優雅なS字型を示して立っていた。女性的な容貌と肉の柔らかさは吉祥天女のどこかに似ていた。機会があればもう一度この地を訪れて、他の窟も日がなゆっくりと訪ねて歩きたいものだ。
憧れの敦煌にやってきてアクシデントに見舞われた。ホテルが変更になったことと、昨夜クーラーに当たりすぎて体調を崩してしまった。「莫高窟」を参観中、どうも調子がおかしい。ホテルへ帰ってから下痢と嘔吐。午後からの参観は取りやめにしてホテルで過ごすことにした。しかし、午前中に見た45窟は盛唐の中でも最も美しいとされる窟で、人物は腰をひねり、優雅なS字型を示して立っていた。女性的な容貌と肉の柔らかさは吉祥天女のどこかに似ていた。機会があればもう一度この地を訪れて、他の窟も日がなゆっくりと訪ねて歩きたいものだ。
 トルファンに向かう途次、王維の詩にもある「陽関」の地を訪れた。「陽関を出ずれば故人なからん」とはまさにこの風景で、風吹きすさぶ砂漠にあるのはだただ寂寥感のみであった。漢の武帝により置かれた関所だが、現在は烽火台の跡が残るのみである。
トルファンに向かう途次、王維の詩にもある「陽関」の地を訪れた。「陽関を出ずれば故人なからん」とはまさにこの風景で、風吹きすさぶ砂漠にあるのはだただ寂寥感のみであった。漢の武帝により置かれた関所だが、現在は烽火台の跡が残るのみである。

 孫悟空で名高い「火焔山」を通り、ベゼクリフ千仏洞を訪れた際には、なんと気温43度を指していた。火州と呼ばれる所以がここにある。しかし乾燥しているためか日本のような不快感は感じなかった。ウイグル語で「装飾された家」はわずかに面影を残すだけで、イスラム教徒の偶像破壊によって、今は時の流れを感じさせるだけであった。
孫悟空で名高い「火焔山」を通り、ベゼクリフ千仏洞を訪れた際には、なんと気温43度を指していた。火州と呼ばれる所以がここにある。しかし乾燥しているためか日本のような不快感は感じなかった。ウイグル語で「装飾された家」はわずかに面影を残すだけで、イスラム教徒の偶像破壊によって、今は時の流れを感じさせるだけであった。
 そして漢の時代に都城がおかれた「交河故城」は、耳を澄ませば亡霊たちのささやきが聞こえてきそうな遺跡で、ついセンチメンタルな気分に誘われてしまう。また元の時代まで高昌国の王都でもあった「高昌故城」も栄枯盛衰を感じさせるものであった。
そして漢の時代に都城がおかれた「交河故城」は、耳を澄ませば亡霊たちのささやきが聞こえてきそうな遺跡で、ついセンチメンタルな気分に誘われてしまう。また元の時代まで高昌国の王都でもあった「高昌故城」も栄枯盛衰を感じさせるものであった。
 泊まったのが緑州賓館、葡萄棚の下で歌と踊りが披露され、名前にふさわしくまさに緑の風が爽やかなオアシスのホテルだった。ウイグル人の歌舞団で、舞踊・弾き語り・合唱など、いずれもすばらしい。衣装も色鮮やかである。
泊まったのが緑州賓館、葡萄棚の下で歌と踊りが披露され、名前にふさわしくまさに緑の風が爽やかなオアシスのホテルだった。ウイグル人の歌舞団で、舞踊・弾き語り・合唱など、いずれもすばらしい。衣装も色鮮やかである。
 至る所に天山山脈からの雪解け水をたたえた「カレーズ」が見られ、葡萄がたわわになっていた。
至る所に天山山脈からの雪解け水をたたえた「カレーズ」が見られ、葡萄がたわわになっていた。
 またバザールやイスラムのモスクもみられ、オリエンタルムードが漂う町であった。
またバザールやイスラムのモスクもみられ、オリエンタルムードが漂う町であった。

 そして今回の旅の西の果て、ウルムチまでやってきた。町の中心に「紅山」があり、ウルムチのシンボル的存在となっている。
そして今回の旅の西の果て、ウルムチまでやってきた。町の中心に「紅山」があり、ウルムチのシンボル的存在となっている。
 翌朝、郊外の「南山牧場」までバスを走らせた。カザフ族の「パオ」や白い羊の群や牛たちがのんびりと草をはむ、いかにも牧歌的な風景が広がっていた。14日間という長旅であったが、始めて体調を崩したが、現地の医者の処方箋でそれも一日で快復し、楽しい旅が続けられ感謝している。
翌朝、郊外の「南山牧場」までバスを走らせた。カザフ族の「パオ」や白い羊の群や牛たちがのんびりと草をはむ、いかにも牧歌的な風景が広がっていた。14日間という長旅であったが、始めて体調を崩したが、現地の医者の処方箋でそれも一日で快復し、楽しい旅が続けられ感謝している。
![]()
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |