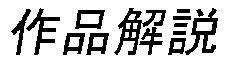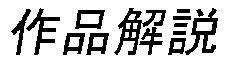1786年12月6日、ヴィーンで作曲された。第1楽章 アダージョ〜アレグロ 第2楽章 アンダンテ 第3楽章 プレスト の構成で、序奏付きのメヌエットなしの3楽章の交響曲である。近年、プレストが最初に作曲されたという説が発表されている。モーツァルトが使用した五線譜などの分析が根拠になっているらしい。モーツァルトは交響曲 第31番 ニ長調 パリ の最終楽章が気にいらず、最終楽章を書き直したが、考えを変え、新たに前半の楽章を書き、交響曲第38番を完成させたという論旨である。交響曲第31番と第38番の間には8年の歳月が流れており、モーツァルトの性格を考えると、あっさり信じることができない部分がある。しかし、指揮者のギュンター・ヴァントが雑誌のインタビューで交響曲 第38番 プラハ はドイツで 「頭でっかち」 と呼ばれていると話していた。確かに、36小節の長い序奏付きの立派な第1楽章に比べ、最終楽章はアンバランスで物足りない印象を受けるし、様式も古い交響曲のスタイルである。
プラハという通称は、1787年1月19日、プラハで初演されたことに由来する。作曲したのは前述のとおりプラハ行きが決まる前のヴィーンで既に完成されている。
モーツァルトの交響曲の発展を三段跳びにたとえるなら、交響曲第35番がホップ、交響曲38番がステップ、後期三大交響曲がジャンプであると思う。長調の交響曲であるが暗い響きの面があり、敏感な耳を持つ人にとっては今までに存在しなかった風景が映る。周知のとおり、歌劇 フィガロの結婚 との関連性も指摘されている。そのように考えてくると、やはり、モーツァルト後期の交響曲として聴くのではなくオペラの序曲風の曲として楽しむべき曲なのかもしれない。それにしても秀逸なのはやはり第1楽章で特に展開部の処理は本当にすばらしい。
演奏・録音
DENON(音源自体は旧コンサートホール) カール・シューリヒト指揮 パリ・オペラ座管弦楽団 1963年6月録音 を挙げる。評論家の宇野功芳氏が熱心に勧めているが、モーツァルティアンからも異論は出ないと思う。シューリヒトのコンサートホールレーベルの録音は海外盤で10CDのボックスで、最近復刻されている。(残念ながら一部欠落しているが。)音質は悪いが、ある程度のシステムで聴くと、近年の作為的なデジタル録音より素直でピントが合っている。
序奏の演奏の仕方や再現部のテンポの取り方は基本的に19世紀のスタイルを踏襲している。注目すべき点は展開部の見事さである。シューリヒトは作曲家としての分析により、このオーケストラをコントロールしている。
Symphony No.38 in D major "Prague" K.504
Music was written in Vienna on December 6,1786.The 1st movement Adagio -Allegro The 2nd movement Andante The 3rd movement Presto,it is the symphony of three movements whithout minuet whith an overture.The opinion that 3rd movement Presto was composed first in recent years is announced.
A common name calld Prague originates in having been premiered in Prague on January 19,1787.It is already compleated in Vienna.
It is the symphony in a major key,there is a field of dark sound.
|