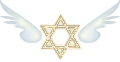
―終わりと始まり―
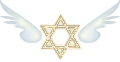
―終わりと始まり―
|
歓声に応えて、最高神官がエリューシアの血に濡れた剣を高々と指し示した時。 その声は、祭壇から零れ落ちた。 『否』 神官は、はっとして彼女を見つめる。もうすでに、エリューシアは絶命している筈だった。 その唇が確かに動いた。 いな、と。 さっと空が暗くなった。どこからか獣の咆哮のようなものが聞こえてくる。 何か目に見えない大きなものが、凄い勢いで彼女の体から噴き出している。 やがてそれは天井を突き破り、高く高く登っていく。 人々の悲鳴が響く。 ギリギリ、と嫌な……骨が折れるような音がして、神殿の白い柱が倒れて崩れ落ちた。祭りを祝っていた、何万という民衆の上に。 柱の上に聳え立つ樹のように、空いっぱいに広がっていたものは、解き放たれたように、地上に向けて牙を向いた。 かっと開かれた口の中は、炎のように赤く、どす黒く渦巻いて見えた。 大きな顎を噛み合わせる。 王国を、喰い千切るように。 ”赤き弟”の目に、紅い紅い花びらが舞っていた。 ……そうだ、次に休暇で帰る時、林檎を持って行こう、と彼は思った。 神殿の温室で真冬にも実る林檎は、一つ金貨一枚する程の高額だが、正神官になれたお祝いに少しぐらい散財をしてもいい。 父も母も、まだ小さい妹も、林檎が大好きだし。 今まではがむしゃらに頑張ってきたが、これからはもっと家族を大切にするのも、いい。 ゆっくりと遠ざかる意識の中で、彼は何故かそんなことを考えていて…… *** ぼんやり、彷徨っている。 ああ、そうだ、林檎のことを考えていたんだ。 もうすでに、自分の名前すら思い出せないそれは、そんな風に思った。 こっち、こっちへ来て。 何かが彼を呼んだ。 そちらに意識を向けると、完全に透明な、僅かに青みがかった光があった。 それは両手を広げ、優しい声で彼らを呼んでいた。 早く、ここに来て。私の中に。 その光に近付く。幾千、幾万の小さな星のような雫が、その周りに散ばっていた。 ああ、自分もこの星屑の一つなんだな、と彼は理解した。 早くしないと、みんな食べられてしまう。 さぁ、早く。 食べられる……? ああ、何か大切なものがあった筈なんだ。 赤くて、とても綺麗なもの。 それをあげたら、きっと彼女は笑ってくれるのに…。 光の中に溶け込みながら、彼はどこかで林檎の香りを感じた。 死ぬ間際とは、色々なことを考えるものだな、と”白き兄”は思っていた。 高神官の彼には、何が起きたのか、薄々解っていた。 生贄が、神と一つになることを拒んだのだ。聖別された筈の子羊が、神を。 それは、とても罪深いことかもしれないが、ある意味当たり前のこととも思えた。 しかし、そのせいで儀式は失敗し、王国は滅亡しようとしている。 …祭らねば、祟るものを神と言う……。 自分の体は、半分以上瓦礫に埋まり、変な風にひしゃげている。 今救い出されても、多分命はない。その前に、助けられることもなさそうだが。 目の前では、若い正神官がすでに絶命していた。 その顔は安らかで、少しほっとする。 彼自身、感覚が麻痺しているのか、殆ど痛みは感じない。 その代わり、とめどなく思考が溢れた。 私は、弟のことが好きだったんだ。 彼は、とても穏かに微笑んだ。 それだけでも、思い出せて良かった。 大好きだった弟が、死んでいくのに何も出来ない自分が悔しくて。 ほっとしてしまった自分が許せなくて。 本当は、選ばれて死んでいく人間なんて見たくなかった。 この国はどこかで、ボタンを掛け違ってしまったのかもしれない。 体から血が流れ出ていく。なんだかとても眠くなった。 これから、私たちは、神の裁きを受ける。 それは、あまり幸せなことではないだろうが…多分、仕方が無いのだろう。 半分以上、諦めきった彼の心に、そっと優しい声が囁き掛ける。 こっちへ、来て。 ああ、君か、と彼は言葉を返した。 早く、私の中に……。 また貴方は、そんな無茶をして。 こんなことのために、力の使い方を教えたわけではないのに……エリューシア。 彼は、小さく苦笑する。 彼女は、神を受け入れる筈の器の中に、王国の全ての者の魂を呼び込んでいるのだ。 早く、早く、神様に食べられる前に。 しょうがない、貴方の我侭に付き合って差し上げよう。 全く、仕方の無い方だ。余計な真似ばかりする。 だけど、ああ……。 貴方は、泣いても良かったのだ。 最後の微笑を残して、彼の呼吸は止まった。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ その行商隊(キャラバン)が、その場所を通りかかったのは、ほんの偶然だった。 日も沈みかけ、そろそろどこかキャンプを張るのに丁度いい場所がないか……と探していた矢先。 見張りの一人が、その人影をみつけたのだ。 用心しながら近付いてみると、呆然と砂の上に座り込んでいる少女がいた。 年齢は十二、三という所だろうか。元々は上等なものだったのだろう、薄い白の服はあちこち破れかけ、 長い黒髪は、途中で千切れたようにボサボサだった。足には何も履いていないし、荷物らしいものもない。 「何をしているんだ? ここらはちょっくら物騒だぜ」 とリーダー格の男が話し掛ける。俺たちも物騒だがな、と男は心の中で呟いた。 行商とは名ばかりで、彼らはちょっと裕福そうな相手を見つけたら、強盗もやってのける集団。 だが、彼等が特別悪いというわけではなく、それだけこの辺の暮らしは厳しいのだ。 少女は、顔を上げて男をまじまじと見た。もしかして、口が利けないのかと思いかけた時、小さな掠れた声が漏れた。 「ここに……街……」 「ああ?街? ここは昔からずっーと岩砂漠だ。一番近い街でも、何日も掛かる」 少女は、大きく目を見開いて、目の前に広がる世界を見つめる。 白く、半透明な砂が、夕日にあたってキラキラ耀いている。所々、大きな水晶のような岩があり、なんとも言えず幻想的だ。 しかし、ここの砂や岩には、多量の塩分が含まれていて、草一本生えない。しかも、その中に微量な毒素があり、 どんな頑強な生き物も住まない、正しく死の砂漠だった。 「……頭領、こいつ…」 ああ、と男は頷く。どうやら、すでに盗賊に襲われて身包み剥がされた上、足手まといだから捨てていかれたのだろう。 そんな目にあったせいで、些か錯乱しているに違いない。そうでなければ、こんな年頃の娘が一人、砂漠の真ん中にいる筈がない。 「どうする?」 彼はふむ、と考えた。確かに砂漠で子供など拾っても、水や食料を消費するだけだろう。 しかし、花一つ無い男ばかりの長旅が彼の気を変えさせた。 旅の間は自分達の世話をさせ、街に着いたら奴隷商人にでも売り払ってしまえばいい。 「おい、ちゃんと働くなら、連れて行ってやってもいいぜ。どうする?」 少女はびくっと顔を上げ、それから小さく頷いた。 男は手を差し伸べると、少女を立たせ、検分するように眺めた。 「お前さん、名は?」 少女は少し考え、それから首を振った。 「ふん、自分の名前も思い出せないのか?」 少女は、少しだけ哀しそうな顔になる。 「ごめんなさい…何も、覚えていません…」 まぁ、その方が俺たちには都合がいいかもな、と呟き掛けて、男は少女の左胸に目を止める。 裂けた布の切れ目から覗くそれは、 「……魔女の刻印……」 ゴクリ、と男たちの喉が鳴る。少女の白すぎる肌の上に、真っ赤な百合の花が咲いていた。 「こんな年で印を押されるなんて、何やったんだ?こいつ……?」 見張りの男が薄気味が悪そうに言ったが、頭領はふん、と鼻で笑い飛ばす。 「神の罪人か。まぁ俺たちも同じ様なものだ。 この世界はすでに神に見放されている。死の砂漠は、日に日に大きくなっていくばかりだ。 それでも俺たちは生きていかなきゃならない。…こい」 記憶を失った少女は、少し乱暴に手を引かれて、おずおずと歩き出した。夕日が、少しづつ遠ざかって行く。 その景色を彼女は、確かに美しいと感じた。 <了> アトガキへ |