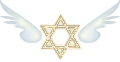
―滅びの獣―
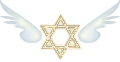
―滅びの獣―
|
「ねぇ、エリー。今日は聖なるお祭りの日なのよ」 街の大通りに面した、美しい屋敷。 窓にレースが掛けられたそこは、ただ一人の子供のための部屋。 青いドレスの幼い少女が、椅子に腰掛け、黒髪の人形を撫でながら、あどけなく笑う。 金色の巻き毛にはリボンを結んで貰い、今日は彼女もおめかししていた。 「また、あのおねえちゃまに会えるかしら? あのおねえちゃまはね…ふふふ、巫女姫様なの。私、知っているの」 だから、お前の髪も大切なものなのよ、と少女は微笑む。 「ソフィア、早くいらっしゃい」 母親に呼ばれて、ソフィアと呼ばれた少女は、はい、と返事をする。 胸に人形を抱いたまま、楽しくて仕方がないように部屋を後にした。 ……祭りで行われる儀式を、彼女はまだ、知らない。 ”白き兄”と呼ばれる高神官は、微かな苛立ちを覚えていた。 「祭りの祝詞はお忘れではないですな? その後の儀式の手順も」 「……はい」 彼はエリューシアの白く細い手から枷を取りながら、念を押す。純白の薄絹に身を包み、髪に銀細工と青玉を鏤めた冠を被せ、 唇に紅を差した少女は、珍しくも美しく見えた。その人形のように表情のない顔も、透き通るベールに白い肌が映えて、 この上なく清らかだ。 (こんな時ぐらい、泣き喚けばいいものを…) 高神官は、不機嫌な表情で乱暴に枷を抜き、手首に出来た赤い痣を見て、僅かに気を良くした。 「最後に、この世界にお別れでもなさるといい。貴方は数時間後には死ぬのだから」 そう言い捨てて、部屋を出る。若い神官がその物言いに咎めるような視線を向けていたのが解ったが、彼は頓着しなかった。 ……そう、彼女は泣くべきだった。どうか殺さないでと縋りつき、無様に喚くべきだ。 彼の弟が、そうしたように。 今でもまざまざと思い出す。弟が生贄に選ばれた時のことを。 七歳になる子供が七年に一人、生贄に捧げられることになっていた。彼と、彼の弟は年子で自分は八歳になったばかりだった。 弟は泣いた。どうして自分が選ばれたのだと。兄ではなく、どうして自分だけ殺されるのだと。 彼は、そんな弟が連れて行かれるのを見ながら、心のどこかでほっとした。自分でないことに安堵したのだ。 神官だった父は、苦しそうに呟いた。『あの子は恵まれている。神に祝福されて死ぬのだから』と…。 それは、自分に言い聞かせる言葉だったのかもしれない。しかし、彼の胸には深く残った。 そう、あのエリューシアという娘もそうなのだ。恵まれている筈なのだ。何も思い悩むことはない。 もうすぐ、彼女も自分の弟と同じ様に儀式に掛けられて、祭壇の上で血を流すのだ。 ”白き兄”は大きく息を吐いて、高神官である自分を取り戻した。 今日は数百年に一度と言われる大事な祭りの日。彼にはすることが山ほどあるのだから。 エリューシアにとって、その朝は何も変わりなく、平凡な唐突さで訪れた。 何週間も前から、彼女の周囲は祭りの準備で忙しく、街も華やかにざわめいていたが、彼女にとってはもはや関係のないことで。 いつもと同じ様に巫女たちに口元まで運ばれた食べ物を食べ、宛がわれた杯の物を飲み、毎日神に祈りを捧げて時間は過ぎて行く。 そして、いつもよりも念入りに沐浴させられ、化粧を施されて、ああ、今日なのだな、とやっと気付いた。 朝から何も食べ物は貰えず、香りの良い酒だけを口にした。それでも白い頬には殆ど赤味が差すことはなかった。 機織を得意とする沈黙の巫女たちが、何ヶ月も前から用意していたという美しい衣装を着せられる。どうせすぐに血で汚れてしまうのに、 と考えた。 更に、繊細な銀細工で一枚一枚花びらを作り、宝珠を巧みに編みこんだ髪飾りを一揃い…冠、額飾り、鎖で繋がったピアス等… を付ける。 腕や裸足のままの足にも飾りが施され、身動きをする度に、チリチリと澄んだ音を立てた。 こんな枯れない花は見慣れているけれど、幼子から貰った赤い花ほど美しくは見えない、とエリューシアは不思議に思う。 そう、確かこんな気持ちのことを、あの”天使”は……。 ふとエリューシアは、小さく眉を顰めた。彼女は神への祈りに入った時、その瞑想の中で”ツァドキエル”という存在に会うことがある。 彼はエリューシアの守護天使(ガーディアン)だと言うが、本当に天使であるのかさえあまりにも曖昧で、神官たちにも話さなかった。 ぼんやりと感じられるその存在は、彼女にこう言ったのだ。 「それが『特別』ということだよ」と……。 唐突に”白き兄”が入って来て、エリューシアの考えは中断された。 「巫女姫に置かれては、ご機嫌麗しゅう」 そういう彼の機嫌は、いつもよりも悪いように見えた。 エリューシアは、彼が自分を嫌っているように思っていたので、それが少し意外だった。 彼は小さな鍵を取り出すと、結局今日まで嵌めたままだった枷を取り外した。手と手が僅かに触れて、体温の低いエリューシアの肌に 彼の温もりが微かに残った。 「祭りの口上はお忘れではないですな? その後の儀式の手順も」 「……はい」 エリューシアは動揺を隠すように頷いた。 今、解った。 この人が怒っているのは……彼自身にだと。 どうして急に。 こんな人の心が流れ込んでくるのだろう。 私が死に近付いたから……? ぼんやりと空を見つめる彼女に何か言い残して、彼は部屋を出て行った。 若い正神官の、気遣わしげな眼差しが残った。 やがて、神殿の七つの鐘が鳴り響き、祭りの始まりを告げると、エリューシアはゆっくり立ち上がった。 「あ…ええと……」 若い神官が、初めて口を開いた。 「…なんでしょうか」 「………。神の祝福を」 「ありがとうございます」 エリューシアは、淡く笑う。初めて見る微笑みに彼が言葉を失っているうちに、彼女はベールを持つ沢山の巫女に囲まれて、 歩き出していた。 祭りは、何事もなく進んでいった。 普段は堅く閉ざされた神殿の正面の扉が開き、白い大樹が民の目の前に聳え立つ。 やがて現われた巫女姫は、黒い艶やかな髪に映える銀の冠を被り、ケセドに相応しい深く青い瞳を向けて、彼らに祝詞を唱えた。 凛と通る声は高く響き、民は彼女に歓声で応えた。 ”赤き弟”は、そんな彼女の傍に礼装を纏い、神妙な顔で付き従っていた。 彼は、”白き兄”が彼女に投げかけた言葉を、心無いと感じていたが、僅か十二歳の少女がそれに傷ついた様子もなく、 怯える姿も見せずに役目をこなしていることを、不思議に思っていた。 だが、これから続く儀式のことを思うと、口の中はカラカラに乾いてしまう。 そういえば、彼女は自分の妹ぐらいの年頃なのだな、と神官は気が付いた。 だから、余計に辛く思うのだろう。……彼女は選ばれし者であるのに。 エリューシアは、ベールを外すと、儀式のために神官たちに付き添われて祭壇に登っていった。 「いや……ダメよ」 観衆の一人、金髪の幼子は、振り上げられた短剣の意味を知って叫んだ。 「嫌ぁ、やめて、やめてぇ……!!」 しかし、たった一人の子供の声は聞き届けられることなく、歓声の中に消えて行った。 エリューシアは、祭壇の上に横たわっていた。 美しく装飾が施された、神殿の白い柱。 塵一つなく磨き上げられた石の床に、白い花びらが舞う。 耳を澄ませば、遠くから楽の音が聞こえる。 清浄な中に、微かな華やぎを添える、人々の笑い声。 目を上げれば、神官や巫女たちも皆微笑んでいる。今日のこの時を祝って。 「神の祝福を…!」 彼女の喉から滴る血が、床の花びらを赤く染めると。 高らかな祈りの言葉が、天に木霊した。 ”身体が冷たくて。 喉が熱くて。 とても、寂しい。 私はずっと、一人きりだったから。 誰とも触れ合うこともなく。 私が愛すべき人は、神様だけだから…。 天から光が差し込む。 私を連れて行くの? なんて温かいんだろう。きっと、哀しむことも、苦しむこともない世界…。 でも……。 愛されなくてもいい。 私は誰かを愛したい。 自分にとってただ……特別な誰かを” 祭りの歓声が遠くなる。神官たちの祈りの言葉ももう聞こえない。 ……少女は、この日、生を終えた。 |